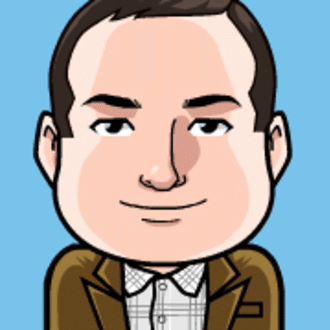邪馬台国の謎 (1)
私の趣味の一つが、歴史の探求になります。
その中でも、古代史は未知の部分が多く、空想しやすい点が楽しいです。
日々の仕事でなかなか時間が取れないのですが、後継者を育ててバトンタッチした後は、全国の神社仏閣や史跡を巡り、歴史探訪をしてみたいというのが、私の夢の一つになります。
さて、日本古代史の中でも屈指の知名度を誇る謎が、
【邪馬台国】 は どこにあったのか?
というものです。
今回は、本論に入る前に、予備知識というか、蛇足のオンパレードから始めたいと思います。
当て字問題(蔑称いろいろ)
まず、邪馬台国という文字は、随分と酷い字があてがわれています。
これは、朝貢を行なった相手国・魏王朝によって当て字が行なわれたためです。
邪馬台国の【邪】という文字を見るだけでも、いかに未開民族・蛮族として見ていたことかを裏付けています。
文明国と自負する国民が、未開の民族を蔑視するのは、古今東西、ごく普通に起こり得ることだという証左といえるでしょう。
古代では日本を馬鹿にして蔑称で呼んでいた【中国】ですが、彼ら自身、日本から【支那】と呼ばれることに、激しい反発を見せています。
なお、【中国】という呼称は、1912年に、孫文によって、中華民国が建国されて以降の正式な呼称となります。
もちろん、古い時代から中華の国(世界の中心にある国)として【中国】という呼び方はありましたが、正式な呼称ではありませんでした。
国号を【漢】とか【唐】としていましたが、【中国】とは名乗っていなかったのです。
したがって、孫文の中華民国以降が、【中国】を正式な呼称として使い始めたということになるわけです。
また、1949年に毛沢東により中華人民共和国が建国されました。
こちらも、【中国】となります。
現状は、中華人民共和国を【中国】と呼び、中華民国を【台湾】と呼んでいますが、どちらも同じ【中国】なので、『一つの中国』というのも、あながち間違いとは言い切れないですね。
さて、中国誕生以前、中国全土を表す場合、秦王朝以来、漢・晋・隋・唐といった【国号=王朝名】で表すか、最初の全国王朝である【秦】と同音の【支那】が使われるようになりました。
ただ、古い時代から【中国】は自分たちの国土のことを【中国】とも呼んでいます。
いわゆる中華思想によるものですが、結局のところ、易姓革命が生じるため、【中国】という名前にしてしまうと、それこそ【第一中国】、【第二中国】といった番号制にせざるを得なくなってしまいます。
この辺り、王朝ごとに区切る考えなら【王朝名】。
中国大陸という風に地域で考えるのなら【中国】でいいかもしれません。
なお、【支那】という言葉は、後漢の時代、紀元1世紀頃に、仏教が伝来し、経典を漢訳していく中で作られた呼び名です。
(恐らく、唐の時代までには、【支那】という呼称は発明され、使われていたと考えられます。)
大陸発祥の言葉ですから、言葉の中に蔑称は含まれていません。
そもそもの意味は、【支那】=『思慮深い』というものでした。
が、唐が滅び、仏教が儒教に圧倒されるようになると、【支那】という言葉が使われなくなっていきます。
一方、大陸とは隔絶した状態(日本は遣唐使廃止以降、大陸文化の積極的輸入をやめた)だった日本では、【支那】の呼称が使われ続けています。
その結果、明治維新以降、再び大陸と接点を持つ中で、日本人は【支那】という古い呼び名を使ったわけです。
その当時、日本と清国は、古代とは立場が逆転していました。
日本は、脱亜入欧で、西欧列強の文明国に仲間入りを果たしたという自負があり、清国は遅れた国という風に見られていました。
【支那】という言葉の起源も意味も清国ではすでに失われていたことから、彼らは【支那】を「蔑称」だと感じるようになり、激しく反発するようになったのです。
この辺り、難しいところですね。
そのため、個人的には、【震旦(しんたん)】と呼ぶのが良いのかもしれないと思っております。
邪馬台国論争の発端とは?
さて、呼称の話はこの辺りにして、邪馬台国論争が巻き起こることになった遠因をお話しておきます。
それは、戦国時代に天皇家が窮乏したことに端を発しています。
特に日野富子が死去して以降、天皇家への資金援助は少なくなり、即位式すらままならない状況になっています。
そのため、天皇や貴族は、宮中の書籍を書き写し、それを売却することで糊口をしのぐ状態でした。
この時に宮廷の外に『日本書紀』が出てきました。
兵法書などの実学系の書籍は早い段階で広まりましたが、日本書紀のような教養系統の学問になる歴史書は、すぐには広まっていきません。
やがて、戦国時代が終わり、江戸時代に入ると、学問が奨励されていくようになります。
この頃になると、教養系統の学問が幅を利かせるようになります。
大勢の学者が輩出されるようになり、その中で、
新井白石
という著名人が、震旦の歴史書である『魏志倭人伝(紹興本とか)』や『日本書紀』から【邪馬台国】の記述を見出すことになります。
新井白石が色々と仮説を出したことにより、他の学者もこの考証に参加、現代にまで続く邪馬台国論争へと発展していくことになったのです。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arai_Hakuseki_-_Japanischer_Gelehrter.jpg?uselang=ja
ただ、新井白石は儒学が本職です。
実は、儒学者は、
「古典をいかにアレンジして都合が良くなるように解釈するか? 」
が、腕の見せ所になります。
というのも、春秋戦国時代の主流派であった荀子学派が秦王朝・漢王朝には衰退し、孟子学派の方が主流派になっていったからです。
青は藍より出でて藍より青し
このことわざでも有名な荀子は、【後王思想】を持っていました。
後生畏るべし、として、時代と共に人間は進歩し、自分なんかよりはるかに学識のある人物が登場してくると荀子は考えていたのです。
だから、荀子学派は、解釈を競い合うことに重きを置かなかったのです。
一方の孟子は、【先王思想】です。
古代の聖王に理想像を置き、最後の理想的人物を孔子に置きました。
だから、古典の言葉は【絶対】であり、それを【正しく解釈】するのが、学問だとしたわけです。
もちろん、この区分は、荀子と孟子の学説のうち、ほんの一部を切り取っての比較なので、時々矛盾することもあります。
(本人たちも、たまに矛盾発言してたりしますし・・・)
新井白石は、生粋の儒学者でしたから、歴史書に対しても、バリバリの儒学系解釈をぶちかましていくことになります。
新井白石のご都合主義解釈としては、
邪馬壹国 → 邪馬臺国 と書き換え、ヤマト→大和国とします。
一大国 → 一支国 と書き換え、イッシ→壱岐としました。
對海国 → 對馬国 と書き換え、ツイマ→対馬としました。
なお、對は、対の旧字です。
新井白石は、中国語の発音と、日本の地名を出来るだけ辻褄が合うようにしていったのです。
そして、日本を代表する王朝は、大和政権しかないのだから、邪馬壹国は大和国であり、書写する段階で誤植が生じたのだとして解釈を進めました。
こう書くと、新井白石がいかにも牽強付会で問題児みたいに感じてしまいますが、現代のコピー機時代とは異なり、昔の書写はとてつもなく大変な作業です。
人間の作業ですから、勘違いやうっかりミスは、あってもおかしくはなかったのです。
だから、文脈上おかしければ、誤字脱字として解釈することが正しい読み方でもあったのです。
こうして、邪馬台国論争は、初っ端の解釈から正しいのか正しくないのか、良く分からない始まり方をしたのです。
いいなと思ったら応援しよう!