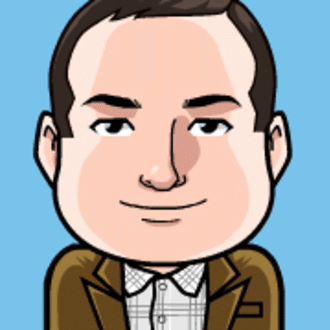邪馬台国の謎(10)
東南陸行五百里 到伊都国 官日爾支 副日泄謨觚柄渠觚 有千余戸 世有王 皆統属女王国 郡使往来常所駐 東南至奴国百里 官日兕馬觚 副日卑奴母離 有二万余戸 東行至不弥国百里 官日多模 副日卑奴母離 有千余家 南至投馬国水行二十日 官日弥弥 副日弥弥那利 可五萬余戸 南至邪馬壹国 女王之所都 水行十日陸行一月 官有伊支馬 次日弥馬升 次日弥馬獲支 次日奴佳鞮 可七万余戸 自女王国以北 其戸数道里可得略載 其余旁国遠絶 不可得詳
(末盧国から)東南へ陸路で五百里進むと、伊都国に到着する。
長官を爾支といい、副官を泄謨觚・柄渠觚という。
千戸余り。代々王を推戴しているが、女王国に従属している。
帯方郡からの使者が往来する時に常駐する拠点になっている。
伊都国から東南へ百里行くと奴国に到着する。
長官を兕馬觚といい、副官を卑奴母離という。
二万戸余り。
東に百里行くと、不弥国に到着する。
長官を多模といい、副官を卑奴母離という。
千家余りある。
南に船で二十日余り行くと、投馬国に到着する。
長官を弥弥といい、副官を弥弥那利という。
五万戸余りある。
南、邪馬壹国に至る。女王が都とするところである。
船で十日、陸路では一月かかる。
長官伊支馬が置かれ、次が弥馬升、その次が弥馬獲支、その次が奴佳鞮という。
七万戸余りある。
女王国より北は、その戸数や道順、距離に関して大雑把に表記できるが、それ以外の周辺国については、遠方であり、使者の往来もないため、記述することすら難しい。
この辺りになると、さらに混乱してしまう記載が多くなります。
狗邪韓国 : 朝鮮半島南部 (伽耶)
対海国 : 対馬
一大国 : 壱岐
末盧国 : 唐津市
伊都国 : 糸島市
奴国 : 福岡市から春日市にかけて
上記の奴国までは、国の特定に関する学説は、ほぼ一致している感じです。
地名と国名の発音の類似性や、経路としての合理性から、上記の国の特定がされているわけですが、方位や距離が合わないものですから、混乱が生じている次第です。
(魏志倭人伝に記載されている方位や距離に絶対的な信頼を置けない)
まず、
狗邪韓国から対海国への海路。
対海国から一大国への海路。
一大国から末盧国への海路。
全てが、千里余り。
一里414mとした場合には、それぞれ414km。

図の写真のように、一里=414mとした千里=414kmで同心円を引くと、狗邪韓国から千里は、鹿児島県にまで到達してしまうことになります。
対海国が鹿児島、一大国が沖永良部島になってしまうんですね。
これはもう・・・エラいこってす。(汗)
まだ翻訳していませんが、後段の帯方郡から邪馬台国まで1万2000里という表現をそのまま計算しちゃうと、台湾を少し通り過ぎて、フィリピン最北端の島バスコにまで到着してしまう勢いです。

で、短里(六十歩で一里と仮定)で同心円を描かせると、
狗邪韓国から対海国への海路と対海国から一大国への海路については、近い線になります。
また、帯方郡から狗邪韓国までの距離七千里も、同心円上では近い数字になります。
このことから、一寸千里法(基準となる棒の影の長さから、大雑把な距離計算をした)の説が出てくることになります。
実際の道のりでは、海岸線沿いを航行していましたので、帯方郡から狗邪韓国までの距離は、もっとあるはずです。
とまあ、ここまでは、短里説で説明がつくのですが・・・
この後が破綻していきます。
一大国から末盧国への海路もまた、千里余りあるはずなのです。

壱岐を起点として、短里で千里の同心円を描くと、
東は宗像 東南方向が鳥栖、南方だと鹿島市や、西海市にまで到達することになります。
次の記述が【陸路五百里】ですから、小値賀島ではないでしょう。
このように短里説も、途中でグダグダになってしまう箇所が出てくるんですね。
次有斯馬国 次有巳百支国 次有伊邪国 次有都支国 次有弥奴国 次有好古都国 次有不呼国 次有姐奴国 次有對蘇国 次有蘇奴国 次有呼邑国 次有華奴蘇奴国 次有鬼国 次有為吾国 次有鬼奴国 次有邪馬国 次有躬臣国 次有巴利国 次有支惟国 次有烏奴国 次有奴国 此女王境界所盡 其南有狗奴国 男子為王 其官有狗古智卑狗 不属女王 自郡至女王国 萬二千余里
ここからは、国名の羅列が続きます。
斯馬国 巳百支国 伊邪国 都支国 弥奴国
好古都国 不呼国 姐奴国 對蘇国 蘇奴国
呼邑国 華奴蘇奴国 鬼国 為吾国 鬼奴国
邪馬国 躬臣国 巴利国 支惟国 烏奴国
奴国
がある、と。
(ここで道程にあった奴国が再掲されるという疑問が出ます)
ここまでが、女王を推戴する国々の境界になる。
その南に、狗奴国がある。
男の王が治める国で、長官を狗古智卑狗という。
この国は、女王に従属していない。
帯方郡から女王国に至るには、一万二千里余りの距離がある。
謎は多いですが、とにもかくにも、女王を推戴する国々の南側に狗奴国という男の王を推戴する国があり、その国は邪馬台国連合に与していないことだけは分かります。
この後も、魏志倭人伝の記述は続きますので、これは、次回にということで。
いいなと思ったら応援しよう!