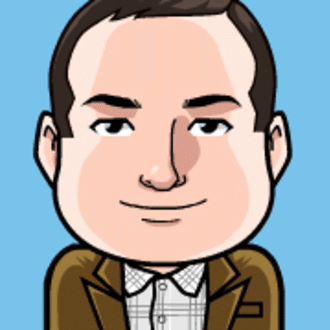邪馬台国の謎 (14)
其国本亦以男子為王 住七八十年 倭国乱相攻伐歴年 乃共立一女子為王 名日卑弥呼 事鬼道能惑衆 年已長大 無夫婿 有男弟 佐治国 自為王以来少有見者 以婢千人自侍 唯有男子一人 給飲食傳辭出入居處 宮室樓観城柵厳設 常有人持兵守衛 又有侏儒国在其南 人長三四尺 去女王四千余里 又有裸国黒歯国 復有其東南 船行一年可至 参問倭地 絶在海中洲島之上 或絶或連 周旋可五千余里
倭では元々は男子を王としていた。
その後、七、八十年で、倭国は乱れ、互いに攻撃しあうことが続くようになった。
そこで、一女子を共に立てて王となした。
名を卑弥呼という。
鬼道を使い、人々をうまく魅惑した。
非常に高齢で、夫はいないが、弟がいて国を治めるのを助けている。
女王になってから、朝見できた者はわずかなようである。
侍女が千人がいて、みな自律的に仕えている。
男子が一人いて、飲食物を運んだり言葉を伝えたりするために、女王の住んでいる所へ出入りしている。
宮殿や高楼は城柵が厳重に作られ、常に武器を持った人が守衛している。
女王国の東には、海を渡って千余里程のところに、別の国が有る。
どこも、倭人の建てた国である。
侏儒国が(女王国の)南にある。
人の背丈は三、四尺で、女王国を去ること四千余里である。
また裸国と黒歯国があり、(女王国の)東南にある。
船で一年ほどで、着くことができる。
倭地を考えてみると、孤立した海中の島々の上にあり、離れたり連なったり、点々と巡ったとして、五千余里ほどである。
「住七、八十年」は、住むことと訳されたり、留まることと訳されることが多いようです。
個人的見解になりますが、これは
後漢書を前提とした記述
で、読むのが正しいと思います。
どういうことか? と言いますと、
西暦107年。後漢の第六代皇帝・安帝の時代。
倭国王・帥升が、奴隷160人を献上するという大規模な朝貢を行なっています。
つまり、西暦107年から7,80年後の177年から187年の頃に倭国大乱があったと、ここでは述べていることになるわけです。
この倭国大乱が何年ぐらい続き、いつ卑弥呼が女王に推戴されたのか?
は、定かではありません。
西暦238年に、魏の国に使者が派遣されていますので、西暦187年と比較すると、238-187=51年。
仮に、卑弥呼が西暦187年に、15歳で女王に推戴されたとするなら、238年には、66歳。
「年長大にして」という表現もむべなるかな、となりますね。
さて。このくだりで驚いたのが、侍女1,000人という表記です。
いやいやいや。もはや大奥ですがな・・・
邪馬台国は連合国家ですし、地方政権です。
千人もの侍女を養うだけの税収を得ていたとは考えにくいというのが、正直な感想になります。
(もちろん千人を養える可能性は0ではないですが・・・)
となると・・・
以婢千人【自】侍
【自】の部分に目が行くことになります。
「自ずから」と読むことが出来ます。
つまり、「自主的に」ということですね。
半分ボランティアみたいな感じでしょうか・・・
卑弥呼一人の世話に千人も必要はないでしょうから、政庁レベルで考えた方が良いのかもしれません。
金や権力で使役するのではなく、好意で世話を焼いてくれる人々が千人。
これは、
事鬼道能惑衆
民衆を魅惑した、という表現が出て来ておかしくないかな、と思います。
なお、現代日本人にとって、「惑わす」は「騙す」のニュアンスが強く、占いということもあってか、多くの学者が「騙す」の意味で使っているように感じています。
私個人としては、「魅了」や「魅惑」の方が相応しい気がしています。
さて。このくだりで一番驚いたのが、侏儒国の住人のお話です。
当時は、一尺23cmぐらいでしたから、三尺=69cm 四尺=92cmです。
後世、30cmぐらいにまで伸びますが、それにしたって、90cmから120cm。
さすがに、平均身長として考えると、低すぎると思います。
世界でも有数の低身長国家であるウガンダのピグミー族ですら、140cm台です。
実際、縄文人や弥生人の発掘遺体の平均身長は150cm台ですから、上述のように成人の身長が1m前後というのは、驚きとしか言いようがありません。
少し誇張が入っているのではないか? と思わないでもありません。
考古学的にそういう人骨が多数見つかるようになれば、事実だったと認定されるでしょう。
【追記ここから】・・・ちょっと説明不足だったので、補足です。
なお、周旋可五千余里は、倭の周長と解釈されることが多いですが、
魏・呉・蜀の歴史書で 【周旋】 と書く場合は、 「あちこち動き回る」という意味で使われます。
つまり、あちこち動き回ったんだけど、まあ、五千里とすべきかな、という意味になります。
【追記ここまで】
で、狗邪韓国までの七千里と、そこから五千里余りで邪馬台国に到着する
ことから、一万二千里という数字になるという仕組みです。
次の段から、卑弥呼の使者が魏に到着して以後の記載となるため、今日は短くなるのですが、文脈上は、ここで切っておくのがバランスが良さそうなので、ここまでといたします。
いいなと思ったら応援しよう!