
【社会人入学】大学院の課題発表をしました。
こんばんは。特別支援学級教員13年目のMr.チキンです。今日は個人懇談終了後、すぐに帰宅しました。通信制大学院の講義を受けるためです。理解してくれる同僚に感謝です。
さて、今日は大学院の課題発表をした話です。
大河内一男論文(1938年)をまとめる
第1回目の課題は、日本における社会福祉理論の創始者である大河内一男という方の論文を読むというものでした。ただ、1938年の論文であったため、文章が難解かつ、時代背景が分からないと理解が難しいという難文でした。
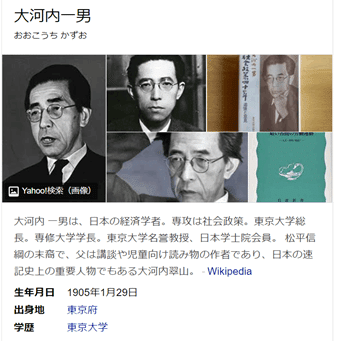
今回の課題については、社会福祉理論の創始者が経済学者??という戸惑いから始まりました。
同じ文章を5回読んでようやく分かり始めた
私は福祉畑の人間ではないので、この論文は初見でした。
正直、同じ文章を5回読みました。
4・5回目はメモを取りながら読みました。
メモは7ページに至りました。

教員をしながら、帰宅後のまとめ作業は正直大変でしたが、
文章にまとめることはnoteのおかげで慣れていました。
やっていてよかったです。
以下、今回の論文のまとめを掲載します。
社会事業と社会政策
一般的に、社会事業というものが、社会福祉に発展していったと言われています。第二次世界大戦に突入する時期であり、社会の変化が大きかった時代に書かれた大河内論文の核は「社会事業と社会政策の関係性」に着目したことでした。

社会事業というものは、社会経済から切り離された人(無職、障害者、老人、女性、児童、病弱者)などを対象としてきました。
社会政策は勤労者や生産者など、経済と連係した人を対象としていました。
社会政策の具体例として、失業保険政策や長時間労働是正政策、最低賃金の保証政策、職業紹介所などが挙げられますが、当時は存在しないor機能していない状態でした。
社会政策が弱いと・・・
社会政策が欠如したり弱かったりすると、社会事業の対象者である社会経済から切り離された人が増加してしまうという指摘を、大河内はしていました。
具体例が、紡績工場で働いていた女性労働者の件です。「低賃金」「重労働」で働いていた女性労働者。
過酷な労働環境のため、結核を患う人が急増します。
しかし、政府は社会政策としての失業保険政策や長時間労働是正政策、最低賃金の保証政策を行うことなく、女性を農村に返すという方針転換を行います。その結果、農村に結核が蔓延し、社会事業の対象が増えるという悪循環が発生したことを紹介していました。

現代の社会問題に関連付けてみた

でも、このいわゆる”結核女工”(大河内原文ママ)の問題は、現代の「教員のなり手不足」の問題に類似しているように感じました。
そこで、パワーポイントの最後に個人的な見解として紹介しました。
大学院の課題発表から得たこと
今回の課題は、すべての受講者(8名)が、同じ論文を読みまとめ、発表するというものでした。同じ大河内論文であっても、共通点や相違点があって面白かったです。
自分の課題発表後、
「教員の問題と重ね合わせる例で、論文の意図が分かりやすくなった」
「自分は具体例の用い方で迷っていたが、チキンさんの扱い方は良かった」
などの感想をいただけ、自信になりました。
教員として、うまくいかないことや取り組めなかったことなどのネガティブな気持ちをもつ日常ですが、大学院という非日常があるというのは精神衛生上も良いものだと感じています。
では、またね~!
