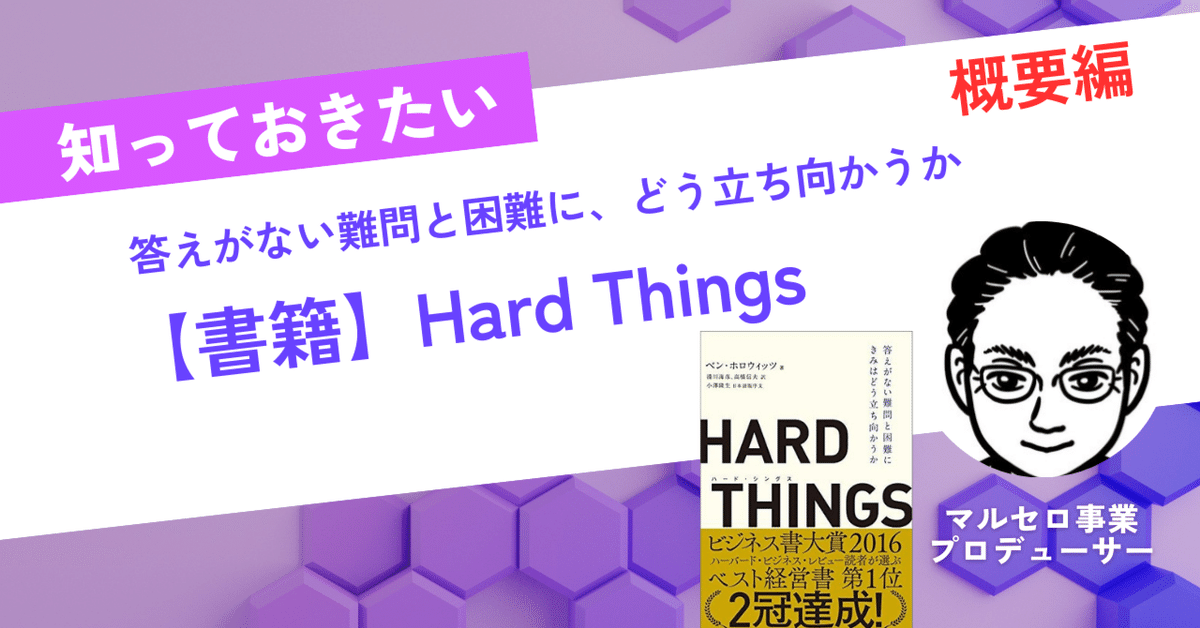
【書籍紹介】Harg Things 答えがない難問と困難にきみはどう立ち向かうか
本書は、スタートアップ向けセミナーで必ず紹介される1冊であり、起業家のバイブルとも呼ばれています。著者のベン・ホロウィッツは、シリコンバレー屈指のベンチャーキャピタル、アンドリーセン・ホロウィッツの共同創業者です。
アンドリーセン・ホロウィッツは、通称「A16Z」で親しまれている、シリコンバレー屈指のベンチャーキャピタル。投資実績には、スカイプ、エア・ビー・アンド・ビー、フェイスブック、インスタグラム、ピンタレスト等の名だたるテクノロジー企業が名を連ねています。
アンドリーセン・ホロウィッツは、ベン・ホロウィッツとマーク・アンドリーセンという二人の共同創業者の名前にちなんで命名。マークは、直観で操作ができるブラウザであるモザイクを開発し、その後のインターネット普及に大きく貢献した立役者。ネットスケープ社を創業し、ジャバスクリプトやSSLといったインターネットの基幹技術も同社から生まれています。
インターネット普及に大きく貢献したネットスケープであったが、その後、マイクロソフトがウィンドウズ95に独自ブラウザをバンドルし、無料配布したことで壊滅的打撃を受け、AOL社への売却を余儀なくされました。マーク・アンドリーセンは、元同僚であるベン・ホロウィッツが立ち上げたラウドクラウド社に参画。今では、一般に普及しているクラウドサービスの起源とも呼べる会社です。
本書では、ラウドクラウド社立ち上げから、インターネットバブル崩壊を経て、事業売却。更に、派生技術を分離しオプスウェア社を設立し、事業売却。一連の激動の中、幾度となく倒産の淵をさまよったベン・ホロウィッツの苦闘の物語が赤裸々に語られています。
本書の翻訳者が、あとがきで以下の通り壮絶な内容を要約しています。
ホロウィッツが詳しく語る危機のエピソードはすさまじい。会社が軌道に乗った直後にバブルが破裂し、資金があと3カ月で底をつくことが判明する。全売上の9割を依存している相手から突如契約解除を通告される。信頼していた会計事務所に買収交渉の土壇場で裏切られる。経営者なら一生に一度でも経験したくない悪夢のような事態が連続する。いったいこの窮地をどう乗り切るのだろうと読むほうも思わず手に汗握ってしまう。
著者も、本書の冒頭で、マネジメント本を読むたびに、本当に難しいのはそこではないと感じていたと以下の通り語っています。
本当に難しいのは、大きく大胆な目標を設定することではない。本当に難しいのは、大きな目標を達成しそこなったときに社員をレイオフすることだ。本当に難しいのは、優秀な人々を採用することではない。本当に難しいのは、その優秀な人々が既得権にあぐらをかいて、不当な要求をし始めたときに対処することだ。本当に難しいのは、会社の組織をデザインすることではない。本当に難しいのは、そうして組織をデザインした会社で人々を意思疎通させることだ。本当に難しいのは、大きく夢見ることではない。その夢が悪夢に変わり、冷や汗を流しながら深夜に目覚めるときが本当につらいのだ。
成功するCEOの秘訣は何かという頻繁に聞かれる質問に対しては、以下の通り解説しています。
残念ながら、秘訣はない。ただし、際立ったスキルがひとつあるとすれば、良い手がないときに集中して最善の手を打つ能力だ。逃げたり死んだりしてしまいたいと思う瞬間こそ、CEOとして最大の違いを見せられるときである。
そして、この様に助言します。
多くの経営書は、物事を正しく処理して失敗しないために何をすべきかに焦点を絞るが、ここでは大失敗したあとに何をすべきかについて考えよう。良いニュースは、私自身もほかのCEOも、大失敗の経験を豊富に持っていることだ。
更に、自身の実体験を踏まえ、以下の様に語ります。
どの起業家も、成功への明快なビジョンを持って会社を立ち上げる。驚くような環境をつくり、もっとも優秀な人材を集めてくる。力を合わせて顧客を喜ばせ、世界をほんの少しだけ良くするすばらしい製品をつくる。どこから見ても最高だ。 そして、ビジョンを現実にするために昼夜を問わず働き、ある朝目覚めると、物事が計画通りに進んでいないことに気づく。
製品は、非常に修正しにくい困難な問題を抱えている。市場は、本来あるべき状態になっていない。自信を失い、辞める社員もいる。辞めた社員のうちの何人かは非常に賢い人なので、残った社員は居残る意味があるのか疑問を抱き始める。現金は底をつき始め、ベンチャーキャピタリストは、迫り来る経済不況の中、資金調達は困難だとあなたに言う。ライバルとの戦いに敗れる。上得意の顧客を失う。卓越した社員を失う。八方塞がりだ。どこで間違えたのだろうか。なぜ会社は思い通り動かないのだろう。自分には経営能力があるのだろうか。夢が悪夢へと変わり、あなたは苦闘の中にいる。
そこで、カール・マルクスの名言が引用されます。人生は苦闘だ。
続けて、著者が実際に体験した苦闘が、これでもかと列挙されます。
苦闘とは、そもそもなぜ会社を始めたのだろうと思うこと。苦闘とは、辞めないのかと聞かれ、その答えを自分もわからないこと。苦闘とは、社員があなたはウソをついていると思い、あなたも彼らがたぶん正しいと思うこと。
苦闘とは、料理の味がわからなくなること。苦闘とは、自分自身がCEOであるべきだと思えないこと。苦闘とは、自分の能力を超えた状況だとわかっていながら、代わりが誰もいないこと。苦闘とは、全員があなたをろくでなしだと思っているのに、誰もあなたをクビにしないこと。苦闘とは、自信喪失が自己嫌悪に変わること。
苦闘とは、苦しい話ばかり聞こえて、会話していても相手の声が聞こえないこと。苦闘とは、不幸である。苦闘とは、気晴らしのために休暇を取って、前より落ち込んでしまうこと。苦闘と多くの人たちに囲まれているがら孤独なこと。苦闘は無慈悲である。
苦闘とは破られた約束と壊れた夢がいっぱいの地。苦闘とは冷汗である。苦闘とは、はらわたが煮えくり返りすぎて血を吐きそうになること。苦闘は失敗ではないが、失敗を起こさせる。特にあなたが弱っているときはそうだ。弱っているときは必ず。
これらの苦闘は、CEOである以上、避けられないものも多いが、つらい時に役立つかも知れない知識として、以下を紹介しています。
ひとりで背負い込まない。分けられる重荷はチームメンバーと分け合う。
打つ手は必ずあると信じる。単純なゲームではない。
長く戦っていれば、運をつかめるかも知れない。
被害者意識を持たない。CEOとは過ちを犯すものである。
良い手がないときに最善の手を打つ。
著者は、自身の経験を踏まえて、ありのまま伝える重要性についても語っています。
若きCEOとして、出資者の多額の資金を預かる身として、著者は日々プレッシャーに晒されていました。常に、プラスを強調し、マイナスを無視することで社員の士気を高めようと努めていました。ところが、実際は、従業員は現実がそれほどバラ色でないことを知りつつ、CEOである著者の話を聞き流していたのです。
ひとりで困難を抱え込むのではなく、正直に困難な状況を共有することで、社内の多くの頭脳を解決に向けて使える様になります。その中でも、特に信頼が重要であると解説しています。
信頼なくしてコミュニケーションは成り立たない。具体的にはこうだ。あらゆる人間のやりとりにおいて、必要なコミュニケーションの量は、信頼のレベルに反比例する。
次の状況を考えてみてほしい。私があなたを全面的に信頼していれば、あなたの行動について何の説明もコミュニケーションも必要ない。なぜなら、あなたがすることを私は、私にとって最大の利益を生むからだ。逆に私があなたをまったく信頼していなければ、いかなる会話、説明、推論も、私に何の影響も及ぼさない。なぜなら、あなたが真実を言っていると思っていないからだ。
会社という環境において、これは決定的に重要なポイントだ。会社が大きくなるにつれて、コミュニケーションは最大の課題になる。社員が基本的にCEOを信頼していれば、コミュニケーションの効率は圧倒的によい。物事をありのままに伝えることは、この信頼を築く上で決定的に重要である。時間と共にこの信頼を築くCEOの能力が、好調な会社と混沌とした会社を分ける。
本書では、更に以下の興味深いテーマについても生々しく語られています。これらについては、別記事でご紹介したいと思います。
人を正しく解雇する方法。
解雇の際、会社に残る人に対する配慮。
親友を降格させるときの対処方法。
友人の会社の従業員を引き抜く際の注意点。
組織設計のコツ。
社内政治がはびこる仕組み。
幹部が対立した際の解決方法。
平時のCEOと戦時のCEO。
困難に挑戦したが結果が残せなかった社員の評価方法。
会社売却時の判断基準。
■動画版は、こちら。
■本書で紹介されている解雇、降格、引き抜きの処方箋。
■本書で紹介されている教育、人事、社内政治に関する処方箋。
■併せて読みたい。
いいなと思ったら応援しよう!

