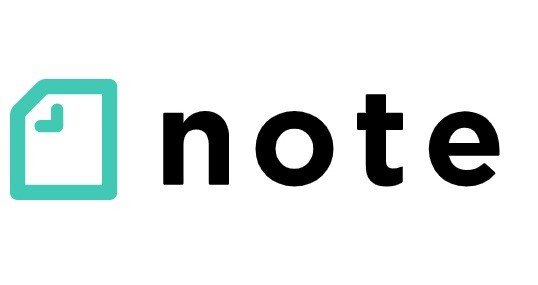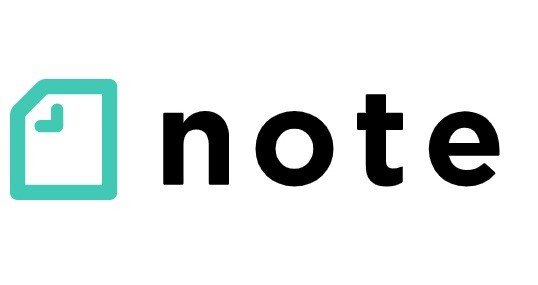虹の身体と光の脈管:仏教における身体の錬金術的変容
昨年末に『虹の身体』長沢哲(ビイング・ネット・プレス)という書籍が出版され、私にとって新たな知見があったので、改めて、「虹の身体(以下、虹身と表記)」に関する当稿をまとめます。
後期密教では、経典や宗派によって、様々な霊的身体を獲得したり、肉体を霊的身体に変容させたりすることが目指されました。
それは、現代に至るまで実践され、実際に実現されてきたようです。
中でも、「光の脈管」と表現される特別な脈管(ナーディ)を使って、肉体を虹の光のような「虹身(光身)」に変容させるゾク