
ねずみの嫁入り(5)嫁入り行列
今日は晴れやかな嫁入り行列の日です。肩衣をつけた宰領ねずみ、提灯ねずみ、長持を担ぐ奴ねずみたち。長持唄の歌声とともに、花嫁ねずみをのせた御駕籠が、壻方の待つ受け渡し場所へと進みます。
前回のお話はこちら ⇒「婚礼の準備(台所仕事)」
🐭


家紋は鶴の丸
なにがあるやら
ちいさいはこじやが おもたひ
(何があるやら)
(小さい箱じゃが重たい)
もうちつとだ
(もうちっとだ)
てうちんを まわして もらおう
(提灯をまわしてもらおう)

こんどの出物いり● おびたゞしい
(今度の出物入り● 夥しい)

ずいぶん ●● /\しの ●●
※ 文意を汲み取れないので、誤読しているかもしれません。

こんやは のんだり もらつたりだ
(今夜は呑んだり貰ったりだ)
あたまから しるわんでのむぞ
(あたまから汁椀で呑むぞ)

むだ口きくでない
(無駄口利くでない)
みなの取つぎませうぞ
(皆の取次ぎましょうぞ)


つう/\と まいりましよ
あとがつかへる
(つうつうと参りましょ)
(後が閊える)
それうたをかへるぞ
(それ唄を変えるぞ)
※ 「つうつう」は、意志や気心などが互いによく通じ合っていること。
※ 「唄」は、嫁入り行列で歌われる「長持唄」。youtubeなどで聞くことができるので、興味があったら検索してみてくださいね。👂

らうそくの しんを きりたいわ
(蝋燭の芯を切りたいわ)
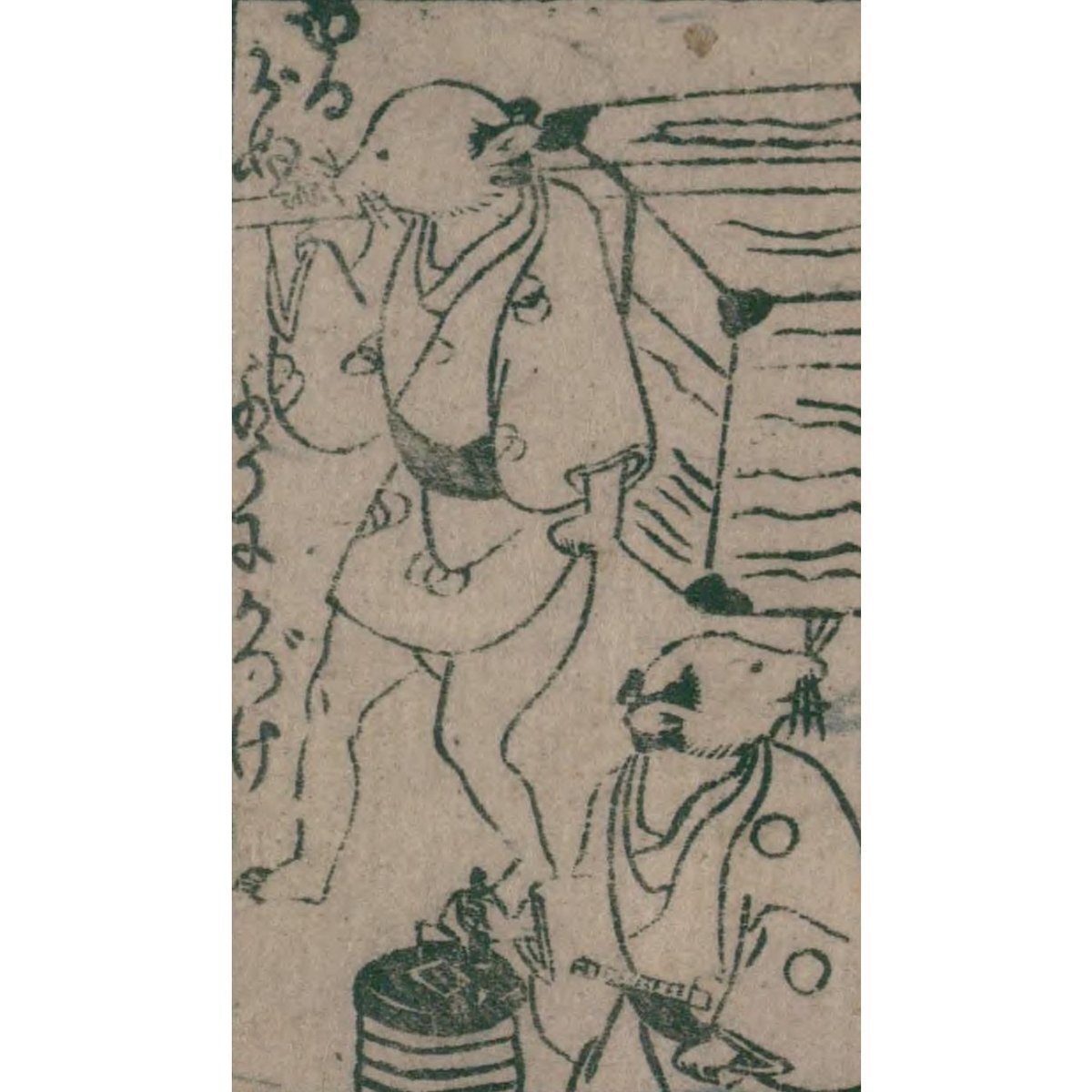
ゆるがぬ ようにかつげ
(揺るがぬように担げ)

大きな ぶげんで ござります
(大きな分限で御座ります)
□□□□□□□ ござりますの
(□□□□□□□ 御座りますの)
※ 「分限」は、持っている身分、財力があること。分限。
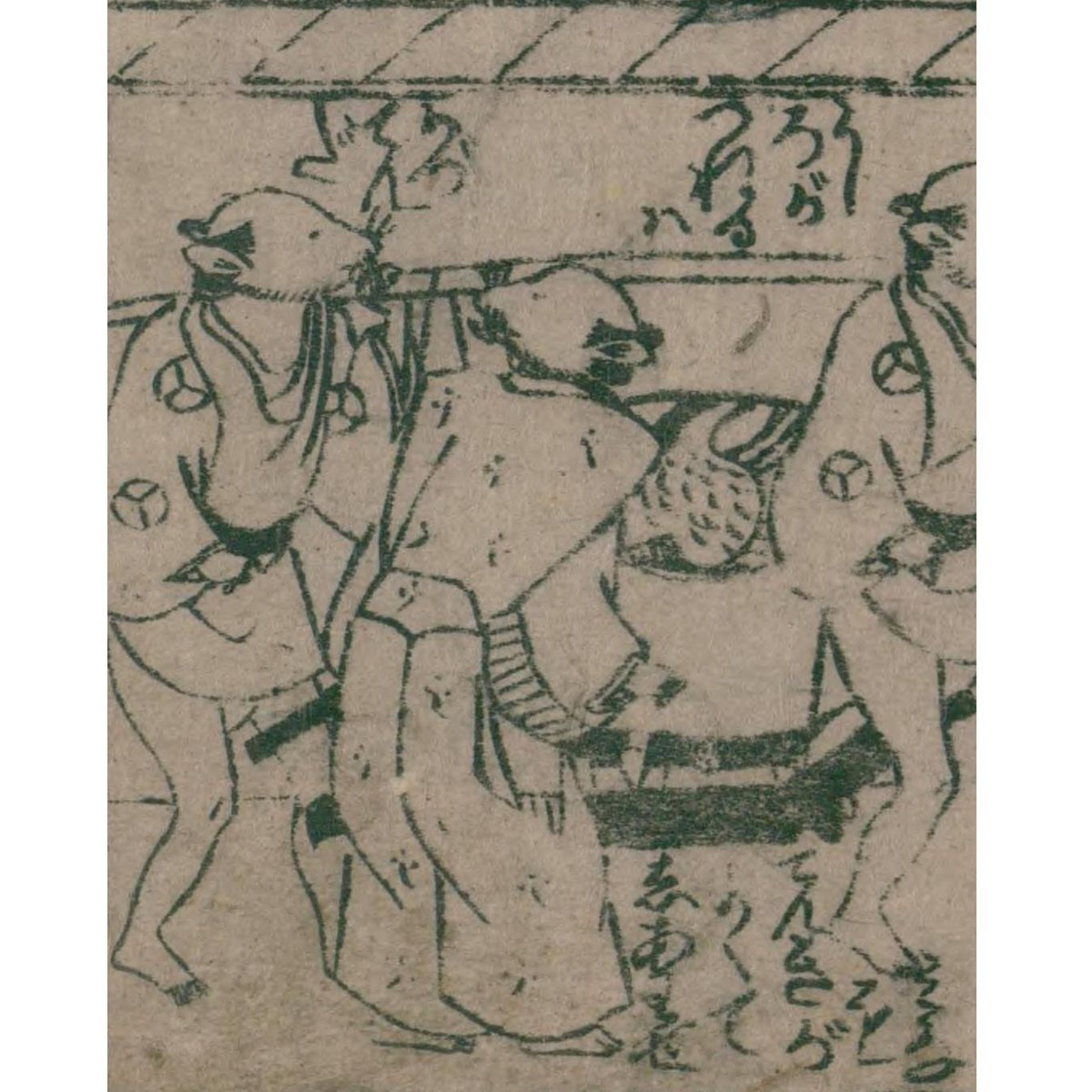
うしろが つれるは
(後ろが連れるは)
がつてんだ
(合点だ)
●●●● てんきがよくて しあわせ
(●●●● 天気が良くて幸せ)


こんやの こしうぎは
大かた またぎづくれる どこかな
(今夜の御祝儀は)
(大かた 叉木作れる どこかな)
※ 「|叉木《またぎ」は、長提灯をひっかける腕木のこと。
※ 文意がくみ取れないので、誤読しているかもしれません…。

そんなに きくなよ
(そんなに聞くなよ)
もらう事ばかりいふな
(貰う事ばかり言うな)
よをふかしたる
あすはねむたかろう
(夜を更かしたる)
(明日は眠たかろう)

これほどの どうぐの ●●●●は
さき□□ 大きな□□□□□□
(これ程の道具●●●●はさき□□大きな□□□□□□)

おみをくりで あとがにぎやかな
(お見送りで 後が賑やかな)

あなたの内は さぞ 御にぎやかだろう
(あなたの内はさぞ御賑やかだろう)
ほうぐみ いつたら のもふぞ
(棒組行ったら呑もうぞ)
※ 「内」は、ここでは家のことと思われます。
※ 「棒組」は、ひとつの駕籠をいっしょに担ぐ相手のこと。

ばんには さけを ひかへさっしやい
(晩には酒を控えさつしやい)
いや此ごろに あたります
(いや此ごろに あたります)

有て恵の作事
(有て恵の作事)
ばんには たはいに しつほりとた
(晩にはたわいにしっぽりとだ)
※ 「有て恵の作事」は、誤読しているかもしれません。
※ 「たわい」は、「酒たわい」の略と思われます。酩酊すること。
※ 「しつほり」は、しっぽりで、しみじみという意味でしょうか。

受け取り渡しの場所に到着しました
みな/\ むかい □ まいりました
(皆々 迎い □ 参りました)
いづれも ごたいぎ様にござります
(いずれも 御大儀様に御座ります)
すなはち 是にて おうけ取申しませう
(すなわち是にてお受け取り申しましょう)
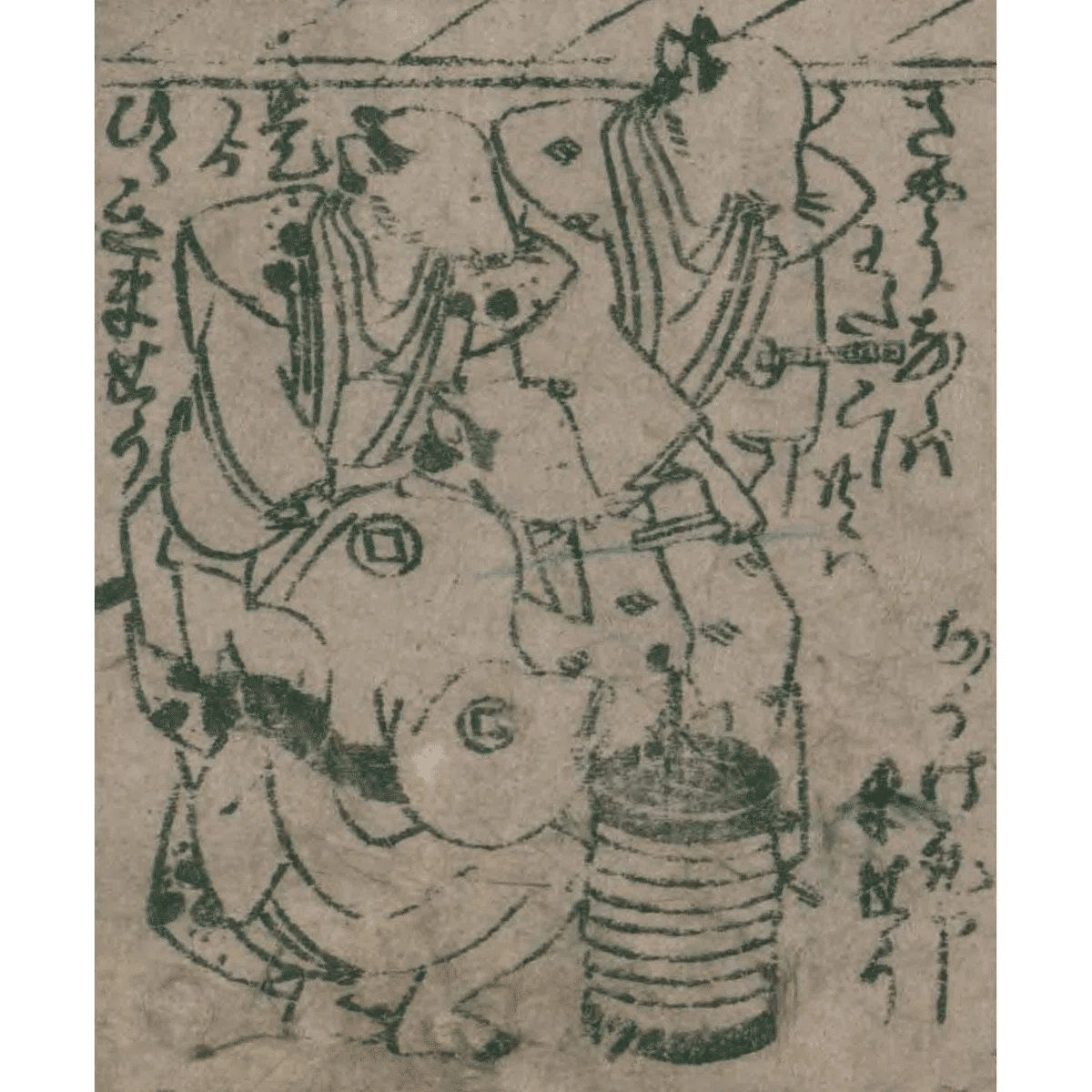
壻方が本宿(新郎宅)まで運びます
さやうならば わたくし共ゝに
是よりひらきませう
(左様ならば私共々に 是よりひらきましょう)


さきのやつこをみよ よろ/\しをるは
(先の奴を見よ ヨロヨロし居るは)

わいらもさけをひかへろ
(私らも酒を控えろ)
こゝろへました
(心得ました)

となるゝ ●●い といふ事は あるまい
よいき □□ だ
※ 文意を汲み取れないので、誤読しているかもしれません。

これ/\ ぶれひのないように
(これこれ 無礼のないように)

おれはさけにはよわぬ
(俺は酒には酔わぬ)
なんのぶれひ
(何の無礼)
こんれいのどうぐも 三とかつぐものだ
(婚礼の道具も三斗担ぐものだ)
ごもんさきだ 何もいわるゝな
(御門先だ 何も言わるるな)
※ 「三と」は、三斗と思われます。斗は尺貫法における体積の単位で、一斗は約18リットル。三斗で54リットル。

あの やつこが うらやましゐ
(あの奴が羨ましい)

もふ 五ツすぎで ござります
(もう五ツ過ぎで御座ります)
※ 「五ツ」は、江戸時代の時刻の数え方で、午前八時頃。

口をきゝますまい
(口を利きますまい)

もんまでかきいれやう しずかに
(門まで舁き入れよう 静かに)
五 ● かたよ
こんやへ おられ●●●
※ 文意を読み取れないので、誤読しているかもしれません。

うけとりわたしは もはやすみました
(受け取り渡しは もはや済みました)
よめごは くわほうな人だ
よい男をもたれました
(嫁御は果報な人だ 良い男を持たれました)
ふたりのしうとたちも 心よしなり
(二人の 舅達も 心良しなり)
※ 「心良し」は、気立てのよいこと。
続きのお話はこちら ⇒「婚礼の儀」
筆者注 ●は解読できなかった文字、□は欠字を意味しています。
新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖
