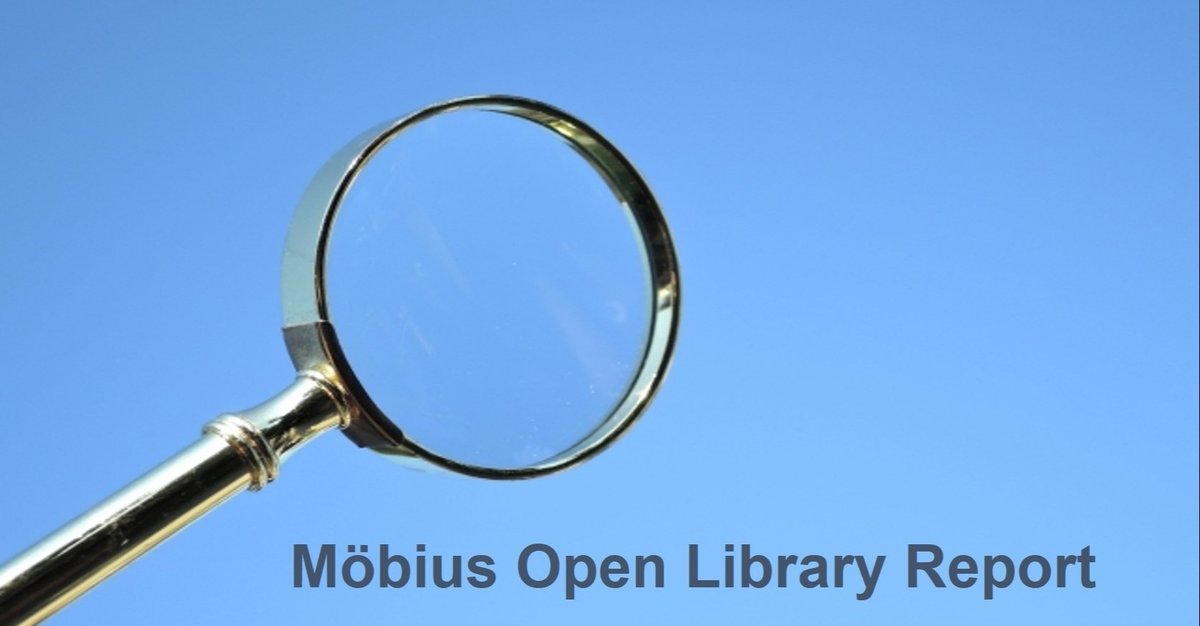
図書館の検索とブラウジングについて考える【Möbius Open Library Report Vol.10】
Möbius Open Library(メビウス・オープン・ライブラリー:略称MOL)では、「学芸大デジタル書架ギャラリー」というウェブサイトで、東京学芸大学図書館で所蔵する2万冊近くの教育分野の本棚をブラウジングできるようにしています。一方で、私(ななたん)は、この夏、「学校図書館の検索のイマ!」というテーマで、学校司書講座を企画しました。検索とブラウジングという本を探す方法について、MOLのコンセプトマップに位置づけておきたいと思います。
学校図書館の検索のイマ!
東京学芸大学附属図書館は、東京学芸大学学校図書館運営専門委員会司書部会と共催で、2020年8月1日に「みんなで学ぼう!学校司書講座 2020オンライン研修<学校図書館の検索のイマ!>」を開催しました。全国の図書館検索サイトを運営しているカーリルから吉本龍司さんを講師としてお迎えして、学校図書館支援プログラムの事業について紹介してもらいました。コロナ禍で全国の学校が休校となる中、学校図書館の本の検索だけでも自宅からできるように、簡易OPAC検索システムを構築する事業です。あわせて、附属世田谷中学校司書の村上恭子さんとの対談方式で、学校図書館での検索の活用や図書館間の連携について話題提供を行いました。
大学図書館で勤務している私(ななたん)は総合司会だったのですが、実のところ、企画段階で「学校図書館にはOPACが無かった!」という事実にむしろ驚き、学校図書館でもOPAC検索が当たり前になればいいのになぁと考えました。児童・生徒にとっても、学校の先生にとっても、そして学校図書館で働く学校司書にとっても、図書館にはどんな本があるのかを簡単に調べられることは大事なことだと思ったからです。そこで、カーリルさんから、現在(イマ)の技術でも簡単にOPAC検索は実現でき、連携もできるということを講演してもらい、その意味で「検索のイマ!」というタイトルでのディスカッションをすることにしました。当日のスライドは学校図書館活用データベースのサイトから公開されています。参加者した学校司書の方々からは次のような感想が寄せられました。
・コロナ禍でも子どもたちの学びを止めないために、学校図書館に何ができるか、考えさせられました。
・(OPACができて)生徒たちが非常に喜んでいた。
・普段は学校図書館に来てもらえばよいと思っていたが、休校中だけでなく自由に図書館が使えない分散登校中もとても助かった。
・ICT化、一人一台タブレットを来年度から導入予定なので、図書館の検索機だけでなく、児童が自分のタブレットから検索できるようになれば、今まで手に届いていなかった本が動くような気がしました。
・学校図書館を活用できる可能性がどんどん広がっていくようで大変興味深い。
この研修会を機に、各地の学校図書館でOPAC検索のインターネット公開が広がってくることを期待しています。学芸大でも附属学校でのOPAC公開と連携を進め、学芸大総合OPACを作っていきたいと準備しています。
大学図書館の検索のイマ?
一方、大学図書館でのOPAC検索はどうなっているのでしょうか。その歴史は日本では1980年代まで遡ります。まず、大学図書館業務の機械化が始まり、学術情報センター(現在の国立情報学研究所)が運営するNACSIS-CATという全国共通の図書目録所在情報システムが整備されました。その後、インターネットの発達とともに、各大学で蔵書目録つまりOPACの公開が進みます。全国の大学図書館が統合して検索できるWebcatも1997年に試行サービスが開始され、現在ではCiNii Booksに継承されています。(余談ですが、2011年11月のCiNii Booksリリースには、ななたんもメンバーとして開発に関わっています。)
つまり、大学図書館にとっては、いまやOPAC検索はすっかり当たり前のサービスであり、東京学芸大学の図書館の場合、年間のOPAC検索回数は約42万件(月平均約3.5万件)です。しかし、この春の臨時閉館中は月に1.5~2万件に減少し、郵送貸出・事前予約貸出を再開しても回復しません。そこで、OPAC検索だけでは本を探すことができないのではないかと考え、書架のブラウジングを提供する「学芸大デジタル書架ギャラリー」を開発した話は以前(Vol.8)でレポートしました。大学図書館にとっては、検索はイマ!ではなくて、「検索の明日(未来)」を考える時期にきているのかもしれません。
「情報行動」という研究分野
「学校図書館では検索が必要だ!」と旗を振りながら、「大学図書館では検索には限界があるのでブラウジングを提供しよう!」と相反することを言っているようにも見えますので、これを整理しておきたいと考えました。検索とブラウジング、これは図書館情報学の中ではどのような位置づけになっているのでしょうか。
調べ始めてみると、「情報検索」に関する本は山のようにあるのですが、検索システムや検索手法あるいはお薦めの情報資源に関するものが多く、ななたんの関心に合うような本がなかなかみつかりません。そんな時、知り合いの専門家の先生から「情報検索」よりも「情報探索行動」や、さらに広げて「情報行動」という研究分野をみたほうがよいとアドバイスをいただきました。いずれも非常に分厚い研究蓄積のある分野です。日本語で読めるものとして、参考になった本を上げておきます。
【情報行動についての参考図書】
・図書館情報学概論 / デビッド・ボーデン, リン・ロビンソン著 ; 塩崎亮訳. -- 東京 : 勁草書房 , 2019.8. -- xvii, 424p : 挿図 ; 22cm. 監訳: 田村俊作 -- ISBN 9784326000463 ; https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB28784473 第9章「情報行動」
・情報行動 : システム志向から利用者志向へ / 三輪眞木子著. -- 東京 : 勉誠出版 , 2012.3. -- 205p ; 19cm. -- (ネットワーク時代の図書館情報学). -- ISBN 9784585054320 ; https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB08800828
・情報探索と情報利用 / 田村俊作編. -- 東京 : 勁草書房 , 2001.7. -- vii, 282p ; 22cm. -- (図書館・情報学シリーズ / 津田良成編 ; 2). -- ISBN 9784326048014 ; https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA52828443
【そのほかの関連図書】
・情報検索の認知的転回 : 情報捜索と情報検索の統合 / Peter Ingwersen, Kalervo Järvelin [著] ; 細野公男, 緑川信之, 岸田和明共訳. -- 東京 : 丸善 , 2008.2. -- ix, 316p : 挿図 ; 21cm. -- ISBN 9784621079454 ; https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA84827666
・情報検索演習 / 原田智子編. -- 三訂. -- 東京 : 樹村房 , 2006.10. -- xiv, 203p : 挿図 ; 21cm. -- (新・図書館学シリーズ ; 6). -- ISBN 9784883671311 ; https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA79414612
・情報検索の考え方 / 緑川信之著. -- 東京 : 勉誠出版 , 1999.10. -- 158p ; 19cm. -- (図書館・情報メディア双書 ; 6). -- ISBN 4585002162; https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA43516461
・情報検索研究 : 認知的アプローチ / P. イングベルセン著 ; 細野公男, 後藤智範, 岸田和明訳. -- 東京 : トッパン , 1995.2. -- xiv, 378p ; 21cm. -- 監訳: 藤原鎮男. -- ISBN 4810189171 ; https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN12209619
・情報検索論 : 認知的アプローチへの展望 / David Ellis著 ; 細野公男監訳 ; 斎藤泰則, 鈴木志元, 村上泰子訳. -- 東京 : 丸善 , 1994.10. -- viii, 180p ; 21cm. -- ISBN 4621040081 ; https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN11508385
・検索の新地平 : 集める、探す、見つける、眺める / 高野明彦監修. -- [東京] : KADOKAWA , 2015.4. -- 250p : 挿図 ; 21cm. -- (角川インターネット講座 ; 08). -- ISBN 9784046538888 ; https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB18528058
・サーチアーキテクチャ : 「さがす」の情報科学 / 吉川日出行編著. -- 東京 : ソフトバンククリエイティブ , 2007.10. -- vii, 271p : 挿図 ; 21cm. -- ISBN 9784797341034 ; https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA83535596
簡単にまとめると、まず、この分野の第一人者ウィルソン氏がいくつかの概念モデルを提示しています。その中で、「情報探索行動」の中に「情報検索」があり、それは情報システム内に存在する情報を探す行為とされていました。情報探索行動のプロセスをモデル化したエリス氏とウィルソン氏は、情報探索を開始してから、関心領域に目を通すブラウジング、参照論文や引用をたどる連鎖、定期的に情報源をチェックする監視という行動の後、情報を選別する差異化・抽出・確認を経て終了するという行動パターンに整理をしています。さらに、ウィルソンの拡張モデルでは、情報探索行動は受動的注意、受動的探求。能動的探求、継続的探求の4種類に区別されていました。
情報探索行動の研究では主として能動的に情報を探す行動に焦点をあていますが、自分でも明確にできないものを求めていて、偶然に情報を発見することもあります。それは「偶然の情報獲得」は「情報遭遇」とも呼ばれていました。エルデレス氏とウィリアムソン氏によって、ブラウジングのプロセスもモデル化されています。
本当に数多くの研究成果がありますので、まだ十分に消化できていませんが、MOLの活動のためのヒントがたくさんありそうです。
知の「提供」と「吸収」を考える
さて、メビウスのコンセプトマップは、このレポートでも初回に取り上げました。左側の図書館の活動「知の収集→整理→保存→提供」と右側の学びの活動「知の吸収→活用→創出→発信」がつながって、無限に知が循環する図になっています。

このコンセプトマップに、検索とブラウジングを位置づけたいと考えました。「情報探索行動」の概念モデルをたくさん勉強したななたんは、「吸収」を「獲得」に変更したほうがいいのでは?とMOLメンバーに持ちかけてみました。図書館が「提供」した知がそのまま「吸収」されると考えよりは、学びの側から「獲得」してもらうと考えたほうがよいのではとも思いました。ところが、ケンケンとフジムーから帰ってきた答えは以下のような感じです。
・「吸収」外のものを内側に取り込み、自分のものとすること。
「獲得」努力して手に入れて、自分のものとすること。
だとすると、自分の外部になるものと接して取り入れる、マージナルな場での営みという意味合いは「吸収」のほうが強い。「獲得」に付随する努力のような頑張る的な姿勢は必須ではない。
・偶然の出会い、というのもあると思うので、積極的に探すだけではないが、出会いを素通りしない「開いた」感じを表現したほうがいい。「吸収しようという姿勢」は大切。
・「獲得」と言ってしまうと、ある程度体系的な知識を頭の中に構築してから活用する、という旧来の教育観を連想する。
・「受容」という言葉もいいが、受け入れるという受動的なニュアンスが強く、「吸収」は吸い取るという能動性も含まれる。
そんな意見を交換しながら、「探す」という行動に囚われ過ぎていたのかなと思いなおしました。検索とブラウジングを学びの円環のほうに位置付けるのではなくて、図書館の円環の「提供」の方法と考え直すと、探している人に効率的に提供する(=検索)のと、探してるわけではない人に知的な刺激として提供する(=ブラウジング)ということができます。差し出された知を受け止め、自分のものとできるかどうかが学びの輪の出発点となります。自分の外部になるものと接して、探していたのであれ、偶然であれ、主体的に取り入れる姿勢をあらわす「吸収」という言葉が、結局のところ、一番良い言葉だという結論となりました。
というわけで、図書館を活用した知の循環を促すには、検索もブラウジングも大事です。11月から始まる第22回図書館総合展ONLINEではMOLメンバーは「学校図書館の検索のイマ!(パート2)」(11月5日10:30-12:00)と「コロナ禍での学芸大デジタル書架ギャラリーの取組み紹介と図書館ミニツアー」(11月6日13:00-13:50)、そして、「図書館と知の循環~これからの学びのなかで学校図書館が担うもの~」(11月14日14:00-15:30)に登場します。お楽しみに。(文責:ななたん)
【これまでのMOL Report】
No.1 Explaygroundと図書館の出会い
No.2 PechaKucha from 3 Booksに至る道のり
No.3 PechaKucha from 3 Booksという「遊び」
No.4 「朝読書ルーム」オンラインに図書館的な読書空間を作る試み
No.5 「朝読書ルーム」ふたたび
No.6 知の創出・発信を試行錯誤する
No.7 MOLの活動はコロナによってどう変化したのか
No.8 デジタル書架ギャラリー 図書館のブラウジング体験をオンラインに
No.9 詩をよむ日
【Explayground URL】 https://explayground.com/
