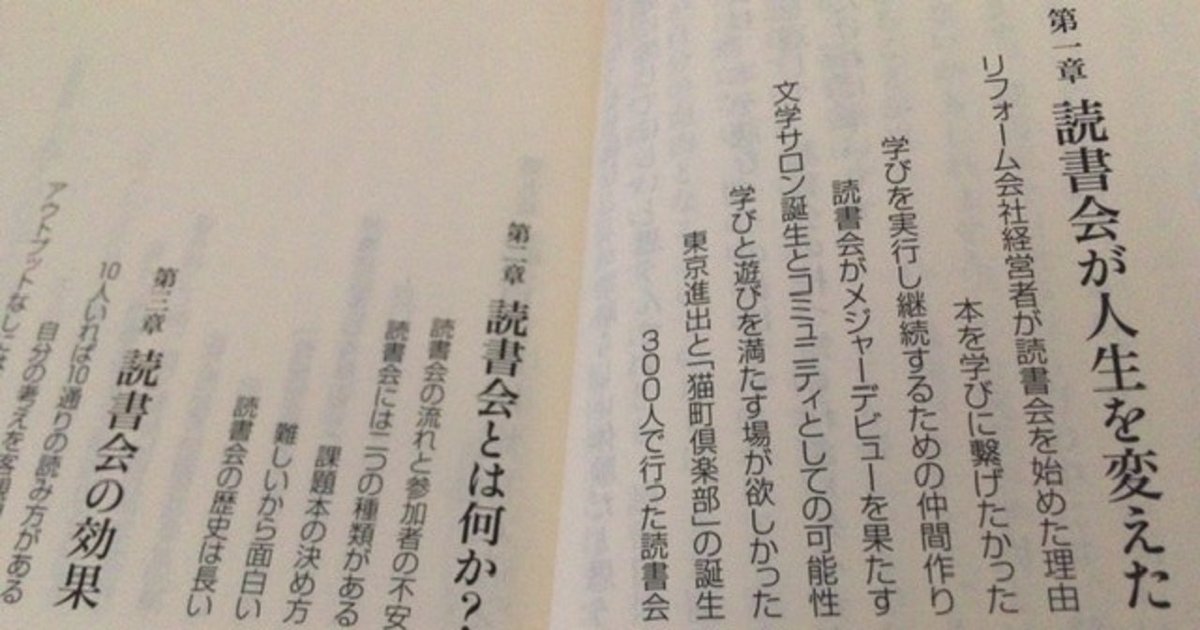
サブカル大蔵経287山本多津也『読書会入門』(幻冬舎新書)
読書界に怪人現る。
音楽評論家・柳樂光隆「猫町倶楽部の読書会に来ると、僕らが忘れがちなジャンルとか情報とかじゃない、もっと本質的な話を知的好奇心からまっすぐに楽しむ人の存在に気づかされる。」p.159
こう紹介される〈読書会〉「猫町倶楽部」主催のタツヤさんこと山本多津也氏。
生きると言う事は、人生に問われ続けると言う事。p.163
山本さんは、頭の中だけでなく、実際に主催者として運営にたずさわり、ハプニングやトラブルを体験した上で、純粋に本の可能性を信じている。だから説得力が凄い。
お寺でも輪読会はじめました。
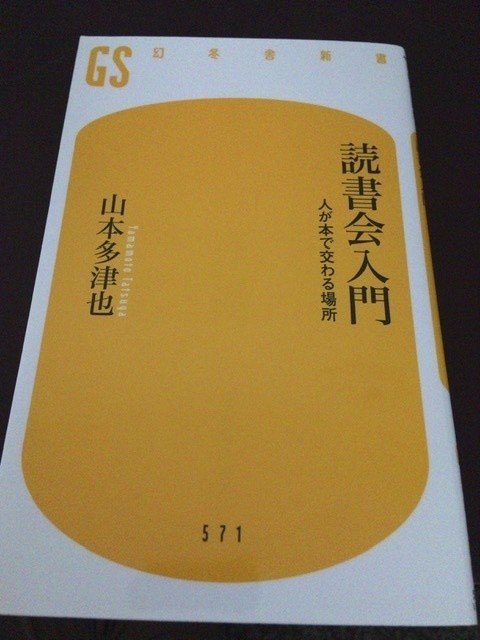
同じ本を読んだのにこんなにもそれぞれ抱く感想が違うものかと驚くでしょう。p.7
たしかに、他の人の話聞いてみたい。でも、その場で発言できるものなのか…。
通常、参加者の6〜8人で1つのグループを作りそこに必ず1人ファシリテーターと呼ばれる司会役を立てます。p.34
本願寺派がとりくむ〈連続研修会〉みたいですね。読書会は〈連研〉なのかぁ。それは印象深いこと、楽しいこと、修羅場、いろんなことがあるでしょうね。
彼女の感想が間違っているわけではありません。私の感想だって間違っているわけではありません。p.53
連研だと思うと、もう20年以上関わっているからこの映像が浮かび上がってくる。語り合い、聞き合い、否定しない。
読書でグレーに留まる力を養う。p.58
私も幅広く読んでグレーだったつもりなんですけどまだ読み足りないのか、偏った地金が出ちゃうばかりです。
気軽に本の世界に触れることができればいいと思うし、そのために読書のハードルを下げたいと考えています。p.74
寺院で、これができたらなぁ。
読書によるインプットと読書会によるアウトプット。けれども、論理的思考だけで世界を把握した気になってはいけないと私は思うのです。p.83
この視点と背景が単なるオタクではないし、理想主義な運動家でもない。論理で人は動かない。
良質なノイズとは、えてして家の外にあるものだと私は思うのてす。(中略)読書会はまさに、自分にノイズを取り入れることのできる場所なのです。p.95
ノイズは騒音かもしれないが、聞いていくと貴重なごちそうになるかも。
つまり私は、読書会を長く続けていくためには、決して尊敬される立場にあってはいけないのだということなんです。/導き出した答えが、"飲み会の幹事"でした。飲み会の幹事はみんなに必要とされ、重宝がられこそすれ、大して尊敬されはしません。しかし尊敬されないからこそ、誰かにその地位を脅かされることもありません。p.128
リーダー論のひとつの名言ですね。
ネットを議論の場にしない。メラビアンの法則。聴覚から38%、視覚から55%、話の内容から7%しか受け取っていない。p.135
今日、看護学校の授業でこれを話してきました。
最終的に私は彼を除名しないことに決めました。追い出してまで猫町倶楽部を続けたいかと考えた時、それなら続ける価値がないと思ったからです。p.140
これだけ濃密ならこういったドラマあっても不思議じゃないですが、すごい判断です。会より人を選択し、排除するなら会の存在意義がない、会をやめることも厭わない。という、この覚悟は私が連研のスタッフだった時にはなかったです。
猫町倶楽部を気に入ってくれたのはとても嬉しいことなんですが、外の人と話したくなくなってしまうというのはちょっとまずいな、と思ったんです。p.148
これも連研イズムだなぁ。この本、連研の参考書になると思います。
私達は何をもって本を「読んだ」と言えるんでしょう。/普通に考えると、生まれてから今まで全く違う場所で、全く違う経験を積んできた著者の意図を、他人てある自分が完璧に理解するなどということは、とてもできそうにありません。と考えてみると、実は「読んだ」と思っている本も「読み切れている」と言うには遠く及ばず、「読んでいない」とそう違わないのではないか、というのがバイヤールの考えなんです。p.154
バイヤールの本読んでみようと思い、今ポチりました。前から気になってたのですが、今Amazon見たら文庫化してましたた!(ちくま学芸文庫)
だからこそ、作家さんや編集者さん、営業さんなど本を作ること、売ることを生業とされている方に、もっともっと読書会に参加してほしいと思うんです。なぜなら多くの読者は、本を作ること、売ることと無関係なところで生活しています。彼らが1冊の本をどう読み、何を感じ、考えているかをぜひ読書会で知ってほしいと思うんです。p.158
作家でも出版社でも書店員でもマスコミでもファンでもない立場。これは得難い。
いいなと思ったら応援しよう!

