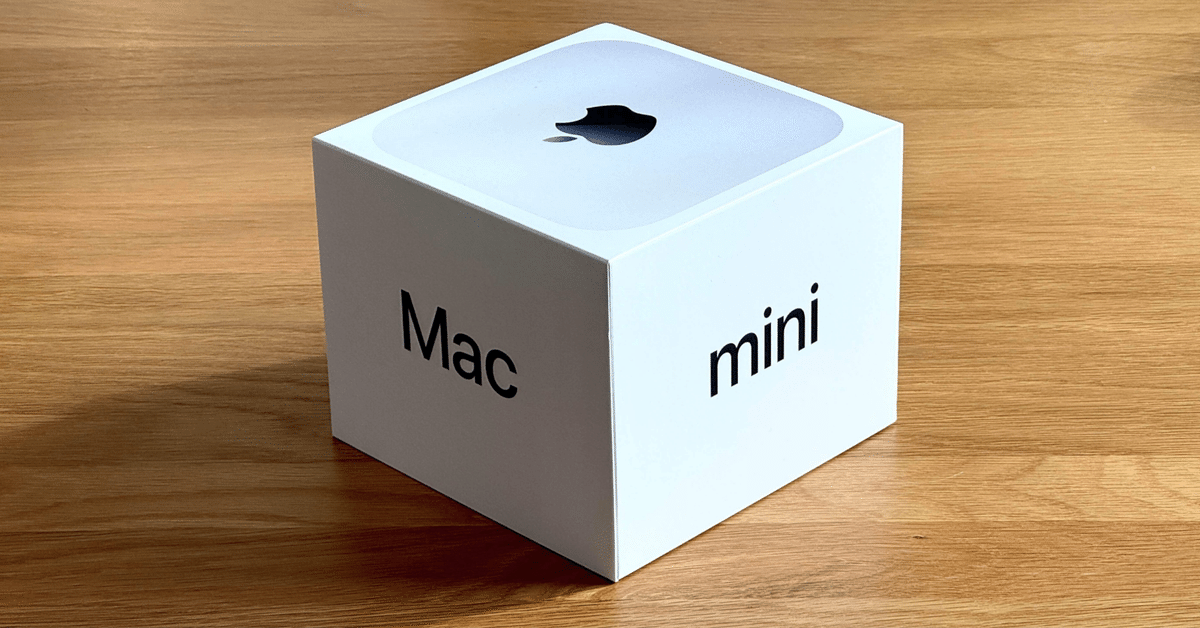
【2025最新版】M4 Mac miniをゲーミングPC運用するための情報まとめ【令和最新版】
Apple Siliconが登場してついに4世代目、M4搭載のMacBookとMac miniが発売されて1ヶ月ぐらい経ちました。
今回の目玉はやっぱりMac miniだと思っていて、最安値モデルは10万円を切る安さでありながら非常に高性能。新しい筐体のコンパクトさも話題性に一役買っていますね。
M4 Mac miniに夢を感じで購入したのですが、今まで持っていたM1 MacBook Airと比べるとパワーアップが想像以上で感動しています。
私はRTX4060Ti搭載のWindowsPCを持っているのですが、もはや私がプレイするようなゲームのレベルではM4 Macだけでやっていけると確信したのでWindowsPCは売ることを決断したぐらいです。
今回はいろんな方法でM4 Mac miniでゲームをプレイしてみたいと思います。
はじめに
大手ゲームであればこのサイトでどの方法が一番快適に動きそうか目星をつけてから試すのがいいですね。
主にApple Silicon Macでゲームをプレイする方法は5通りあります。
基本的に上のほうが快適&安定してプレイできる方法になります。
Mac向けNativeアプリをそのまま動かす
iPhone / iPad向けNativeアプリをPlayCoverで動かす
Intel Mac向けアプリをRosetta2で動かす
Windows向けアプリをWineで動かす
Windows向けアプリをParallels Desktop上で動かす
順番に解説します。
Mac向けNativeアプリをそのまま動かす
これは名前の通りで、App StoreとかSteamで普通に売ってるゲームをそのまま動かすというやつですね。

Apple Silicon Macで動くように作られていて、販売されているゲームなので動かないことはほぼありません。
SteamではMac向けとなっていても、Intel Mac向け(Rosetta2)のやつもあるのでそれはよく調べてください。
iPhone / iPad向けNativeアプリをPlayCoverで動かす
iPhone / iPadとMacのプロセッサはほとんど違いがありません。
なのでiOS(iPhone / iPad)向けに作られているアプリは端末固有の互換性さえ問題なければMacで動きます。
なのでiOSアプリをMacで動かすのはコンバーターが挟まらないため非常に良い選択肢です。そしてそれを実現できるアプリがPlayCoverです。
アプリのインストールファイル(IPA)を用意すれば簡単にアプリのインストールができます。
IPAファイルはDecryptされたものでないとMacでインストールできないので、https://decrypt.dayなんかでダウンロードするのが一般的です。
この手法で遊べるのはスマホ専用だったりマルチプラットフォームなゲームとかですね。原神なんかのmiHoYoゲームを遊びたい方には最適な方法ですし、WindowsPCでAndroidエミュレータを使ってスマホゲーを遊んでた方にもぴったりかと思います。
大体のゲームは問題なく起動しますし、最適化もバッチリなのでM4では非常に快適に遊べます。

M4 Mac miniでは原神を全部設定最高にしても4Kで100~144FPSで安定してプレイ可能です。またMac miniの冷却性能が優秀なので長時間プレイしていてもMacBook AirとかiPadと比べてフレームレートが安定しているのもメリットですね。
ちなみに普通は内蔵SSDに保存されてしまうゲームのアップデータを外部SSDに保存して内蔵SSDの容量を節約できる方法を書いた記事もあるので気になる方はぜひご覧ください。
Intel Mac向けアプリをRosetta2で動かす
MacがIntelだった時代からMac向けゲームというのは少ないですが存在していて、いまだにそういうゲームは残っています。そういうアプリはApple公式がサポートするRosetta 2というコンバーターで動いてくれます。
とはいえこれから新しくMac向けにゲームをリリースしてくるデベロッパーは基本的にはNativeで動くように作ってくると思うので、今後数は減っていくと思いますが息の長いゲームなんかはこのタイプで残り続けるでしょうね。

私はパラドゲーがそこそこ好きなんですが、例えばHoi4では設定いじれば4Kで60FPSぐらいなら安定するかなぁという感じです。
stellarisとかはもっと重いので大胆に設定落とさないときつそうですかね。
この手法のメリットはNativeアプリと同じで何も考えずインストールさえすれば簡単に動くという点ですね。ただ次に紹介する手法の方がフレームレートが向上する場合もあるかもしれません。
Windows向けアプリをWineで動かす
Wineって昔からあって色々とめんどくさいというイメージしかないんですが、最近は簡単に扱えるラッパーが色々あるんですね。
今一番HotなのはWhiskyというやつみたいです。
あとは有料ですがCrossOverも有名です。WhiskyとCrossOverの関係はいろいろややこしいようで、基本的には競合しないようWhiskyはCrossOverの下位互換を維持するらしいです。
手順は書きませんがWhisky&Steamはかなり簡単に導入できました(15分ぐらい)。
注意点としてSteamをインストールするタイミングではMacの言語設定を英語にしないと進まなくなるっていうところぐらいでしょうか。
DXVKにも対応していて、初期設定ではオフになっていますがオンにしたらかなりフレームレートが上がりました。

Windows専用ゲームの信長の野望 新生を遊んでみたのですが、4K速度優先では30FPS切るぐらい、WQHDでは60FPS安定していました。WQHDで60安定するなら全然実用的って感じですね。
ただDXVKオンでは一部の3Dオブジェクトがうまく表示されていなかったのですが、オフにしたら正常に表示されていました。
残念ながら先ほど試したHoi4はこの手法では動きませんでした。
Wineはいろいろ設定を変えたり有志のライブラリに差し替えるとか、何かしらの手順を踏めば動きますっていうのもあったりするんですが、いちいち調べるのは大変だしアプデで使えなくなったりすることも多いのでめんどくさいですね。
Windows向けアプリをParallels Desktopで動かす
この手法は割と最終手段ではあるのですが、お手軽さでいえばNativeに次ぐぐらい簡単です。ただ大前提としてParallels Desktopを買わないといけないので(1万円ぐらい)そこはデメリットでしょうか。
とはいえゲーム一切抜きでもParallels Desktopはめちゃ便利なのでMacユーザーはぜひ購入することをお勧めします。特にWindowsマシンを持っていない方は。
この手法では割といろんなゲームが動いていて、上でも試してみた原神・Hoi4・信長の野望は全部動きます。
ただしARM版Windowsをエミュレートして仮想GPUでDirectX11を動かすという流れを踏むので、かなり処理能力のロスが発生します。
Hoi4も信長の野望も4Kではまともにプレイできず、WQHDならまぁできなくはないって感じ、それでもかなり画質設定を下げてです。
なので基本的には軽いゲーム(昔の32bitアプリも結構動く)とかインディーズゲームとかを動かすのがメインになりますかね。
あとはM4 ProとかM4 Maxとかのスペックでゴリ押すっていう手もありますが・・・。
番外編:Android エミュでゲームをする
Windows PCではいろいろなAndroidエミュレーターがあって、ネットブラウジングの傍らソシャゲを周回してるという方もいるかと思います。
ただApple Siliconで使えるエミュは非常に少なくて、私が調べた限りはMuMuPlayer Proだけでした。
あとは開発用ですがAndroid StudioもApple Siliconで動きます。
まだベータ版で動かないゲームもあるようですが、無料で使えるBlueStacks Airというのも出ています。
基本的にはMuMuPlayerのほうが快適に使えると思いますが有料です。現在の価格設定は365日で72$なので約1万1千円ぐらいです。とてもですが安いとは思えないですね。
今後ほかのエミュが対応してくれると嬉しいですね。
Apple SiliconにはWindows PCでは(実質)不可能なiOSエミュレーターであるPlayCoverがあるので、まずはそちらで何とかならないか試したほうがいいと思います。
まとめ
ここまで試せば大半のゲームはプレイできるはずです。
とはいえコンバート系できついのアンチチートシステムが入ってるようなオンライン対戦ゲームですね。
アンチチートが起動を妨害したり、起動しても不正な動作としてBANされたりするリスクもあります。
私は今それ系のゲームを一切やっていないので気になりませんが、そういうゲームをメインに遊んでる方にはまだMacをゲーミングPCにするのは難しいのかな。
