
面白い本・好きな本|建築文学篇
とうとう東京2020オリンピックが開幕。
そして、無観客での開会式。
でも、ランダムな座席配色のおかげで、不思議と無観客であることが気にならない。
木漏れ日をイメージした5色のアースカラーのシートのおかげで、距離や明るさによっては賑わっているように見えてしまう。

競技場を設計したのは建築家・隈研吾。
昔から「地方」や「木材」や「日本的」といった時代のニーズを掴むのがとてもうまい方。
今回はそれが「コロナ」となる。
当然運もあると思うんだけど、それでもやっぱり、すごいなぁと開会式を見ながら関心してしまう。
か・かた・かたち
遡って、前回の東京1964オリンピックで選手村を設計した建築家・菊竹清訓は、当時「メタボリズム」という考えを提唱。
時代のニーズの変化に対応して、建築や都市も柔軟に変化する必要があるのでは?、というもの。
また、形(かたち)を一語ずつ分解して、「か」「かた」「かたち」の3つの言葉でデザイン論を展開する。
か:構想や本質
かた:典型や技術
かたち:形態や感覚
「か」から「かた」ができて「かたち」が生まれる、とのこと。
概念的すぎて頭にスッと入ってこない。。
と・とこ・ところ
文句を言うだけなら簡単なので、対案を無理矢理捻り出す。
と【戸】:戸をくぐり
とこ【床】:床につき
ところ【所】:拠り所ができる
戸をくぐり、床につき、拠り所ができる。
概念的すぎる「かたち」より、「ところ」の方が建築の本質をついているような気がするような、しないような。。
※※※
と、いうことで建築にまつわる文学作品を3つ選出。
1900年〜1950年〜2000年と出版年が約50年ピッチになったのは、たまたま。
五重塔/幸田露伴/1892
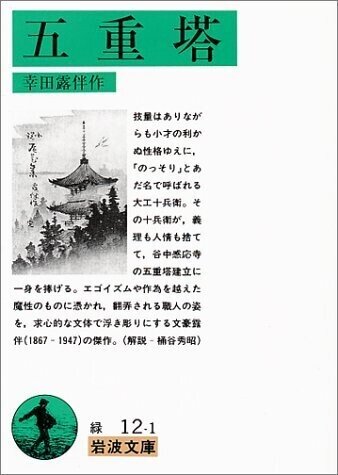
読みにくい文章だなぁと、思いつつも読み進めるともう止まらない。
あれだけ読みにくいと思った文章が、とてもリズミカルで心地よく感じてくる。
腕はあるが愚鈍な性格から世間から軽んじられる大工の十兵衛。
一生に一度あるかないかの大仕事、五重塔の設計施工。
なんとしてもその仕事をしたい、という強い思いで模型までつくってクライアントに見せて、親方から仕事を奪おうとする始末。
理解ある親方とクライアント。
図面を描いて、建物を実際に建てていく描写はとても臨場感があり、ものつくりの原点のような良書。
金閣寺/三島由紀夫/1956

言わずと知れた三島由紀夫の代表作。今回のテーマなら金字塔というべきか。
金閣寺の放火は実際にあった事件で、その1年前には、法隆寺も火災により国宝の壁画が焼失している。
最近でも沖縄の首里城が火災で焼失し、ノートルダム大聖堂やサグラダ・ファミリアも火災にあうほど、今日的な問題でもあるわけで。
刹那的な儚さや無常観に美を見出す日本の精神性〜、、というありきたりなコメントにはなるけど、やっぱりそんなことを考えさせられる小説でもある。
20年に一度、式年遷宮のある伊勢神宮は、強制的に消失と再生を繰り返すところが、やっぱりとても日本的だなぁと思ったり。
火山のふもとで/松家 仁之/2012
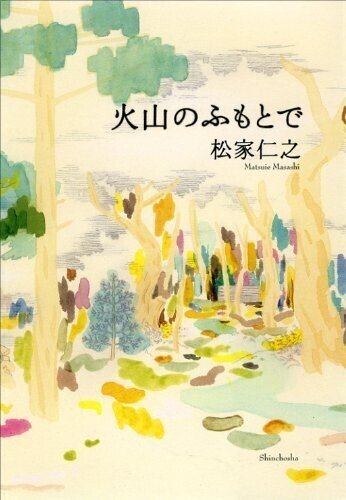
建築家・吉村順三がモデルの小説 。
・クライアントがいて、期日がある
・いつまでもこねくりまわして相手を待たせておくほどのものが自分にあるのか
・建築は芸術じゃない。現実そのものだよ。
・基本設計で少しでも腑に落ちない部分が残ると、実施設計の段階でかならず問題が再熱するからね。
・うまくいった家はね、こちらが説明するときに使った言葉をクライアントが覚えてくれていて、訪ねて来たお客さんに、その言葉で自分の家を説明するようになる。われわれ建築家の言葉がいつしかそこに暮らす人たちの言葉になっている。そうすれば成功なんだよ。
設計する上で考えること、建築との向き合い方、クライアントとの関係、事務所内でのやりとり、などなど。
建築に携わる人がみても、まったく違和感のない描写の数々。
そして、もちろん作品としても、とても面白い。
