
本音や人生について話すことは、生きていく支えになる大事なことなんじゃないか。/デンマークのホイスコーレマガジン編集長に生中継で話を聞いてきた!
「それ、何のためにやってるの?」と聞かれるたびに、「これはねこういうことなの…」とぐちゃぐちゃであいまいな思いをまるで懺悔するかのように言葉にしたことは少なくありませんでした。
それはなかなか相手に理解されず、そんなことを何度か繰り返すうちに、もうこんなこと人に言わないようにしようと、私は心の中で芽が出そうだった思いをそっと隠してしまうことが多くあった気がします。
でも、自分でも不確かな何かを安心して人に話せることや、大人になっても人生についてゆっくり考えたり、話す機会は、長い人生を歩むわたしたちにとって生きていく支えになる大事なことではないでしょうか?
そこで今回は、安心して本音で議論できる土台が整っていたり、社会人になっても教育を受ける機会がある国デンマークの義務教育から社会人向けの教育までをご紹介します!現在のデンマークの状態は、どんな要素が含まれているのかを解説していきます。
「どうして日本は、議論する習慣がないんだろう…」
「もっとフラットな社会にするにはどういう意識が必要なんだろう…」
と現在の社会にもやもやしている方にとって、ヒントになる内容になっているので、ぜひ日々の生活の参考にしてみてくださいね。
今回は、デンマークのロラン島に住むニールセン北村朋子さんと、デンマークのジャーナリストで、ホイスコーレマガジン・Højskolebladet 編集長のSofie buch hoyer(以下、ソフィーさん)に生中継でお話をお聞きしました!そこでの話をもとに書き進めていきます。
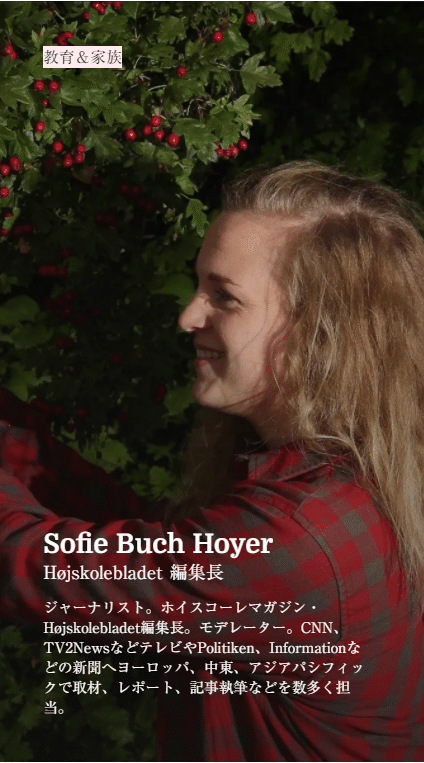
今回参加したのは連続講義形式のイベントです。
詳しくはこちら↓
デンマークの義務教育
デンマークの義務教育は、0年生から9年生までの10年間。(日本の小学1年生から高校1年生に該当)
9年生を終えると、半数の生徒が10年生を選択します。これは、中学から高校のあいだのギャップイヤー期間に相当し、10年生を選択した半数が「エフタスコーレ」という寮制の専門学校に通います。演劇や音楽のほか、ジャーナリズムや哲学、スポーツなど自分が関心のある分野を複数選択し、1年間の寮生活をします。そこで掃除や洗濯などを自分でやることになるので、自立に役に立つんだとか。
また、高校卒業後も直接大学に進学する人は少なく、大抵アルバイトや旅行をしたり、フォルケホイスコーレ(詳細は、後述)に行ったりします。
デンマークの社会人教育
25~26歳の3人に一人がなんらかの成人教育を受講しており、
基本的に、年間14日のあいだ希望する教育機会へ参加でき、交通費や受講料も支給されます。また、その期間の給与も支払われるほか、失業中もその権利があるんです。

でも、
仕事の時間を削ってまで教育の機会を与えた人が、その結果、他社に転職してしまっては元も子もないのでは?
と疑問に思う方もいるかもしれません。
たしかに何かを学ぶことで視野が広がり、新たな分野に携わったり、ほかの会社で働きたいと思う可能性は高まりそうですよね。
そしてこの疑問に対しての、返答はこんなものでした。
どの雇用現場でも同じように社会人教育を行えば、優れた人材が労働市場に増えることにつながる。
この考え方は、自社だけに優秀な人材が集まればいいというものではなく、労働市場全体に優秀な人の母数が増えることで、結果的にどの現場でも優れた人材がいることにつながるということですね。
一年に2週間研修を行うこともあり、市役所や企業に電話すると「担当者は今日、研修でいません」と伝えられることも多いんだとか。そのくらい学びの機会がスタンダードになっているんですね。
大人の学校:フォルケホイスコーレ
社会人教育が盛んなデンマークには、フォルケホイスコーレという170年以上続く大人のための学校があるんです!入学試験をはじめ、成績評価、資格の取得、卒業証書もありません。

そんな学校で学ぶことの価値は、主に3つあるとソフィーさんは言います。
1.人生について考える
2.人間とは何かについて考える
3.民主主義を自分のものとして理解する
人生いうもの自体に正解はなく、「人間とは何か?」という問いへの答えもハッキリとしたものはありません。そして民主主義についても、多くの立場の人がいるぶんそれぞれの主張が存在し、一筋縄で物事が進まないこともあります。それらのテーマについてじっくり考えたり、探究することは、普段の忙しい生活の中ではなかなかできないからこそ、それらをじっくり学ぶ機会があることは価値があることかもしれません。
国内に約70校あるというフォルケホイスコーレ。人生や民主主義について学べる場所がこんなにもあるなんて驚きです。日本では、そういったことを学びたいと思ってもなかなか理想とする講座を探すのが大変だったり、そもそも学ぶ時間が取れないこともありそうですよね。
でも人生について考える意味は、人生がある程度進んでみないとわからないこともあるとソフィーさん。民主主義に関しても社会に出てから、より具体的に何をどうすべきか徐々にわかってくることがありそうですよね。
そういった意味で、ある程度大人になった時点で立ち止まり、自分自身について考えたり、世界がどう動いてるのかを見ることは、一般の学校でできることではないことであり、とても意味があることのように感じます。
フラットな関係性が議論を活発化させる

ソフィーさんは、デンマーク語で「フォルケリーデル」という言葉を紹介してくれました。
日本語にすると、人間臭さ・人間であることという意味合いが近いと朋子さん。
みんなひとりの人間でしかないという認識が根強いことで、上下関係が生まれづらく、自分を高く見せたり、低く見せる必要性が少なくなります。
自分よりも助けが必要な人を助けて、同じ土俵に引き上げる。
先に行き過ぎている人がいたら、みんながそこに上がれるように調整する。
などなどたくさんの人が同じ土俵で話し合える環境が整えられてきました。
そんなフラットな関係性の土台があることで、権力を持っている人とそうでない人、教師と生徒などそれぞれの立場を越えて安全かつ建設的にディスカッションすることができるのかもしれません。
たしかに、まだ考えがまとまっていないことや本音は、信頼できている相手にでないとなかなか話そうと思えませんよね。そういった意味で、何者でもない人間と人間という関係性のなかで議論することができるのはとても意義のあることだと思います。
そして、議論を長く続けてきたことで共通の価値観が醸成されていることも、ヒエラルキーの少ない社会につながっている要因の一つだとソフィーさん。
デンマークでは、19世紀から民主主義社会ではできるだけたくさんの人の意見が反映されるべきだと認識されていたことから、議論することの重要性自体が、共通の価値観として作り上げられてきました。このようにデンマークの人々の間で共通の価値観が育まれてきたんですね。
終わりに
長く続く人生のなかで自分自身とのつながりを保つには、自分の考えを安心して話すことができる周囲の人との関係性がとても大切なように感じます。
教育体制ももちろん大事ですが、自分から変わることも環境を変える大きな一歩になりそうです。
「身近な人ともっと本音で話したい。」
「人生について話したい。」
という思いがあるのなら、ぜひあなたから自分の人間臭さを開いてみてはいかがでしょうか?
