
浮腫ってなに?

絶賛毎晩足がむくんでいる(ただ単に太い?)みこです。
みなさん今日もお疲れ様です。
今回はよく見かける「浮腫」についての解説をしていきますよぉぉぉぉぉ!
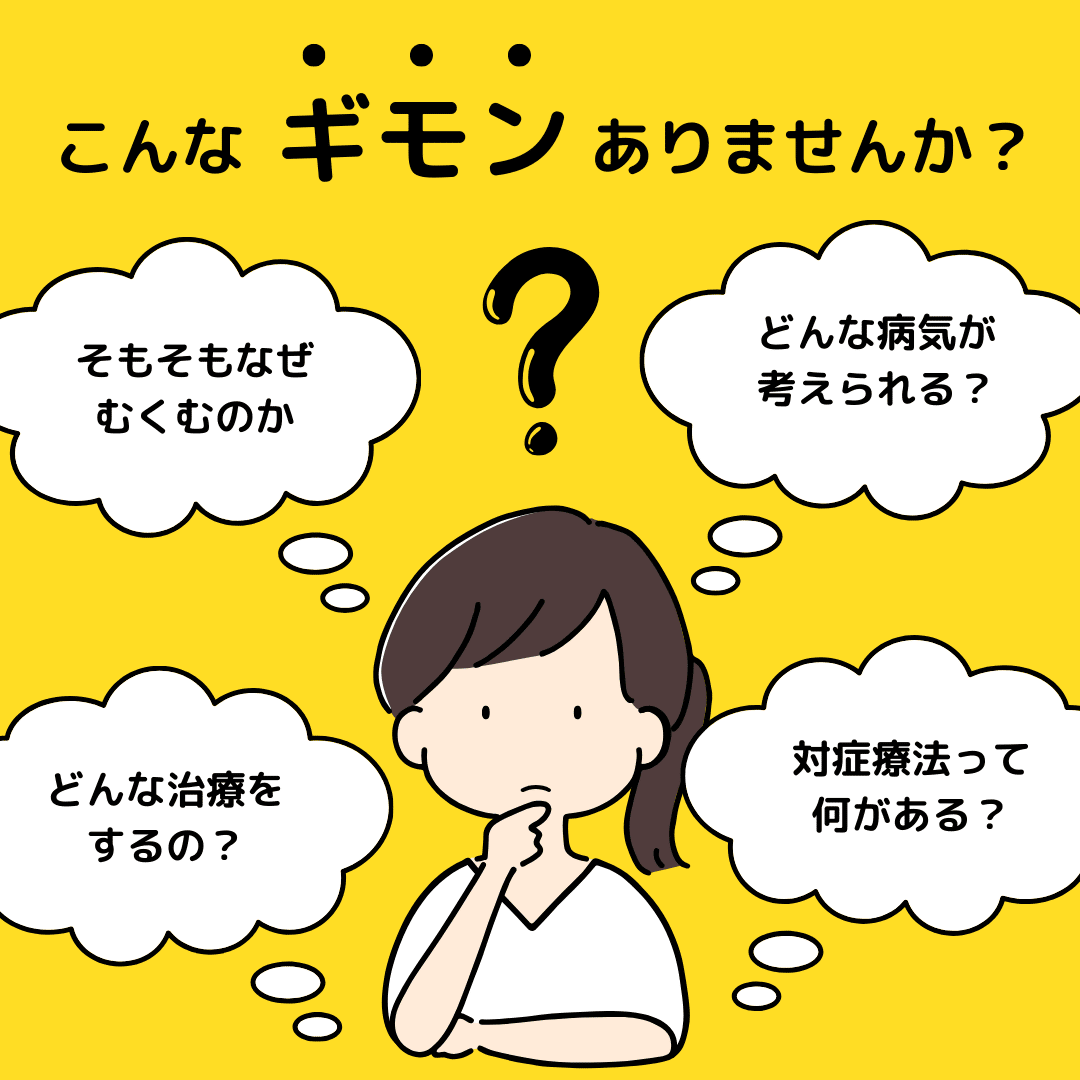
浮腫とは
浮腫(ふしゅ、edema)とは、組織間隙に生理的代償範囲を超えて過剰な水分が貯留した状態である。水腫と同義語であり、一般的にはむくみともいう。
臨床では「エデマ」っていうことが多いかな?略してEDって書くこともあるよ!看護実習でも浮腫のある患者さんを受け持ったことがある学生さん多いんじゃないかな?
そんな身近な症状の浮腫について改めて勉強してみましょう!
主な原因

血液循環の低下

私たちの体には、血液を体中に巡らせる「血管」という通り道があります。血液は心臓がポンプのように動くことで流れますが、長い間立ちっぱなしや座りっぱなしだと、特に足に血液が溜まりやすくなります。これが「むくみ」の原因になります。たとえば、ふくらはぎの筋肉は心臓に血液を押し戻す手助けをする大切な役割を持っています。デスクワークや立ち仕事をしていると、この筋肉が動かず血流が滞ってしまうため、足がむくみやすくなるんです。
「静脈瘤(じょうみゃくりゅう)」があると、血液が足に溜まりやすくなることがあり、むくみを引き起こします。
ナトリウム(塩分)の取りすぎ

私たちの体は、適度な「ナトリウム」という成分を必要としますが、ナトリウムを多く含む塩分を取りすぎると、体がその塩分を薄めようとして水分を溜め込みます。体の中では、血液中の「ナトリウム濃度」を適正な範囲に保つようにコントロールしています。ナトリウムは、体内の水分バランスや血圧を調整するために必要な成分ですが、多すぎると体の細胞に悪影響が出ることがあります。もし血液中のナトリウム濃度が上がりすぎると、体はナトリウムを薄めるために水分をため込みます。これによって、血液中のナトリウム濃度を安全な範囲に戻そうとするんです。この調整のおかげで、私たちの体はナトリウム濃度を一定に保つことができていますが、その結果としてむくみが起こることもあります。
腎臓機能低下

腎臓は、体内の老廃物や余分な水分をろ過して、尿として膀胱に送る役割をしています。腎臓の機能が低下すると、このろ過機能がうまく働かなくなり、体内に水分や老廃物が残ってしまいます。膀胱に溜められる尿の量には限りがあるため、腎臓がうまく働かないと、余分な水分が血液中や細胞の間にたまってしまうのです。これが原因でむくみが生じます。腎臓が働かないと、必要なものと不要なものを分けられないため、体内に不要な水分がどんどん溜まってしまいます。
心不全や肝不全

心臓や肝臓は、体の中で血液や水分のバランスを整える役割を持っています。
心不全では、心臓のポンプ機能が低下して血流が悪くなり、下半身に血液がたまりやすくなります。その結果、下半身がむくむことが多いです。
一方、肝不全の状態では、肝臓が生成するアルブミンというタンパク質が不足し、血液が水分を保持する力が低下します。そのため、血液中の水分が細胞の間に染み出し、腹部や足に浮腫が出やすくなります。
ちなみに、肝臓は、私たちの体の中で「栄養素の管理人」のような役割を持っていて、血液中の栄養や水分のバランスを整えています。例えば、食べ物から摂取した栄養素は小腸で吸収され、最終的に肝臓に運ばれます。そこで必要な量だけが血液中に出され、余った分は体内に蓄えられます。また、肝臓は血液中に含まれる「アルブミン」というタンパク質を作り出しています。このアルブミンが不足すると、水分が血管外に漏れやすくなり、むくみの原因になります。肝臓が健康なときは、このようなタンパク質の調整によって水分や栄養のバランスが整えられているんですね。
ホルモンバランスの変化
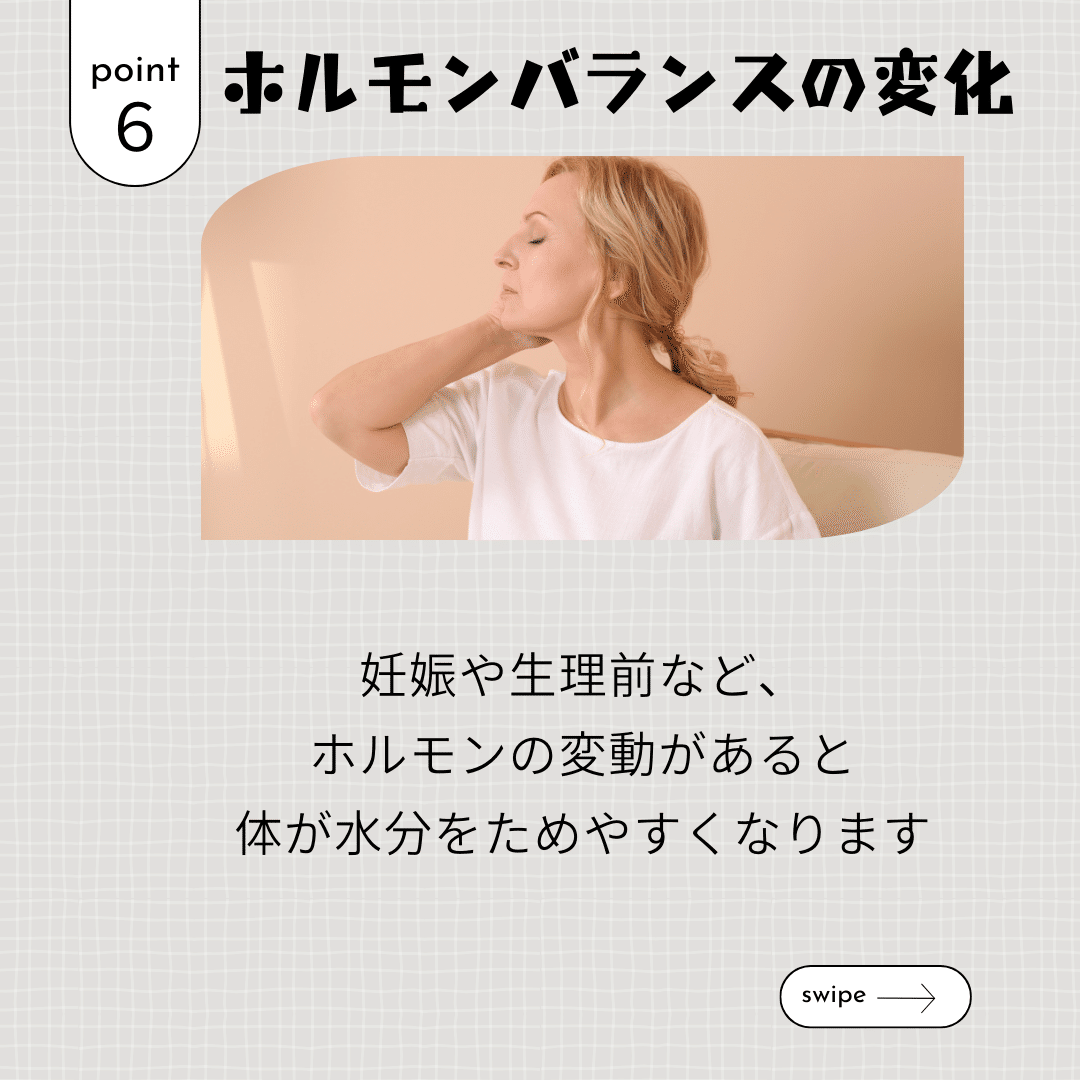
体の中には「ホルモン」という調整役のような物質があり、水分の調整もしています。特に女性は、生理前や妊娠中にホルモンバランスが変わり、体が水分をためやすくなるため、顔や足がむくみやすくなります。ホルモンの影響で血管やリンパ管がむくみやすくなるんですね。
むくみに関係するホルモンにはいくつかありますが、特に以下の2つがよく知られています:
プロゲステロン:女性ホルモンのひとつで、妊娠や生理前に分泌量が増えます。プロゲステロンは体に水分をためこむ作用があり、特に生理前にはこのホルモンの影響で体がむくみやすくなります。
アルドステロン:副腎から分泌されるホルモンで、ナトリウムを体内に保持し、カリウムを排出する役割があります。アルドステロンの量が多いと、ナトリウムと一緒に水分も体に溜めこみやすくなるため、むくみが発生しやすくなります。
これらのホルモンは体の水分や電解質のバランスを保つために重要ですが、増えすぎたりバランスが崩れたりするとむくみにつながります。
栄養不足(低タンパク血症)

血液中のタンパク質(特にアルブミン)が不足すると、血管内に水分を保持する力が低下します。タンパク質は血液中の水分を血管内に引き留める働きをしているため、不足すると水分が血管の外に漏れ出しやすくなります。栄養状態が悪い方や、肝臓や腎臓の疾患がある場合に見られやすい症状で、顔や四肢がむくむことがあります。
薬の副作用

一部の薬には、浮腫を引き起こす副作用があります。例えば、降圧剤は血圧を下げるために血管を拡張させますが、その影響で水分が血管外に漏れ出し、浮腫を引き起こすことがあるの。
そして、ステロイド剤は体内の水分やナトリウムのバランスを変化させるため、長期使用によってむくみが出ることがあります。他にも、ホルモン薬や抗炎症薬などが影響することもありますので、浮腫が気になる場合は薬の副作用も確認する必要があるよ。
浮腫の評価
アセスメントスケール

これを、定義つけておけば、評価の時にどのレベルなのかはっきりと示すことが出来るし、人によって「重度の度合いが違う」っていう認識のズレも改善できそうですね💡
体重管理
体重管理も大切な浮腫の観察項目の一つだよ!
1週間で2キロ以上の体重増減がないか確認しましょう。
IN・OUTバランス
体に入っている水分(点滴や飲水量)と体から出る水分(尿量や下痢や嘔吐)などの差を観察するよ!
汗などの不感蒸泄や代謝水もあるから多少の誤差はあるけど、大きな誤差があるときには注意が必要です。
※健康な人の不感蒸泄量は900ml、代謝水は体重当たり5mLと言われています(例えば50㎏の人は250ml)
便は平均100mlと言われているけど、量や形状によっても含水量が違うから難しいよね…
ICUなど急性期の場合にはインアウトバランスも観察項目の大切なポイントになるので、学生さんは覚えておいてくださいね(精密尿測用バルーンバッグもあるのよ)
治療法・対症療法
簡単に表形式にまとめました。

まとめ
浮腫の理解とケアについて学ぶことは、患者さんのQOLを守り、回復を支える看護の重要な役割です。この知識があれば、原因に応じた対策や患者さんに合わせたサポートがより効果的に行えると思います😊
現場で日々のケアに取り組む看護師の方々、そしてこれから看護師を目指す看護学生の皆さん、学んだ知識やスキルは必ず患者さんの力になるよ!
困難な場面も多いけど、一つひとつのケアが患者さんの安心と回復につながることを忘れずに、どうか自信を持って取り組んでくださいね!
今回はこの辺で!
ばいらびゅー💛
