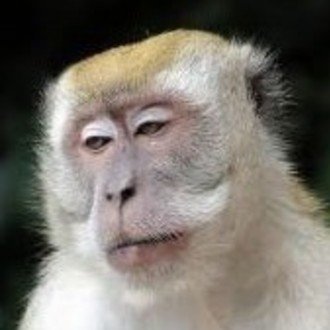石油の話#04/「民族の自由と尊厳」ほど儲かる商売はない
第二次世界大戦は、人類史における大きな転換点となり、これを契機に世界はこれまでの歴史とは全く異なる方向へと再編成されていきました。戦争がもたらした破壊と混乱は、旧来の国際秩序や経済構造を揺るがし、植民地支配を基盤とする帝国主義に終止符を打つ動きを加速させました。その結果、アジアやアフリカを中心に独立運動が活発化し、多くの国々が新たな国家として誕生しました。
特にイギリスやフランスといった伝統的な植民地支配国は、第二次世界大戦後の経済的復興や社会の再建に多大な労力を割かざるを得ませんでした。そのため、かつてのように植民地を維持するための軍事的・経済的リソースを投入することが困難となり、次々と植民地を放棄せざるを得なくなりました。このようにして旧勢力であるヨーロッパ諸国の国際的地位は相対的に後退し、新興勢力の台頭が見られるようになったのです。
こうした植民地独立の潮流の中で、「民族の自由と尊厳」を掲げた独立運動を支援し、結果的に多くの新興国家の誕生を後押ししたのが・・外ならぬ米国でした。米国は、冷戦下でのソ連との対立を背景に、資本主義陣営の拡大を図るため、新たに独立した国家への援助や支援を行いました。しかし、こうした支援には単なる人道的意図だけではなく、経済的利益という側面も隠されていたのです。
米国が「民族の自由と尊厳」を支援する背景には、ドルが基軸通貨としての地位を確立したことが大きく関係しています。独立を果たした国家は、独自の領土と政府を持つだけでなく、国家の基本的要件として独自通貨や軍隊も保有する必要があります。しかし、新興国家の多くは、自国通貨だけで貿易を行うことは不可能です。国際貿易を円滑に行うためには、貿易用外貨準備としてドルを確保する必要がありました。
この仕組みによって、新たな独立国家が誕生すればするほど、それらの国々はドルを必要とすることになります。結果的に米国はドルを海外に供給することで、基軸通貨の地位を強固なものとし、自国経済を大きく潤すことができるようになりました。
ここで重要なのが、ドルの製造コストの低さです。例えば、100ドル紙幣を印刷するコストは12~14セント程度に過ぎません。つまり、米国は海外で生産された100ドル相当の商品を、わずか12~14セントで手に入れることができるのです。この利益は「シニョリッジ(seigniorage)」と呼ばれる通貨発行益にほかなりません。
さらに、独立国家が保有する外貨準備金は通常長期間にわたりストックされるため、米国にとっては実質的に返済義務のない「借金」のような形になります。この仕組みにより、米国は世界規模で経済的な優位性を確保し、基軸通貨としてのドルを武器に莫大な利益を得ることができたのです。
いいなと思ったら応援しよう!