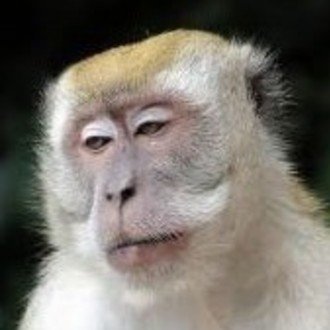ワインと地中海#49/マグナ・グラエキア#06
「東ローマ帝国のマグナ・グラエキア統治は500年以上続いた」
「安定政権だったのね」
「ん~でもない。ペルシャに襲われたりスペインに襲われたり、揺籃を繰り返した。ローマはテマ制の総督領Catepanate of Italyだったからね、自国領と言っても脆弱に部分はあった」
「テマ制ってなに?」
「派遣された治政管が全て軍民すべてを統治するやり方だ。東ローマの属領はこの方法が多かった。しかし本体の東ローマが弱体化すると、テマ制はさらに脆弱に歪(いびつ)になっていった。そこにノルマン人のロベルト・イル・グイスカルドが攻め込んだのは11世紀後半。ローマ総督領は脆くも崩れた。ノルマン人はここにシチリア王国を開き、以降イタリアに東ローマがへ戻ることはなかった。そして東ローマ帝国そのものが滅びるのは1453年だ」
「ん~~でも、ギリシャから移民した人々は残ったんでしょ?」
「ん。残った。殲滅されなかったし、奴隷として売られたりもしなかった。僥倖だった」
「11世紀でしょ?もう奴隷制は衰退していたんじゃないの?」
「そんなことない。東ローマもスペインも、ヴェネツィアも、奴隷売買は大きなビジネスとして成立していた。ノルマン人がマグナ・グラエキアで人狩りをやらなかったのは、そのまま農民として働かせて税金を払わせる方が儲かるからだ。おかげで、植民してきたギリシャ人も先住民だったカラブリア人もサレンティーニ人も、命の露を繫げたんだ」
「農民としてノルマン人たちに仕えたわけね」
「ん。サレント半島の話を頭に置いて南イタリアの話を続けると・・実はマグナ・グラエキアのなかで、プーリアは山岳地が少ない地域なんだよ。広い沿岸部そしてそれに付帯する平野と丘陵の地だ。たしかに、もともとプーリアに海を渡って東から入ったのはフェニキアだったが、彼らが沿岸部より奥に入ることはない。通商のためのハブとしてのりようだったからな。平野部/丘陵部へ大きく広がっていったのは、家族を連れて渡ってきたギリシャ人たちだ。フェニキア人たちは、ここでもギリシャ移民が台頭すれば、さっさと軒を閉めて立ち去っている。プーリアは、先住民たちと鬩ぎあいながら葡萄とオリーブを植えたんだよ」
「まさにイタリア半島版の西部開拓史を作り上げたのね」
「そのとおり・・だから逆に言えば、先住民がどう扱われたかは、アメリカのインディアンを見れば推して知るべしだな・・そしてAC500年ころから始まる東ローマの総督領時代になっても、入植した人々/家族はギリシャ側からだった。やはり陸地深く入り込んで同地の開拓をしている」
「そう考えると・・南イタリアはラテン人の国と言うより、ギリシャからの移植した人々が作り上げた国・・というわけなのね」
「ん。支配者は何度も変わった。しかし農家も漁夫もギリシャ人系が、今の今まで残っている」
「新しい支配者たちは、住民を一網打尽にして奴隷で売られなかった?」
「うん。西アフリカ象牙海岸や黒海北東側ではそれが続いていたがな。キリスト教は奴隷制度を忌諱していた。だから、これが国教化されると、欧州内での奴隷使用は極力避けられるようになっていたんだ。それでもオランダ人/スペイン人/ポルトガル人は、アフリカ西海岸で現地の支配者から無数の黒人奴隷を買って売りまくっていたがな。ヴェネツィア人もそうだ。奴隷Slaveと言う言葉の語源は、ヴェネツィア人が黒海北東でスラブ人を奴隷として狩っていたからたからだ」
「Slavic(スラブ人)がslave(奴隷)になったのね」
「ん。合成調味料を、何でもかんでも"味の素"という、うちのオフクロみたいなもんだな」

いいなと思ったら応援しよう!