
令和6年度保育士試験を一次の独学11時間で一発合格した話
またこんないかがわしいタイトルの記事を書いてしまった…。
こんにちは。近藤ろいです。5歳と2歳の子どもを育てるフルタイムワーママです。
このサイトでは、主に5歳の娘が3歳児健診で片目弱視が見つかった話をお送りしています。
時々、サイトの宣伝も兼ねて世間の関心の高い「保育士試験受験」の話題をお送りしていました。
今回もその一環です。(その他の記事はこちら)
令和6年保育士試験(後期)を一発合格しました。前の日の午後から勉強して。
一次試験:合計675点(得点率85%)

二次試験:合計 69点

総得点744点で合格です(得点率82%)。
フルタイムワーママでも家事育児みっちりでもおばさんでも関係ないね! 合格する奴はするのさ!
なんて大きい看板掲げてみる。
当方、フルタイムで働くくたびれ40代です。
「3ヶ月で合格しました!」などの体験記はちらほら拝見しますが、
さすがに「試験前日の午後から勉強をし始めて、11時間で一次試験を突破した」という話はなかなか無いと思いますので、
記事として残しておきます。
なお後述する理由で、このシリーズの記事を有料販売するつもりは無いです。
その代わりちょっとだけ目を貸してください。
~コマーシャル~
このブログは普段は「育てにくいと思っていた娘が、3歳児健診で生まれつきの片目弱視(遠視)を指摘されて治療している」という趣旨で運営しています。
普段は治療用眼鏡を掛けており、家庭では健眼にアイパッチをつけ、見える方の目をわざと遮蔽して過ごしています。
もしも保育園くらいの年齢の子で、眼鏡を掛けている子がいたら、
「スマホやYouTubeの見せすぎかな」と思いがちですが「治療中なのかもしれない」ということを思い起こして頂けましたら幸いです。
~コマーシャル終わり~
では、本題に。
試験前日にやっと勉強しようと思えた
試験前日。
(いくらなんでも、全く勉強せず受けるのもふざけ過ぎだよなあ)
突然心を入れ替えた私は、忙しかった仕事がちょうど切れ目だったのもあり、
一緒に仕事をしている同僚と直属の上司に
急遽半日休の許可を得に行きました。
「課長、明日が保育士試験一次なんですけど、殆ど勉強していないので、ちょっと勉強しに帰ってもいいでしょうか?」
「ぇええっ!? …う、うんいいよ」
心の広い上司です。
仕事の最後の後始末をして、急遽午後からお休み。
自宅近くのカフェにて初めて、過去問とテキストを開きました。
感想
うーん結構難しいなあ。
わかる分野もあるわ。
もっと早く勉強しておけばよかったなあ(←!?)。
というか…
カフェで自己学習するのって楽しすぎない!?
普段はワンオペ家事育児に追われる身分。
ところが…この状況たるや…
自分のために時間を使える!
誰も膝に乗ってない!
しかも飲み物甘いものつき!
何て楽しい時間なんだ!!
前日に気づいた私でした。
それまでは、ちまちまユーキャンのテキストを眺めて通勤途中に「フーン教育原理っていう教科があるんだー」と眺めていた程度。
問題集やテキストを広げて机の上で勉強したのは、これが初めてでした。
なぜギリギリまで勉強できなかったか
普段は持ち帰りの仕事(予習とか)で手一杯
子どもをお迎えに行きお風呂に入れてあとは寝るだけの状態にするまでワンオペ
相次ぐ子どもの体調不良ロンド(巻き込まれる親)
どこの家庭とも一緒です。
さらにさらに、少し元気になった私に
上の子5歳「エルサのアイパッチを作ってほしい」

下の子2歳「便器にまたがってトイレするでしゅ! 踏み台を作るでしゅ! この牛乳パックを張り合わせた、アンパンマン仕様のでよろしくでしゅ!(意訳)」

という要請が入り、寝落ちしそうな身体を起こして夜な夜な作成していたのでした。
勉強…うーん眠い…また今度にしよう。
詰め込み11時間の学習スケジュール
試験前日 5.5時間
午後2~5時半まで カフェで過去問をさらう(3教科分) 2.5時間
午後5時半~10時 子どものお迎え・夕食・入浴・寝かしつけ(寝かしつけの前までワンオペ)で勉強できず。
午後10時~深夜1時まで 自宅で過去問+間違えたところの見直し(3教科分) 3時間
試験1日目 3.5時間
5時半起床
午前7時~8時半 会場に向かう途中のファーストフード店で勉強(過去問+見直し+保育所保育指針の覚え直し) 1.5時間
帰ってから勉強(全く手つかずだった「子どもの保健」「食と栄養」過去問)2時間
試験2日目朝 2時間
午前7時~9時 同じく勉強(「教育原理」「社会的養護」の覚え直し、「保育実習理論」の絵画と楽典の部分の暗記) 2時間
計 11時間
ギリッギリやな! というていたらくでした。
厳密には、会場入りした後から試験説明開始までや、各試験問題は30分で解き終わるので早めに退出して20分くらいを学習時間に当てるなど、せこい時間の稼ぎ方はしていました。
使ったテキストはユーキャンの速習テキストです。
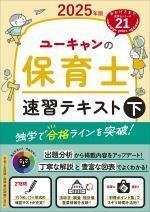
試験直後は「このテキストに無いことばっかり出た」と酷評が吹き荒れたのですが、くたびれ40代ワーママはそもそもフルカラーじゃないと頭に入らないという…。
過去問は桜子先生のものでした。
解説が詳しいのと、「キャラクター形式なら頭に入りやすいか?」という軽い気持ちからです。
後に、どえらい集団凝集性の高い一派であることを知りました。つまり何でも良かった。
テキストにマーカーを引く時間も、
解説系YouTubeを見るヒマなど無かった!!
社会福祉士ならば3教科免除なのですが、申し込み後にそれを知った私…。がぷり四ツで全教科受験です。
試験会場で、自作のノートを広げておられる他の受験者さんを見て「こんな体たらくで同じ会場にいてごめん…」と思いました。
11時間で出来たことといえば、
過去問解く→間違えたところを叩き込む
直前に人名と歴史を叩き込む
楽典は当日朝に勉強したけど理解できなかった!!
この程度です。
幸い、全く知らない分野なのが楽典と栄養くらいなので、
知っていることを試験向けにチューニング
ちょっと知ってるけど怪しい知識を修正
全く知らないことを叩き込む
これで何とか形になりました。
というかこれで時間切れ。
それでもまあ、結果は上記のとおり高得点一発合格でした。
なお二次(造形)の学習時間は40時間くらいでした。
「無課金くたびれおばさんは、いかにして効率よく知識を付けたのか?」
本題。
私自身の置かれた来歴には大きなアドバンテージがあったと思います。
もともと臨床心理士
駆け出し臨床心理士は食っていけないので、若い時に市役所や福祉事務所のバイトをしていた。
その知識と経験を形にしたくて、3年位前に社会福祉士の通信制学校に通い、試験を受けて資格を取った。
ついでに第1回公認心理師試験も受けて通った
そんなこんなしている間に5歳児と2歳児の子育て体験
加えて、今年度は
「育児休業から復帰してみれば、今までの業務と全く違う、日々保育所やこども園の設置条件や運営上の法令・国指針を調べる仕事に置かれた」。
わからないでは済まされません。
ここで毎日必死になって調べ物をする毎日でした。
専門外の知識を付けざるを得なかったのだから、何かアウトプットをして結果に残そうと思ったのと、
せっかくなら回答する相手の「保育」というものの専門性をちゃんと知ろうと思ったのと、
昨今の保育士不足を目の当たりに、何かの折いささかなりともお役に立てればと思ったのと、
将来的に転職またはリタイヤ後に何かをするにあたり、したいことへの入り口として保育士の資格は魅力的だったこと
これらの動機で受験を決意しました。
立場に恵まれているから短時間の勉強で済んだのか、否!
立場と経歴は確かにアドバンテージですが、それらを通して身に着いたのは、それが「生きた知識」になるよう意識していたからだと強く思います。
子育てをされた事がある方なら、「栄養」「保健」は割と実生活の中で使う知識も多いのではないかと思います。
離乳食はもう始めた方がいいの? 目安は? 何から食べさせる? それはなぜ?
我が子どもがりんご病にかかったかもしれない。
「どのくらい仕事を休むことになるのかな…?」
出席停止の定義と登園の目安を思いめぐらせます。
同じように保育所保育指針は、多様な保育を展開する各施設に「それでもこれだけは守ってほしい」という骨子を示したもので、当時の厚生労働省の公示であるため、法的拘束力を有します。
保育というものが「ただ子どもを預かり、遊ぶだけ」以上の専門性を持つ技能集団として、適正なサービスを提供するための施設としての責務を盛り込んでいます。
例えば、子どもに応対するその技術が、「ただの感覚的な経験知」に拠らないよう、職員は研修を受けるように。
日々の保育が「各先生の自己満足で終わり」にならないよう、個人そして施設としての自己評価を実施し、地域に向けてしていることの説明責任を果たしていくための公表を――。
社会福祉の分野もです。例えば知らない制度に出会ったならば。
(福祉サービス運営適正化委員会なる制度があったのか…? 私の住む自治体ではどこにある?
!! 行ったことのあるビルだわ! 確かに階段の踊り場の展示に、それっぽいものがあったなあ。
勤め先の近くにはあるかな?
ああ~、設置は都道府県で、同じような事業は市の社会福祉協議会にもあるのか…)
なんて考えます。都道府県に設置義務があること、業務内容はもう忘れません。
動物行動学者の「ローレンツといったらインプリンティング は有名だけど、どんな顔の人なんだろう?
ローレンツ氏を親と思いこんじゃったカモはそのあとどうなったんだろう?」
なんてね(とても面白い逸話が残っています)。
覚える知識は「お勉強で暗記すること」ではなく、自分たちの生きる社会を作る制度の一つであるし、
もしも自分が保育士として保育所や障害福祉施設に勤務した時、
「あれっ」と思った時にそのモヤモヤを解消していける根拠や相談先があるかもしれない。
…と思いながらテキストや過去問にも向き合ったので、
短い学習時間でも、1回の学習でも、生きた知識、エビソードとして頭に入るのですごく定着したように思います。
そして私が立場や経歴で恵まれてきたのは、こうした「生きた知恵」をつける機会だと思いました。
おわりに:保育士試験一次の出題傾向から見る 保育士として問われていること
あるいは「なんでこんな関係なさそうなことまで覚えなきゃならないんだ?」
臨床心理士と社会福祉士、2つの学校に通い(社福の方は通信制大学)「その名称が持つ専門性と社会的責務」と叩き込まれた身からすると、
保育士試験の出題傾向からは、同じように「保育士」という専門性への高い誇りを感じます。
保育士は「ただ子どもと遊んでいるだけの楽な仕事」なのか?
否!
養護と教育を一体的に提供することを求められ、
それも行き当たりばったりではなく、
「全体的な計画」に基づく年・月案、週・日案のもとに「ねらい」及び「内容」が展開されるように企画されたものある必要があります。
そうした計画類や、安全管理の最低基準を知っておくことは、
もしも心意気は善良だけど法令遵守意識には弱い認可外保育施設にご縁があった時、
「園長、これはまずいんじゃないでしょうか」と言うための根拠となり得ます。
また、保育士という立場は、保育所やその他の福祉施設に勤める機会がありますが、
様々な家庭背景に出会うことになります。
「子どもはいい子だけど、どうもゴミ屋敷らしい」と思った時に、訴える先を思いつくかどうか。
それらの知識を「少しでも知っている」だけで、目の前にいる子どもの人生は変わるかもしれない。
保育士は「ただ遊ぶだけ」以上に、子どもを取り巻く背景、社会制度も含めて関わりを持っていく立場なのだ!
…という高い職業意識が見て取れます。
それは、普段はそうした保育所等をめぐる基準や法令・通知などを調べる仕事をしている私が、
やすやすと保育士試験一次を合格してしまったことからも裏付けられるように思います。
これから保育士試験を勉強する方へ
ということで、今回は「勉強時間11時間で保育士試験一次を一発合格した話」という、
センセーショナルなタイトルの記事をお送りしました。
効率的な勉強の仕方とか、時間の作り方といった話ではなくて、
「どうせ勉強するなら今の自分のいる社会や将来の自分に結びついた生きた知識として叩き込め」という、
なかなかコピーしにくい話題だと思うので、有料記事にはしませんでした。
そして二次試験(実技)では、準備したにも関わらず30点台をくらうという結果も頂いたので、保育士試験の話題はこのくらいにして、
アイパッチ作成おばさんに戻りたいと思います。
これから先受験される皆様にいいことがありますように!
近藤ろい
