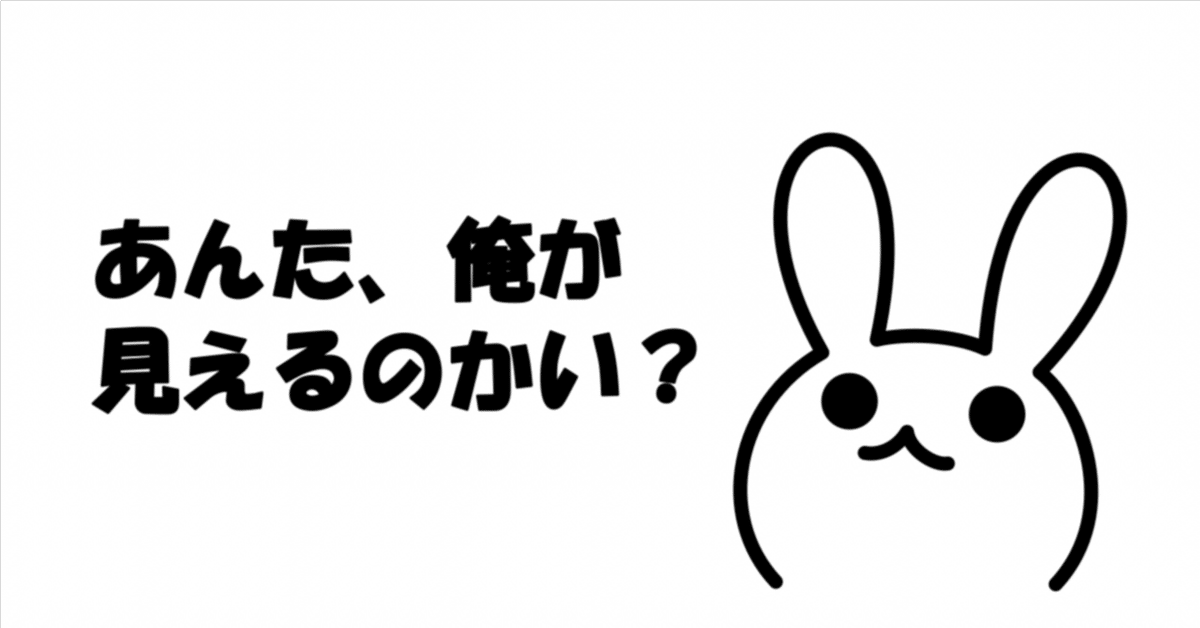
学校という虚構
学校は虚構です。
「いやいや、あんた何を言っているんだい。私の街には確かに「学校」があるよ。あんたは頭がおかしいのかい?」
いえいえ、学校は虚構です。
確かに「建物はある」かもしれませんが、建物自体は学校ではありません。
N校が典型ですね。校舎はあるかもしれませんが、その教育活動のほとんどは「ネット」の中で行われています。
学校と同じように「貨幣」も虚構です。
日本円に価値があるのは、みんなが「日本円には価値がある」と思っているから成立しているわけですね。明日、日本が瓦解するなら、日本円の価値は暴落して、文字通り「紙切れ」に変わるわけです。そんな貨幣は誰も持ちませんよ。日本は「いつまでも崩壊しない」という信頼が日本円の価値を担保しているわけです。まあ、有史以来、崩壊しない国なんて存在しないのですが。
貨幣と同じように「国家」も虚構です。
国家には実態がありません。国土はあっても、その領域は任意に変更が可能です。ロシアという国が現在も国土を広げるべく戦争をしていますね。イスラエルはハマス殲滅を名目に、パレスチナを自分の国にしようと必死になっています。
そもそも、現在の国民国家が成立したのは、神聖ローマ帝国が解体したウェストファリア条約以降であり、まだその歴史は350年程度です。人類の歴史に比べれば、その歴史は赤子のようです。
そして、貨幣や国家と同じように「学校」も虚構です。
これは経済学者の宇沢弘文先生の概念を借りれば、社会的共通資本の中の「制度資本」になります。制度資本は、教育の他には、医療、司法、金融、文化などがあります。
これらの制度資本は、みんなが「あると信じている」から「存在する」ものです。これを歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリは「共同主観的なもの」と述べます。この部分のハラリの説明を引用しましょう。
オオカミやチンパンジーのような動物は、二重の現実の中で暮らしている。一方で、彼らは木や岩や川といった、自分の外の客観的なものをよく知っている。他方で、恐れや喜びや欲求といった、自分の中の主観的な経験も自覚している。それに対して、サピエンスは三重の現実の中で生きている。木や川、恐れや欲求に加えて、サピエンスの世界にはお金や神々、国家、企業についての物語も含まれている。歴史が展開していくなかで、神や国家や企業の影響は、川や恐れや欲求を犠牲にして大きくなっていった。世界には依然として多くの川があり、人々は恐れや願望に相変わらず動機づけられているが、イエス・キリストやフランス共和国やアップル社などが川にダムを造って利用し、私たちの最も深い不安や憧れを形作る術を覚えた。
ハラリの説明をまとめると、動物たちは「二重の世界」を生きています。それは「客観的なもの」と「主観的な経験」です。「客観的なもの」は「木や岩や川」などです。そして「主観的なもの」は「恐れや喜びや欲求」です。
そして、サピエンス(ハラリは人類をサピエンスと呼びます)はその二つの世界に加えて、さらにもう一つの世界を生きています。それが「イエス・キリストやフランス共和国やアップル社」などのような「共同主観的なもの」です。
これは人間だけが持つ「世界」であり、人間はこの「共同主観的」な世界を共有することができるからこそ、協力をすることができ、その力で地球の覇者となったというのがハラリの見解です。
ちなみに「協力する生き物」なら、他にもいますね。アリやハチなどもそうです。しかし、彼らの協力には「柔軟性」がありません。彼らは「大きな巣」は作れても、女王アリに対する「反乱」は起こせません。それが、アリやハチと人間との違いです。
確かに、「イエス・キリスト」にも「フランス共和国」にも「アップル社」にも実態はありません。「客観的なもの」と違って、「それ」を指し示すことはできません。さらに「主観的な経験」と違って、「それ」を感じることもできません。例えば「神」の存在を、現実のようにありありと感じることができる人もいれば、全く感じれない人もいます。
これらは「ある」信じる人たちの間でだけは、確かに「ある」と感じることができ、そのように信じることができない人たちには、全く感じることができないような、そういうものなのです。
そして、学校も間違いなく「共同主観的なもの」です。だから、「ある」と信じている人の間でだけ存在するような「虚構」なのです。
しかしそうは言っても、「貨幣は虚構だから無価値である」ということを、たった一人で言ったところで、何も意味はありません。その他の多くの人たちが「貨幣には価値がある」と信じていれば、「貨幣には価値がある」ということになります。
20年前に「ビットコイン」の話をしても、誰も信用しなかったでしょう。「データが貨幣になる」なんて夢物語にしか聞こえなかったはずです。でも今は、多くの人が信じるから「データが貨幣になる」ということが、現実に起こっています。そして、その価値は驚くほどの高騰を続けています。
この「共同主観的なもの」は、「書字と貨幣」という人類最大の発明を生み出します。これらはその世界をどんどん広げていきます。
貨幣については、過去に漫画『キングダム』の呂不韋の話として取り上げていますので、以下の記事をご覧ください。
今回は、書字について考えていきましょう。ハラリは、書字が生まれる以前の狩猟採集民や農耕民の暮らしと、書字以後の古代エジプトを比較して以下のように記します。
狩猟採集民は木に登ったり、キノコを探したり、イノシシやウサギを追いかけたりして日々を過ごした。彼らの日常的な現実は、木々やキノコ、イノシシやウサギから成り立っていた。農耕民は畑を耕したり、作物を取り入れたり、小麦を挽いたり、家畜の世話をしたりして日がな一日、野良で働いた。彼らの日々の現実とは、素足で踏み締めるぬかるんだ大地の感触や、鋤を引く牛の臭い、かまどから取り出した焼きたてのパンの味だった。一方、古代エジプトの書記は、ほとんどの時間を読んだり書いたり計算したりするのに捧げた。彼らの日常の現実は、パピルスの巻物の表面に残されたインクの印から成り立っており、その印によって、誰がどの畑を所有し、牛一頭の値段がいくらで、その年に農民がどれだけの税を払わなければならないかが定められた。書記はペンをさっと走らせるだけで、一つの村全体の運命を決められた。
この対比は、「文字を覚える前の子ども」と「それ以後の人」でもいいでしょう。文字を覚えた人は、それ以後、様々な経験を「書字」から得ることになります。それは「経験」だけでは味わなえない世界です。
写真が発明される以前、人は書字によって世界を知りました。江戸時代、海の向こうの世界を知りたいと思った者たちは進んでオランダ語を学び文献を読み漁りました。聖徳太子は、異国の宗教である仏教についてたくさんの書物からその知識を得たと言われています。書字という発明は、人類の世界を途方もなく広げることになったのです。
「書字は単なる文字である」と、その価値を否定したくなるかもしれません。しかし、人間はこの書字によって生かされたり、また殺されたりしたのです。
第二次世界大戦の最中、ユダヤ系フランス人の亡命を助けたポルトガルの在ボルドー領事だったソウザ・メンデスは、ビザを発行できる「ゴム印」で3万人の命を救いました。日本人の杉原千畝も同様の救出作戦で1万人の命を救っています。単なる紙切れによって、何万人もの命が救われることもあるのです。
一方で、1950年代後半からの中国の大躍進政策は、文書記録の残忍さを伝えます。毛沢東が中国を一気に超大国に変えようと望んだ結果、地方の役人たちは、毛沢東の意思を忖度して、各地の穀物の生産数を過剰に記載しました。その結果、1958年の中国の穀物生産高は現実の五割増になり、そのせいで史上最悪の大飢饉が起き、何千万人の人が命を落としたと言われています。(同書 p205)
書字の発明以後、人類は書字の書かれた紙によって生かされ、殺されてきたのです。ハラリはそれを総括して以下のように述べます。
書字の歴史はこの種の災難に満ち満ちているが、少なくとも政府の視点に立てば、行政の効率向上がもたらす利益は、たいていコストを上回った。筆を振るうだけで現実を変えようとすることの魅力に抗える支配者はいなかったし、それが惨事を招いた場合の救済策はどうやら、なささら大量の覚書を書き、なおさら多くの規準を定め、布告や命令を出すことだったようだ。
中略
税務当局や教育制度、その他どんな複雑な官僚制であれ、相手に回したことのある人なら誰もが知っているように、事実はほとんど関係ない。書類に書かれていることのほうが遥かに重要なのだ。
これらは学校制度にも適用できます。
例えば、管理職は自分の管理する学校の全教室の授業を毎時間見ることはできません。だから、学期末の各学年の成績一覧表や、学力調査の結果を見て、自身の管理の適切さを判断することしかできません。上がれば喜び、下がれば指導する。
教育委員会も文科省も同じです。
書類に記載された数値でしか、もはや教育内容の適否は判断できなくなっている。
いじめ件数が増えれば対策を指示し、学力が上がれば成果を強調する。
これを虚構と言わずして、一体、何と言えるのでしょうか。
虚構は悪くない。不可欠だ。お金や国家や協力などについて、広く受け容れられている物語がなければ、複雑な人間社会は一つとして機能しえない。人が定めた同一のルールを誰もが信じていないかぎりサッカーはできないし、それと似通った想像上の物語なしでは市場や法廷の恩恵を受けることはできない。だが、物語は道具に過ぎない。だから、物語を目標や基準にするべきではない。私たちは物語がただの虚構であることを忘れたら、現実を見失ってしまう。すると、「企業に莫大な利益をもたらすために」、あるいは「国益を守るため」に戦争を始めてしまう。企業やお金や国家は私たちの想像の中にしか存在しない。私たちは、自分に役立てるためにそれらを創り出した。それなのになぜ、気がつくとそれらのために自分の人生を犠牲にしているのか?
学校教育に殺されるのは馬鹿げている。
そんなものに悩まされるのも馬鹿げている。
これらは虚構なのだ。
しかし、虚構は人間にとって不可欠である。
さて、その中で、どうやって生きていくのかを考え続けないといけない。
