
【感想】『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』と「単語」に捉われない考え方
こんにちは、白山鳩です! クルッポゥ!
マガジン『本を読んだら鳩も立つ』での本のご紹介です。
前回の記事はこちらです。↓↓↓
さて、今回は引き続き森博嗣さんから。
『人間はいろいろな問題についてどう考えていけばいいのか』を通して、
「抽象的思考」の大切さ、
そして「単語」に捉われずに考えることの意義を考えていきます。
1つの記事あたり、だいたい5分で読めますので、お気軽にスクロールしてみてください!
ただし、ネタバレ注意です!
「抽象的思考」
さて、妙に長々としたタイトルの本を取り上げました。
106. 人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか
— 白山 鳩/note連載中 (@mbapigeon810) April 28, 2021
森博嗣さんの新書。
さて、本のタイトルにもなっているこの問いに対する答えが「抽象的思考」です。
そういえば、タイトル自体が既に抽象的であるとも言えます。名は体を表す。
そう、この著書では全編を通して「抽象的思考」の重要さを説いています。
客観的に考えるというのは、簡単にいえば、自分の立場ではなく、もっと高い視点から物事を捉えることだが、身近な表現でいえば、「相手の身になって」というような思考も含まれるだろう。
ようするに、自分を棚に上げて、自分の立場ではない視点から考えることである。
また、抽象的に考えるというのは、簡単にいえば、ものごとの本質を掴むことで、見かけのものに惑わされることなく、大事なことはどこにあるのかを探すような思考になる。
さて、「いろいろな問題」について考えるときには当然、その問題の解決方法を「発想」しなければなりません。
しかし……何かを発想するのって、けっこう大変ですよね・

この「発想」すなわち、「思いつく」ことは、実は一般に認識されている「考える」とは、まったく違った頭脳活動なのである。
だから、「考えればわかるだろう」と言われて考えてみても、
計算する、
論理的に導く、
手法を当てはめる、
過去の知識や経験を思い出す、
最適なものを選ぶ、
というような普通の「考え方」では実現できない。
「じゃあ、どうすりゃいいんだ!」と思ったみなさん。

ご心配なく、抽象的に考えりゃあいいんです。

発想というのは、論理のジャンプのような行為であって、筋道のないところへ跳ぶ思考ともいえる。
当然ながら、それは「非論理的」である。
発想には、想像力が必要のように思えるが、では、想像してみよう、と言われても、なにをどう思い浮かべれば良いのか、さっぱりわからないだろう。
想像というのは、ないものを思い浮かべることだが、
まったくないものを突然頭にイメージすることは極めて難しいし、
また、できたとしても、無関係で使いものにならない無駄なことばかり思いついてしまうだろう。
全然関係のないものではなく、少しは掠っていなくてはいけない。
つまり、なんらかの「ヒント」になりそうな、なにかしら「関連のあるもの」を思いつければ、ヒットの効率が高まる。
それができれば苦労はしねェ!!!
同書を読んだとき、鳩は思ったと言います。
「それができれば苦労はしねェ!!!」

「簡単に言うな! そんなもん、すぐにできるか!」
……しかし「簡単にできない」というのは、抽象的思考の本質でもあるのです。
長い時間をかけて、少しずつ自分が変化するしかない。
たった今からそれを目指し、いつも意識して、抽象的に考えよう、と自分に言い聞かせていなければならない。
非常に面倒なことなのである。
ただし、それを続けていると、自然に頭が馴染んできて、だんだんできるようになる。
人間には「慣れる」性質があるためだ。
「抽象的思考」とはいうなれば、「日々の姿勢」のようなものでしょうか。
なにか関係のあるものを思いついて問題を解決するというのとは逆の方向性になるけれど、
ふと思いついたことを、将来なにかほかのものに応用できないか、
とそのつど考える癖を持つことも大事だ。
目の前に問題がないときでも、使えそうなものをストックする。
そんな思考の「備え」というべき習慣を持つと良い。
目の前の事柄について意識的に、抽象的に考える習慣をつける。
そうして癖付けを続けていくと、次第に抽象的に考えられるようになっていく……。

手法のようなもの
森博嗣さんは「抽象的に考える」ためのハウツーはないとしながらも、「手法のようなもの」として、次の6つを語っています。
①なにげない普通のことを疑う
いろいろな物事に対し、すなおに「どうして?」と思うことが重要であり、この「見方」が新しい発想を生むと説いています。
ただし、日常的に口にしていると性格の悪さを誤解されるので、「自分で思うだけで充分」とし、「ただ、身近な人に聞いてもらい、反応を見ることは勉強になるだろう」としています。
残念ながら、鳩はもうすでに誤解と付き合う生き方を選んでしまっています。

②なにげない普通のことを少し変えてみる
「もしも、~だったら」と仮定のことを真剣に考えてみると、思考の柔軟さが養われるとともに、具体的な条件を排除するので抽象的な思考の基本にもなると説いています。
③なるほどな、となにかで感じたら、似たような状況がほかにもないか想像する
類似の事象を考えることで共通点が抽象化されるとともに、類似点からのフィードバックで発想も修正され、次第に普遍的な法則へと洗練されるのだとしています。
いわゆる「帰納法」とはこの考え方を指していますね。

④いつも、似ているもの、喩えられるものを連想する
目にしたものを別の言葉でたとえる習慣は有効だとしています。
鳩の場合は、「なんだか人生みたいですね」という比喩が気に入っています。

⑤ジャンルや目的に拘らず、なるべく創造的なものに触れる機会を持つ
「絵」「詩」「音楽」といった芸術に触れる機会が、ものごとを抽象的に捉える「完成」を育てるとしています。
自分自身の感性という判断軸に基づいた審美眼こそが抽象するための力です。
「他人がどう評価しているか」を気にするのは、
「みんなが笑っているから私も笑う、というロボットのような動作であって、人間の感性のすることではない」
と、同書は批判しています。
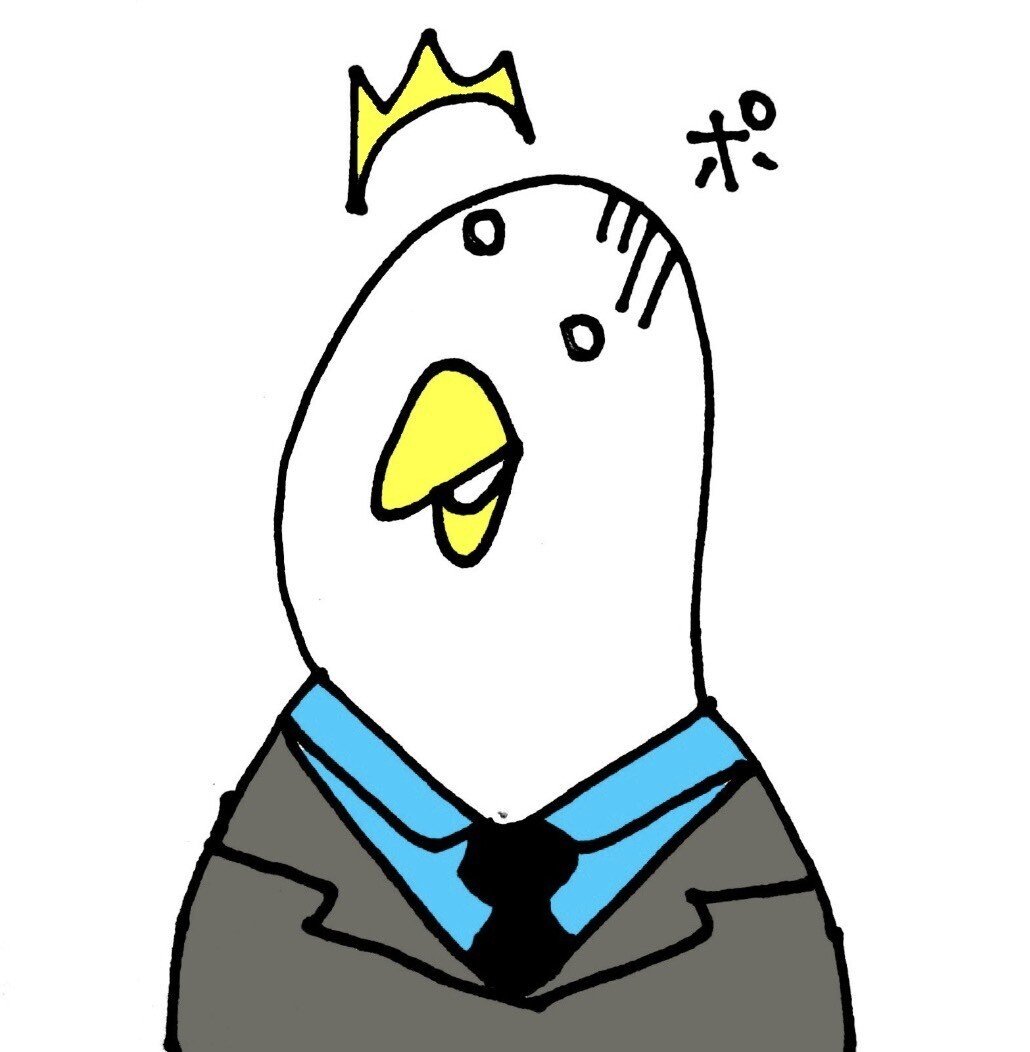
⑥できれば、自分でも創作してみる。
創作するときは、「なんか、こういうのって良いな」と思った、「感動できるけど言葉にならない」気持ちが原動力となります。
「創作へ向かう欲求には、抽象的なものの捉え方が根底の部分で不可欠なのだ」と森博嗣さんは指摘しています。
抽象的な思考の注意点 | つかず離れず
さて、森博嗣さんの座右の銘として、
「なにものにも拘らない」
というのは、本人もさまざまな場面で発言しています。
抽象的な思考は、自分の中で「普遍的な真理」という型を生みだすのに役立ちます。
しかしそれは同時に、自分の中の「普遍的な真理」に捉われるきっかけにもなる、と説いているのです。
過去に自分が持った発想が、抽象的な「型」あるいは「様式」になって、次の発想のヒントになる。
抽象的に考える人ほど、この型を沢山持っていて、どんどん問題解決能力が高まる理屈になるのだが、実はそうとばかりもいえない。
それは、自分が過去に発送した「型」や「様式」に囚われるようになるからだ。
型の数が増えるほど、その型の再利用で問題が解決できる機会が多くなり、そうなるともう新しい発想を生み出す姿勢が失われる。
「型」の功罪については、こんなことも語っています。
また、自分自身が発想したものではなく、人から教えられた「型」も、その人の考え方を縛る結果となる。
学校で子供たちに算数の問題を解く方法を教えているが、「つるかめ算」という型を教えることによって、その子供は、それをヒントにした発想をしなくなる。
(中略)
つるかめ算が凄いところは、「もし、つるの脚が四本だったら」と想像するところにある。
そんな四本足のつるはこの世にいない。
それでも、問題を解くために、それを想像するのが人間の「凄さ」なのである。
痺れるくらい凄まじい発想ではないか。
この凄まじさを体験することこそが、算数の醍醐味であり、教育の本質といって過言ではない。
鳩は個人的に、世間で言うところの「ことわざ」もまた、同じようなものだと考えます。
たとえば、「意外な場所や筋違いな理屈で仕返しをすること」という意味で、「江戸の敵を長崎で討つ」ということわざがあります。
「意外な場所や筋違いな理屈で仕返しをすること」という意味を最初に抽象し、そして「江戸の敵を長崎で討つ」ということわざに初めて具体化した人を、鳩は尊敬します。
一方で、このことわざを覚えて、一つ覚えのように「江戸の敵を長崎で討つ」ということわざを使うだけなのも考えものです。
ことわざの裏にある、抽象と具体を行き来する「痺れるような」発想を忘れてはいけません。

また、「型」に関しては、「物事の細部の違いを受け入れられなくなる」という点も注意喚起されています。
当然ながら、注意する必要があるのは、「型」はあくまでも「型」であり、
また抽象化されたものは、具体的なディテールが捨てられたものだ、
という認識を忘れないことである。
だから、こういった考えを持つことは、自分自身の理解のためだとまず割り切る方が良い。
他者にあれこれ話すことは誤解を招くだろう。
「あいつは、こういうタイプの人間だから、きっとこう考えているはずだ」などと吹聴しない方が良い。
逆に相手からは、「この人は、人間を全部自分のモデルに当てはめて考えようとする」という「型」で見られてしまうだろう。
(中略)
さらに言えば、深い考えをする人間ほど、なかなか本心というものはわからない。
どう見せようか、ということを考えて行動しているため、言動から類推できることは、あくまで作りもの、演じられている外交的な型でしかない。
そういう人は、場合によってはまったく違うタイプになることがあって、あたかも多重人格者のようにも観察されるが、それは、こちらの見方が、部分的だから起こることである。
重要なのは、決めつけないこと。
これは、「型」を決めてしまって、そのあとは考えない、では駄目だという意味だ。
抽象的に、ぼんやりと捉えることで、決めつけない、限定しない、という基本的な姿勢を忘れないように。
たしかに、
「趣味は人間観察です」
などと言っている人が、
実は人間のことを類型でしか見ていないせいで、かえって一人ひとりの特徴をつかめないでいるなあと、鳩は思うときもあります。

他人を分析することは大切だが、
その分析結果を全面的に口に出さない方が良いし、
その分析に基づいて行動するときは、あくまでも仮説だということを忘れてはならない。
(中略)
そもそも、「型」は抽象的であり、具体的なディテールを剝ぎ取った「本質的な傾向」を示すものだ。
必ずいつも絶対にそうなる、というものではない。
そこまで単純化できるはずがないことは、誰だって想像できるだろう。
怒りっぽい人だって、笑顔になることはある。
どんなものにも例外はあるし、また、あるとき突然その型から脱皮するような変化が訪れるかもしれない。
抽象的に考えるというのは、ぼんやりとしたイメージや傾向といった「型」を抽出し、それを応用することであるが、
その「型」を言語化したときに具体的になりすぎて、杓子定規に「常にそうなるものだ」と決めつけてしまうと、持ち味だった「ぼんやりとした抽象性」が失われてしまう。
この落とし穴に、いつも気をつけること。
「単語」に捉われない考え方
さて、ここまで「抽象的思考」に関する話を、同書を頼りに見てきました。
この「抽象的思考」の大切さを頼りに、鳩がいま一番重要だと感じているのは、「単語」の落とし穴です。
たとえば、「あの人は『犬みたい』だね」とたとえたとしましょう。
「犬みたい」という言葉を聞いて、みなさんはどんな印象を受けますか。
「ペットみたいでかわいい」という印象で捉えたでしょうか。
「主人に忠実な存在」という印象で捉えたでしょうか。
「よく走るヤツ」という印象で捉えたでしょうか。
「主人に忠実な存在」という印象で捉えたとしても、
「上司に忠実で、よく仕えてくれている」という良い印象なのか、
「自分の考えもなく、ただ使われているだけ」という悪い印象なのか、
それは人によってさまざまです。
そのように、それぞれが具体的なイメージに捉われた状況のまま会話をした結果、コミュニケーションがとんちんかんなまま終わってしまい、
「何かを話したようで、実は何も話していなかったような……」
という気分で終わることはありませんか?
子どもたちが大きくなったときには、
— 白山 鳩/note連載中 (@mbapigeon810) March 17, 2021
「大人というのは会話しているように見せかけて、実際はほとんどの場合、自分の言いたいことを交互に発信しあっているだけだよ」
ということを伝えたい。
「自分がその言葉に対して持っている具体的なイメージ」だけに頼った会話をすると、このような結果に終わることがあります。

特に、何かを語るときの重要なテーマとして、象徴のようなものを持ち込むときにはこれが重要ではないでしょうか。
たとえば「今日は『企業風土と犬』について語ります」と言ったとき、
あなたが伝えたいことは、
「犬が主人の振舞いを見て態度を決めるのと同じように、
従業員は企業の方針を見て、働く態度を決めますよ」
という内容なのに、
「犬といっても、日本の犬と海外の犬では、必ずしもそういう態度を取りませんよ。
たとえば海外の犬の場合、このような例外があって~」
などと言われると、
(あれ、本当に話したかったことはなんだっただろうか……)
と、具体的思考の迷宮に入り込んでしまいます。

たとえ話をする。
あるいは、ある単語を用いる。
そんなときでも、
「私がいま伝えようとしていることはこれなんだ!」
という、本質を抽象して忘れない態度を取らなければ、自分自身も「具体の迷宮」に入り込んでしまいます。
「具体的」な単語は物事をイメージさせやすくなりますが、劇薬でもあるということを覚えておこうと思った鳩でした。

次回「本を読んだら鳩も立つ」では、『風の歌を聴け』の冒頭の一節から、
「同じだけど違うもの」について話してしまう瞬間について書いていきます。
お楽しみに。
to be continued...
参考資料
・森博嗣(2013)『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』(新潮新書)
