
御成敗式目 - 日本最初の固有法
今回は御成敗式目をご紹介します。
(1)御成敗式目の意義
・古くは律令、新しくは大日本国憲法、これらは外国から輸入したものですが、この御成敗式目は、日本の当時の慣習(泰時的には「道理」)を文章化したものなので「固有法」と呼ぶことは可能だと思います。そんな御成敗式目には当時の(主に武家の)価値観が表れていると思ったので一度調べてみました。現在主流の西洋的価値観との違和感の元があるのではないかと思います。
(2)御成敗式目の概要
・源頼朝が鎌倉幕府を作ったと言っても、彼が日本全国を支配したわけではなかった。まあ武士団の中で一番力はあるが、あくまでも棟梁の一人と言う程度でしょう。そして朝廷を頂点とした「権威」にぶら下がる貴族や寺社といった勢力は別の統合をしていて、いわば2つの政権が並立しているようにみえる。武家は半独立しているようでもあり、天皇を頂点とする国家権力の一部にも見える。軍事的には武家が強いものの、歴史・文化・経済を背負う公家には頭も上がらないという緊張関係です。
・しかし、この均衡を破ったのが承久の乱。鎌倉幕府執権の北条義時が朝廷(後鳥羽・順徳・土御門の各上皇他)と正面対決をしてこれに勝利し、3上皇を島流しにして、更に仲恭天皇(順徳天皇の子で在位わずか3ヶ月で3歳)を退位させ後堀河天皇(わずか10歳)を擁立するという前代未聞の結果となった。なぜ前代未聞かと言うと、これまでは武士はあくまでも院宣や令旨といった皇室の命令に基づく戦いしかしてこなかったし、今回は院宣は逆に義時追討であり、彼らは逆賊なのであった。北条氏はここで勝てば天皇の地位を奪えた可能性はあるが、そこまではしていないことは注目でしょう。それほどの権威が「(個々の天皇にではなく)皇室」には備わっていたということでしょう。しかしこれ以降は、事実上朝廷側の権力は制限され、幕府の権力が全国に及んで行くことになる。武家政治の始まりと言えます。
・そしてこれまでは法と言えば律令や公家法などしかなく、処理できない事件も多く発生したり、各地で歴史や慣習も異なることもあって、武家社会の統一的な裁判の規範として、北条泰時を中心にして評定衆などとも協議の上にこの御成敗式目が1232年に制定された。その後、御成敗式目を基本(本式目)として、判例などを元に条文が追加され、追加文は700条ほどの規模になっている。
(3)御成敗式目の目的:北条泰時による「消息文」より
・御成敗式目は武家社会の特徴である「道理」と、源頼朝以来の「先例」を基礎としていて、従来の公家法とは異なる規定も含まれていたため、泰時は六波羅探題として京都にいる弟の重時に二度にわたって書簡を送り、式目制定の趣旨を朝廷側に正しく理解してもらうように伝えました。内容はおおよそ以下の通り。
「裁判に関わる法令を集めたものは本来目録と名づけるべきですが、やはり政治についての内容も載せたので、これを執筆した人たちは当初『式条』という字をあてました。しかし、私はその名が大袈裟に感じたので、『式目』と改めました。」
「この式目が何を根拠にして書かれたのかと不審に思うでしょう。実はこれといった根拠はありません。ただ「武家の道理」から導ける事柄を書いたものです。こういうことを事前に定めておかないと、争い事が理非ではなく当事者の力の強弱によって決まってしまう恐れがあり、また過去の判例を忘れたふりをして再度訴訟を起こすような輩もいます。ですから事前に裁判のきまりを定め、当事者の身分の上下に関わらず、依怙贔屓なく判決が下されるように、このように詳しく記述しておきました。」
「この内容は律令の内容と少々異なる点もあります。律令格式は、漢字を知っている者にとっては簡単に読めるでしょうが、仮名しか知らない者は、漢字を見だけでもう駄目になってしまいます。ですから、この式目は世間に多い仮名しか知らない者にも納得させやすいように、武家への配慮のためだけに作ったものです。これによって京都の朝廷での規則や律令の規定を変える気など毛頭ありません。」
「律令格式は立派なものではありますが、武家や民間の中で、それを知っている者は100~1000人のうちで1~2人もいないでしょう。ほとんどの人が律令を知らないため、知らず知らずの内に犯してしまって、急に律令でもって正邪を判断されたり、律令に詳しい官僚が法律を恣意的に引用したりして、判決結果が一致せず、皆迷惑しています。従って、字の読めない人でもあらかじめ考え、判決が時によって変化しないように、この式目を作成致しました。京都の人々で非難を去れる人がいたら、この趣旨を重々心得て伝えてもらいたい。恐々謹言。」
・つまり、あくまでも武家の争いごと解決の為に作ったものですと、朝廷にずいぶん気を使っていますが。その一方で武家世界に対する立法権・司法権を宣言しています。このあたり、朝廷と幕府の関係をどう理解するかはなかなか難しい。私は例えばイランの最高指導者と大統領の関係になぞらえてます。イランの最高指導者は俗事(三権)より上の精神的存在とでもいうか。イスラム教国に限らず、国という共同体は全員が守るべき最低限のルールがありますが、そのルールには背後に価値基準を持っています。イスラム教国の場合はイスラム教ですが、日本の場合にも確実に何かがあります。コーランの様に文章化されていないだけで、私のこのNoteの主題はそこにあります。
・泰時の「道理」は「忠君愛国」「親孝行」「夫唱婦随」「信賞必罰」と言った従来からの価値を重視すれば世の中は治まるということでしょう。泰時が際立って評価が高いのは、このように(天皇個人ではなく)皇室や伝統に基づく価値への忠臣であり、かつ性格的に温厚で謙虚で無欲であり、いわゆる大岡裁き(というか、時代としては泰時が元祖ですよね)も見せ、一方戦いでは勇猛であるというところにあるのでしょう。
・これがあるべき日本人の1つの表れと言えます。ただ泰時にしてみれば、単に逆臣とその口車に乗った失徳の皇族を討ったということに過ぎないのかもしれません。つまり湯武放伐そのものです。なので承久の乱後も相変わらず皇室への敬意は変わらないのではないでしょうか。
・そんな泰時が弟子入りしたのは京都高山寺の明恵上人で、この方から相当な影響を受けているという話です。その意味では明恵という人も大変興味深い。この辺りの事情は『日本的革命の哲学』(山本七平)に詳しい。これも名著です(^^)。投稿の多くの部分はこの本に依存していますが、ただ例によって読むのは一苦労です。
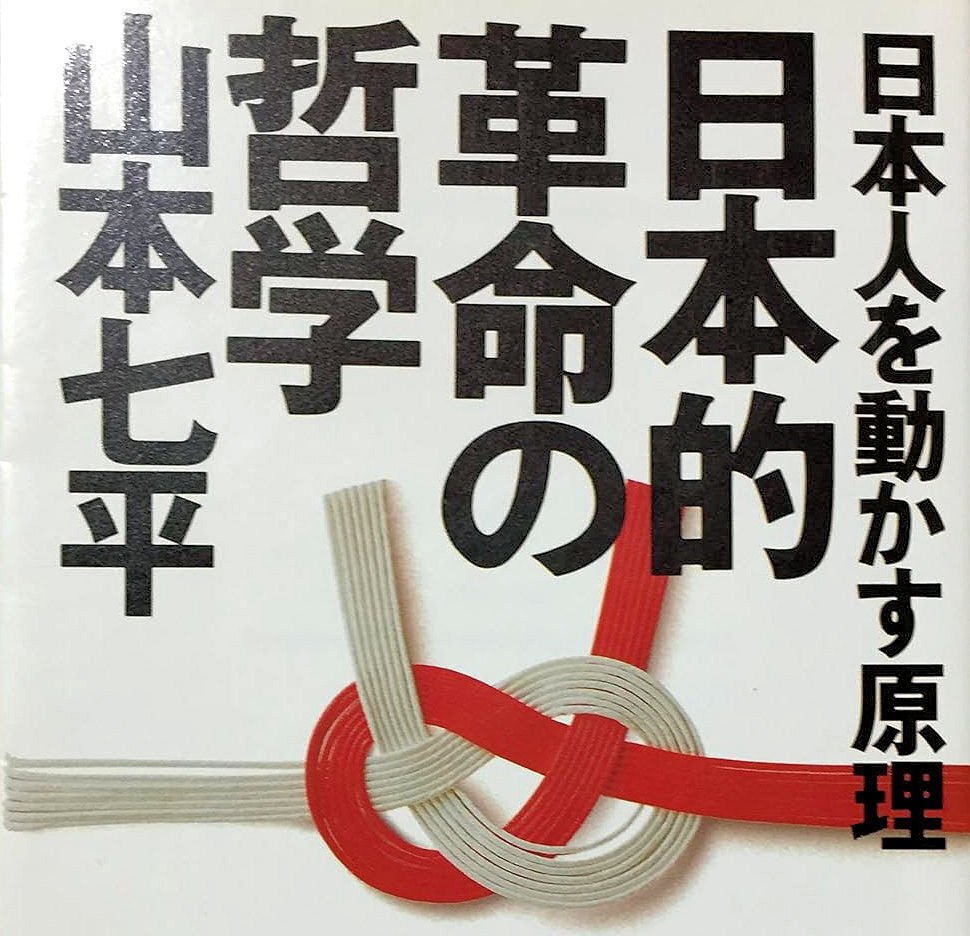
(4)当時の政治体制:
・当時の複雑な政治体制が分からないと条文を見ていてもよくわからないので、ざっくり解説します。細かなところで正確性には欠けるかもしれませんが、おおよその理解としてはこんな感じで良いかと思います。
①朝廷側(公家)の体制:
・古代の公地公民から始まり、墾田永年私財法以降、公家や寺社中心に土地所有者が増えてきた。それらを「荘園」と呼びます。そもそも公地公民時代は朝廷の財政基盤は収穫物の3%程度を租(税金)として徴収することで成り立っていたのですが、荘園は所有者によって好き勝手に経営されており、脱税もやり放題。困った朝廷は「国司」という管理者を任命し、その国司に「細かいことは言わないので、とにかく税金を納めてくれたらあとは何をしても良い」みたいな丸投げを行っていた。
・国司の支配下にはない「荘園」もあり、ここでは天皇・貴族・寺社が直接領主となっていた。天皇などの最上級荘園領主を「本家」、一般貴族や寺社の領主は「領家」と呼ぶ。また裁判権を持つ荘園領主は「本所」と呼ばれたりする。
②幕府側(武家)の体制:
・将軍と主従関係を結んだ武士を「御家人」と言います。通常は一族の長(惣領)が将軍と主従関係を結び、一族郎党はその惣領に従います。御家人でない武士もいたりして、彼らは荘園や寺社に直接雇われています。御家人になるか否かは武士側が選択できたようです。
・鎌倉幕府の将軍を頂点に国(武蔵とか摂津とか68カ国あった)ごとに設置した地方官が「守護」。守護の役割は「大犯3箇条」と言われ、①御家人の大番催促(京都での皇室・洛中の警護)、②謀反人の追補、③殺害人の追補です。簡単に言えば警察機能(軍事や治安維持)が主な役割。守護は信頼の厚い御家人から選ばれます。
・「地頭」は鎌倉幕府が守護とは別に荘園や公領ごとに(守護は国ごと)細かく設置した役職。御家人から選ばれます。守護が兼任していることも多いというか、地頭の中のリーダー格が守護のイメージかもしれません。主な役割はその荘園・公領の徴税・治安維持です。しかし幕府は守護と御家人が個別の主従関係を結ぶのを嫌っていて、守護は頻繁に交替していた。
・守護も地頭も本来は幕府の行政官に過ぎなく、必ずしも領地を「所有」している訳ではありません。土地は荘園とか公領とかの形で貴族や寺社などが過去から所有をしています。行政官は警察であり国税庁という感じです。とはいえ論功行賞で土地を譲り受けた御家人もいますので、彼らが地頭に任命されれば、「土地持ちの地頭」になります。
・国司と地頭の関係も正直わかりにくいですが、国司は奈良時代からの役人で、現地に行かずに代理人に任せてサボっていたりして次第に力を失い、逆に地方に根差した御家人が実質的に力を持ち、国司はその職を奪われてきたようです。
③武家は「将軍と御家人の関係」だけで、公家は「朝廷の国司の関係」だけなので、厳密には2つの世界が存在しています。承久の乱の時に出陣した泰時は途中で引返し父義時に「もし途中で後鳥羽上皇自身の御旗に出くわしたらどうすれば良いか」尋ねたところ、義時は「上皇に弓を引くことは出来ない。武装解除して上皇の命に従うこと」と命じた。この逸話が示す通り、武家の上位には歴史的・文化的・思想的に皇室があるという意味では1つとも言えます。
大まかに図示すればこんな感じかと思います。

関係者にとっては所領がメシの種であり、荘園領主との紛争を含め、勝ち取ったもの・譲渡されたもの・相続されたものなど所有権移転の事実に対して様々な争いごとが起きていたので、これの判断標準を求めて御成敗式目が作成された。また難しい言葉で書かれた律令格式は多くの武士は理解できなかったという背景もありそうです。
(5)各条文について。
・では各条文を見ていきましょう。本式目だけですが51条あります。
まずはリストアップしておきます。
第1条:「神社を修理し、祭祀をきちんと行うこと」
神は敬うことによって霊験があらたかになる。神社を修理してお祭りを盛んにすることはとても大切である。そうすることによって人々が幸せになるからである。また、供物は絶やさず、昔からの祭りや慣習をおろそかにしてはならない。関東御分国にある国衙領や荘園の地頭や神主はこのことをよく理解すべし。神社を修理する際に領地を持つ神社は小さな修理は自分たちで行い、手に負えない大きなものは幕府に相談すること。内容を調べた上で適切な方法をとる。
第2条:「寺社を修理して、僧侶のつとめを果たせ」
僧侶は寺や塔の管理を正しく行い、日々のつとめに励むこと。寺も神社も人々が敬うべきものであり、建物の修理とつとめをおろそかにして非難されるようなことがあってはならない。また、寺のものを勝手に使ったり、おつとめをはたさない僧侶は直ちに寺から追放せよ。
⇒神仏への祈りが世の中の安寧につながるという思いが強かったのでしょう。特にこの時期は戦乱だけでなく寛喜大飢饉など多くの災害も発生していた。対象は関東御分国に限られるようですが。
第3条:「守護の役割は「大犯3箇条」が基本」
頼朝公が決められて以来、守護の仕事は、大番催促と、謀反人・殺人犯の追補(注:「大犯3箇条」と呼ばれる)である。更に、夜討ち、強盗、山賊、海賊の取締まりもある。守護の中には代官を村々に送り勝手に村人を使役したり徴税する者がいる。更に国司でもないのに地方を支配したり、地頭でもないのに徴税する者もいる。それらは全て違法であり禁止する。
また、代々の御家人といえども所領を持たない者は、勝手に大番役(注:京都・鎌倉での護衛。名誉な仕事されている。)にはつけない。荘官の中には御家人といつわって、国司や領家の命令に従わない者がいる。このような者には望んでも諸役を任せない。頼朝公が決めたときのように守護の仕事は大番役を決めることと、謀反人や殺人犯の調査・逮捕であり、それ以外のことをしてはならない。この取り決めにそむく守護が国司や領家に訴えられたり、地頭や庶民に対する不法が明らかになり次第、解任し適切な者を守護に任命する。また、守護の代官は一人しか決めてはならない。
⇒守護に関しての細かな定義がある。限定列挙であることで、朝廷に気を使っている。
第4条:「守護が罪人から勝手に所領を没収することを禁止」
重犯罪は詳細に取調べ、結果を幕府に報告し、幕府の指示に従わなくてはならない。これを怠り守護が勝手に罪人から没収した財産を自分のものにすることは許されず、従わない者は解任する。また、例え重罪人であってもその妻子の住む屋敷や家具を没収してはならない。共犯者の場合、没収すべき財産が無ければ財産に関して不問とする。
⇒守護が私的に運用することを禁止。
第5条:「集めた年貢を本所(=荘園領主)に納めない地頭の処分」
年貢を本所に渡さない地頭は、本所の要求があればすぐそれに従うこと。不足分はすぐに補うこと。不足分が多く返しきれない場合は3年のうちに本所に返すこと。これに従わない場合は地頭を解任する。
第6条:「国司や領家の裁判に幕府は介入しない」
国衙や荘園の本所あるいは神社や寺が起こす裁判に幕府は介入しない。本所の推薦状がなければ荘園や寺社の訴えは幕府ではとりあげない。(御成敗式目は御家人が対象である。)
第7条:「頼朝公や政子様から与えられた領地の権利は奪われない」
頼朝公をはじめ源家三代の将軍のとき、および二位殿(北条政子)の時に御家人に与えられた領地は、本所などからの訴えがあっても権利を奪われることはない。
所領は戦の勲功や役人としての働きによって御家人に拝領されたものであり、その所有には正当な根拠がある。にもかかわらず「先祖の土地なので返せ」と訴えることは、御家人にとってはとても不公正なことである。従ってこのような訴訟は取りあわない。ただし、その御家人が罪を犯した場合には領主が訴えることは認める。但し一度判決が出た後に再び訴訟することは禁止。以前の判決を無視することは許されず、そのような場合は不実であることを書類に記録する。
⇒出世は出自・階級・コネではなく「実績」主義であるべきことが表れている。今でもそうですね。
第8条:「御家人が20年間支配した土地は、元の領主に返す必要はない」
頼朝公が取り決めたように御家人が20年間支配した土地は、元の領主に返す必要はない。しかし、実際には支配していないのに、支配していたと偽った者には、たとえ証明書を持っていても、適用されない。
⇒これも有名な「二十箇年年紀法」で20年という時効を設定したもの。
第9条:「謀反者の扱いは過去の例を参考にしながら裁判を行う」
謀反の刑罰を細かく決めておくのは難しいので、くわしく調べて、過去の例を参考にしながら裁判を行う。
第10条:「殺害や刃傷などの罪科は無関係な犯人の父子には及ばない」
言い争いや酔った勢いでの喧嘩であっても相手を殺してしまったら殺人罪であり、犯罪者は死刑か流罪とし財産は没収する。ただし、犯人の父子がそれに無関係ならば、その者たちは罪は及ばず無罪であり、これは傷害罪についても同様である。
ただし、子や孫、あるいは先祖の仇と称して人を殺害した場合は、たとえ犯人の父や祖父がその旨を知らなくても同罪とする。結果として父祖の憤りをなだめるために宿意(積年の恨みを晴らすこと)を遂げることになるからである。なお、子が地位や財産を奪うために殺人を犯した場合は、父が無関係の場合は無罪とする。
⇒全体に「家」が最優先ではあるが、ここは「個」の責任を優先させている。仇討については同族を罰することで、争いを抑制しようとしている。当時は戦で家族が敵味方に分かれて戦うことも多かったからかも知れません。(→仇だらけになってしまう)
第11条:「夫の罪が重罪の場合は妻の財産が没収されるが、軽罪の場合は没収されない」
重罪(謀反・殺害・山賊・海賊・夜討ち・強盗)の場合は夫の罪であっても妻の領地は没収される。しかし、夫が口論によって偶然(ぐうぜん)に相手を傷つけたり、殺害してしまったような場合は妻の領地は没収されない。
第12条:「悪口の禁止」
争いの元である(裁判での)悪口はこれを禁止する。重大な悪口は流罪とし、軽い場合でも牢に入れる。また、裁判中に相手の悪口をいった者は直ちにその者の負けとする。また、裁判の理由が無いのに訴えた場合はその者の領地を没収し領地がない場合は流罪とする。
第13条:「他人に暴力をふるうことの禁止」
人に暴力をふるうことはうらみを買うことであるからその罪は重い。御家人が相手に暴力をふるった場合は領地を没収する。領地がない場合は流罪とする。御家人以外の場合は牢に入れる。
第14条:「代官の罪を幕府に隠した主人は罪になる」
代官が罪を犯した場合、任命した主人はそのことを幕府に報告すれば主人は無罪とする。ただし、主人が代官をかばって報告を怠った場合は主人の領地は没収し代官は牢に入れる。代官が年貢を横取りしたり、あるいは先例や法律を破った場合にも主人を同罪とする。
代官もしくは本所による訴訟が行われる時、鎌倉もしくは六波羅探題より呼び出しがあったにもかかわらず応じなかった者は主人の領地を没収する。ただし、犯した罪の重さによって軽重がある。
第15条:「文書偽造文書は罪」
偽の書類を作った者は所領を没収する。領地を持たない者は流罪とする。庶民の場合は顔に焼き印を押す。頼まれて偽造文書を作った者も同罪とする。また、裁判中に嘘をついた者は神社や寺の修理を命じ、それができない者は追放とする。
第16条:「承久の乱で謀反人でなかったことが証明された者の領地は返還される」
承久の乱後に領地を没収された領主のうち、後に謀反人でなかったことが証明された者の領地は返還される。既に、返還する領地に入っていた新たな領主には代わりの領地を与える。彼らは合戦の時によく働き戦功があった者たちだから。
御家人であったにもかかわらず幕府に謀反した者の罪は重く、死罪の上、財産は没収する。ただし、今より以後、朝廷の味方になっていたことが分かった者については、特別に許し財産の五分の一を没収する。御家人以外の下司や荘官の場合は今後財産を没収することはしない。なお、本領主と称して財産を没収された時の領主を違法な領主として、「私こそ真の領主なので没収地を返して欲しい」などの訴えが多いが、その時の領主をさしおいて今になってから調べることは不適当であるので、このような訴えは却下する。
第17条:「承久の乱で鎌倉方と朝廷方に分かれて参戦した親子でも鎌倉方は恩賞が朝廷側は罰が与えられる」
御家人の場合、父子が朝廷側、幕府側と分かれて戦ったとき、幕府側にいて戦功のあった者が父であれ子であれ恩賞が与えられる。反対に朝廷側であったときには父であれ子であれ罰せられるものである。なお、西国の武士の場合、父子いずれかが朝廷側であった場合は互いに同意した者として父子共に罰せられる。しかし、父子が遠く離れていて互いに連絡がつかなかったような場合は、朝廷側についた者だけを罰する。
第18条:「女子が相続した所領にも悔い返し権を認める」
男女の違いはあっても親の恩は同じ。これまで女子には返還の義務はなかったが、今後は相続したあとであっても親は所領を取り返すことが出来る。これは、後の争いを恐れて女子に相続することをためらったり、女子が親に対して不道徳な行いをすることを防ぐためである。この保障により、相続した女子が親に孝行をし、親は安心して女子を養育し、土地を与えることができる。
⇒女性にも相続権があったことは特記すべき事と思います。式目が慣習法であることを考えると、当時既に女性相続権が一般的に認められていたのだろうと思われます。
⇒公家法では女子への悔還はなかったが、武家法では男女同じとした。悔い返し権については26条を参照。
第19条:「忠実を装い財産を与えられた家来が主人死亡の後に態度を変えた場合は没収する」
主人を敬い、よく働いたために財産やその譲り状を与えられた家来が、主人死亡の後にその恩を忘れて財産を奪おうなどと子供等と争った場合、その財産を取りあげて主人の子供等に全てを与えることとする。
⇒これも一種の他人への悔い返し権でしょう。
第20条:「譲り状を与えた子供が死んだ場合、御家人は次の相続人を自由に決めてよい」
財産の譲り状を与えた子供が生きていても相続権を変える場合もあるので、子供が死んだ場合、(当然)御家人は次の相続人を自由に決めてよい。
第21条:「離別した妻や妾が譲り受けた所領でも、彼女らに大きな落ち度があった場合は知行できない」
離別した妻や妾に大きな落ち度があった場合、前夫から譲り受けた所領を持つことは、契約書があっても知行することはできない。前夫が新しい妻や妾のことだけを大切にし、なんの落ち度もない前妻や前妾に与えた土地を取り返すことはできない。
第22条:「家の為によく働いた先妻の子供にも財産を与えること」
家のためによく働いた子供であるにも関わらず、後妻やその子らに追い出されてしまった者には、相続の際に嫡子相続分の五分の一をその子に分け与えること。ただし、離縁前に多少なりともその子に財産が分けられていた場合はその分を差し引いても良い。しかし、その子が怠け者や不幸者のときはその必要はない。
⇒家を守るということが最重要であることが見えてます。
第23条:「夫の死後、女性が養子を取って所領を譲ることは問題ない」
夫婦に子供が無く、夫が死んでしまった後に養子をむかえ領地を相続させることは、頼朝公の時から認められており何ら問題はない。
⇒女性は養子も取れます。
第24条:「後家が再婚した場合、亡夫から相続した所領は亡夫の子供に与えること」
夫の死後、妻はその菩提を弔い、式目の定めのとおりに働かなくてはならない。にもかかわらず、死別後すぐに再婚するというのは良くない行いである。後家が再婚する時には亡き夫から遺産相続された領地を亡夫の子供に与えなければならない。子供がいないときには別の方法を考えて対処する。
第25条:「御家人の婿となった公家は武士としての働きを行うこと」
たとえ出自が公家と言っても、御家人としての働きを行うこと。父親が存命中の代行は許されていても、父親死後はその者が御家人として働かなくてはならない。それでもなお公家としての実家の権威を利用して怠る場合は、所領を相続することを辞退させる。また武家の娘が幕府内で働くときに公家のしきたりを入れてはならず、そのような者は所領を治めることはできない。
第26条:「一旦子供に相続させた土地を、父母の気持ち試打で別の子供に相続させなおすことは可」
御家人が所領を子供に相続し将軍から証明書をもらっていても、父母の気持ちによって他の子供に相続を替えることができる。
⇒これが有名な悔い返し権です。「父母の」という点も要注意です。所有権に絶対性が無ければ資本主義経済が成り立たないが、日本人には心情的に理解できる部分があるのではないでしょうか。例えば、友達が大事に使うというので、安く譲ってやったモノを、その友達がメルカリで高値で売って儲ける行為に何か釈然としないものを感じないでしょうか?親が子供の為に残したものを売り払ってハワイ旅行の資金にする行為に少し罪悪感を感じるか否かですね。ここに日本人の心情が純粋な資本主義と調和しない原因がありそうです。
第27条:「親が遺産配分を決めずに亡くなった場合は働きに応じて妻子に分配する」
御家人が相続の決める前に死亡した場合は、残された財産を働きや能力に応じて妻子に財産を分配すること。
⇒能力主義が表れている。評価対象には妻や女子も含まれている。
第28条:「ウソの訴えをしてはならない」
言葉たくみに人をだますことの罪は大変に重い。所領を望んで嘘の訴えをおこした者はその者の領地を没収する。領地がない場合は遠流とする。また役職が欲しいために嘘をついた者はその職には就かせない。
第29条:「本来の裁判官をさしおいて、別の裁判官に頼むことを禁止」
裁判を有利に進めるために担当の裁判官をさしおいて他の裁判官に頼むことが分かった場合は、調査の間しばらく裁判を休廷する。そのようなことは許されない。担当役人はそのような二重の取次をしてはならない。また、裁判が長引き20日以上かかった場合は問注所(もんちゅうじょ)において苦情を述べることができる。
第30条:「問注所の判決の前に有力者の書状を提出し、裁判を有利に進めることの禁止」
有力者を知るものが得をし、そうでないものが損をするような不公平な裁判は幕府の信頼を失うので禁止。それぞれの言い分は裁判中に述べること。
第31条:「裁判に負けた者がやり直しを訴えることの禁止、誤った判決を下した裁判官の罷免」
裁判に負けたにもかかわらず「偏向判決」だと、事実ではないことを持ち出し裁判官に不服を訴えた場合は、領地の三分の一を没収する。その領地がない場合は追放とする。ただし、実際に偏った判決を行った裁判官は辞めさせ、再び裁判官に任命してはならない。
第32条:「盗賊や悪党を自領内に匿うことの禁止」
地頭は領内に盗賊がいることが分かったらすみやかに逮捕すること。また地頭が賊徒をかくまった場合は同罪とする。もしその疑いがあった場合は鎌倉で取り調べを行い、その期間中に地頭が国元に帰ることを禁止する。また守護所の役人が入れないところ(管轄外)に賊徒がいたと分かった場合でも家来を遣わしてすみやかに逮捕すること。これを行わない地頭は解任し代行の者をおく。
第33条:「強盗犯と放火犯は断罪(=馘首)」
これまでの決まりどおりに強盗犯は断罪(馘首)する。放火犯も強盗犯と同じあつかいとし、これらの犯罪を無くすこと。
第34条:「人妻との密通や道路での女性拉致の禁止」
人妻と密通をした御家人は所領の半分を没収する。所領がない場合は遠流にする。相手方の人妻も同じく所領の半分を没収し、ない場合は遠流とする。また、道路上で女性を拉致(らち)することを禁止する。それを行った場合、御家人の場合は100日間の停職とし、郎従以下の一般武士は頼朝公からの先例にしたがい片側の髪をそる。僧侶の場合はその時々の状況に応じて罰を決める。
第35条:「被告が呼び出しに応じない場合の裁判は原告だけで行う」
呼び出しを三回無視した被告は、原告だけで裁判を行う。原告が負けた場合は争っている財産や領地は他の御家人に分け与える。牛馬や下男などはその数を数えた後に、神社やお寺の修理のための寄付をしなくてはならない。
第36条:「原告が自分に有利な境界線を持ち出して裁判を起こした場合は厳密に調査する」
自分に有利な境界線を持ち出して領地を広げようとするものがいる。敗訴しても今の領地が減らないと思うからである。今後はこのような訴えがあった場合、現地に調査官を派遣し厳密に調査して、訴えが不当な場合は奪おうとした領地と同じ面積の土地を訴えられた者に与える。
第37条:「朝廷の領地を奪うことを禁止」
頼朝公の時に禁止されたにもかかわらず、いまだに上皇や法皇またはその女御の荘園を侵略する者がいる。今後もこのことを行う御家人はその所領の一部を没収する。
第38条:「惣地頭(地頭の統轄職)が荘園内の他の名主の領地を奪い取ることの禁止」
惣地頭は「将軍から与えられた所領だから、全部が自分の勢力範囲」と言って、領家の証明書を持っている名主の土地まで取ることはできない。それにもかかわらず名主の土地を奪おうとする者がいる場合には名主に別の証明書を発行する。しかし、名主が集めた税を地頭にあずけない場合はその名主をかえてしまうことができる。
第39条:「幕府を経由しない官位・官職の申請を原則禁止」
勤勉に働きその功が認められた者は公平に吟味したのち幕府の推挙によって朝廷から官位をもらうことができるが、自ら昇進を願って直接朝廷に申し出ることは誰であっても厳に禁止する。ただし受領や検非違使については、幕府の推挙無しに職位をもらってもよい。また、年功により官位をもらう者も今までのとおり制限しない。
第40条:「鎌倉在住の僧侶が勝手に官位を取得することを禁止」
年少者や低位の僧侶が勝手に官位をもらって年長者や高僧を飛び越すようなことは寺の秩序や仏の教えにそむくものとして、勝手に官位をもらった僧侶はこれをやめさせる。これは幕府付きの僧侶者も同様である。
第41条:「奴婢や雑人について」
頼朝公の時に定めたように、10年以上使役していない奴婢や雑人は自由とする。次に、奴婢の子については男子の場合は父に、女子は母に属すこととする。
⇒奴婢は奴隷のように売買される人だが、西欧の奴隷のように買主に生殺権が完全にあるわけではなさそうなので、「奴隷」とは基本的に異なるようです。
第42条:「逃亡した農民の財産をその妻子から奪ってはいけない」
領内の農民が逃亡したからと言って、その妻子をつかまえ家財を奪ってはならない。未納の年貢があるときはその不足分のみを払わせること。また、残った家族がどこに住むかは彼らの自由にまかせること。
⇒悪徳地頭の横暴から農民の奴隷化を防ごうという感じですね。
第43条:「理由なく他人の領地や年貢を奪うことは違法」
理由もなく他人の領地をうばい年貢や財産を奪うことは違法であり、年貢は速やかに返納すること。そして行った者の所領は没収する。所領を持たない場合は遠流とする。また間違って発行した土地の証明書は認めない。その証明書は速やかに破棄すること。
第44条:「裁判では当事者以外の発言は取り上げない」
係争中の土地を望み、第三者が当事者に不利な発言をして罪におとしいれようとすることは許されない。裁判では当事者以外の発言は取り上げない。武士とは真面目に働くことで領地を得られるものである。
第45条:「判決前に被告を免職することの禁止」
判決が出る前に被告を免職してはならない。有罪無罪を問わず極めて不満を残すことになるからである。判決は十分に吟味して出さなけらばならない。
第46条:「新任国司は前任国司の私物・牛馬・家来をうばってはならない」
徴税は新任国司の仕事であり、その際に前任国司の私物や牛馬・家来を奪ったり、恥をかかせてはいけない。但し、前任国司が罪を犯し解任されたものであるときは別である。
第47条:「実効支配していない所領を他人に寄進することを禁止」
実効支配していない領地を有力者に寄進することで実効支配を行おうとした者は追放、受け取った者には寺社の修理を命ずる。また、本所にことわりなく領地を貴族や寺社に寄進することを禁止する。これにそむいた名主(地頭が管理する土地の所有者)は名主職を奪い地頭の配下に置く。地頭がいないところでは本所の配下とする。
第48条:「幕府から恩賞で与えられた所領の売買を禁止」
御家人が先祖代々支配していた所領を売ることは問題がないが、恩賞として将軍から与えられた土地を売買することは禁止する。これを破った者は売った者も買った者もともに罰する。
⇒勝手に売買されたら御家人所領が流出し、幕府側には脅威となりますから。ここでも近代資本主義的所有権が制限されています。
第49条:「調書のみで勝敗が明らかな場合は議論なしに直ちに判決を下す」
原告・被告の提出した書類を調べて明白に理非が判断できるときは、わざわざ双方を呼び寄せず直に判決を申し渡す。
⇒原告・被告の双方の言い分を聞くというのが原則であったと思われるが、それでは裁判が遅くなりすぎるので、省けるものは省くという考え方たのでしょう。
第50条:「調査目的で事件現場に行くのは良いが、加勢目的では禁止」
暴力事件が起きたとき、その詳細を調べに行くことは許されるが、一方に加勢するために行くことは罰せられる。
第51条:「尋問状で被告を脅すことを禁止」
受理された訴状に基づき被告に出される尋問状を原告が手に入れ、その威力によって被告をおどかすことは罪となる。今後は訴状を吟味し不当な訴えに対しては質問状の発行をしない。
⇒尋問状は訴訟受理を示すのみ。これをネタに被告を脅かすような輩(原告)が多かったのだろう。
(6)最後に
・御成敗式目は世の中で認めれてきた過去の判例や慣習(=道理)を元にして、具体的な事例を必要に応じて修正や追加を加え、慣習(=道理)をUpdateしている慣習法である。
・個人の権利というより「家」を守るという社会目的が見える。戦前まであった家督相続も「個」ではなく「家」(最小の共同体)を守るのが最優先という考えの表れですね。西洋キリスト教では神と個人の契約がベースになって個人主義が蔓延っていますが、日本で個人主義が今一つ進まないのはこんな歴史があるからでしょうか。
・「泣くこと地頭には勝てない」という言葉があるが、それぐらい地頭を含む御家人と言うのは理不尽であったのでしょう。頼朝という重しを失ったが、承久の乱で朝廷も西国を一旦抑えたものの、御家人たちはこれを奇貨として、敗戦側を圧迫し、隙あらば領地を横領しようする乱暴な世界だったようです。泰時はそんな地頭の悪事を抑制する意図が強かったような感じもします。
・違和感の少なさは、この精神が現代にも生きているという証であり、御成敗式目が現代人の思考の源の1つであると思います。
