
九鬼の記事vol.7(2019.01.26)
0.今週の記事のレビュー
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
「今週の記事のレビュー」では、本記事を簡単にまとめています。★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
1️⃣今週の学び:「スレッド走のトレーニング」です。重たい重量を引っ張って走るスレッド走トレーニングは、スプリント動作にそのまま抵抗かけられるトレーニング手段として、広く用いられています。今回は、ある先輩からの連絡を受けて、そういえば、、、と思って読んだ論文をもとに話を展開していきます。自分の失敗談も、恥ずかしながら紹介しています。
2️⃣今週の陸上部:陸上部はテスト休みなので、弟のトレーニング動画を少し。骨盤の動きと調子について少し話しています。
3️⃣今週のオススメ論文:今週の学びと近い内容です。スレッド走トレーニングに関する有名な論文を引用しています。スレッド走をトレーニングとして用いる場合は必読の論文です。
4️⃣時事ネタ・記事の紹介とコメント:複数ありますが、猶本光選手が浦和レッズレディースに移籍になった記事を取り上げています。猶本選手とは、一年以上もトレーニングを一緒にした仲間です。日本での活躍と、代表での活躍がますます期待です!
5️⃣Q&A:
1.今週の学び
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
「今週の学び」では、今週のできごとから九鬼が感じたことについて述べています。主にトレーニング・コーチングの現場での気づきを発信したいと思います。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
今週の学びは、「スレッド走」です。
みなさんご存知だと思いますが、スレッド走とは重たいソリのようなものを引っ張って走ることで、スプリント動作に負荷をかけて、脚の力発揮やパワーを高めるトレーニング手段のことです。
ちなみに、今週のオススメ論文でもこの「スレッド走」に関する論文を紹介します!
今週、とある先輩から
「スレッド走するときの至適な重さってどのくらいだっけ?」
と連絡が来まして。そういえば、結構重たいのでやるのがいいよ、っていう論文があったと思います、と答えて、改めて論文を読んでみることに。
スレッド走は、主に加速区間のスプリント能力を高める効果があると考えられているので、論文でも扱っている選手は球技系の選手が多かったです。
ですが、陸上競技の短距離選手でもよく使用されるトレーニングです。念のため、動画を貼っておきます。
このトレーニングの最も大きなメリット(と一般的に考えられている)は、やはりスプリントの動作の中で抵抗をかけて筋に対してアプローチできる点であります。
通常では、体重の5-7%程度が至適な重さであると考えられています。体重が70kgの選手であれば、3.5kg-4.9kgの範囲でスレッド走を行うといった感じでしょうか。このトレーニングをしたことのある人であれば、「そうそう、そのくらいの重さだった」と思われるかと。
ですが、近年の研究では、「その重さでは軽すぎ!もっと重たい重りにしたほうが加速区間のスプリントには効果が大きい!」という研究結果が得られています。
(以下、オススメ論文で紹介する内容とカブるところがあるのですが、ご容赦ください)
じゃあ、どのくらいの重さかというと。体重の69%〜という重さで行うと効果的、という結果が。しかも複数の研究で検証されていて、さらにそれに関するレビュー論文も発表されるほど。(日本の研究者の方が執筆した論文もあります)
※レビュー論文とは、とあるトピックスに関する先行研究を複数集めてきて、それらの論文をまとめて議論する論文のこと。
体重の70%〜、というと、70kgの選手にとっては48.3kg〜の重さを引くことになります。一般的な見解では、より重たくすることによって
✅スプリント中に、推進方向(前方向)に発揮できる力がより改善される。
✅スプリント中に、上方向に出る力を前方向により傾けられる。
といったところが、主な効果だと考えられています。
ちなみに、数年前の僕は、「なるほど!」と思って、実際に弟に冬季トレーニングとして重たいスレッド走を行わせました。
結論から言うと、大失敗。😱😱
見事なくらいに100mが走れなくなりました。語弊を招くといけないので断っておきますが、スレッド走が悪いと言うわけではなくて、単純に僕の使い方が悪かった、と言うことです。お間違えのないように!
ただ、その失敗からは、選手が持っている脚の「伸展と屈曲のタイミングを崩す」とここまで走れなくなるものか、と言うことが痛いほどわかりました。走っているスピードが速くなればなるほど、接地瞬時のブレーキ成分が大きくなっていくので、このブレーキ成分をいかに小さくするか、と言うのも重要な戦略になってきます。
(ちなみに、このブレーキ成分を小さくするのは、疾走速度に及ぼす影響は小さい!と主張する論文もある点に留意)
そうなってくると、ランニングのサイクルの中で、脚および股関節をどこまで伸展させて、どのタイミングで脚の伸展を止めて屈曲させるのか、と言うタイミングの話が非常に重要になってきます。
もっと詳細に言うと、股関節を屈曲させる力だけではなく、骨盤の前傾後傾なども関係してきて。女子選手でよく見られるのは、骨盤が過度に前傾しすぎて、脚のスイングが遅れてしまうと言うケースがあります。
・・・この話をしだすと話が大きく、大きく、脱線してしまうので(笑)、また別の機会にします。
すみません、完全に脱線しました。スレッド走のトレーニングがどう失敗で、どう使用するべきだったかはオススメ論文のところで紹介します。
ちなみに、弟に走らせたその動画はこちら↓
ここから先は
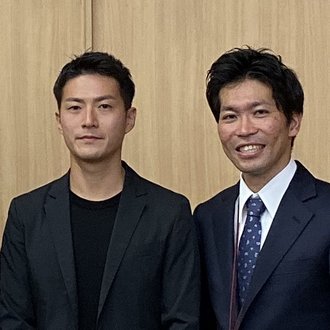
市民ランナー高速化プロジェクト
✅市民ランナー✅指導者・トレーナー✅スポーツ科学を勉強する人、へ役立つ専門情報を届けます👍 知識をアップデートしたい方、僕たちと「オモロイ…
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
