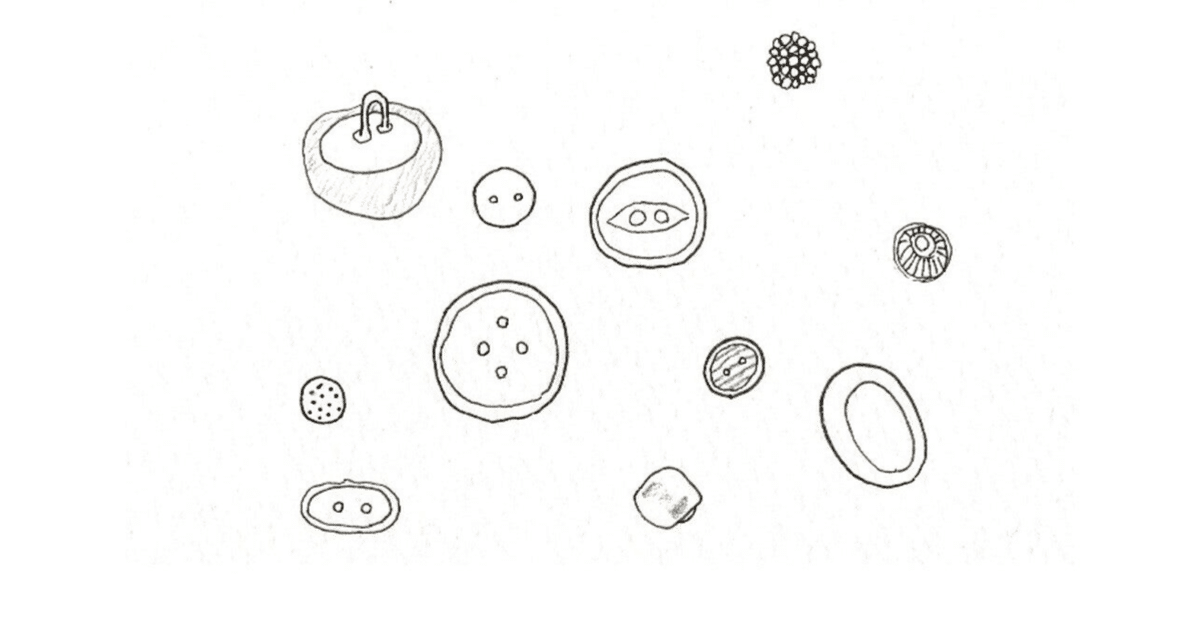
ボタン
「あっ…」
スーツからゆっくり落ちていく。ほつれそうと思っていた矢先だった。地面に落ちた茶色のボタンは、もの寂しそうな表情をしていた。僕は、まじまじとヤツを眺めることを止めなかった。
「こんなところに…」
立ち止まる人影を感じた。誰だかすぐに分かった。しゃがんで拾い上げると、ヤツの雰囲気が変化し始めた。華奢な親指と人差指に摘まれた格好で、申し訳なさそうにしている。拾ってくれた人と目が合った。
「これ…」
「取れてしまったんだ」
「付けてあげる。ほら、上着を脱いで」
彼女は職場の同期、洋子だった。グレーのスーツ姿でボブヘアの黒髪には艶があり、足元は濃紺のピンヒールが印象的な女性だ。部署は違うが、同期が僕と洋子しかいないこともあり、時々話はする仲。
たまたま、洋子のフロアに書類を提出して戻るところだった。入社して2年目。少しは仕事も任されることも多くなってきたところだ。
僕は洋子に言われた通りに、上着を脱いで差し出した。洋子は溢れそうな瞳で視線を合わせると、大きく頷いた。口元を動かす。
『ちょっとまっててね』
僕も小さく頷いた。すると洋子は近くにある自分のデスクに座り、バックの中から、裁縫道具を取り出すと、手際よくボタンを付け始める。
少し遠目から、僕は洋子の姿を眺めている。感謝しながらも、自分の心は湧き踊っていた。
『時間よ、止まれ…』
そんな、叶わぬことを思っている自分に、苦笑いをした。
「おまたせ」
「ありがとう。助かったよ」
「タイミング良かった。偶然でも役に立てたね」
「このフロアに来てラッキーだった」
僕は洋子に深々とおじぎをした。洋子の瞳が更に大きなビー玉のように澄んでいる。僕は頭を上げ、視線を合わせると、より一層華やかな顔立ちに変化していく。
洋子の満面の笑みを僕は独り占めする。
「今度の休み、海に連れて行ってよ。ボタン付けたお礼に!」
洋子ははにかみながら、砕けた口調で言った。僕は一瞬視線を逸してから口を動かす。
「そうだ、お礼しないとね。分かった!」
「やったあ。約束だよ」
「うん、約束は守るよ!」
「楽しみ!!海に行くの久しぶりだし」
「俺も行ってない、楽しみになってきたよ」
「ヨロシク。それじゃあ」
「うん」
僕は、入口のドアを開けると、エレベーターの前まで歩いて行った。無意識に握りこぶしを作っていることに気がついた。
手を開くと、さっき付けてくれた上着のボタンに触れてみる。ボタンは違った生き物のように、生暖かった。
休日…
外見が龍宮城をモチーフにした駅舎の前で、僕は立っていた。空は一面、灰色の雲に覆われている。シーズンが過ぎた海岸線は、人も疎らで、寒々としている。
僕は、カーキー色のジャンバーポケットに手を突っ込みながら、小刻みに身体を動かしていた。息が白い。
「お待たせ!」
僕の背後から声が聞こえた。振り向くと、そこには細身でショートヘアの女性が立っていた。
「えっ…」
一瞬、時が止まった。僕には、長い時間のように思えた。走馬灯のように頭の中で記憶が蘇ってくる。
「びっくりしたでしょ?」
目の前の女性は、少しハニカミながら、それでいて落ち着いた口調で、僕に話しかける。僕は我に返った。
「どうして、ここに…」
「そうだよね。不思議でしょ?いつ以来かなあ…あなたに会ったの…」
「最期に会ったのは…」
「言わなくていいよ。そんなこと…」
僕が、たどたどしい言葉を察知するかのように、女性は言葉を遮った。
僕は、俯いて口を摘むんだ。
「洋子から聞いたんだ。それでやってきたの…」
「洋子が?どうしてこんなことを!」
「洋子、言ってたよ。最近、更に一生懸命だって。洋子が気を使ってくれたんだよ。私たちのために…」
「えっ、洋子が…」
「そう…」
「どうして?」
「私たちのこと…気に掛けてくれていたみたい」
「でも、もう終わった話じゃ…」
「ボタンだよ」
「ボタン?」
「そう、ボタン…」
女性は、海岸に向かう一本道を歩き始めた。僕も糸で結ばれているように後を追う。
海岸は、濃厚な灰色の雲が覆われていて、海の蒼さが濃く印象つけられている。砂浜を歩いていると、口の中が乾燥して、何とも言えない苦い味覚を感じていた。
「以前、ここを歩いたよね。夕日の沈む景色が最高で…」
女性は、懐かしい表情を見せながら、僕に視線を向けた。そう、確かにそんな時があった。脳裏にその情景が浮かび上がる。
「かなり年数が経ってしまっていたんだな、俺らって…」
「そうだよ。お互いね」
「もうお互い、忘れていると思ってた」
僕は、無意識に言葉を発していた。女性は僕に背を向けながら俯いた。
「あなたのこと…忘れる訳…ないじゃない。本位じゃなかったんだから…」
「そうだったんだ…てっきり俺は…」
「ボタンの掛け違い。お互い、それが分からなかっただけだよね…」
僕は、女性のそばに歩を進めると、華奢な透き通る冷たい手を、愛しく包み込むように優しく触れた。
咄嗟に女性の表情は、あの頃の笑顔に戻っていく…
「本当にごめん。分かってあげられなくて…」
「いいよ、現在(いま)こうやって会えているんだから」
「歩こうか。俺、それだけで構わないから…」
「もちろん、私も…」
僕と女性は、同じ方向を一歩ずつ進み始める。お互い何も語らず、足元を動かし続ける。歩調が少しずつ同化していく感じがした。
今まで閉ざしていた心が、温もりで徐々に溶け始めている。
一面を覆う灰色の雲が、にわかに明るくなっていた。僕と女性は、更に歩み続ける。
僕は一瞬、洋子の顔が浮かんだ。
スーツのボタンを付けている洋子を…
この記事が参加している募集
お読み頂いた方に少しでもお役に立てれば幸いです。頂いたお気持ちは、更に成長出来るように勉強費用に充てさせてもらい、皆様に執筆することで還元致します。
