
■深みのない本と印象深い本
現代散文自由詩人の独り言(81)
11月の読書記録
図書館から借りて月内にすべて読み切った本は5冊。
久保りこ「爆弾犯と殺人犯の物語」と宇野碧「レペゼン母」、そしてノンフィクションの鮫島浩「朝日新聞政治部」―の3冊は既に感想はそれぞれ書いた。
書ききれなかった2冊について、簡単に触れる。
◇川添象郎「象の記憶」
ディスクユニオン刊 2022年8月初版
副題「日本のポップ音楽で世界に衝撃を与えたプロデューサー」とある。筆者は明治の元勲のひとり、後藤象二郎のひ孫。YMOを手掛けたプロデューサーだったり、女優風吹ジュンの元夫だったり、大麻で何度か逮捕され、刑務所に入っていた人物…ということは知っていたが、どんな時代をどう生きたかが、この本である程度わかった。
内容
YMOで社会現象を巻き起こし、ユーミン、吉田美奈子など、いま、シティポップとして世界で評価される音楽をプロデュースしてきた著者が、その破天荒な人生を語る。『団塊パンチ』連載に加筆して単行本化。
名家に生まれ、その交友関係や親のコネでどんどお世の中を泳いで行った話が、生き生きと描かれてはいる。
しかし、この方はあくまでプロデューサーであり、アーティストではない。
自分で何事かを創造した…という人ではない、と思う。
彼が手掛けた成功談がいくつも語られていて、60-80年代の日本のポップカルチャーの最前線がわかるような気がする。
しかし、彼が何度も結婚離婚を重ね、大麻での逮捕、刑務所暮らしの経験といったネガティブな話は本当にサラリとしか書かれていない。
自分が過去に犯したいいたくない話にほとんど触れていない。その点が、深みのない本になっているのである。
この方、血筋のよさと運の良さだけで世の中を渡って来たんだ、と思った次第。
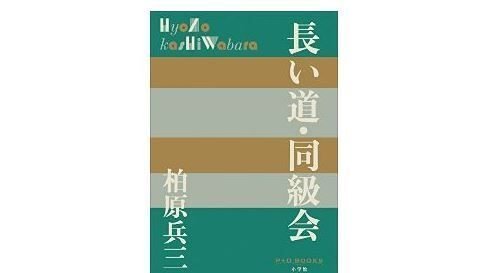
◇柏原兵三「長い道・同級会」
小学館刊 2018年5月初版
表題作「長い道」は1969年刊。筆者はその後芥川賞を受けるも38歳で早世した独文学者。その後、藤子不二雄Ⓐが1978年に「少年時代」のタイトルで漫画化し、1990年に映画にもなって発掘された小説といえる。
内容
太平洋戦争末期、都会からの疎開児への地元っ子の愛憎を中心に、戦争の影にゆれる海辺の村で繰り広げられる人間模様を描き、「少年時代」として漫画化、映画化された「長い道」を収録。その後日譚「同級会」も併録する。
20数年前、疎開した国民学校(小学校)時代の記憶を、もちろん創作部分もあるのだろうが、おそろしいほどの記憶力で再現したような物語である。
その人間関係が実にイキイキと描かれていて、読む価値のある一冊と思った。
この小説の影響を受けて、「長い道」として詩にもしてみた。
「象の記憶」とはまったく傾向は異なる本だが、前者が面白くはあっても考えさせられるようなものがほとんどないものに比べれば、読んでおいてよかったと感じた本である。
