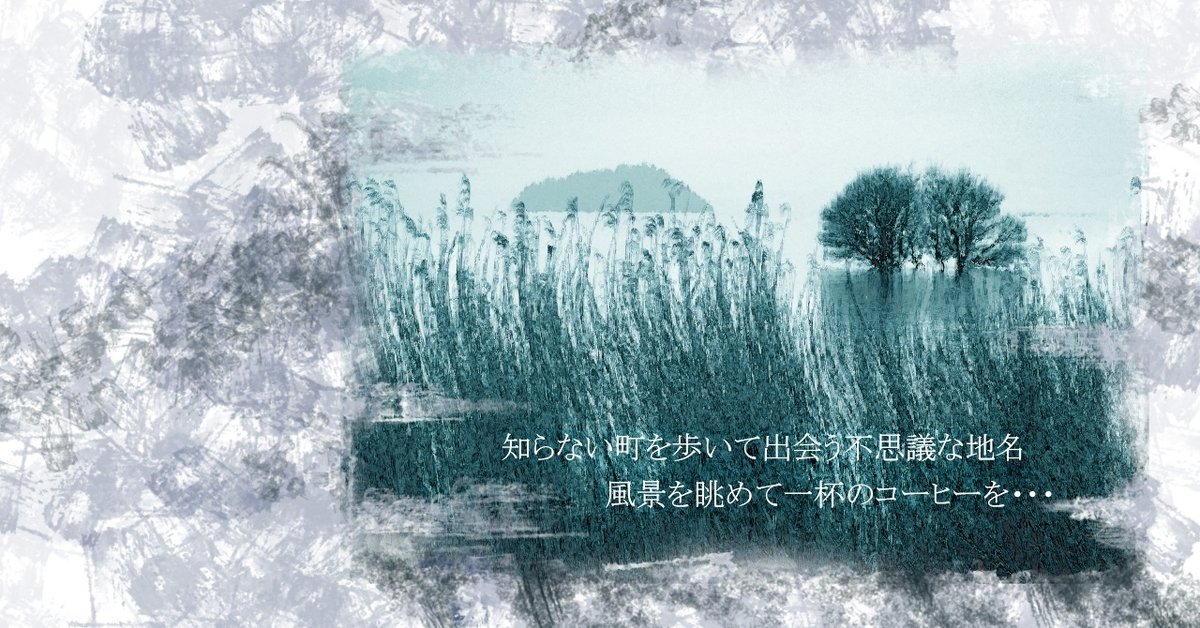ある地名の風景
谷保天神の神楽殿 yabo-2
JR南武線の駅名は「やほ」ですが、
本来の地名は「やぼ」だったようです。
その証拠に、谷保村の鎮守谷保天満宮には
「やぼ」とルビがあります。

天満宮の縁起によると
平安時代にはこのあたり一帯が
分倍荘栗原郷だったとあるそうです。
”谷保”という地名がいつ頃からあるのか・・
これはどうもはっきりしたことがわかりません。
でも、江戸時代初期には谷保村があるので
やはり中世の後半にはあった地名でしょうね。
では一体、”やぼ”とはどんな意味なのでしょう。
分からいないまでも
いつものように持論を展開しようかと思っております。
「それはヤボだ」なんて言わないでお付き合いください(笑)
「綜合日本民俗語彙」の中に「ヤボガミ」という言葉があります。
佐賀の方で、畑の隅に残る三角形の木立を言うそうです。
これは無縁の塚を祀ったのが始まりといわれています。
でもちょっと谷保には無関係かな。
同じく「ヤブヤキ」という言葉もあります。
静岡などの山間部で焼き畑耕作のことだといいます。
草木の繁茂した場所を利用して焼き畑をおこすという意味でしょうね。
宮崎の山間部では藪のことを”ヤボ”と言うそうです。
オキヤボ、カラメヤボ、キッカヤボなどの言葉があるとか。
では国立あたりでも”ヤブ”(藪)という言葉が
”ヤボ”に変わったのでしょうか??
(つづく)
(東京都国立市)