
漠然とした「不安」が人の生死を左右する。抗うために必要なのは、「生きる」方法を事実として知り、分かち合うこと
新型感染症の世界的流行という未曾有の社会情勢下で、私たちは今、これまでになく「医療」と「自由」を巡る自己決定を求められています。他人と自分の命を守ることを、これほどまで要請されたことがあるでしょうか。一方で、それが自由とのトレードオフであることが、事態をより複雑かつ困難にしています。
この「医療」と「自由」のせめぎ合いは、実は古くて新しい問題です。医療の発展による、出生前検査の普及、人工呼吸器装着のための気管切開という選択。相模原・津久井やまゆり園の殺傷事件――。いずれも、この社会で「われわれがどう生きるべきか」というテーマが通底しています。
立命館大学大学院教授で社会学者の立岩真也さん、ALSの患者・家族やケアに携わる人の支援団体を運営する川口有美子さん、「NPO法人親子の未来を支える会」設立者で医師の林伸彦さんが登壇した2020年2月のLITALICO研究所 OPEN LAB 第8回 「『生きる』を誰が決めるのか – 生命倫理と医療・経済」から、このテーマを掘り下げます。
本記事は、2019年度に実施した、LITALICO研究所OPEN LABの講義のレポートとなります。会場・オンラインでの受講生限定で開講・配信した講義シリーズの見どころを、一般公開いたします。
(レポート執筆: 朽木誠一郎)
歴史に立ち返り、拠って立つべき基盤を見つめ直す
冒頭、主催のLITALICO・鈴木悠平さんから問題提起がありました。医療の発展により、これまで救えなかった命が救えるようになる。生きたいと本人が願い、生かしたいその家族が願い、医療や福祉がそれに応える。たくさんの善意により、このような切実な願いが叶うようになりました。
一方で、出生前検査の普及は、事前に特定の疾患を発見して治療する可能性をもたらすと同時に、障害のある子どもの中絶を実質的に促してしまうことが否めず、障害それ自体のスティグマを維持増大してしまうおそれがあります。ALSなどの難病において延命のために人工呼吸器を装着するとき、気管切開により痛みや苦しみ、自立機能の喪失が発生します。
医療の発展により「生きる」ことができるようになると、今度はその命の価値を推し量り、選別するかのような揺り戻しが起こります。その極端な例が、2016年に相模原の知的障害者福祉施設・津久井やまゆり園で元施設職員の男性が入所者19人を刺殺し、26人に重軽傷を負わせた事件だとも言えるでしょう。2020年7月には、医師によるALS患者嘱託殺人事件も起こりました。

鈴木
「人が生きる」とはどういうことなのか、それを誰が決めるのか。歴史に立ち返り、改めて私たちが拠って立つべき倫理基盤を見つめ直す必要があります。
もう一つの「相模原事件」が与えた影響
1人目の登壇者は川口有美子さん。ALSの患者・家族と在宅ケアに携わる人たちのサポート団体「NPO法人ALS/MNDサポートセンターさくら会」の運営や、在宅人工呼吸療法のための介護サービスを提供する活動に取り組んでいます。また、ALS当事者の日常を描いたノンフィクション作品の執筆などを通じ、ALSをはじめとする難病当事者の自己決定の課題について生命倫理の観点から提言している方です。

川口
今回、私のパートには「自己決定、からの自由へ」というタイトルを、勝手につけさせていただきました。医療に関することは自分で決めるのが一番いいとされ、「事前指示」だ「リビングウィル」だと言われるのですが、そう言われても難しいということ、母の介護をしながら考えてきたことを話します。
川口さんがALSの母親の介護を始めたのは1995年。2003年から介護事業所を設立して自分の母のために介護派遣をするようになり、同じ年にさくら会を立ち上げた。「最初は個人の問題でしかなかったことに、いわゆる公共の問題として取り組むようになってきた」と言います。
川口
母は60歳を前にALSを発症して全身性の麻痺が進み、翌年にはもう胃ろう造設、人工呼吸器装着ということで、1年未満のうちにどんどん病気が進んでいった、ALSの中でも非常に進行の早いタイプでした。99年になると意思疎通が全くできなくなる「TLS;Totally Locked-in State(完全閉じ込め状態)」になってしまって。
そこからが長くて、およそ8年ぐらいその状況で自宅で過ごし、2007年9月に71歳ので永眠、という経緯です。在宅での介護は、家族の生活の中にちゃんと自分の位置づけができる、つまり私の母親に戻り、父の妻に戻り、息子のおばあちゃんに戻り、友人が来れば友人に戻れるということで、豊かです。ただし、やっぱり家族は大変でした。
介護中心の生活の中で、2004年8月に起きたある事件が川口さんの胸に刺さった。一般に「相模原事件」というと、先に挙げた2016年のものを連想するが、実はもう一つ、相模原で痛ましい事件が起きています。自宅で療養していたALS患者の男性の人工呼吸器のスイッチを、その介護をしていた母親が思い余って切り、自身も自殺未遂をしたという事件です。
川口さん自身、「ときおり、母親に殺意が芽生えることがあった」と振り返ります。介護は重荷であり、自分も自由になりたい。「かわいそう」と思う気持ちもある。「安楽死が合法化されれば」と願ったこともあるそうです。
川口さんはその事件の公判をALS患者と一緒に全て聞きにいきました。そのときに語られたことの中で「私の身勝手で生きさせてしまっているのではないか」という言葉が印象に残っているといいます。
「息子を励ましてきたのは、私のわがままだったのではないか」「自分が息子の温もりを感じたいがために、息子を叱咤激励してきたけど、息子にとっては酷だったのではないか」「息子は嫌がっているけれど、レスパイト(介護者を息抜きさせる目的の入院)をしてほしい。でも病院では何もしてもらえないだろう。息子がかわいそうになってきた」「このまま病院に行かせたらいけないと思った」
母親が思い余ってスイッチを切ってしまった日は、次の日から息子がレスパイト入院をする日の前夜だったそうです。判決では息子が「呼吸器の設定を止めないでほしい」と言い残していたことや、母親にしか身体介護をさせなかった共依存関係が見落とされ、嘱託殺人のような扱いに終止。川口さんは「これが家族による介護の限界だ」と感じたと言います。
この事件は判決後、その母親が自殺未遂をしているところを父親が発見し、止めを刺して殺害、自首という、非常に重い結末を迎えました。患者会や医学界にも「激震が走った」と川口さん。以降、もう一つの「相模原事件」が終末期医療のルール作りの議論の場で参照されるようになったそうです。
その後、川口さんは後に登壇する立岩真也さんと「安楽死・尊厳死の法制化を阻止する会」を結成し、医学書院から『逝かない身体』を出版しました。
「『病状が進行した患者が惨めな存在であり、意思疎通ができなければ生きる価値がない』というのは、は誤解ではないか。自分のためだけに生きるという生き方も、誰かのためになら生きられるという生き方も、どちらも選ばれていいのではないか」と考えるようになったと言います。
川口
生きる意味を、自分ではっきりと理解していれば一番いいのですけれども、そういう意味を見失ったときに、他者によって生きる意味が見出される、ということもあります。それは否定されなくていい。
そもそも生きる意味など要らないって言うこともできるんですけれど、でもやっぱり、人は生きる意味をどうしても求めてしまうものです。生きる意味を見失うとやはり死にたくなってしまう。そういうときにどうしたらいいか。
私についてであれば、TLSの状態の母は医学的にも脳が機能している可能性があった。その生体反応から「あなたたちと一緒にいたい」という声を感じ取って、そう伝えていると思うようにしていました。これは「家族が勝手に生かしてしまう」状態と言えるかもしれないけど、私自身が生きる意味を持ち続けるためにも必要だったと思っています。
一方で、「ただ生きているだけ」「尊厳が失われている」など、「死の意味も他者によって見出されてしまう」ことへの懸念も川口さんは指摘します。また、「最善の利益」という言葉があるように、医療資源にも限りがある以上、「費用対効果による治療の決定というものもあり得る」「例えばイギリスはもう治療ガイドラインにも気管切開が削除されて、ありません。人工呼吸器は不要だとされているのですね」と川口さん。
その上で、「『生きる』を誰が決めるのか」ということについては、一定の結論に落ち着いたと言います。
川口
私が考えてきたことをまとめると、「自己決定していなくても救命してもらえる」ということがあってもいいんじゃないか、という意見です。その結果、本人が愚痴を言うことはもちろんあると思いますけれど、生きていれば何か改善されていくっていうこともあります。
これは、「家族の気持ちを慮って救命を望まない」という状態を防ぐ、つまり家族に縛られないで生きられることにもつながります。家族もまた、当事者を巡る意思決定から解放される。私はこれを「個人単位の社会保障」と定義して、推進する活動をしてきました。
周りに「産むか産まないか」を迷っている人がいたら
2人目の登壇者である林伸彦さんは産婦人科の医師です。「出生前検査が普及すると、障害のある子どもが生まれにくなってしまうかもしれない」という懸念の一方、「出生前検査を避けると、治療によって防げるはずの障害や救える命を見逃してしまう」というジレンマに課題意識を抱き、「NPO法人親子の未来を支える会」を設立しました。
出生前検査の意義や胎児医療の倫理的諸問題の検討、社会への働きかけ、障害への関わりについて多面的かつ組織的に向き合う活動をしている方です。
法人設立は2015年。「生まれる前の命」を主なテーマにしながら、生まれた後の育児や就学・就職なども支援しています。具体的な活動は医療的ケア児の支援、家族会の設立支援、就学ガイドの作成など。林さんは「医療の発展が患者に自由をもたらすのか、『生きる』を誰が決めるのかというのは自分にもよく問いかけるところなので、この機会に考えをまとめてみました」と話し始めました。

林
生まれてくる子どもが健康かどうか知りたいというのは当然のことだと思っています。それを知るために、出生前の医療も進歩してきました。ただし、医療の発展が本当に家族のためになっているのか、本当に選択肢が増えているのか、考えれば考えるほど疑問です。「産むか産まないか迷う」とき、自分自身の価値観や信念と実際の選択とが一致することは、なかなか少ない。産みたいけれどパートナーが反対して産めなかったとか、両親が反対して産めなかったとか、よくあります。
産んだ後、必ずしも社会はサポーティブではないという問題もある。「病気があると知りながらなんで産んだのか」「どうして出生前検査を受けなかったのか(検査をしていれば産まなくて済んだのに)」などと心ないことを言われることもあります。結局どっちの選択をしてもなかなか周囲から理解されない、そういう難しいテーマだと思っています。
そこで、「今日は、より自分事のように捉えられるよう想像して欲しい。もし周りに『産むか産まないか』迷っている人がいて、『出生前検査を受けた方がいいと思うか』と相談されたときに、みなさんならどう答えるでしょうか」と会場に問いかける林さん。
その答えとして例えば、「不安になるだけだったら受けない方がいいんじゃないの」「もし病気や障害があったら産まないの」「検査しても全部わかるわけではないから、受ける意味がないんじゃないの」「パートナーはどう思ってるのかちゃんと話してみたの」など色々あると思います。すべて間違いではないものの、林さんは「自分自身の価値観で他者にアドバイスすることにすごくモヤモヤする」そうです。
林
検査を受けた方がいいとか、よくないとか、僕はまずその結論が、必ずしも白黒はっきりするものではないと思っています。それは、いろんな状況によって変わるから。
例えば、周りの人が検査を受けている環境の妊婦さんは、より「受ける」という選択をしやすいでしょう。20歳の人より40歳の人の方が、より切実に病気や障害の有無を知り、自身が高齢になった後も本当に育てることができるかを考えたいかもしれない。
また、受けようか悩んでいる検査の精度がどの程度かによっても受けるかどうかの選択は変わります。100%確実という検査もあれば、そんなに確実ではない検査もあります。もし不確実なら、始めから受けない方がいいかもしれないですよね。そもそも胎児の「障害」って何なんだ、っていうところもちゃんと定義されていないし、検査への正しい理解が浸透しているとも言い難い。そういう状況なんです。
一方で、出生前検査によって救われる命もあります。例えば「胎児貧血」という疾患では、生まれる前にわかっていれば、胎児へ輸血をすることで赤ちゃんを救うことができます。。他にも、胎児を母体から取り出して治療をしてからまた母体に戻す「胎児治療」と呼ばれる治療ができる病気もあります。
イギリスに留学し、胎児治療に取り組んできた林さんは「日本の課題は、出生前検査が議論されるときに『治療やその準備のための検査』という視点が抜け落ちていること」だと指摘します。
林
命の選択に繋がりうるという議論はよく聞きますが、産み育てるかどうかを決めることはとても難しい問題です。意思決定に関わる要因というのはものすごく多岐に渡ります。異常の内容や重篤度によっても異なるし、元々のライフプランとか本人・パートナーの希望によっても変わる。他に、中絶に対する価値観とか、宗教感とか。またもし中絶という選択肢をとるならそれにも費用が発生しますから、経済状況も重要です。
それを1人で決めるわけではなく、パートナーと2人で、あるいは家族で決めなければいけない。意思決定に関わる要因はこのようにたくさんあって、いつ、どれが与えらるかによって揺らぎやすい。このプロセスを整理しようというのが僕たちのNPOの活動です。
思っていた通りの妊娠じゃないことがわかったときに、パニックになったり、ショックを受けたりする。そこできちんと情報を整理して、当事者が一番、納得する結論を出すためのプロセスをサポートする。相談員の価値観でアドバイスをするのではなく、相談者の価値観で結論を出すのをお手伝いするわけです。もちろん、決して、出産や中絶のどちらかを推奨するわけではないし、反対するわけでもないです。
出生前検査を巡る真の課題は「検査がいい/よくない」ではない――それが林さんのまとめです。良いか悪いかの二元論ではなく、検査を受けるかどうか迷っている人をサポートしたり、診断された後の人をサポートしたりすることが必要。その上で、「なぜ病気や障害の可能性があったら産めないと思うのか」というところに話を進めていきたいとのことです。「そもそも、どんな子でも温かく迎えられる社会があれば、おそらくこんなにみなさん迷ったり困ったりしないはず」と語ります。
最後に、「医療の発展は患者の自由をもたらすのか」という問いについて。「安全であるという条件のもとで、選択肢が増えることはものすごくいいこと」「それを自由と捉えるのか不自由と捉えるのかは、社会の姿勢やリテラシー次第」だと林さん。
「大事なのは新しい医療が出てきたときに、それを拒絶したり見て見ぬふりをしたりするんじゃなくて、その医療がどうしてできたのか、その医療によって何が起きるのかっていうのを理解すること」と結びました。
社会は「根拠のない不安」に基づいた言説に影響される
そして、3人目の登壇者は立命館大学大学院先端総合学術研究科教授の立岩真也さん。社会学者として、筋ジストロフィーやALSなど重度障害のある方への聞き取り調査を通した研究を長く続けています。また、自己決定や生存権について考察した著書を数多く執筆。障害当事者を取り巻く社会環境が「善意の集合体によって温存されてきた」と、その構造的構造についても指摘しています。
まず、立岩さんは冒頭、「安楽死・尊厳死」「出生前検査」は生命倫理というジャンルの二大テーマであるとしました。立岩さんは1997年に『私的所有論』(勁草書房)を出版(2013年に生活書院から第二版を出版)。その第8章を出生前診断についての論考に充てています。また、青土社から2000年に初版を、2019年に第二版を出版した『弱くある自由へ』の冒頭では安楽死について論考しています。
このように、長きに渡りこのテーマを考え続けてきた立岩さんだからか、「20分やそこらの講義では何もわかりはしない」「長い時間をかけて話したり読んでもらったり、そういうことをするしかない」と参加者に注意を促しました。

立岩さんはその上で、「倫理のことは僕はあまり考えたくないんです。なぜなら、考えなくても大概のことはできるから」とあえて言い切ります。生命倫理のテーマについての論考を世に送り出しながらこのように言うことには、どんな意図があるのでしょうか。
立岩
ごく簡単に言えば、人間、生まれたからには生きていればいいわけで。生きているからには、うまい具合に生きていければいいわけで。本当はそれだけのことなんです。でも、そのためには手練手管を尽くして、生きていくための手段を獲得することが必要で。倫理それ自体を考えることよりは、その具体的な方策をいろいろと考えたい、力を尽くしたいというふうに思っているんです。
立岩さんの基本的なスタンスは「他人のことを決めるのはいいことではない」。「産むか、産まないか」といった問題は、あくまで本人の意思決定によるべきであるという立場です。さらに「生きたいという人が生きられるようになった、その後だったら死ぬことについても決めたり考えたりもしてもいいかな」。逆に言えば、生きたいという人が生きられなくなる状況の中で、死について決めたり考えさせられたりしてしまうのはよくない、ということでもあります。
そして、これらの状態を可能にするための「現実をどのように作っていくか」を検討するとき、「我々がどのぐらいのことを正しく知っているか」が大事になってくる、と立岩さん。そこには、社会にはびこる「根拠のない不安」への危惧がありました。
立岩
理想に対して「そうは言ってもね」とツッコミが入ることがいくつもある。例えば、資源の不足。ALSの患者に気管切開をしてまで人工呼吸器をつけることは医療資源のムダなんじゃないか、みたいなことです。「人は生きてきゃいい」と簡単に言うけれども、いや、そんなことをしたら社会は保たない、と。
でも、これについては僕は明確に「足りないことはない」と言えると思っていて。大変なんだけれども、ある種、悲壮な覚悟を持ってがんばるというか、そういうことはできると思う。むしろ、どうして諦めと言うか、「社会は保たない」の方がこんなにも受け容れられてしまっているのか、我々はそれをこそ考えるべきなんじゃないか。
2016年の相模原事件はその例で、「我々の社会に対するある種の不安」が共通していることが浮き彫りになった、と立岩さん。事件を起こした被告が抱いていたとされる優性思想が「障害を持っている人をこの社会が許容しきれないのでは」という不安に立脚しているとして、多くの人々は「そうは言っても、そんなことをしちゃいけない」と感じたのではないか。
だとするとつまり、「障害を持っている人を社会が許容しきれないのでは」という発想自体は、すでに社会に共有されてしまっている、ということになります。そして、「その前提がどこまで正しいのかについて、我々は知恵を絞っているのか」と立岩さんは訴えます。
「これから世の中はもっと大変になってくわけだから、生まれてこない方がいい人は生まれてこないでもらって、早く死ぬ人は死んでもらおう」という言説に対して、「そもそも本当に世の中はもっと大変になっていくのか」と疑念を抱く姿勢こそ望ましい、とします。
立岩
我々の社会は、実は根拠のない不安に基づいて積み上がってきた言説に影響され、構成されてきてしまったのではないか、ということを考える必要があるんです。もう一度、社会に広がる漠然とした不安というものを直視して、それを構成する根拠を一つひとつ検証して、未来の社会を再構成していく。こういうことが求められているし、僕自身はそれが可能だとも思っているんです。
「自分で決める」の対置は「みんなで決める」ではない
講義はその後、パネルディスカッションに移りました。まずは立岩さんの言う「手練手管」の例として、川口さんが自身の取り組みである「さくらモデル」を紹介します。

川口
私の友人であり、さくら会の理事長でもある橋本みさおさんが、初めて人工呼吸器を装着したALS患者として一人暮らしをした。それが2003年です。コミュニケーションはまばたきしかできないし、足の指1本しか動かない、ほとんど不動の体で一人暮らしというのはちょっと前代未聞だったので、当初はみんなで反対したんです。でも本人は「やる」と言うので。
それが、結局うまくいった。日中はプロのヘルパーさんたちが介護に入り、夜は介護を学ぶ学生さんたちが夜勤をして、外出支援も学生さんたちが担当しました。それを橋本さん自身がマネジメントして、問題なく今に至るわけです。みんなできないと思ったけど、できちゃった。それはちゃんと伝えなければいけないと思って、2006年の「ALS MND International Alliance」という世界的な会議で発表、そこで「さくらモデル」という名前がついたんです。
超重度障害者が一人暮らしをしながら介護支援事業所を運営し、自分の会社でヘルパーを登録・育成しながら自分自身に派遣するということによって、収益が会社に貯まる。自分への介護給付金を自分で使うことのできる画期的なモデルであり、現在はさくら会の支援により同様のモデルで生活をする人たちがいます。地域の保健所との連携も進み、世界的にも評価されています。川口さんと協同することも多い立岩さんは、このモデルをこのように分析します。

立岩
さっきの「足りないことはない」話ですが、何が足りないんだと言えば、まず金が足りないわけです。ただそこを見るより、究極的には物が足りないか人が足りないか両方なんだから、そこを見ればよい。呼吸器を作れないほどものは足りないのか。定年で辞めるしかなかったり、失業があるのに、人は足りないのか。こうして順番に考えていくことによって、我々は前向きに、気持ちがよくなる。漠然とした不安の解消につながるわけです。
林さんも医療的ケア児の支援活動から「どんな子でも『産んでみたらなんとかなる』ということを感じる」とした上で、「それが見えないと人は不安で前に進めない」と振り返ります。そこで林さんが取り組むのは医療的ケア児を育てる家族に対してのオンライン「ピアサポート」です。同じような立場の人同士のミーティングにより、それぞれの家族を支援します。
林
結局、見えてくるのは、医師やNPOの立場でできることはそんなに多くなくて、むしろ当事者が「私たちは普段こういう子育てをしています」「困ったときには周りからこういうサポートを得ています」とか、そういう情報を出し合うことで解決できる課題がとても多いということです。迷ってはいるけれど、答えをすでに自分の中に持っている場合もあって。適切なサポートがあれば、人は難しい選択もできるようになるんだと感じます。

加えて、自己決定については「Shared Decision Making(共同意思決定)」の概念も重要であると林さん。本人だけに責任を負わせるのではなく、適切な知識を持った周囲の人がある程度の介入をすることで、本人が後悔のない選択をしやすくなる、ということもあり得るとします。川口さんも正しい情報に基づく判断が重要である点に同意し、選択には当事者間の「格差」も影響すると問題提起しました。

川口
例えば長崎県に壱岐という島があります。5〜6年前、壱岐でALSの患者さんが発症したときに、その対応ができるような準備が何もなかったんです。でも、患者さんの娘さんがドイツにいて、その娘さんがドイツからメールで壱岐のひとつしかない病院と、訪問診療している先生と全部、交渉して。療養を可能にするシステムを作っちゃったんです。やろうとすればできる、でもこれはその娘さんの行動力によるものですよね。こうした地域格差、個人格差みたいなものは、行政にも是正してほしいと思います。
自己決定を阻むさまざまなハードル。それを乗り越えるためにこうして知恵を出し合うことが生命倫理を巡る問題の突破口になることは認めながらも、立岩さんは「『自分で決める』ことに対置されるのは『みんなで決める』ではない」と警鐘を鳴らします。
立岩
自分で決めることに限界はもちろんある。そういうときにたくさんの人の知恵があった方が、いいアイディアが出るのは当然です。だけれども、現実に今「みんな」と言ったときにその「みんな」は誰で、その一人ひとりがどういう利害、意見を持っているのかを問わずに「みんなで」と言うのは最悪なわけです。「みんなが言うんだからそういうことかな」と思考停止して物事が決まっていくと物事はちっともよくならない。
ただし、「倫理は考えたくない、考えなくても大概のことはできる」というのはもう一度、強調しておきます。さくらモデルも壱岐の事例もまさにそうなんだ。本人や周囲の想いが先行して、実際に「生きる」ことが可能になっている。それをファクトとして知った上で、これはいいも悪いもない現実であることを認めよう。生きたい人が生きることができるようになったら、死ぬだのなんだのという難しいことを話し合ってもいいんじゃないかな。僕が言いたいことはそういうことです。

「withコロナ」といった言説がもてはやされる社会情勢は、まさに立岩さんの言う「我々の社会に対するある種の不安」を反映しているように感じられます。それがもし、根拠のない不安なのだとしたら。われわれがするべきことは、理想を定め、それに向けて現実を整えていくことなのではないか。そのために必要なのは、正しい知識を持ち、自分の中の先入観を疑うことです。
今回、議論された「人工呼吸器装着のための気管切開」「出生前検査」「相模原・津久井やまゆり園の殺傷事件」とコロナ禍。表面的なテーマこそ違えど、通底するのは「『医療』と『自由』のせめぎ合い」だと言えるでしょう。そして、この古くて新しい命題には、蓄積された議論がある。だとしたら、ここで歴史に立ち返り、拠って立つべき基盤を見つめ直せば、あるいは――。社会に悩ましい命題は尽きずとも、どうそれと向き合うかについては、先人たちが歩んだ道があるのです。
レポート執筆: 朽木誠一郎
1986年生まれ、茨城県出身。医学部卒業後、2014年メディア運営企業に入社。編集プロダクション・有限会社ノオトを経て2017年にインターネットの報道機関であるBuzzFeed Japanで「医療記者」としての活動を開始。2018年3月に単著『健康を食い物にするメディアたち ネット時代の医療情報との付き合い方』(BuzzFeed Japan Book)を出版。2019年に朝日新聞社に転職、記者として医療やヘルスケアを主なテーマに活動しながら、2020年3月より朝日新聞「withnews」副編集長に就任する。2020年6月『医療記者のダイエット 最新科学を武器に40キロやせた』(KADOKAWA)を出版。
Twitter:@amanojerk
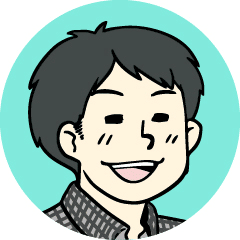
写真撮影: たかはしじゅんいち
1989年より19年間のNY生活より戻り、現在東京を拠点に活動。ポートレイトを中心に、ファッションから職人まで、雑誌、広告、音楽、Webまで分野を問わない。今までトヨタ、YAMAHA, J&J, NHK, reebok, Sony, NISSAINなどの広告撮影。現在Revalue Nippon中田英寿氏の日本の旅に同行撮影中。著名人 - Robert De Niro, Jennifer Lopez, Baby Face, Maxwell, AI, ワダエミ, Verbal, 中村勘三、中村獅童、東方神起、伊勢谷友介など。2009年 newsweek誌が選ぶ世界で尊敬される日本人100人に選ばれる。
https://junichitakahashi.com/
編集: 鈴木悠平
執筆協力: 雨田泰
同講義のダイジェスト動画はこちら (一般公開)
(川口有美子さん編)
(林伸彦さん編)
(立岩真也さん編)
(パネルトーク編)
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
