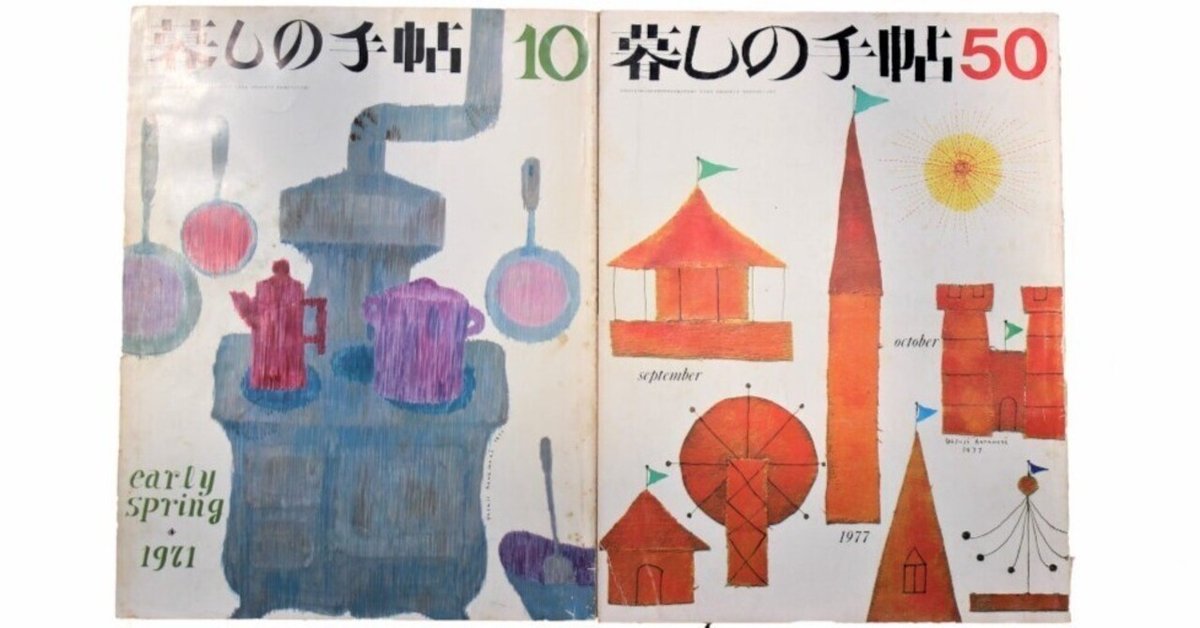
続・「暮しの手帖」を読む
懐かしい寄稿者
初期の「暮しの手帖」は、当時の各界著名人による随筆が人気コーナーだった。文壇で活躍する作家・評論家のみならず政治家や科学研究者、メディアで活躍していた人たちも寄稿している。現在も元気にご活躍中の、あるエッセイストさんのお名前の由来も「暮しの手帖」で知ることができる。
1965年発行の第80号から、グラビアページに続く本文用紙ページの頭から15ページを「雑記帳」として、読者からの寄稿にあてた。最初は編集部員のご家族や花森編集長と親しい人に書いてもらい、合間に外国家庭雑誌から引用した小話などを囲み記事として載せていたが、次第に外部の人からの投稿も増えていった。
投稿者名は文末に肩書きなしで添えられている。よく読んでいくと、当時壮年世代に人気のあった作家や評論家、詩人などの名前が登場する。石垣りん氏も寄稿していた。三木鶏郎氏、藤本義一氏などメディアで活躍した人や、芦田伸介氏、佐多稲子氏など懐かしいお名前の俳優もいる。完全な素人向けではなく、ある程度社会的知名度がある人を対象としていたとみられる。
若手の投稿も掲載されている。代表格は坂本九氏。第2世紀に入る頃、すなわち1969年から1970年ごろにかけて幾度か投稿している。当時の坂本九さんはデビューから10数年が過ぎ、アイドル的人気を卒業して大人のタレントへの入口に立っていた。その立場ゆえの悩みや青年ならではの決意、強い結婚願望、そして下ネタに至るまで「九ちゃん節」を披露している。多分お子さんたちも読んでいるとは思うが、どのような心証を抱いただろうか。
「上を向いて歩こう」を作詞した永六輔氏によると、ある時花森編集長を自宅に招いたところ花森氏は本棚を一瞥して、その後原稿依頼を断ったという。それを後年「暮しの手帖」の花森安治記念号(2004年)で暴露する永さんも永さんならば、本棚の中身を見ただけで「頭の中が知れる」とばかりに断った花森氏も花森氏である。やはりドラマにはしづらいお方だろう。
第2世紀第10号(1971年)には渥美清氏のインタビュー記事「ぼくのアフリカ」が掲載されている。17ページに及ぶ特大記事。羽仁進氏とともに映画の撮影のためタンザニアに行き、想像を絶するカルチャーショックを受けながらもなぜか気に入り、その後プライベートで幾度も訪れるようになったとお話されている。アフリカの話題にとどまらず、子供の頃は船乗りになることが夢だった話、普段の生活上における価値観や人生観の話、前回の記事でも紹介した芸名の由来など幅広く語っている。
当時の渥美さんは、山田洋次監督が作ったひとつの役に後半生全てを捧げる、その入口に立っていた。私や母はテレビ番組「底抜け脱線ゲーム」スポンサーCMに登場する「パンシロンのお兄さん」という認識だった。その時期に自分のことをこれだけの分量話した記録は貴重である。芸能雑誌ではなく他ならぬ「暮しの手帖」で話したあたりに、芸能メディアに対する渥美さんのスタンスもうかがえる。
1970年代半ばには服部良一氏が連載を持っていた。「東京ブギウギ」は省線電車に乗っているうちにメロディーを思いついた曲という話は連続テレビ小説「ブギウギ」でも取り上げられたが、普段家で作曲すると家族全員をピアノの前に集めて聞かせる習慣があったということは「暮しの手帖」で知っていた。
その話を書いた号はあいにく手元にないが、第2世紀第50号(1977年)では、レコード流行歌黎明期からの歌謡作曲家列伝を載せている。中山晋平、古賀政男の両氏を”別格”として割愛しているので、前半は古関裕而氏、吉田正氏、遠藤実氏くらいしかすぐイメージできる人がいない。その中で、万城目正氏が「旅の夜風」(1938年)「リンゴの唄」(1945年)を作り、米山正夫氏が「リンゴ追分」(1952年)「三百六十五歩のマーチ」(1967年)を書いたというキャリアについて学べる。
後半は当時中堅から若手にあたるポップス系作曲家の紹介。中村八大・いずみたく・浜口庫之助・平尾昌晃・筒美京平・都倉俊一・浜圭介・中村泰士・すぎやまこういち・村井邦彦・井上忠夫(井上大輔)・宇崎竜童・弾厚作(加山雄三)・小林亜星の各氏が取り上げられている。名前があがっていないとすぐに気がつく人は三木たかし氏くらいで、当時のヒットメーカーがほぼ網羅されている。「スター誕生」視聴者を中心にファンクラブができていたという都倉氏の写真が添えられている。
ここで気がつくのは、いわゆる「職業作曲家」は完全に「男性の世界」だったことである。女性作詞家は早くから世に出ていたが、作曲は男がやるものという暗黙の了解があった。女性の作曲家はシンガーソングライターの時代になってから本格的に登場したという歴史の流れがわかる。今の”昭和歌謡ポップス”ファンの研究材料のひとつになり得るだろう。
服部氏はメロディーを「メロデー」と記している。「ディー」の表記は1960年代から現れはじめ、1970年代に定着した。当時の年長世代は「デー」表記のほうになじみがあった。こういったことも現代の時代考証家には留意していただきたい。
第50号のレコード案内欄には、1910年代に人気を博した「浅草オペラ」のスター、田谷力三氏が78歳でレコーディングした「恋はやさし野辺の花よ」が紹介されている。ドラマ「ブギウギ」で花田鈴子(福来スズ子)が母親に歌って聞かせたあの曲。大阪でどれほど流行したかはわからないが、なかなか楽しい発見だった。
音楽・芸能関係者のお話は読んでいて楽しいが、文壇の人には気難しいお方も多い。
近年までご健在だったある高名な作家は1965年に、当時泥沼化していたベトナム戦争の戦況私感を書いている。その内容は割愛するが、タイトルが「活字にならぬ話」。
しかし、私の推察が正しかったとしても、このことは、少なくともあと三十年や五十年は、活字になって世に出ることがないであろう。
と締めくくっている。
あのー、「暮しの手帖」だって活字で、ちゃんと世に出ているのですけれど…というツッコミをすれば、草葉の陰から怒鳴られるだろうか。
この作家先生にしてみたら、「暮しの手帖」なぞは読み捨てられるもので、活字のうちに入らないという認識だったのだろう。題名の隣に筆者名が入る形の原稿ならば、予想が外れた際に責任を取らなくてはならないが、署名が末尾に記される形ならば気軽に書ける、といったところか。
一般読者投稿
対して一般読者からの投稿は、こういう商品があればよいというアイデアを募る「こんなものがほしい」、商品の仕様やサービス方法の改善アイデアを提案する「どうぞこんなふうに」が古くから掲載されていたが、投稿文がそのまま載る「読者の手帖」コーナーの開設は1960年代に入ってから。前号の感想をメインとしていた。
1960年代には旅行記や「もし私が大臣になったら」など、編集部で特定のテーマを用意して投稿を募る企画が幾度か行われた。
「大蔵大臣になったら、紙幣の図柄から男性を追放し、たとえば紫式部女史など女性の偉人を配します。」という人がいて笑えたが、紫式部よりもまず定子さまでしょう。もっともあまりにも有難すぎて、かえって使う気になれないか。
今の感覚でいえば稚拙にすぎる”公約”がほとんどだが、東京-神戸-呉-門司間長距離フェリー構想や、納税者が税金の使途を指定できる制度など、おや?と思わせるアイデアもいくつか見られる。
1969年には「亭主&女房学校」という欄がスタート。こちらは完全匿名で、連れ合いに対する不満を思い切りぶちまけてもらう趣旨。かなりの悪態も見られ、後年の何とかちゃんねるの先駆とも言えるふんいきさえ漂う。
ネットの時代の匿名掲示板と大きく異なる点は、その場でしか通じない独特のスラングがないこと、及び「ネタにマジレス」に代表される”冷笑の姿勢”が見られないこと。冷笑、そしていわゆる”いじり”は1980年代以降の”芸人文化”が後世に遺す「負の遺産」である。
第2世紀に入るとこの欄は「家庭学校」と改題して、広く家族や親類縁者の困った言動を吐き出してもらう場になったが、あくまでウィット精神を持ち、相手の尊厳を冷笑しないことをマナーとしている。
1970年代半ばには「すばらしき日曜日」という投稿欄が別途登場。「いささか反語めいた、皮肉な味つけを期待しているが、文字通りすばらしい内容も大歓迎」とのこと。あいにく掲載号を手元に残していないが、プロ野球広島カープの熱心な”推し”、すなわち「カープ女子」の先輩の投稿が愉快だったことを覚えている。
お好きな方がいらしたのか
「暮しの手帖」には鉄道もよく登場する。以前の記事で神戸市電や東京都電31系統の写真について紹介したが、第69号(1963年)には「寝台車の上手な乗りかた」というグラビア記事が掲載されている。
1963年3月、東海道本線の寝台急行全盛期。最初の写真は夜の東京駅14・15番ホームで、そのまま「点と線」の世界。取材班は東京22時00分発の大阪行き寝台急行「月光」に乗車して、必要な切符、車内設備、備品、乗客側で持参すると便利なもの、深夜の寝台や朝の洗面所でのマナーなどについて詳しく解説している。
当時は1等二段式・2等三段式寝台だったが、基本的な構造は2016年にブルートレイン客車が運転を終了するまで引き継がれていた。
1971年の第2世紀第10号では弟子屈町在住の写真家が撮影した釧網本線のグラビア写真、同年の第2世紀第15号では翌年の廃止が決まっていた都電24系統(須田町-上野駅-柳島車庫)の乗客インタビューとレポート写真記事、1977年の第2世紀第50号では若い編集部員3名が東京-博多間を普通列車で乗り通し、乗り合わせた人にインタビューする記事が掲載されている。
東京6時25分発沼津行きでスタート、三原22時16分着。これは1994年に宮脇俊三氏が「青春18きっぷ」を使った旅をレポートした際の行程(小学館「駅は見ている」1997年収録)に似ているが、1977年の「暮しの手帖」取材班は20時47分岡山着であったのに対して、1994年の宮脇氏は東京6時31分発沼津行きでスタートして17時56分岡山着、そこで宿泊している。愛知県内や京阪神の新快速の威力を改めて思い知る。
取材班は三原駅前の交番で宿を紹介してもらい、翌日は6時18分三原発、14時54分博多にゴールイン。できたばかりの周防大島大橋の写真が掲載されている。宮島ボートレースに向かうおじさんの、朝から「一杯やりんさい」が愉快な一方、下関付近で乗り合わせた島根県の老夫婦は、話が戦死した息子に及ぶとそのまま黙ってしまう。
その他、現代の鉄オタがどれほど望んでも乗れない列車や路線も登場する。他の交通機関がまだ発達していなかった時代とはいえ、編集部にこの方面がお好きな方がいらしたと想像できる。
いつの時代のお話か
以前の記事で「暮しの手帖は、コミック文化やカワイイ文化のメインカルチャー入りを予見できなかった」と書いたが、その一方で「これ、60年前の文章だよね?」と驚くほど、今の世の中にもそのまま通じる指摘や問題提起がしばしば現れる。
1959年の第48号には「このごろのお天気は、どうしてこんなにへんなのでしょうか」という記事が載っている。1958年夏の少雨、初秋の台風連続上陸(22号狩野川台風など)、晴天の少ない秋、暖冬と例をあげて「地球は暖かくなっている」「炭酸ガスが増えてきた」「だんだん日本にも四季はなくなる」と考察していて、背筋が寒くなってきた。
当時まだ生まれていなかった私が小学生だった頃もまだ、冬は寒さにふるえていたのだが、これほど昔から地球温暖化を予見していた人が気象庁にいたとは驚きだった。1970年代にノストラダムスの大予言に便乗する形で流行していた「21世紀は寒冷化して、世界的な食糧不足が起こる」というアオリは一体何だったのか。
1964年の第73号には「朝ごはんをたべてこない子供たち」。ある小学校の教員から「午前の授業中に突然倒れた子がいた。朝食を取ってこなかったという。」と聞いた「暮しの手帖」編集部がかなりの危機意識を持って実態調査を行った記事である。当時の編集部員は全員が戦中戦後の食糧不足を体験していた世代のはずで、あえて朝食を取らないという発想自体が驚天動地だったのだろう。摂食障害や過度のダイエット、醜形恐怖などメンタルな面の影響にはまだ及びがつかなかった時代である。
この記事には米国の雑誌から転載された子供のイラスト2点が使われている。ひとつは数人で輪を作って踊る子供、もうひとつはひとりきりで眺める子供の後ろ姿。私は、もちろん後者の子のほうに重なる。小学生時代はこの絵のようにいつもひとりぼっちだった。
この2点のイラストはサイズを変えて、繰り返し記事内に挿入されている。レイアウト上の都合だろうが、今読み返しても胸の奥にしまっている思いがほろ苦くよみがえる。
突然の交通事故で家族を失い、加害者が未成年だからという理由のみで守られ、誠意ある態度を示さない。
指定席を買って列車に乗ったのに、後から来た夫婦が「夫婦だから」という理屈で、席を変わるよう執拗に要求する。
いずれも1960年代の号の「雑記帳」欄に掲載されている投稿である。50年以上、私たちは何をしてきたのか、何をしてこなかったのか。
1971年の第2世紀第10号、松田道雄氏の「晩年について」。筆者は長年「暮しの手帖」に医療記事を掲載してきた医師。老衰の問題、老人ホームの問題から始まり、延命治療の可否や安楽死の問題にまで踏み込む。
晩年は矛盾にみちた時代である。(中略)その矛盾のなかで、いちばん現代的なものは、自分は美しく死にたいのに、みにくく死ぬことしかゆるされないことだろう。…われわれは、今日、自分の死の美学をもつことはゆるされない。
著者はしめくくりでこう訴える。
人間はそれぞれ自分だけしか生きられない生き方をしたのだから、その人間にふさわしい死を、死んでいく人にえらばせるべきである。他人が押しつける死は、どんなに最新の医学であっても、非業の死である。
医者が病気でなしに、人間をみてくれることを切望する。
私はこれに加えて「その人間にふさわしい弔われ方も、死んでいく人にえらばせるべきである。」と主張したい。
故郷の墓に対する執着があまりにも強く、今の世を生きるわが子より墓が大事といった言動を取り、時に暴言さえ吐いてきた父や、葬儀の後「故人もにぎやかなほうが喜ぶでしょうから」と勝手に決めつけて酒を飲んで騒ごうとする老人たちの姿を見るにつけ、私は「弔われたくない」と思う。生きているうちは散々見下しておきながら、死んだら急にしおらしく惜しがるなど、如何なる了見か。
衛生上の悪影響が及ばないように処理さえしてもらえたら、それで結構。葬儀も墓も一切不要。わが命は大して親しくもない人たちの飲み会を設けるためにあるのではない。亡骸は明石海峡にまいてもらいたい。私という人間が生きてしまった証は、一切残らないようにしてもらいたい。
松田氏は政治についても、今の世にそのまま通じる見解をたびたび述べている。「暮しの手帖」はまだ古典になっていないと、改めて思う。
お願い・お知らせ・注意喚起
毎号、本文ページの最後には「編集者の手帖」という1ページコラムが掲載されている。やわらかく品ある筆致で、読者へのお知らせ、原稿募集、取材対象者へのお礼などを載せている。
第80号(1965年)では、東麻布にある暮しの手帖研究室の様子を紹介している。東京タワーの近くにあり、完成当初「タワーから研究室が見えるだろうか」と、社員が展望台に上って備え付けの望遠鏡で確かめたら、留守番の社員の顔まではっきり映ったという、のどかなお話もある。今では望むべくもない。
その一方で、毅然とした文章でお願いや注意喚起をすることもある。
(1)なりすまし(第42号・1957年)
北海道で「暮しの手帖社の者」と言って、食事や宿泊の世話をさせて、時には金銭を恵んでもらう「いかにもインテリの編集者らしい男性」がいたという。
口惜しいことには、実際の暮しの手帖社には、編集長はじめどう見たって、「インテリの編集者」らしいのは一人もいないのですから皮肉なものです
と笑いを取っているが、これは立派な犯罪行為ではないか。当時の状況では捜査や検挙が難しかったのだろうか。
(2)建築相談(第56号・1960年)
この時期編集部には「住まい」の設計に関して相談やアドバイスがほしい旨の手紙が殺到して、その返信に窮していたという。ただでさえ激務の雑誌編集に加えて、好意で返信するにも限界があるというところだろうが、手紙を出す側からすれば「家を建てるは一生に一度。工務店のおやじ以外のセカンドオピニオンが欲しい、暮しの手帖ならば”キッチンの研究”を掲載しているし、信頼感は抜群だし、良い知恵を出してくれるのではないか」という期待があったのだろう。一般庶民には新聞雑誌以外に情報をつかむ手段がなかった時代であることを考えると、一方的に非難できない。
(3)値上げ(第82号・1965年)
物価上昇に抗い、この1年間もう1号、もう1号とがんばってきたが、ついにどうにもならなくなったので値上げしますと、余白を半分以上残して宣言。編集部員の苦渋ぶりが余白から伝わってくる。
創刊15周年にあたる第71号(1963年)では花森編集長自らこの欄の筆を取り、この雑誌の編集哲学に触れている。90号を越えると少し余裕が出てきたのか、随想的な文章が現れる。第99号(1969年)は「暮しの手帖流・春はあけぼの」といった趣。第100号(1969年)で再び花森氏が筆を取り、編集者として生きてきた上で幸せだったことを語り、次を「第2世紀第1号」とすると宣言した。
グリーフケアはまだ遠く
最後に、第2世紀第1号(1969年)の「雑記帳」に掲載された投稿について紹介する。
ビルマ(ミャンマー)の日本大使館員夫人が、日本からの戦没者遺族団旅行受け入れの話が来るたびに「嫌ねえ」と顔をしかめるという。
戦没者の遺族はおとなしく、案内先で静かに祈りを捧げる。一方、当時出征した元兵士が来ると状況が一変する。かつての戦場が近づくと目の色が変わり、ヘビやトカゲまで食べて生き延びた、戦死した友人を置き去りにして、その靴を履いて逃げた…などと語り始め、最後は声をあげて大泣き。どれほどなぐさめても効かないという。
それゆえの憂鬱ということだが、これは単に外交官夫人になったという人に聞き役を押し付けるものではなく、専門のカウンセラーが対処すべき案件であろう。戦後かなり経って、高度成長ですっかり豊かになってもなお、トラウマやPTSD、グリーフケアの概念はほとんどできていなかった。それどころか「いい年をしたおじさんが人前で泣くなんてみっともない」という偏見が「嫌ねえ」の背後に隠れていないだろうか。
次に「暮しの手帖」について取り上げる際には、戦争体験に関するこの雑誌のスタンスについて考えていきたい。
