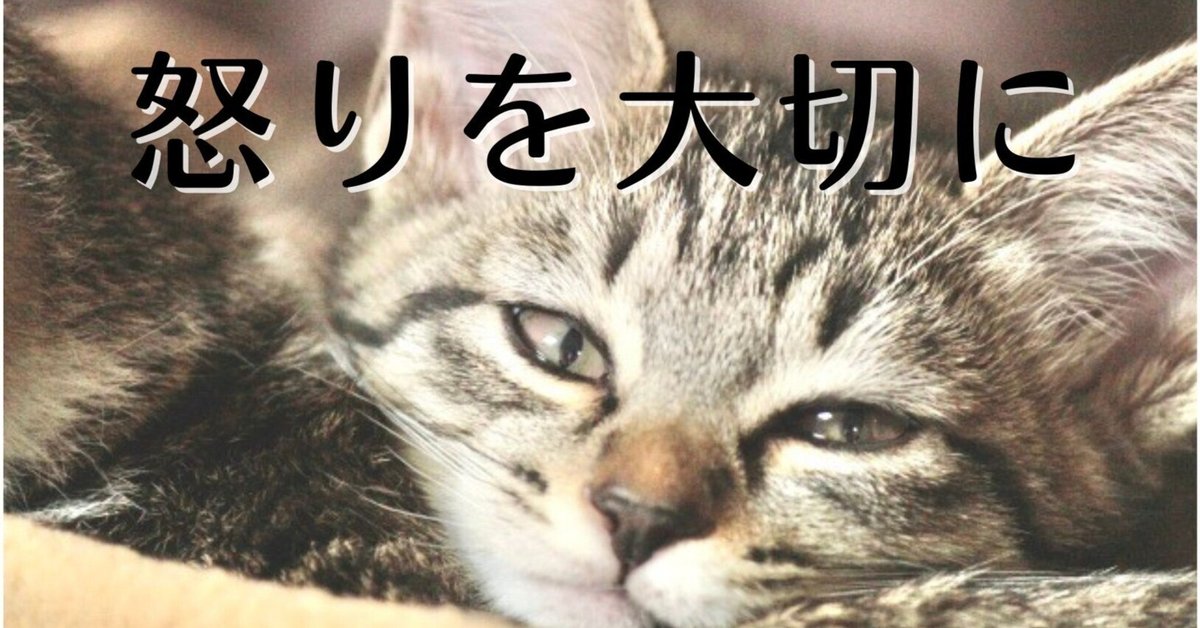
怒りを大切に.1
[スピリチュアル・アンガーマネジメント]のための資料として…
これまで、セッションやセミナーでお伝えして来た
「喜怒哀楽の意味」の中の「怒り」についてまとめました。
・「喜怒哀楽」の大切さについてはこちらを
→https://note.com/leoriel/n/n7a80bca86053
・怒りのマネジメント【怒りの三原則】についてはこちらを
→https://note.com/leoriel/n/n3f855c261c35
(怒りをガマンしない生き方)
喜怒哀楽(きどあいらく)の感情のうち、わりと「扱いにくい感情だ」と言われてきた「怒り(いかり)」について解説します。
人間の感情(喜怒哀楽など)は、人間にとって必要(重要)だから持っている、与えられています。
でも使い方の解説書が学校で配られているわけではないので、
まだまだもてあましている人は多いようです。
場合によっては、「感情を抑えなさい」「感情を捨てなさい」などの、
不親切な情報や危険な思想を押しつけられて、病んでしまう人もいます。

怒りは「心の痛み」をあらわす大切な感情
「怒り」を大切にしていただきたいと思います。
「怒り」は、喜怒哀楽の中でもとくに
「心の痛み」をあらわす重要な感情だからです。
「怒り」=腹を立てた時、怒っている時は、
エレガントに表現するのがむずかしい感情ではあります。
でも、表現しないとならない。
表現しないと、体調をくずすことになるくらい大事な感情です。
例えば、喜び・楽しみの方は表現しやすいですし、もし表現できなくてもあまり身体に害はないでしょう。
楽しい時には、快感ホルモンと呼ばれるドーパミン、ベータ・エンドルフィンやエンカフェインなどの身体に良いホルモンが出るということなので、体調もよくなることが解っています。
ウツを防ぐセロトニンもバランス良く分泌されると聞いていますし、
笑顔を見るだけでも、免疫をつかさどる細胞が増えるという説もあります。
でも、怒りや悲しみのときは
ノルアドレナリンやアドレナリンなど毒性の強いホルモンが出て免疫力を下げますから、それを溜め込んでしまったり、しょっちゅう怒っていると、
どんどん身体を悪くしてしまいます。
ネガティブ感情は、毒性ホルモンを早く中和するためにも、なんとか上手く解消しないとならないわけです。
怒りは、我慢しすぎると体調だけでなく心理的にも危険で、鬱病や統合失調症になってしまったケースもあります。
これはあまり知られていないようなのですが、「統合失調症」が治った人を研究すると理解が早いと思います。
(スピリチュアルの良いところは、医師と違って診断はできずとも、根本原因を知って対処の仕方をチャネリングできるところですね)
怒りは早めに解消するのが一番。
かといって、なりふりかまわず怒りを外にぶつけては、
だれかを傷つけてしまったり、ハネ返って自分が傷ついたりして危険です。
だから
「怒り」を対処しにくいものだと思い込んでしまうのも、無理はないんですね。
そう書いている私自身、マネジメントできる時と時間がかかる時がありますから(笑)
もしかしたら「感情」を上手くマネジメントできないのは、何かの陰謀(?)のせいかもしれません。
感情を誰かにあやしてもらう文化
冗談はさておき、陰謀というか歴史的なこととして。
日本人は「自分の感情は誰かにコントロールしてもらうものだ」と思い込まされて来ているのではないか…
昔から、よく不機嫌な父親が、その感情を妻や子どもにぶつけたり、
DV(ドメスティックバイオレンス)は当たりまえ、
はては、ちゃぶ台をひっくり返して大切な食べ物をムダにしてしまったり、そういうシーンを見たことがある人がいると思います。
幼児的なその態度は、あきらかに*インナーチャイルドが傷ついているのですが、当時はそれを効率よく癒すすべもなかったわけで、
自分の感情をマネジメントできなかったんですね。
*インナーチャイルドとは:子どもの頃の体験記憶や、子どものように純粋な感覚のこと。「内なる(インナー)子ども(チャイルド)」。
インナーチャイルドが傷ついている人は、アダルトチルドレンと呼ばれ、トラウマ(心的外傷性ストレス)を持っていることも多く、自分らしく生きられない悩みを抱えやすい。
大人になってもエレガントな感情表現ができず、
はては自分より弱い立場のものに当たり散らすという…
幼稚園児と同じことをしても、何だかんだ許されて来た文化があったと思います。
まったくみっともない姿でしたが…
それが解消できる時代になりました。
本来なら、大人になったら「自分の感情は自分でマネジメントする」もので、それが「自己管理」であって、だれか他人(ましてや弱い立場の人間)にあやしてもらうものではないわけです。
もちろん、一人で感情をマネジメントするのが難しいときは、効率良くサポートを依頼するのもおすすめですが、
セルフイメージが低くて自分に自信がないと、だれかに助けを求めること自体、ハードルが高いんですよね。
今でこそ、自己啓発系のセミナーやコーチング講座では
「感情」を前向きな視点で取り組めるようになってきましたが、
感情的になる(感情に溺れる)と、判断を間違えて失敗しやすいので
昔は「感情」自体を怖がって、「良くないもの」「危険なもの」だから
なるべく「抑え込むもの」として否定的に扱っていたと思います。
とくにひどい場合は、自分の感情を認めることができず
「おまえが私を怒らせるのが悪い」と相手のせいにする人もいますね。
(相手が意図的に怒らせにくるケースも無いわけではありませんが、いずれにしてもマネジメントするのは自分自身です。「怒りの三原則」参照)
古い文化の幼児的な価値観から抜けられないままだと
「自分の感情はだれかが何とかしてくれるものだ」と思い込んだまま、
DVや、様々なハラスメントにつながって行くことになります。
怒りを否定してはいけない
怒りを悪いもの・いけないものだと思うから、怒りを否定してしまい、
怒りを持っている自分を否定してしまう。
自己嫌悪になったり、怒っている人を非難してしまう。
でも、喜怒哀楽の感情は、潜在意識からのメッセージなので大事なものです。
「怒り」という感情自体は、とても重要な役割をもっているので、
大切なものであって、悪いものではありません。
まずは「怒りは大切なメッセージ」なので、それを解読して役立てることができるという姿勢から、
「自分の怒り」は、自分の内面で起きていることなので、自分で管理しないとならないもの、と認識していただきたいです。
怒りは、否定するものではなく、マネージするもの。
だれかに腹を立てたとしても、だれかに何かをされた結果だとしても、
最終的にそれをどう表現し・どう解消するのかは、「あなたの選択次第」ということです。
「怒り」を、怒鳴ったり殴ったりで表現するのか、
コトバできちんと伝えるのか。
暴言や暴力や何かを壊したりして解消するのか、
冷静な話し合いや効果的な方法で解消するのか
選ぶことができます。
「でも、怒りは瞬間的なものだから、そう簡単にマネジメントできないよ」という心配もあるかもしれません。
それは訓練しだい。
まず、「怒りの正体」を知って、そこから対処法を知っていれば、あとは練習しだいなのです。
修行僧や人徳者がいう「怒りをおさめる」は、このマネジメントができている状態のことをあらわしていて、知識と訓練のたまものだと言えます。
心の傷は目に見えない
怒りの解消方法はいろいろありますから、
まずは「怒り」の正体を知ってもらいたいと思います。
正体が分って、なにが原因かが解れば、その原因を取り除くことで怒りを消せるからです。
怒りの正体は、「心の痛み」です。
身体に傷を負ったり、怪我をしたら、ふつうはキズが痛みますよね。
ズキズキと…
それによって、ケガをしたことがわかり、手当てができる。
痛みの強さによって、そのケガの重症さが分かるようになっている。
時には、あまりに傷が重症過ぎて痛みを感じない(マヒする)場合もありますが。
心も同じです。
グサッとやられて傷を負えば、痛みます。
身体の傷が「ズキンズキン」なら、
心の傷は「ムカムカッ」や「イライラ」という感じ。
深くて大きな傷なら「カーッ」と怒りが燃えてくるかもしれません。
それが第1の怒りの正体です。
そしてやはり、
体の傷が深すぎるとマヒして痛みを感じないことがあるように、
心の傷も、深すぎてムカッとする怒りすら感じない場合もあるわけです。
身体の傷は、血がダラダラと流れたりして目に見えことも多いので、
場所も原因も特定しやすいし、手当てが必要なことがわかりやすいですが、
心の傷は目に見えないので、
どこでなにが起きたのかを含め、傷ついたことを知らせるために「怒り」という感情を使うわけです。
だから当然、怒りを感じたら「手当て」をしないとならない。
無視してはならないわけです。

心が折れる=心の骨折
たとえば、ケガをしてボタボタと血を流している人を見て、放っておく人は少ないと思います。
骨折して骨が異常な方向に曲がっていたら、痛みを緩和したり、なんとか元どおりにしようとしますよね。
--ところが
心が傷ついて(ケガをして)辛くても、心が折れていても、
手当てをするどころか
「怒りを静めなさい」「楽しいことを考えなさい」「怒りを捨てなさい」と言う人がいます。
心は目に見えないけれど、
ノルアドレナリンなどの毒性ホルモンが出ています。
(スピリチュアルでは、そこからエネルギーがダダ漏れしています)
それによって、免疫力が低下していたり、心にトラウマを抱えたり、
セルフイメージが下がったりして、解消できずに長く苦しんだりします。
傷ついて出血している人に、そんなことを言うのでしょうか?
止血するのが普通ですよね。
患部に対して「なんで出血してるんだ!止まりなさい」と叩いたり、
「出血なんて気にするな」「痛みを忘れろ」とは言わないはずです。
(「怒りを止める」は「出血を止める」の誤解かもしれませんが)
なのに、心の傷は「恥ずかしい」とか「気にするな」とか言われ、
手当てもされないままに何十年も放っておかれたりします。
骨折なら、なるべく元の形に戻そうとする。
決して「なんで折れているんだ!」とか「気のせいだ」などと言わないはず。
でも、心が折れているのを無視して、
そのまま折れ曲がったり、ねじ曲がったりしている人々がいるのです。
さらに解ってきたのは、
ケガした心を無視したり、否定したりして傷の手当てをしないでおくと、
そこがまるでただれたり膿んだりするように、「恨み」の感情で表現される…ということ。恨みは、心の膿(うみ)なんですね。
怒りは、心の傷を知らせる警報であり、サインであり、メッセージだということです。
心の傷もいろいろ
そして「心の傷」もいろいろです。
じつは、何千年ものあいだ、人類が「怒り」の感情をうまく癒せなかった理由はここにあったかもしれません。
ひとことで「心の傷」といっても、これがいろいろあるわけです。
よく、会話の中で「それは傷ついちゃうなあ」とか
「今のことで、私は傷ついた!」などのセリフがありますが
心の傷というのは、
受け手の感じる度合いによって、浅い・深いがちがいます。
さらに、相手がもたらす場合と、自分から起こす場合があります。
相手に悪気があろうと、無かろうと、
こちらにとって大きな衝撃になるなら、そのときに感じた怒りは「大きな傷」または「深い傷」になりますし。
敵意のある相手からの攻撃でも、マトが外れていると「かすり傷以下」で、笑ってすますこともあると思います。
相手が攻撃的で、あなたのエネルギーを奪いたいという無意識の意図で、あなたを傷つける言動をすることがあります。
一方で、
対話の相手が、悪意なく自分の感想をのべたのに、こちらには「カチン」とくる、ということもあります。
いずれにしても「怒り」を感じるというのは、自分にとって「存在の危機」を感じたからです。
(本当に怒らなければならない時と、怒らなくてもよい時の区別は「怒りの三原則」をご参考に)
人体が「存在の危機」を感じるような時は、殺されそうになっている場面ですから、そんな場面からは早く逃げないとなりません。
心が「存在の危機」を感じている時は、
その「危機」がどれくらいの重要度なのか知って
(心が)殺されそうになっていたら逃げなければなりません。
自分に対して、誰かが「攻撃」してきた時はもちろんですが、
自分をないがしろにされたと思ったとき(尊重されなかったとき)、
自分が努力したことがムダになったと感じたとき、
自分の主張を誤解されたと感じたとき、
相手の対応が、何か不当だなと感じたとき、
気を遣いすぎてエネルギーを奪われ続けたり、
エネルギーを与えつづけて補填していないとき、
強い悲しみを感じたのに、我慢しつづけたとき
なども、
その人の心や思いが「存在の危機」に陥っている状態…と言えます。
そうなると、人間は、自己管理をしなければなりませんから、
安全のために「警報ブザー」が鳴るようになっているんですね。
生き延びるため、安全に暮らすために、心の健康を守る警報
それが「怒り」という感情です。
悲しみを我慢しすぎると心身が病む
怒りの前段階には、「悲しみ」(喪失感)というものもあります。
「第一次感情」と呼ばれる、軽い「心の痛み」です。
悲しい、むなしい、こわい、がっかり……など

それは、なにか自分にとって大事なものを失った(または、失いかけている)ことを知らせる感情です。
「喪失感」というくらいですから、誰か・何かを失った時もそうですが、
自分自身を失いかけた時も悲しみを感じ、
それが表現できずに抑圧される(押さえ込まれる)と、
次の段階が「怒り」として強い痛みで表現されるわけです。
この感情のリレーは、ホルモンのリレーでもありますが、
幼児期からの体験を経て神経回路が磨かれていくので、成長すると
一瞬で「悲しみ」から「怒り」に点火するため、
「第一次感情」に気づかない人も多いと思います。
大事なものを失うということは、命や、生きがいや、愛かもしれないのですから、無視したり忘れてしまったりしたら困るわけです。
それも「自分の存在否定」=「存在危機」につながります。
怒りを大切にしなければならない理由が、おわかりかと思います。
怒りを探求することで、
あなたにとって大切なものが浮き彫りにされ、守ることができますし、
もう要らない価値観なら手放すこともできるわけです。
怒りというギフト
「心の痛み」の中には、じっさいはたいして重要でないこともあります。
たとえば--
猫好きな彼が、彼女を褒めようとして「キミは猫のようだね」と言ったのを、猫嫌いの彼女が「それって、どういう意味!」と怒ったりする時などは、単純に定義の誤解がおきているわけです。

でも、心には「存在の危機」や「喪失感」を感じています。
自分にとって嫌いな「猫」に例えられた不満、
互いに分り合えないという一瞬の不安や絶望感、など。
相手の言動が、「自分の存在に価値をおいていないように感じる」ということが、=「存在の危機」ということになります。
客観的な視点ではなく、あくまでも、感じた人の側から
「これは自分自身の存在の危機だ」となったとき、
「このままにしておいたら、自分の安全な状況を脅かされるのでは?」と感じたとき、そのシグナルが「怒り」としてやって来ます。
重要度によって「小さなムカつき」や「強い怒り」などの違いがでます。
他方、誰かがあなたのエネルギーを奪いにやって来たとき、
それに気づかせるための潜在意識からの(魂レベルの)シグナルとして、何か不満を感じたりもします。
妬みや悪意にさらされることはもちろんですが、
たとえば、妬みからの誹謗中傷や、詐欺にあったり、暴力を受けたり
「おまえのためだ」という価値観を押し付けられたり
尊厳を奪われたり、努力を無にされたり、
何かによけいな気をつかうことでエネルギーを奪われ続けたりすると、
疲れて免疫力が下がっていく…
心身を病んだら「生ける死人」になってしまうのですから、
その手前で「怒り」というシグナルが来るのは当然だったのです。
怒りは、「あなたの存在の危機を知らせる、心の痛み」です。
よく見たらたいして重傷でないな…という「危機感」の場合は、すぐに解消できます。そのときは、「怒りを捨てる」「忘れる」ことができるはずです。
放っておいたら本人にとって心身の死にいたるような問題なら、
「危機感」=「怒り」も強くなり
原因を取り除くまで、そう簡単に捨てるわけにいかない。
怒りの原因である「存在の危機」を見つけられれば…
それが誤解であれば解消できますし、
もし、誹謗や中傷のように、誰かが本気でこちらの「存在を脅かす」つもりで来たのなら、はやく気がついて避けるために対処する必要がでてきます。
また、相手との関係性をあきらかにすることができたり、
怒りのもととなった価値観をみることで、
自分の中のいろいろな観念(価値観)に気づくことができます。
たとえば--「こうするべきだ」「人はこうあるべきだ」という考え、
自分はずっとガマンしていたのにずるいという思い
相手が自分の鏡だった…という気づきなど。
これらは、さらに深いメッセージを持っていたりするので、
たくさんの気づきや学びから「ギフト」を受け取ることにもなります。
怒りをやみくもに無視したり、捨てたりすると、
これらのギフトを受け取るまで、怒りが何度もくり返す場合があります。
怒りと恐怖の抑圧からの統合失調症
身体の傷が深いと、痛みが強く感じられるのとおなじで、
心の傷も、深いときには「怒り」を強く感じます。
怒りの度合いや量で、そのときの心の傷の深さを知ることができます。
そして、丁寧に診て、癒す必要があるわけです。
決して、痛みを無視したり、ガマンし過ぎてこじらせたりしないように。
もしも怒りを無視したりガマンし続けると、
感情がマヒして「無感動」になったり、「無気力」になったりします。
虐待やハラスメント(弱いものいじめ)などに遭うと、
本来は怒り(または悲しみ)を感じ、悔しく思うのが普通のシグナルですが、
直接言い返すとかえって暴力をふるわれたり、すぐに相手を拒否できない場合もありますよね。
怒りをガマンし(無視し)続けると、感覚や感情がマヒしてきます。
チャゲ&飛鳥の歌「YAH YAH YAH」の歌詞の中で
「傷つけられたら牙を剥け、自分を無くさぬために」というのは
尊厳を失うと、心が死んでしまうからですね。
暴力的に返すのは危険ですが、
怒りによって「心の傷」に気づき、それを手当てをする必要があります。
感情が麻痺すると怒りも感じませんが、喜びも感じなくなっていきます。
場合によってはうつ状態になりますが
精神疾患だと統合失調症になっている人が多い気がします。
怒りというのは、瞬発的な攻撃や逃避のエネルギー(戦うか・逃げるかの行動を促す)でもあるので、
怒りを抑圧して危機を無視しつづけていると、最後は怒りが爆発して攻撃的になったりします。
「キレる」という状態です。
その攻撃性が、外に向かえば「暴力」、
自分の内側に向かうと、慢性的な身体の病気や心の病気になってあらわれます。
たとえば…
不当にハラスメントを受けた社員が、その正当な怒りを表現できなかったために抑圧してしまい、それが幻聴を引き起こして統合失調症になったケースがありました。
「怒り」は、
恐怖と戦う(対峙する・立ち向かう)時に、役立つ感情でもあるからです。
それを抑圧してしまうことは、自らを犠牲者にして、生きることを終わらせてしまいかねない。危険なことだったのです。
あまりにもショックな出来事、あまりに悲しみが強いとか、
あまりに絶望感が強くて呆然としそうなとき、そういう状況・そういう感情になった時も「怒り」が必要な場合があります。

怒りをうまく活用する
ショックでエネルギーを大量に失ってしまうと、身動きできなくなります。
ところが、それだけの衝撃を受ける状況というのは、その人にとってとても危険なわけですから、はやくその場から離れたほうが良いわけです。
なので、魂はその時に「怒り」という感情を使うことがあります。
「火事場の馬鹿力」や「窮鼠(きゅうそ)猫を噛む」のように。
「怒り」はとりあえずの爆発的エネルギーなので、人を行動に移すことができるからです。
実際、怒っている人の波動は低いですが、エネルギーは強いです。
(そのぶん、持続性はない)
「怒り」を上手に使うと、行動を起こすエネルギーになってもくれるということですね。
その一方で
「怒り」というのは、状況をあらわす「信号(シグナル)・サイン・警報」なので、そこにずっと執着する必要はないわけです。
人が怒ると、アドレナリンやノルアドレナリンなどの毒性の強いホルモンが出ますので、1時間も怒りつづけてはいられませんが…
「怒りの感情」に執着するのは健康に悪いですから、
それならできれば「はやく怒りを解消した方がいいね」となるわけです。
怒りにとらわれてしまい、解消しにくいときは
原因となる「恐怖」が解明され、対処されていなかったり、
失った感情のエネルギーをまだ取り戻していなかったりする時なので、
まずは丁寧に診てあげることが大事なんですね。
「何を不当だと感じたか」が解れば、怒りはかなりの部分がおさまります。
イメージとして、
身体の「打ち身」などのように、ぶつけたその時は痛くても、
重症でなければ、痛みを気にせずに過ごして治って行く、ということがあります。
それと同様に、「怒り」という心の痛みも、
誤解から来たものなどは、気を紛らわせて笑っていたら解消される程度のものもあります。
カウンセリング講座では、「心に入って来たものは、コトバで外に出す必要がある」と伝えられています。
身体の健康管理は、食べて、不要なものはトイレで外に出しますね。
それができないと「便秘」という状態で、身体が不調になったり、病気のもとです。が、
心の健康管理の時になると、嫌なことを聞かされたりして、それが心に不要であっても、ガマンして外に出さない人がいます。
それは、心の便秘ということになりますよね。
心が狭いとか、ふところが浅すぎて、心に溜めておけなくて、むやみやたらと誰にでも(または聞いてくれそうな人誰にでも)すぐに怒りを口に出す人が近くにいると、つい自分はそんな迷惑をかけたくない…と思ってガマンしてしまう優しい人も多いと思います。
それで、自分自身は心の便秘になってしまうか、
無意識に子どもや配偶者にグチってしまっている場合も…
ひどいときは、「私は怒っていないし、グチってもいない。ただ、感想を言っているだけ(評価をしているだけ)」と言って、
じつは不満や怒りを家族にぶちまけている人もいました。
目に見えないことなので、わかりにくいかもしれません。
トイレはトイレに、ゴミはゴミ箱に
不要なもの(ゴミ)でも、出すべき所に出せば、喜ばれることがあります。

怒りを解消するために…
怒りを解消する方法は、ワークショップで具体的に説明をしているため、記事にまとめられないのですが、
【怒りの三原則】に要点をまとめていますので、
ご参考にしていただければと思います。
--
この記事は(2009/12/04)にまとめられたものを再編集しています。
あとで、偉い学者さんの研究資料が出るかもしれませんが、それを待っているあいだに心の傷をこじらせないために、先にまとめました。
最近は「感情を大切に」という人が増えてきて何よりです。
2000年を過ぎるまで、感情はネガティブにとらえる人が多かったんですよね。
当時、スピリチュアルを学ぶ人が「怒り」を上手く手放せずに先へ進めなくなっていたので、メッセージをお伝えしていました。
アメリカの心理学者ロロ・メイ著「我が内なる暴力」(誠信書房)がとても参考になるのですが(絶版らしいです)
・「喜怒哀楽」の大切さについてはこちらを
→https://note.com/leoriel/n/n7a80bca86053
・怒りのマネジメント「怒りの三原則」についてはこちらをご参考に。
→https://note.com/leoriel/n/n3f855c261c35
・怒りを大切に.1(元記事FC2ブログ)
http://leoriel.blog105.fc2.com/blog-entry-309.html
(スピリチュアル・アンガーマネジメント)
「アンガーマネジメントを習っても上手くいかない人が最初にやるべきたった一つのこと」のための資料記事。
いいなと思ったら応援しよう!

