
Essay|出国日の朝に。
出国する日の朝は、自ずと目が覚める。身体に静かな緊張が走っているからだろうか。
ただ、今日は目が覚めたときには九時をまわっていた。出国前には珍しく、ゆっくり休むことのできた証拠だろうか。それとも今朝に至るまでに詰まっていた用事で疲れていたせいだろうか。
***
出国する日の朝は、なぜタイに行くのかということを考える。
中学生や高校生の頃の何も知らない自分は、世界には教育を受けられない子どもたちがいて、その子たちに手を差し伸べる仕事に就きたいと漠然と考えていた。
何も知らないのにも関わらず、進路を決めることを求められ、将来を決めることを求められ、大人に対しても、ある程度「恵まれている」自覚のある自分に対しても、納得できる答えを見出さなければならない。
考えてみれば、ある程度「恵まれている」中高生も何かを決めなければいけない葛藤に苛まれている。自分が誰であるかを知らないうちに、そしてそこに明確な答えなどないことさえも、知らないうちに。
自分の場合は、そこにたまたまタイがあった。同い年のタイの友人がいた。普段は英語という、お互いにとっての外国語で話をしていた。だからこそ、タイ語で話してみたかった。
〈彼/彼女ら〉と、〈彼/彼女ら〉の言葉で話すことで、〈あなた〉として出会い直してみたかった。
だから高校生の頃の自分は、大学でタイ語を専攻することを心に決めた。
誰から求められたわけでもない、自分で下した初めての大きな決断だったかもしれない。
それでも、視野の狭い高校生の自分は、「子どもたちのために」から逃れられなかった。だから、自ら選び取った「タイ」と絡めて、「タイの子どもたちのために」を推し進めようとしていた。
まだ何も専門のない自分には、何もできないことも知らず。
まだ何も知らない自分には、別に全身全霊を捧げなくても「子どもたちのために」できることがあることも知らず。
そのまま、大学の最初の二年間を突っ走ってしまった。
***
交換留学なども経て、今の自分は大学院にいる。そして、研究者になることを志している。
「その研究が何につながるのか」
研究のドアをノックして、必ず返ってくる問いはこれだった。もちろん、学術的なフレームに載せて、応答しようとする。でも、必ずしも自分を納得させられない。フレームに乗せることに、学術的には意味があるものなのは確かだ。しかしそれは自分が見てきたものにとって、そして自分に熱心に声を聴かせてきてくれた人たちにとって、何の意味も持たないからだ。
それはまさにただの〈枠(frame)〉でしかない。枠の中を乾いた冷たい風が通り抜ける。
***
大学院に入って最初に読んだ本に、宮地尚子さんの『傷を愛せるか』という本がある。そこで〈目撃者(witness)〉という言葉を知る。
最愛の夫を亡くした友人の仮通夜や葬式に、宮地さん本人が出席したときのことが書かれている。
彼女にどう接すればいいのか、わたしにはわからなかった。どんな慰めをいっても、手を握っても、ハグをしても、なんの力にもなれないと思った。すべてが薄っぺらくて、自分が下手な芝居を演じているような気さえした。
そばにいても、彼の代わりにはだれもなれない。そのことは、痛すぎるほど明白で、動かしようのない、どうしようもない事実である。
(…)
ちゃんと見ているよ。なにもできないけど、しっかりと彼女が喪主の役割を果たす姿を目撃し、いまこの時が存在したことの証人になるよ。そしてこれからも彼女が彼女らしく生きていくのを、見つめているよ。
何もしてあげられない。どんな慰めも空疎で、空回りしていく。それでも、彼女の悲しみの、彼女の最後の役割の、そして彼女のこれからの生の、証人となる。
〈目撃者(witness)〉になる。これを、これからの生き方としても、研究者としても、目指していきたい。そんなことを考えていた。
しかし、〈目撃者(witness)〉になるということは想像以上に難しい。
誰かが困っているとき、自分はどうしても「大丈夫?」という言葉が口から漏れている。
本当は「大丈夫」でないことなどわかっている。その問いかけに対して、「大丈夫」としか返ってことないこともわかっている。そして「大丈夫」でなくても、自分には何もしてあげられないこともわかっている。
「大丈夫?」という言葉の裏には必ず「—いつでも、あなたの話を聞いてあげたい」「—あなたが望むならば、僕はあなたの声を聞く準備がいつだってできている」そんなメッセージがある。
あるひとは、「大丈夫?」という言葉の代わりに、うまくその場を茶化して本人を笑顔にしようとする。そちらの方が、本人の心の緊張を解くことだってある。ただ、自分にはそれがうまくできない。
いつだってバカ真面目に向き合おうとしてしまう。その真っ直ぐさが、相手をされに息苦しくすることもある。その真っ直ぐさをできるだけ逸らそうとして、相手をもっと窮屈にする。
〈目撃者(witness)〉になるというのは、本当に難しい。
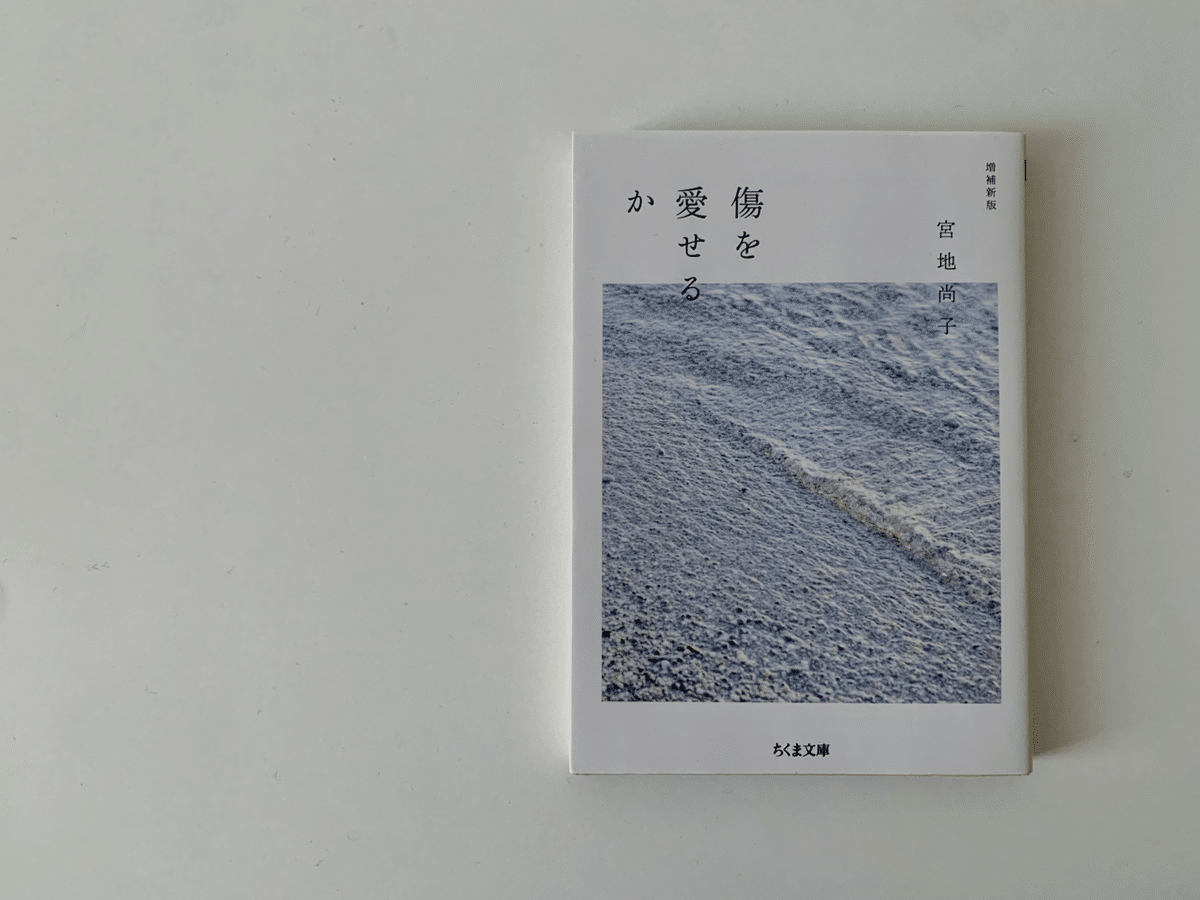
***
昨夜まで読んでいた本に、上間陽子さんの『裸足で逃げる〜沖縄の夜の街の少女たち』という本がある。
沖縄でキャバ嬢として働く、あるいは「援助交際」をしながら生活していた、主に六人の若い女性たちの生活史だ。
教育社会学者である上間さん本人が耳を傾けた彼女たちの声が—ときに筆者本人の声とともに—臨場感を含みつつも、懇切丁寧に紡がれている。
特に好きな章に、「記念写真」というものがある。パートナーの暴行によって、マスクをしても覆い隠せないほどの傷を顔に負った翼。親友の美羽は「大丈夫?」という言葉をかけるのではなく、自分自身も大きなアザのメイクを施し、翼と一緒に「記念写真」を撮り、笑い合う。
「写真は日々の生活の記録だ。だからこれは、翼が暴行を受けた記録であるとともに、美羽がその目撃者となることを引き受けた記録でもあるのだろう。そしてそれは同時に、もう二度となぐられることのない未来が訪れることを、翼に予感させるものにもなったのではないだろうか。」
美羽の〈目撃者(witness)〉の実践に、僕は心を打たれた。美羽は翼に「大丈夫?」とは言わない。その代わり、自分もアザメイクをし、一緒に写真を撮る。相手の痛みを代わりに感じてあげることもできなければ、本人の人生を肩代わりしてあげることもできない。自他の輪郭が融解しようとしているのにも関わらず、自他の境界は常にそこにある。そんなとき、言葉はどこまでも無力だ。
だからこそ、あなたの苦しみも、辿ってきた道も、全て理解できるわけでも肩代わりできるわけでもないけど、見守っているよ、そんなメッセージを—〈目撃者(witness)〉として常に伝えたいと思ってきた。大切な友人が就活の面接前で緊張に押しつぶされていても、昔の教え子が「親に何もわかってもらえない」と夜な夜な連絡をしてきても、フィールドで話を聞かせてくれる子がきょうだいを空爆で亡くしていると知ったときも。
自分はどこまでも不器用で、うまいように〈目撃者(witness)〉になれない。
だからこそ自分はフィールドに飛ぶのかもしれない。
〈目撃者(witness)〉になるために。
〈目撃者(witness)〉になる方法を探るために。
〈目撃者(witness)〉であるために。

***************
いま、自分は空港の搭乗口で飛行機を待っている。もう夜はすっかり暗い。真っ黒な滑走路を、さまざまな光が彩っている。
確かに、書いておきたいことがある。
〈目撃者(witness)〉であろうとするとき、言葉は空虚で、どこまでも無力だ。でも、だからこそ、自分は言葉の力を信じていたい。なぜなら〈目撃〉したことを、確かに残しておくためには、言葉が欠かせないからだ。確かに伝えていくには、言葉が欠かせないからだ。
それが誰にとって、どのような意味を持ち得るかはわからない。
それでも、自分の直感は叫んでいる。
言葉は死なない。
〈あなた〉と〈あなた〉の言葉で話したことは、〈あなた〉と〈わたし〉の中で、確かに生き続けていると。
今回も良き旅になりますように。
〈あなた〉の言葉で一つでも多くの声を拾えますように。
そして無事に帰ってきて、〈あなた〉に出会い直せますように。

