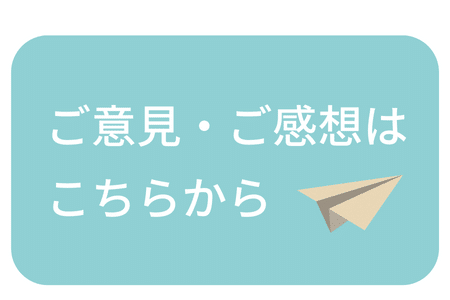大学受験を巡る親子の愛憎が生んだ事件 教育虐待はなぜ起こるのか 「母という呪縛 娘という牢獄」齊藤彩さん(元共同通信記者)インタビュー
2018年3月、琵琶湖の南側に位置する野洲川の河川敷で、手足や頭のない、体幹部だけの遺体が発見された。県警の捜査で身元は近くに住む58歳の女性と判明。死体遺棄容疑で逮捕されたのは、同居する当時31歳の娘だった―。
5年前に滋賀県守山市で起きた「母親殺害・死体遺棄事件」の真相に迫るノンフィクション「母という呪縛 娘という牢獄」が昨年末、講談社から出版されました。
犯行の克明な描写から、大学進学をめぐって対立する母娘の壮絶な日々の記録に至るまで。濃密な取材結果が詰め込まれたこの書籍は、twitter や書評サイトなどで話題を呼び、刊行から2カ月で第5刷に至りました。
2018年に母親を殺害し、遺体をバラバラにし遺棄した罪で逮捕された当時31歳の女性が、記者に自身の半生を語る、斉藤彩『母という呪縛 娘という牢獄』。
— 本屋プラグ🌴📚🍊 (@books_plug) January 16, 2023
異常な学歴信仰とプライドから、自身の期待に沿わない娘に、暴力や罵倒の虐待を続ける母との生活から、結局は誰も彼女を救えなかった事が辛い。 pic.twitter.com/CnKS9N01R7
著者の齊藤彩さんは2021年12月まで共同通信の記者をしていました。実は、大阪社会部でも司法(裁判)担当として活躍していた私たちの元同僚なんです。この事件についても共同通信の深掘り企画「47リポーターズ」として、大阪社会部から記事が配信されています。
そんなご縁にかこつけて、今年1月、都内でインタビューの機会をいただきました。取材の裏側や教育論、メディア論などさまざまな観点から語ってくれた齊藤さん。さらに、大阪社会部の note で取り上げるに当たって、彼女の「もう一つの顔」や共同通信記者の仕事についてもお話を伺いました。
本を読んだ方も、まだ手に取ったことがない方も。ぜひ、この note で著者の素顔とその思いに触れてみてください。(聞き手= note 担当・山本)
※共同通信は守山市の母親殺害・死体遺棄事件の被害者や加害者を実名で報道していますが、この note では「母という呪縛 娘という牢獄」に則って仮名で表記します。
■ 事件の概要

2018年3月10日、土曜日の昼下がり。滋賀県、琵琶湖の南側の野洲川南流河川敷で、両手、両足、頭部のない、体幹部だけの人の遺体が発見された。遺体は激しく腐敗して悪臭を放っており、多数のトンビが群がっているところを、通りかかった住民が目に止めたのである。
滋賀県警守山署が身元の特定にあたったが、遺体の損傷が激しく、捜査は難航した。周辺の聞き込みを進めるうち、最近になってその姿が見えなくなっている女性がいることが判明し、家族とのDNA鑑定から、ようやく身元が判明した―。髙崎妙子、58歳(仮名)。
遺体が発見された河川敷から徒歩数分の一軒家に暮らす女性だった。夫とは20年以上前に別居し、長年にわたって31歳の娘・あかり(仮名)と二人暮らしだった。
さらに異様なことも判明した。娘のあかりは幼少期から学業優秀で中高一貫の進学校に通っていたが、母・妙子に超難関の国立大医学部への進学を強要され、なんと9年にわたって浪人生活を送っていたのだ。結局あかりは医学部には合格せず、看護学科に進学し、4月から看護師となっていた。
6月5日、守山署はあかりを死体遺棄容疑で逮捕する。その後、死体損壊、さらに殺人容疑で逮捕・起訴に踏み切った。一審の大津地裁ではあくまで殺人を否認していたあかりだが、二審の大阪高裁に陳述書を提出し、一転して自らの犯行を認める。
■ 加害者の立場から事件を見る
――そもそも、齊藤さんがこの事件を取材することになったきっかけを教えていただけますか。司法担当として取材していた裁判の一つだったんですか。
そうですね。大阪社会部で裁判を取材していた時に、ルーティンワークとしてチェックしていた高裁事件の一つです。私が最初に取材したのは2020年11月に開かれた二審の初公判でした。
でも、初公判の時はそこまで深く内容を調べていなくて。事件の発生時や一審段階で配信された過去の記事を読んだくらいです。その日、必ず記事を書くという心構えもなく「ちょっと見に行こうかな」というくらいのテンションで傍聴に行きました。

あかりさんは一審では否認していたので、二審でもてっきり否認するんだろうと思って見ていたのですが、証言台に立った彼女は、いきなり母親殺害を認め始めたんです。そこで私も「え?」ってなって。「なんで急に否認から認めに変わったんだろう?」と思ったんです。最初は、そんな風に態度を一変させた理由に興味を持ちました。
――その後、母娘2人の半生を掘り起こすほど深く取材することになったわけですが、そこには何か特別な理由があったんですか。
この事件を掘り下げようと思った理由は二つありました。一つ目は私自身の事件取材に対する考え方がベースになっています。それまでも、いろんな事件を取材していたんですが、どちらかと言えば被害者側に話を聞く機会が多かったんですね。
もちろん被害者のお話を伺うことも大事です。でも「事件を防ぐためにはどうすれば良いか」を突き詰めて考えると、「何が人を加害者たらしめるのか」っていう原因にもっと迫る必要があると思ったんです。その原因を調べることが、ひいては再発防止や教訓を得ることにつながるだろうと。
そういう視点で考えた時、自身の罪に向き合い、胸の内にあった思いを切々と語るようになったあかりさんには、ぜひ話を聞きたいなと思いました。彼女の話を聞くことが、加害者の視点に立って事件と向き合うきっかけになるだろうと。それが一つ目の理由ですね。
二つ目はもっと個人的なことなんですけど、私自身にもあかりさんと似たような経験があったんです。彼女の家庭ほどではないんですが、私が育った家庭も結構、母親の声が大きくて。私自身かなり悩んだ時期がありました。だから取材をしているうちに「教育を巡る親子の確執というのは、わりと普遍的な問題なんじゃないか」という仮説を思い付いたんです。
この事件を深く取材して記事を書き、読者の反響を確かめ、仮説を検証してみたいと考えるようになったこと。それが二つ目の理由です。
■ 自分自身の体験から

――家庭環境に似た部分があったということですが、具体的には彼女が置かれた境遇のどんな部分に共感したんでしょう。
端的に言うと、母親の期待と娘の意思が一致しないっていう状況ですね。特に「母親の声が大きくなる」っていうのは、すごく重要な部分だと思っています。子どもって親に経済的な基盤を握られているわけじゃないですか。すごく弱い立場なんですよ。
さらに、子どもの方は、自分の希望とは違う進路を親に押し付けられたとしても「それもまた親の愛情なんだな」と考えてしまうことがある。「親の思いも受け入れなきゃ」っていう気持ちが心のどこかに芽生えてしまう。だからむげに断ったり、反抗したりできなくなってしまうんですよね。そこがこの問題の難しいところだと思います。
――齊藤さんのご家庭でも、問題になったのは教育とか進学のことですか。
はい、大学進学です。その点もあかりさんと似ていますね。
――なるほど。ちなみに齊藤さんの場合は、お母さんの希望とどういう風に折り合いをつけたんですか。
私は結局、母親の要求を満たしつつ、自分も一番ストレスのない環境を選ぶことにしました。要するに家を出たんです。母親の求める一定水準以上の要件を満たす大学の中で、東京の実家からは通えない場所。実家から出て行かざるを得ないところ、ということで北海道大学を選びました。
――私も中学、高校時代は母親と二人暮らしだったので、なんとなく分かる気がします。親と子の近すぎる距離感が、かえって確執を深め、相手への悪感情を高めてしまうんですかね。
そうですね。これが例えば職場なら、定期的な人事異動によって改善される可能性がありますよね。上司が部下にパワハラをしたとか、このペアはうまくいかないっていう問題があったとしても、人が入れ替われば状況は変わっていく。でも、家庭の場合はそういう人の入れ替わりがない。良くも悪くも家庭は替えがきかないんです。
だから一つの手段として、親元から離れることと、その前提として自分で経済基盤を持つということは大事だと思います。私も大学時代の生活費はアルバイトをして自分で稼ぎました。
成人すれば、アパートを借りたり、仕事をさがしたり、自立するためのいろいろな手続きが自分でできるようになります。親と折り合いが付かず、強いストレスを感じる極限状態が続くのであれば、そういう手段も選択肢に入れて良いと思います。
■ 声を上げられない人たち

――齊藤さんはこの事件について、共同通信に在籍していた2021年3月に1本の長いネット記事を出しました。公開直後からPVが急伸し、記事には数多くのコメントが寄せられましたが、この反響についてはどう思いましたか。
予想以上でしたね。PVもある程度は伸びるだろうと思っていましたが、ここまで大きな話題になるとは思いませんでした。驚いたのは、他のメディアもこの問題を頻繁に取り上げるようになったことです。やはり、かなり関心の高いテーマなんだなと感じました。
あと、記事に寄せられたコメントなどを読んでいて思ったのですが、この問題は当事者の立場から声を上げることがすごく難しいんですよね。一般的には衣食住が満たされた環境で教育を受けられるのは幸せなことだっていう風に言われますし、日本には道徳的思想や儒教文化があるから「親孝行をせよ」っていう価値観も根強い。
そういう社会の空気、風潮の中では、本当は親の過剰な期待や干渉に苦しんでいても、なかなか声を上げられない人がたくさんいるんだなと改めて認識しました。
――寄せられた意見や読者のコメントの中で、特に印象的なものはありましたか。
これは2年前の記事ではなく、今回の書籍を出した後に読者や友人から教えてもらったことなんですが、韓国でも10年前ぐらいに同じような事件があったんですね。韓国は日本よりさらに「親を敬うべきだ」という価値観が強いと言われますけど、そんな社会の中で学歴偏重の教育に耐えられず、親を殺してしまう。加害者側にとっても相当なストレスがあったんだろうと思います。
韓国の事件について知ったことで、これは日本だけの問題ではないんだなと考えるようになりました。他の国にも通じる問題なんだと。そこはちょっと視野が広がったように感じます。
■ 手紙で届いた159枚の原稿用紙
――今回の書籍を出すにあたっては、相当な追加取材をしていますよね。その作業はどういう風に進められたんでしょう。
一番重要なのはあかりさんへの取材ですよね。彼女は刑務所にいるので、基本的には手紙の文通という形でやり取りしました。面会も何度かトライしたんですけど、親族とかごく限られた関係者以外は許可されないんです。判決が確定する前、拘置所にいた時には何度か面会できたんですが、刑務所では窓口で門前払いになっちゃうんですよ。だから収監された後の取材は全て文通です。

書籍化に当たっては、最初におおまかな本の構成や章立てを考えました。その構成にしたがって、各章を執筆する上で必要な要素を検討し、質問項目を練るんです。だいたい1章当たり20個くらいの質問を作ったと思います。それを月に1回か2回、手紙にまとめて送る、ということを繰り返しました。
彼女から返ってくる手紙には書籍の中で引用した「原稿」に当たる部分と、私に宛てた「私信」とがあるんですが、私信に当たる分を除いても、届いた手紙は400字詰めの原稿用紙で159枚ありました。
文通作業と並行する形で、私は彼女以外のソース(情報源)にも当たって、事実関係を検証しました。その過程で、時には彼女からは聞いたことのない、全く知らなかった事実が出てくることもあります。そういう部分は、また改めて手紙で質問を送り、回答を原稿に盛り込んでいくわけです。結果的に、最終的な構成は当初案から結構変わったんじゃないかと思います。
■ 加害者も地続きの世界に
――159枚というのはすごい分量ですね。かなり濃密なやり取りがあったんだと思いますが、齊藤さんから見ると彼女はどういう人物なんでしょう。
あかりさんについて思うことは二つあります。一つは内省的で文章を書くのがうまい人、自分の思考を的確に言葉にできる人というイメージです。もう一つは「感性」というか、物事の捉え方が私の身の回りにいる人たちと地続きなところがあるなと。そんな印象を持ちました。
誰かを殺めた人っていうのは、もちろん許されない罪を犯しているわけですが、そのせいで「ちょっとこの人はヤバい人なんじゃないか」とか、市井の人とは違う世界にいる、異なる感性を持った人なんじゃないかっていう風に思われがちじゃないですか。
でも、少なくともあかりさんについて言えば、何かを見て、何かを感じ、考えることは私たちとあまり違わない。決して別世界の住人ではなく、私たちとつながった世界にいるように感じました。

――最初に伺った質問で「加害者側の取材に取り組みたかった」というお話がありましたけど、実際に取材してみてどうでしたか。考え方が変わったり、何か分かったりしたことはありますか。
そうですね。やっぱり加害者を加害者たらしめる背景や構造というものがあって、それがより見えてくるなっていう感覚はありました。罪を犯してしまうのは、個人の自己責任だけじゃなくて、やっぱり何かしら社会に歪みがあるからだと。
この事件について言えば、経済や社会の影響もかなり大きいと思います。亡くなったお母さんに取材することはできないので断定はできませんが、母娘2人が生まれ育った時代背景の違いも、事件が起きた一つの要因になっていたように感じます。
お母さんが生まれたのはまだ「戦後」と言われた時代。これに対して、あかりさんが生まれたのは1986年です。ちょうどバブル経済に差しかかった頃で、男女雇用機会均等法などが施行された年なんですね。2人が生まれ育った時代を比べると、お母さんが育ってきた環境より、あかりさんが育った環境の方が経済的に豊かで、女性が活躍するチャンスも広がっていたと思います。
そういう時代や社会の変化に、人が本能的に持つ子どもへの愛情が重なると、親は「子どもに良い思いをしてほしい」「幸せになってほしい」と考え、子どもにどんどん投資したくなる。結果的に、その期待が過剰で相手を苦しめることになったとしても、です。そんな構図が、あかりさんに限らず、親との確執で苦しむ人を量産してしまった一つの要因なんじゃないかと思います。
■ 読者には自由な発想をしてほしい
――なるほど、確かにそういった時代背景が影響しているのかもしれないですね。教育を巡る親子関係の問題は、多くの方が関心を持っていると思いますが、齊藤さん自身は今、この本をどんな人に読んでほしいと考えていますか。
原稿を書いている時は、子育て中の母親とその子どもたちに読んでほしいなと思っていました。母親に対しては「もっと子どもの声に耳を傾けてあげて」ということを、子どもたちには「同じように苦しんでる人は、他にもいるんだよ」ということを伝えたかったんですね。
でも、実際に本を出してからは、考え方がずいぶん変わりました。今は「誰に何を伝えたい、感じてほしい」っていう思いはほとんどありません。
どういうことかと言うと、出版後、本当にいろんな反響をいただいたんですよ。もちろん、想定していた読者層からの反応もあるんですけど、それ以外の年齢層の方からも、たくさんの感想をもらいました。中には、著者である私の想像を超える解釈や考察をしてくれる方もいて、私の方がむしろ学ばせていただいているような状況です。
そういう体験を重ねるうちに、読む人にどう思ってほしいかという希望を持つのは、なんだかすごく失礼なことなんじゃないか、みたいなことを考えるようになりました。だから今は、本を読んでくれた人にはそれぞれの受け止め方で、自由に発想していただきたいと思っています。
■ 知られざる「もう一つの顔」
――ありがとうございます。今回の書籍やその取材過程についてのインタビューはこれで終わり…なんですが、最後に少しだけ、共同通信について、お話を伺ってもよいですか?
もちろんです。ご協力できることであれば、何なりと。
――単刀直入に伺いますけど、なんで共同通信を辞めたんですか?
それですよね(笑)。まあ、やりたいことが他にもあったのでやめました、ということに尽きます。
――やりたいこと…とは?
これも二つあるんですよ。一つはもっとネットのゾーンでメディアをやってみたいと思うようになった、ということです。

共同通信は他のメディア向けに記事を配信するBtoBサービスがメインの会社ですよね。配信した記事は加盟社が使ってくれますし、多くの場合は何らかの媒体に載っています。それは事実です。
一方で、なんて言うか、その媒体に載った記事が読者に届いているのかというと、なかなか手応えがない感じがして。コメントや反響をダイレクトに受け取ることが少ないので、記者としては実感に乏しいんですよね。加盟社が記事を使ってくれるのはありがたいことなんですけど、もう少し読者にダイレクトに情報を届けるような仕事をしたいという思いがありました。これが一つ目です。
――なるほど。そしてもう一つの理由は…「ラクロス」ですよね?
そうですね。今は社会人クラブチームに所属しています。学生時代から続けているのですが、ここ数年で改めて「やりたかったことにもう一度向き合おう」と考えるようになり、共同を辞めました。もっとラクロスができる環境を作りたいと思ったんですね。
――やっぱり共同通信で働きながら選手を続けるのは難しかったということですか?
うーん、会社の体制っていうより私の問題なんですけどね。ラクロスって基本的に土日の活動が多いんですが、新卒で共同に入った時は、土日にラクロスに打ち込むということは想定してなかったんです。記者は土日も仕事が入ることがあるので、私もそのつもりで入社しました。
そのつもりだったんですけど、社会人1年目の時に日本代表候補の活動に招集されたんです。残念ながら途中から仕事で行けなくなってしまったんですが…。その頃から「私もまだまだ選手として上を目指せるんだな」って思うようになり、さらに練習を積み重ねる中で「もう1度腰を据えてラクロスをやろう」と決めた感じです。
■ 予期せぬ関心との巡り合い

――そういう思いがあるということは知っていましたけど、改めて聞くと本当にすごいバイタリティーですね。ぜひ頑張って下さい! あと一つだけ、この note を読んでくれている方には、メディア志望の学生もいるので伺いたいのですが「共同通信の記者をやってて良かったなぁ」と思うことってありますか?もしあれば、教えてください。
ありますよ。やっぱり組織に所属して取材するっていうのはめちゃくちゃメリットがあります。一つは十分なリソースを使えるということですね。時間と費用は確保されているので、そこにやりたいという意志さえあれば、何でも取材できる環境があると思います。共同のデスク、少なくとも私が関わった方からは「記事を出すな」と言われたことはなかったですし、本当に取材しやすい環境でした。
もう一つは予期せぬ自分の関心に巡り合う時があるっていうことです。良くも悪くも、若手のうちって自分の意志とは関係なく担当する取材分野が決まっていくところがあるじゃないですか。
私は大学時代、理学部だったので、科学部の記者になりたいと思って共同に入社したんです。でも、初任地の新潟では主に事件と裁判、2カ所目の大阪でも裁判をやることになりました。入社当初にやりたいと思っていた取材って実は1ミリもやってないんですよ。
それでも、いざやってみたら事件も裁判も意外と熱中できるし、面白いなと思う瞬間がたくさんありました。そういう体験は、共同にいたからこそできたんだと思います。
――本当ですか?この際なので、本音を言ってもらっても良いんですけど…。
いやいや、本当に。これはマジです。それこそ5年前、入社するまではこんなに事件を掘り下げて取材して、本を出すことになるなんて全く考えていなかったので。そういう機会を得られたことについては共同通信に感謝しています。これは本当に、本当です!
■ 取材後記
私が齊藤さんの記者時代を振り返る時、真っ先に思い出す場面があります。それは、今回の事件に関するネット記事が公開される少し前のこと。
職場で夜勤シフトに入っていた私が、深夜、宿直室のあるフロアを歩いていると、作業机が並ぶスペースの隅っこで、齊藤さんが一人、頭を抱えるようにしてパソコンに向き合っていました。
若い記者がこんな時間まで仕事をしているなんて。「もう帰った方が良いよ」と促すか。「何の仕事をしてるの?」と水を向けるか。少し逡巡しましたが、彼女の鬼気迫る表情を見た私は、結局「おつかれさま」としか声を掛けることができませんでした。
しばらくたってから、ネットで公開された5000字を超える長文記事を読み、「ああ、これを書いていたのか」と一人で納得したことをよく覚えています。あの時に垣間見た集中力や取材への熱意が、今回の書籍に結実しているんだろうと思います。
あれも、これも、ラクロスも。色々あってお忙しそうですが、ご活躍を祈念しております。ときどき、共同通信にも遊びに来てください!(山本)

齊藤 彩(さいとう・あや) 1995年生まれ、東京都出身。2018年、共同通信社入社。大阪社会部で司法担当をしていた2021年3月に守山市の母親殺害事件に関する記事を執筆し、ネット上で大きな反響を呼ぶ。21年末に退社。その後もこの事件の取材を継続し、22年12月に「母という呪縛 娘という牢獄」(講談社)を上梓。
< 皆さんのご意見、ご感想を是非お聞かせ下さい >