
国際語の英語と日本の国際化
神奈川大学外国語学部英語英文学科です。学科の先生によるコラムマガジン「Professors' Showcase」。今回は英語教育学が専門の髙橋一幸先生による「国際語の英語と日本の国際化」です!

1.英語は 「国際語」?
英語は「国際語(international language)」「世界共通語(lingua franca)※」と呼ばれています。英語を話す人の数はどのくらいなのでしょうか。英語を教える教師としては知っておくべきことですね。
※lingua franca:イタリア語を借用した英語表現で「フランク族の言語」の意味。これはイタリア語、フランス語、ギリシャ語、スペイン語、アラビア語、トルコ語などからなる混成語で17世紀~18世紀頃に地中海沿岸地域の交易の共通語として機能したため、一般に「共通語」を指す呼称となった。
① 英語を母語として用いる話者の数は?(Ethnologue 2020 のデータによる)
次は「母語話者数の多い言語のBEST 10」(1億人超)です。
1位:中国語(12.84億人)、2位:スペイン語(4.37億人)、3位:英語(3.72億人)、4位:アラビア語(2.95億人)、5位:ヒンディー語(2.60億人)、6位:ベンガル語(バングラデッシュなど2.42億人)、7位:ポルトガル語(2.19億人)、8位:ロシア語(1.54億人)、9位:日本語(1.28億人)、10位:ラーンダー語(パキスタンなど1.19億人)、
世界にはおよそ7,000の言語があると言われていますが、母語話者数が1億人を超える言語は上記の10言語にすぎず、大多数の言語が消滅の危機にあると言われています。母語話者の多い言語ベスト3は、上記の通り中国語、スペイン語、英語で、英語はここ20年ほどの間にスペイン語に抜かれて2位から3位に後退しました。世界の人口を約70億人とすると、英語は4億人弱と母語話者数では5.7%程度で、必ずしも突出した割合ではありません。次に、母語話者数以外に国際的影響力を持つ要因である非母語話者数を見てみましょう。
② 英語を第二言語、または外国語として用いる非母語話者の数は?
こうなると大きく数字は変わってきます。歴史的な経緯から英語を第二言語の公用語(ESL)として使っているインドやフィリピンなどの国々、日本のように教育として重要な外国語(EFL)として学ばれている国々の人数(およそ中級程度の能力を有する人)を概算すると約12億人となります。英語を第二言語とする国々には人口増加国が多いため、今後の英語非母語話者数の更なる増加が見込まれます。
▶ ①+②を合計すると ?!
母語話者数と非母語話者数を言語の国際的影響力を示す指標として合計すると、英語は約16億人の話者(世界人口のおよそ4人に1人)を擁することになり、中国語やスペイン語を抜いて世界第1位に躍り出ることになります。②の最後に述べた、今後の英語非母語話者数の更なる増加が続けば、英語話者が将来、世界人口の2~3人に1人に達する可能性もありそうです。ちなみに神奈川大学外国語学部の3学科は、英語・中国語・スペイン語の「世界3大言語」です。
2.日本の 「国際化」 ?! ―真のグローバル化に必要なこと
日本政府は、2020年度に予定されていた東京オリンピック・パラリンピックの開催を機に、わが国の「グローバル化」を進めるために、国際語である英語の運用能力を高めるべく「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」(2013年12月)を発表しました。同計画に基づいて、小学校英語の教科化を含め「小・中・高を通じて一貫した学習到達目標を設定することにより、英語によるコミュニケーション能力を確実に養う」新教育課程を実施しました。また、「グローバル化に対応した英語教育改革の五つの提言」(2014年9月)では、改革を要する背景として、「グローバル化の進展の中で国際共通語としての英語力向上は日本の将来にとって極めて重要であり、アジアの中でトップクラスの英語力をめざすべき」であると述べています。
英語でのコミュニケーション能力向上は国際経済競争に勝ち抜く上でのビジネス上の理由から国益に叶うという政治判断は、理解はできます。「理解はできる」と敢えて書いたのは、すべての児童・生徒の公教育を担う学校は、国際的大企業の人材育成所ではないと考えるからです。学校教育の立場からは、外国語教育は、子ども達にもうひとつの眼を与える「異文化理解教育」であり、その究極の目的は、言葉によるコミュニケーションで平和的に物事を解決する「異文化共生」にあります。この意味で、外国語教育は、同じ日本人同士も含めて互いの違いを認め、尊重し学び合おうとする態度を育てる「人権教育」であり、広くは「平和教育」でもあります。
しかし、これらはどちらも我々日本人を中心に置いた考え方で、「グローバル化」には相手のことを考える視座が不可欠です。近年、学校現場では、「外国につながる子ども達」にどう対応し指導していくのかが大きな課題となっています。日本は少子化による人口減と働き手の減少による税収減で社会保障制度の存続が危ぶまれています。この解決策のひとつとして、日本国政府は労働力として積極的な外国人労働者の受け入れを進めています。コンビニのレジや飲食店などでも外国人の店員さんが一生懸命働いている姿をよく見かけるようになりました。これら外国人労働者が独身の一時的労働者なら問題はありませんが、子どもを伴って来日されている方も少なくありません。このような児童・生徒の中には、日本語が理解できず、さらに英語でのコミュニケーションも十分できない子ども達も多数存在します。私の友人の中にも、日本語も英語も分からずスペイン語しか話せない生徒と保護者への対応を、「英語教師だから」という理由で、担任として指導するよう任された中学校教師もいます。このN先生は、NHKのスペイン語講座を聴いて学び、何とか意思疎通できるようになったそうですが、大変な負担とご苦労であったと思います。
2024年11月22日(金) 5限の教職課程4年生必修科目の「教職実践演習」では、横浜市の日本語支援拠点施設「ひまわり」の金澤真澄先生をお招きして特別講義を伺いました。外国籍や外国につながる子ども達の数は、年を追って増加し、2024年現在は、外国籍の子ども5,353人、外国につながる子ども6,629人の計11,982人が横浜市内に居住しているそうです。外国籍で突出して多いのは中国・台湾の3,247人、次いでフィリピン415人、ベトナム281人、韓国・朝鮮229人と続き、これらの国を含み、ネパール、ペルー、インド、米国、インドネシアの10の国籍の児童・生徒がいるそうです。
「ひまわり」では、日本語でのコミュニケーションに困難を抱えている児童・生徒が「日常的なtopicsについて理解し、学校生活に適応し授業にある程度参加できる」ことをめざして、小学校1~3年生の「はな組」、4~6年生の「みどり組」、中学生の「そら組」を設け、日本語指導、教科指導、生活適応指導等が行われています。免許を持った教員が授業への適応指導を行う「プレクラス」は、水・木・金の週3日間4週間コースで、この間、月・火は学校に登校するそうです。また、小中学校には、このような子どもたちを指導するための「国際理解教室」が設置され、児童・生徒数に応じて担当教員が配置されています。教室数は年々増加し、2024年度現在、横浜市立小学校338校中190校(56%)に、中学校は147校中52校(35%)に、これらの子どもたちを支援・指導する「国際理解教室」が設置されています。指導する教員は、横浜市ではこれらの子ども達5人に1人ですが、全国平均は18人に1人だそうです。
横浜市の取り組みは素晴らしく、このような自治体の行政としての取り組みは重要ですが、それには当然予算措置を伴う人員配当が必要なため、すべての市町村が十分なサポート体制を取れるわけではありません。また、N先生のような学校の教職員の努力、たとえ言葉が通じなくても当該の子ども達を見守り、寄り添う指導も尊いものです。しかし、外国人労働者を国の政策として積極的に受け入れるならば、その人々と共に必ずしも自ら望んで来日した訳でもない子ども達が、日本で生活し、学校の授業にも適応できる日本語指導と日本の文化や習慣の指導、さらに、それらの子ども達の母語と自文化という「アイデンティティ」を保ち守ってあげる支援を与えることは、本来、国の責任です。それができてこそ、真の「グローバル国家」と胸を張れるのではないでしょうか。外国人青年の非行や犯罪も単に彼らだけにその責めを負わせられぬ面もあると思います。以上、金澤先生のお話を伺って感じたことです。
<参考・引用文献>
金澤真澄(2024)「外国につながる子どもたち」(「教職実践演習」特別講義資料)
髙橋一幸(2021:16-19)『改訂版・授業づくりと改善の視点』(第1章, 3.(5) 「Key Number 「3」 のルーツを探る」)教育出版
髙橋一幸(2025)「Swan, M. (1984) Basic English Usage. 語法・文法研究ノート改訂増補版」(Swan解説レポート)神奈川大学・髙橋ゼミ「教職基礎研究」資料
堀田隆一 (2011:12-19)『英語史で解きほぐす英語の誤解―納得して英語を学ぶために』中央大学出版部
※本稿は、2025年1月発行の髙橋ゼミ誌『英語教師入門(2024年度・第26号)』の巻頭コラムに掲載したものです。
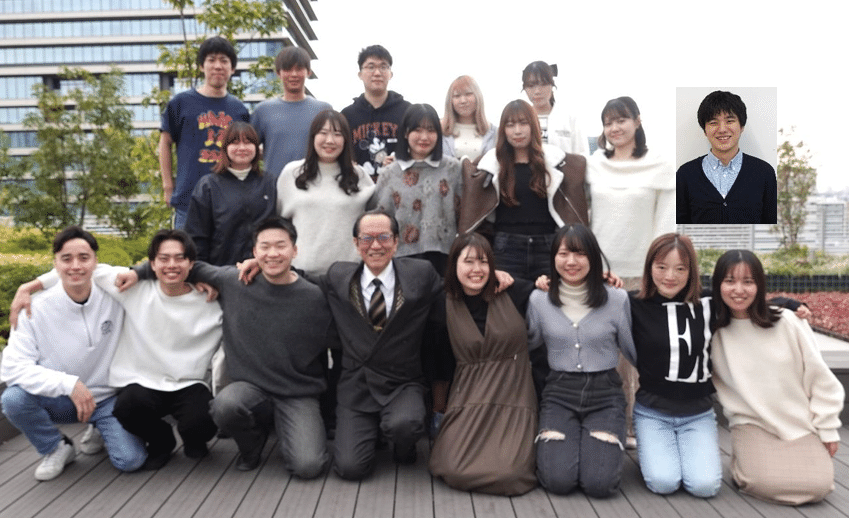
記 髙橋一幸
髙橋先生についてもっと知りたい方はこちらから!
髙橋ゼミについてはこちらから!
英語教員養成特修ゼミナール 2023年度 卒業論文発表会&神奈川大学英語教育講演会はこちらから!
