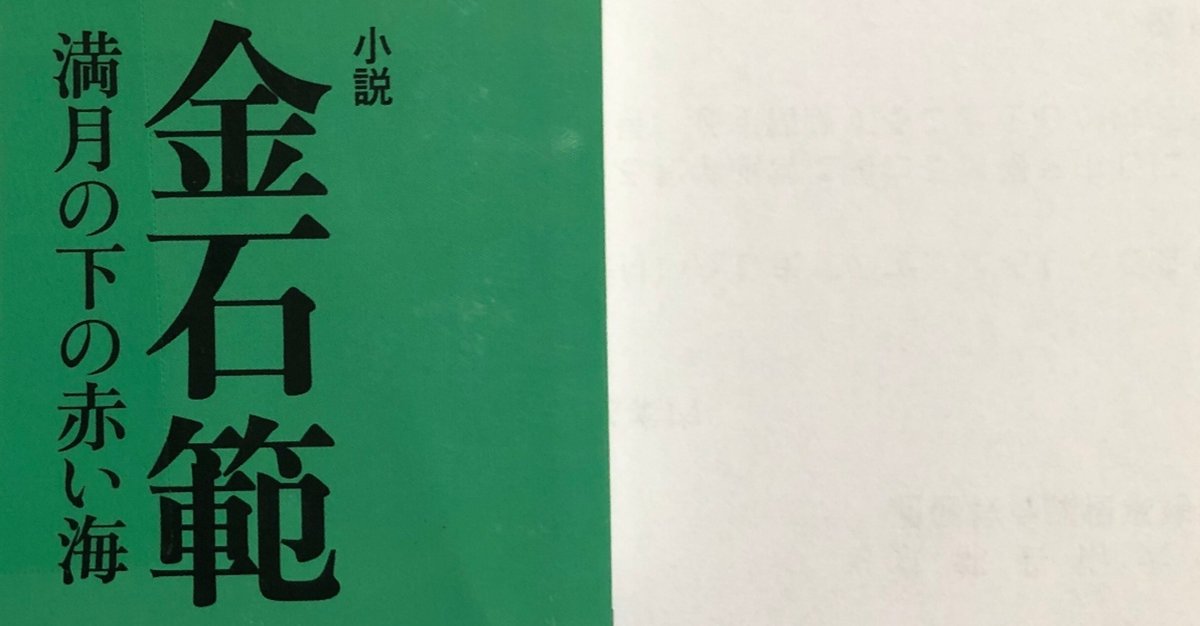
金石範『満月の下の赤い海』「すばる」2020年7月号
大阪で生まれたものの、ルーツは済州島あった。しかしほんの少し済州島にしかいることができなかった。そして渡日後、入れ替わるように四・三事件が起きた。以降金石範は事件にたいして、単なる糾弾だけでなく、贖罪の気持ちもあり、「鴉の死」「火山島」など、この事件をモチーフにした作品を書き続けてきた。
事件は時代とともに風化したり、逆にそこにいた人々とは違った意味合いが、歴史として残ってしまうことにある。
さらにこうした事件を語るということ自体が困難である。恐ろしい記憶、ゆえにその殆どは思い出したくない記憶であるだろうから、それを語るということはとてつもない困難があるだろう。
金石範はさらに、事件のときにそこにいなかったため、語り部としての正当なる権利が果たしてあるのかどうか自問自答することになるのだから、もう一つ困難があることになる。
しかし単なる歴史家ではいられない。だからこそ金石範は書き続けてきたのだろう。
韓国と日本の関係、半島と済州島の関係。少なくともこの二重の関係は事件の前からあり、事件のあとにもあった。金石範が生まれた大阪にもこの関係が大きな影を落とした。そこには他の在日コリアンとは同列には語れないものがあったのだろうか。私はそのことについての知識はあまりにも不足している。
ただ金石範が四・三事件について書くということは、忘れ去ってしまったものを書き記すということではなくて、覆い隠そうとすることに抵抗するということである。
ところでこの作品は、事件について語ってきた作品の範疇に入るだろうが、直系ではない。そして事件を振り返るものではなく、事件を書き続けた金石範そのものと、あるいは足跡そのものを振り返るように書いたものと言える。
この抵抗は金石範の上の世代、同世代に対して行われたものであろうことは間違いない。ではあとの世代はどうなのか?
このことが描かれたのがこの作品なのである。そしてすくなくともヨンイという若い世代の人間が、この事件を、あるいは済州島の歴史と文化そして自然すべてを世界史的な視点へと昇華し問い始めようとするところで終わるのである。
歴史を紡ぐということが、意味があるとしたら、それはきっと全ての人類にとって真実を明らかにさせるということであろう。もちろんこれが理念的な可能性にすぎないとしても、それでもなお語りたいと渇望の源泉はそこにあるのだろう。
歴史そのものは必要なものである。何がどんなふうに描かれるかはともかくとして、歴史すなわち記憶が全く欠如した人類があったとしたら、それはもはや人類たりえないだろう。もし何かを考え、何かを行動しようとするときに、全く参照ができない状態、それまでの蓄積がない状態、すなわちそれは原始の状態であろうから。
だから歴史は常に未来のためにあるのだろう。この作品はそのことを端的に示したと言える。
