
社会学者 松村一志さんが読む『英国心霊主義の抬頭』──わたしの仕事と工作舎の本#3
工作舎の本って、どんな人に読まれているんだろう。
どんな役に立っているんだろう。
「わたしの仕事と工作舎の本」第3回の寄稿者は
社会学/科学論 研究者の松村一志さんです。
松村さんの著書『エビデンスの社会学』(青土社刊)は
英国の名探偵シャーロック・ホームズの作家コナン・ドイルが関わった
ある事件の紹介から始まります。
私たちが判断の拠りどころとする確からしさや科学的証拠とは何か?
その概念がどのように成立してきたのか?
松村さんが注目したのは19世紀に大流行した心霊主義と科学の関係でした。
著書の参考文献のひとつとなったジャネット・オッペンハイムの
『英国心霊主義の抬頭』(工作舎刊・品切)についてお書きいただきました。

ジャネット・オッペンハイム=著 和田芳久=訳
A5判上製632頁 定価 本体6,500円+税 1992年 工作舎
*残念ながら品切のため、図書館や古書店でお探しいただければと思います*
ジャネット・オッペンハイム
『英国心霊主義の抬頭——ヴィクトリア・エドワード朝時代の社会精神史』
松村一志
疑似科学を考えるとはどういうことか
疑似科学の歴史には不思議な魅力がある。例えば、19世紀の欧米では、人間や動物の間にも一種の「気」の流れを見出す「動物磁気」や、頭蓋骨の形から性格を読み取る「骨相学」が流行していた。現代人には半ば滑稽にも見えるこれらの発想を真面目に信じていた人々がいたのは、一体なぜなのか。過去の疑似科学はそうした疑問を掻き立てる。
しかし、考えてみると、現代人が「正しい」と思っていることもまた、100年後には「間違い」になるかもしれない。つまり、疑似科学を信じる人々の姿は、私たち自身の姿だとも言える。その意味で、科学と疑似科学の境界線がどこにあるのかという問題は、決して他人事ではない。実際、原発事故や新型コロナウイルス感染症をめぐっては、何が「科学的」であり、何がそうでないのかが切実な問題になってきた。
私の専門である科学論は、科学的知識の性質やその歴史、あるいは科学という営みの特性や科学と社会の関係といった問題を扱う分野だが、疑似科学もまた重要な研究対象の一つである。というのも、疑似科学を考えることは、科学とは何でないのか(あるいは何でないとされてきたのか)を教えてくれるからだ。私自身、科学と疑似科学の境界線がどう変わってきたのかを研究テーマにしている。その一環として、「科学的証拠」の歴史という観点から「心霊主義」も扱ってきた。
とはいえ、ある時期までの私は、霊魂の不死性を信じる「心霊主義」に研究上の関心をほとんど持っていなかった。
その理由の一つは、「心霊主義」が「疑似科学」というよりも、むしろ「オカルト」に見えたからである。「疑似科学」が「科学と似て非なるもの」であるとすれば、「オカルト」には「科学とは似ても似つかないもの」というニュアンスがある。例えば、血液型性格診断は科学的な装いを持つが、霊的体験には科学的な装いがない。だから、「心霊主義」は「疑似科学」ではなく「オカルト」に見えてしまい、あまり関心を持てなかったのだ。
もう一つ、より個人的な理由もある。中高生の頃の私は奇術を趣味にしていた。一口に奇術といっても、カードマジックやコインマジックなど様々なタイプに分かれるが、その一つにメンタルマジックと呼ばれるジャンルがある。メンタルマジックとは、霊能力・超能力風の演出をする奇術のことだ。例えば、「スプーン曲げ」や「念力」あるいは「透視」をイメージしてもらえば良い。もちろん、奇術なのでタネも仕掛けもあるのだが、演出一つで心霊現象や超能力が働いているかのように見せることができる。実際、奇術の歴史の本を紐解くと、そこには「心霊主義」で用いられたトリックがしばしば登場する。だから、「心霊主義」は単なるトリックだというイメージが強く、科学論の扱うべき対象だとは思えなかった。
科学は「嘘」に対して脆弱なのではないか
そんな考えが変わったのは、大学院の博士課程に入ってしばらくした頃のことである。当時、STAP細胞の問題が注目を集めており、科学と「嘘」の関係が気になってきた。人はしばしば「嘘」をつくが、「嘘」を首尾よく排除できなければ、科学という制度は成り立たない。しかし、ひょっとすると、科学は「嘘」に対して脆弱なのではないか。そもそも科学は「嘘」をどう扱ってきたのだろうか。そんなことを考えているとき、ふと「心霊主義」のことを思い出したのである。
そこで、すぐに手に取った研究の一つが、本書『英国心霊主義の抬頭』だった。19世紀後半には、霊媒を通じて死者との交信を試みる交霊会が大流行し、欧米で「近代心霊主義」と呼ばれる動きが広がっていた。この本は、その英国における展開を描くものだが、それは「心霊主義」に対して持っていた私の先入観を大きく塗り替え、「心霊主義」が研究に値するものであることを教えてくれるものだった。
本書は何よりもまず、英国において「心霊主義」が広がった歴史的背景を明らかにしている。例えば、「心霊主義」と階級の複雑な結びつきや、キリスト教・反キリスト教と「心霊主義」の微妙な関係性が仔細に描き出される(第I部・第II部)。
中でも、強く興味を惹かれたのは、霊媒と奇術師の関係である。今でこそ「奇術」はエンターテインメントの一種になっているが、もともとは超自然的な能力としての「魔術」と区別がつかなかった。ところが、19世紀になると、両者の区別がはっきりしてくる。そのため、心霊現象を引き起こすと称する霊媒と、それをトリックにすぎないと暴露する奇術師との対立関係が存在していたという(第1章)。社会学では、近代における世界像の合理化のことを「脱魔術化」と呼ぶが、超自然的現象をめぐっては、言わば「魔術の脱魔術化」が起きていたのだ。


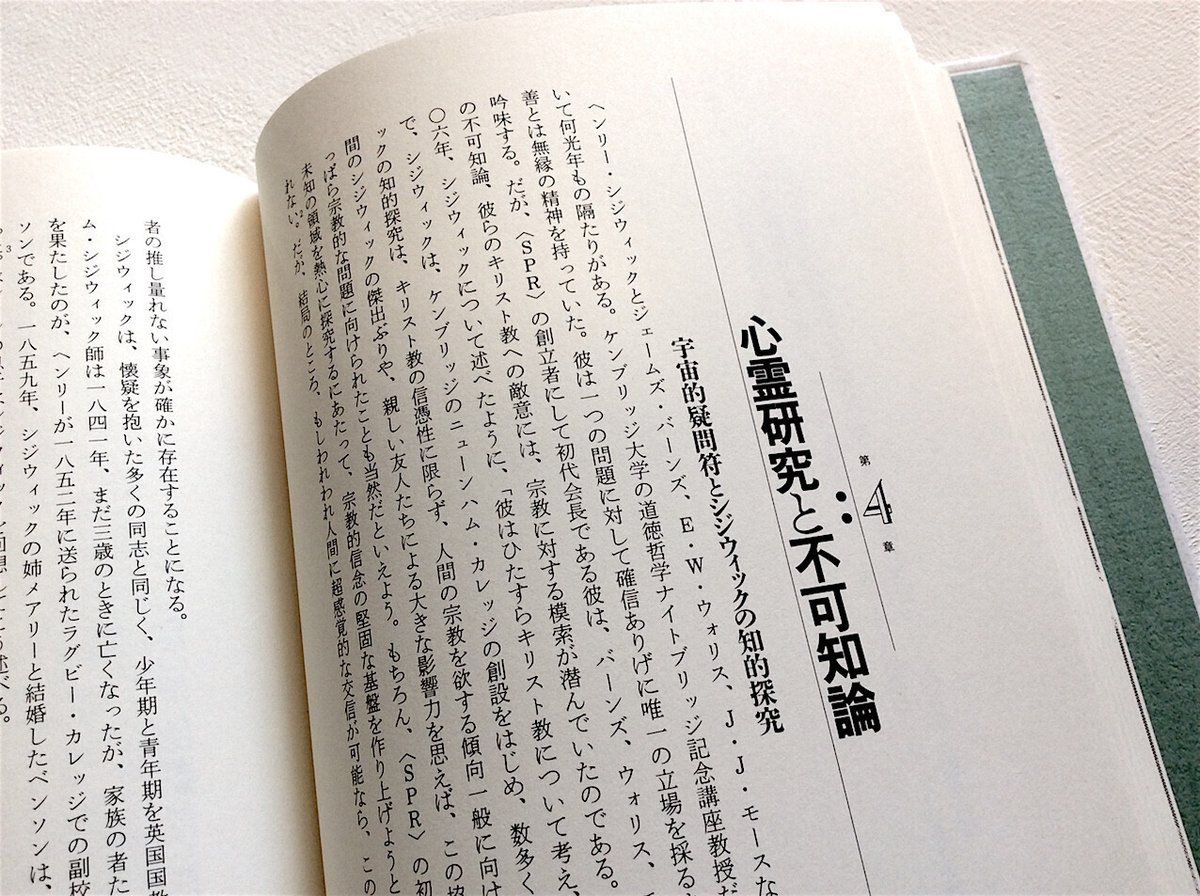
「心霊研究」の歴史は、「嘘」との戦いでもあった
ところで、科学論という観点から重要なのは、「心霊主義」と科学の関係である。原著のタイトルが、THE OTHER WORLD: Spiritualism and Psychical Research in England, 1850-1914であることからもわかるように、本書のテーマは「心霊主義spiritualism」と「心霊研究psychical research」である。「心霊主義」は死者の魂の存続を信じる思想だが、実はその動きの一部(あるいは部分的にそれを踏み越える動き)として、心霊現象を科学的に解明しようとする「心霊研究」が存在していた。心霊現象には、ポルターガイストのような物理的現象もあれば、テレパシーのような精神的現象もある。「心霊研究」はとくに精神的現象を中心に、実験を行ったり、証言を収集したりした。その意味で、「心霊研究」は「オカルト」というよりも「疑似科学」と呼んだ方が良い。
とくに興味深いのは、当時の著名な学者たちが「心霊研究」に取り組んでいたことである。例えば、倫理学者ヘンリー・シジウィック、博物学者アルフレッド・ラッセル・ウォレス、物理学者ウィリアム・クルックス、同じく物理学者のウィリアム・フレッチャー・バレットやオリヴァー・ロッジといった面々が、「心霊研究」に取り組んでいた。ただし、「心霊研究」には固有の困難があった。霊媒がトリックを使っている可能性が拭い去れなかったのである。したがって、「心霊研究」の歴史は「嘘」との戦いでもあった。
そうした曰く付きの領域であるにもかかわらず、著名な学者たちが「心霊研究」に挑戦したのはなぜなのか。本書は、これらの人々の著作や書簡をつぶさに検討しながら、その理由を明らかにしている(第III部)。この点は、ぜひ本書を読んで確かめてもらいたい。おそらく、最初は奇妙に映っていた心霊研究家たちの考えが、「疑似科学」と言って片付けるには複雑な、しかし同時に強固な時代的制約を抱えたものとして立ち現れてくるだろう。そのことは、私たち自身の持つ科学と疑似科学の境界線を、今までよりも繊細な形で見つめ直すことを可能にしてくれるはずだ。
松村一志(まつむら・かずし)
1988年生まれ。専門は社会学・科学論。
東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。現在、成城大学文芸学部マスコミュニケーション学科専任講師。2021年に単著『エビデンスの社会学 証言の消滅と真理の現在』(青土社)を上梓。
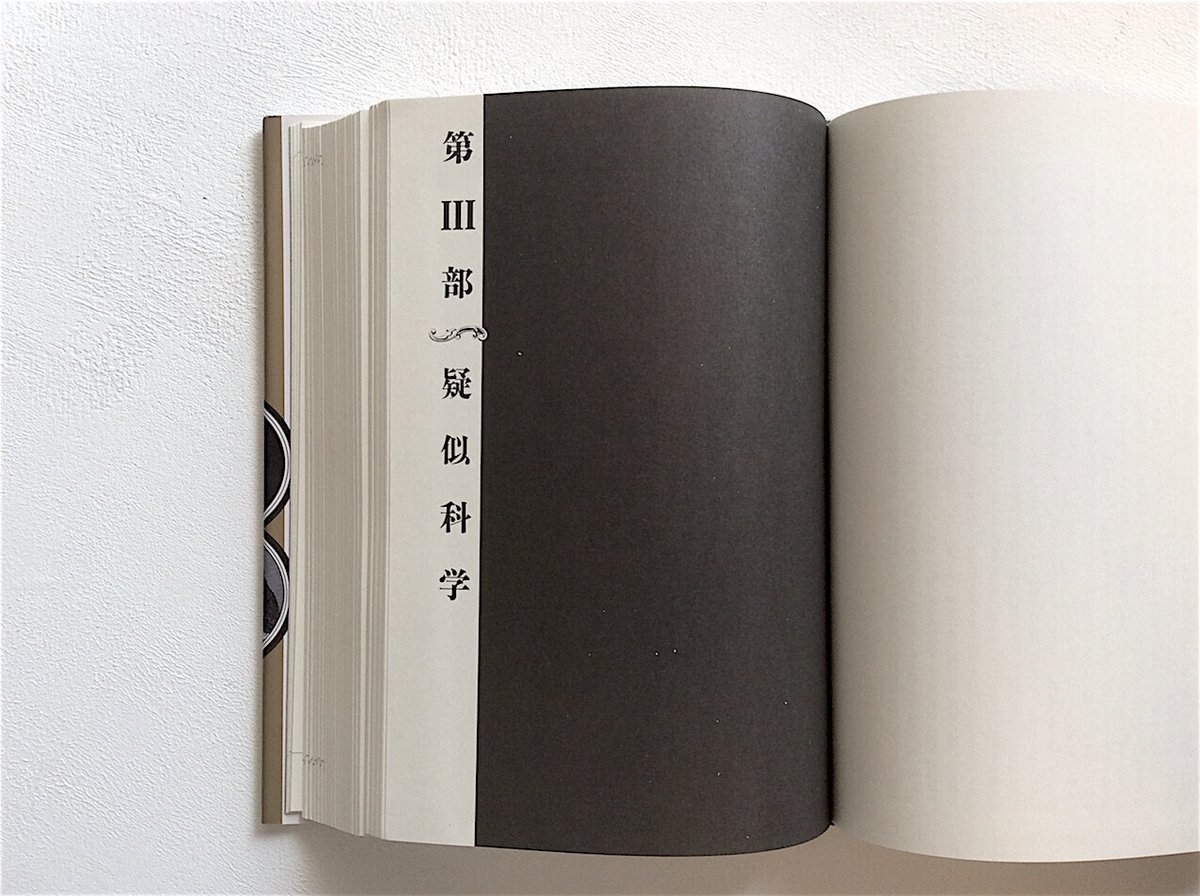
『英国心霊主義の抬頭』について──工作舎より
近代英国精神史を専門とするアメリカの歴史学者ジャネット・オッペンハイムによる『英国心霊主義の抬頭──ヴィクトリア・エドワード朝時代の社会精神史』は、1992年に和田芳久さんの翻訳で工作舎から刊行されました(原著"THE OTHER WOLRD: Spiritualism and Psychical Research in England, 1850-1914"は1985年刊行)。600頁を超える大著で本体価格6,500円のゴツい本です。
残念ながら現在では品切となっており、社内倉庫で見つけた僅少在庫もおかげさまで完売となりました! 図書館や古書店などで見つかることもあるかもしれませんので探してみてくださいね。
さて、ご寄稿くださった松村一志さんも書かれているように、本書には「心霊主義者(spiritualist)」と「心霊研究者(psychical researcher)」という二つの集団が登場します。霊魂の不滅や死者との交信を信じることをためらわなかった心霊主義者に対して、心霊研究者は可能な限り客観的な調査を試み、「科学的態度」をもってのぞんでいたといいます。
『英国心霊主義の抬頭』p.495より
心霊が実際に作用していると主張した科学者たちは、批判者たちの議論を直接に否定することがなかった。彼らは、心霊現象が曖昧で科学の実験室における研究対象として理想的ではないという点では同意した。彼らが否定したのは、心霊現象の性質のために、その現象自体が正当な科学的関心の枠外に置かれているという考えであった。予見可能、測定可能、観察可能、理解可能なものだけが時代の科学の関心の対象となり、世界を理解せんとする科学者の研究において有効な証拠たりうるという考えを拒否したのである。

心霊主義が大流行していた1859年、ダーウィンが『種の起源』を出版し、進化論は多くの生物学者の賛同を得ます。しかしダーウィンと同じく自然選択説を提唱する盟友であったウォレスはやがて超自然的存在を認めるようになり、心霊研究に踏み込んでいきました。ダーウィンはそのようなウォレスを理解しがたいと感じていたようです。
本書には、1874年にダーウィン自身が交霊会に出席したときのエピソードが書かれています。
『英国心霊主義の抬頭』p.369より
理解できず、受け入れることもできない現象に直面しながらも、この霊媒を必要十分に調査するスタミナを欠いていたダーウィンは、自分の右腕ハクスリーにウィリアムズの霊媒能力をテストするよう頼んだ。ハクスリーが一月二十七日に書いたウィリアムズに関する体験の報告を読んで、ダーウィンはほっとした。彼はハクスリーに深く感謝し、安堵を隠せない口調でこう宣言する。「いまや、この現象がペテン以外のなにものかであるということを私に信じさせるためには、莫大な重みの証拠が必要だろう」。
疑わしさを十分に感じながらも自ら判断を下すことはせず、心霊否定論者のハクスリーに「証拠」を提示してもらって安堵するダーウィン。なんだか、エビデンスを求めてやまない私たち自身の姿のようにも思えてきませんか?
松村さんの『エビデンスの社会学』(青土社刊)は理論篇と歴史篇の二つのパートが中心になっています。
理論篇では、実証主義(実在論)に対する相対主義(反-実在論)から生まれた社会構成主義(反-反実在論)、ニクラス・ルーマンの科学システム論、ミシェル・フーコーの真理論などから、科学的証拠を論じるための理論を検討しています。そして後半の歴史篇では、19世紀から20世紀にかけての具体的事例を通して、科学と疑似科学の境界が形成されていく過程を追っていきます。そして最終章は、臨床医療の領域から生まれた「エビデンス」という概念が、科学だけでなく広く社会の中で用いられるようになった現代に当てられています。
人々が拠りどころとする確からしさのレベルや合意のためのルールは、社会制度や科学技術の発達によって変わっていきます。現在、マーケティング分野などを中心にAIが活用されていますが、今後さらに政策立案など高度な意思決定に大きな役割を果たしていくことになるでしょう。AI時代に提示されるエビデンスとはどんなものになるのでしょうか。私たちはそれをどのように検証し、信頼していくのでしょうか。(文責・李)

松村一志さん『エビデンスの社会学』(青土社刊)↓
科学と宗教の関係について関心のある方におすすめ
コペルニクスから現代まで科学と宗教の「互恵的」な精神史を論じたJ・H・ブルック『科学と宗教』(工作舎刊)↓
『英国心霊主義の抬頭』時代のジェンダー観とは?
ヴィクトリア朝時代に形成された性差の科学の系譜を探るシンシア・E・ラセット『女性を捏造した男たち』(工作舎刊)↓
こちらもジェンダーと科学に関心のある方におすすめ
1992年初版から大幅に修正改訂をおこなったロンダ・シービンガー『科学史から消された女性たち 改訂新版』(工作舎刊)↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
