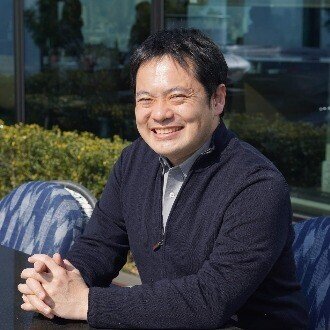習慣・週刊OUTPUT 2020/9/12
先週お休みを頂いていたお陰で、今週は大変充実していました。ですが、だからこそ人にお伝えするために隙間時間を有効活用してインプット及びアウトプットがたくさんありました♪
気持ちを「言葉にできる」魔法のノート
プラトンの言葉「賢者は、話すべきことがあるから口を開く。愚者は、話さずにはいられないから口を開く。」その自分の中にある気持ちを言語化するのにあたって、外に発信すべきなのか?中に留めておくべきなのか?そもそも気持ちを言語化するにはどのようにすればいいのか?トレーニングするドリルのような書籍です。プレゼンテーションをするのに一度は意識するのによいかもです。すぐに読めます。
こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
障害者ボランティアの世界に問題提起を投げかけた作品の映画作品です。書籍データでは、伝わらなかった、現場の葛藤というようなことが上手に描かれています。この映画をみたおかげで、折角の名著も、ボランティア経験がなかったり肢体不自由の方と接点がない人には、上手に伝わらなかった部分があったかもしれないと学びました。ダイバーシティが言われている時代に、介護の葛藤・育児の困難さ等などはこのように映像が強いということ。そしてVRコンテンツによる世の中の教育の改革の可能性等を考えました。
日本を滅ぼす教育論議
OECDで各国の教育政策の比較研究等をしていた著者が、日本だけで信じ込まれている理論や、はたまた勘違いしてしまっている理論、逆に知らないために損してしまっている価値がある理論等を紹介しています。教育議論は、教育を受けた人が全員が専門家になってしまうからこそ、研究ベースでしっかりと議論する必要があると思います。教育論は、子供がいなくても、部下や後輩に教えることがあるので、是非とも直接自分がどのような場面に教育をしているのか?教育を受けているのか?とイメージしながら読むとより価値高く読める作品です。
脳(ブレイン)バンク 精神疾患の謎を解くために
1997年に決定して、2001年に出来た福島県の脳バンクに関することを、研究者から臨床家等多様な立場の方からの寄稿でまとめられた書籍です。19世紀後半にメンタル疾患は脳神経疾患であるということが分かってから、脳からどのようなアプローチで治療にいけるのか?アイバンクや臓器バンクのように、様々な人の脳の提供によって原因が解明されて、新たな治療法がうまれてくる可能性を説明してくれている作品です。
経済界 2020年 09月号 日本の大問題
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?