
共生の時代にも挑戦心を。冒険を愛する教授は、ナタを片手にキャンパスを拓く
いま、日本に何度目かのアウトドアブーム、キャンプブームが訪れています。
このキャンプをアカデミックな視点から考え、発信しているのが、國學院大学のランタントークという試みです。國學院の教授陣が教育、歴史、考古学などそれぞれの専門分野から、縦横無尽にキャンプを語っています。
このnoteは、より広い方々に「キャンプ×アカデミア」のおもしろさに触れてもらうことを意図した、いわば出張版。ランタントークにも登場する教授がもう少し柔らかい語り口で、自身のキャンプ体験なども交えながら話す入門編と位置づけています。
連載1回目では「野外で学ぶことの大切さ」に触れました。2回目の今回登場するのは、野外で学ぶためのフィールドをキャンパス内にみずからつくってしまった男、北海道短期大学部の田中一徳教授です。

國學院大が誇る「北海道の冒険王」は、大学構内にある背丈ほどの草が生い茂る広大な土地に飛び出し、約3年かけて少しずつ野外教育フィールド「アウトドアキャンパス」を開拓。次第に周囲からの協力を得て、この夏からは本格的に授業で使い始めています。田中教授が専門とする「冒険教育」とはどのようなものなのか、詳しく聞きました。
たった一人の非公式活動として始まった

取材はZoomにて行いました
── 田中先生がみずから開拓したという「アウトドアキャンパス」なるものについて教えてください。
大学のキャンパス内にまったく活用されていない、手つかずの自然環境があったんです。
いま、子どもたちにも自然体験や防災教育を施すことが大切だと言われていて、文科省からもそういうお達しがあります。せっかく大学構内に自然環境があるのであれば、それを整備して有効活用すれば、わざわざ遠くまで行かなくても、こうした教育ができるのではないかと考えたのが始まりです。

構想としてはだいぶ前からあったのですが、実際に草刈りを始めたのが3年前。昨年度は新型コロナウイルス感染症対策でオンライン授業が多いため、学生は参加せず、私一人で地道に草刈りを続けてきました。
今年度からは大学のパンフレットにも「アウトドアキャンパス」が掲載され、正式に認められたかたちです。学生やシルバー人材センターの方にも草刈りを手伝っていただけて、いよいよ授業で使える状態になってきました。
── 始めた当初は大学のお墨つきを得た公式の活動ではなかった?
まったく違いますね。いろいろな方に話しましたが、反応は薄めでした。
現時点でもかなり広いのですが、草刈りをすればするほど広げられるので、終わりはありません。いまでは正式に認めてもらえて、バックアップしてもらえるのは非常にありがたいです。

── まだ完成途上とのことですが、「アウトドアキャンパス」ではどのような活動を?
ちょうど7月末に「國短キャンパスアドベンチャープログラム」という企画の中で「ソロキャンプ」をテーマに実習を予定しています(インタビューは7月中旬に行った)。学生が草刈りをして自分のサイトをつくるところから始め、そこに一人でテントやタープを張って、一晩過ごします。
自分が担当している、レクリエーション・インストラクター養成のカリキュラムの一環として、これまでにも、メタルマッチを使った火おこし体験やアルコールストーブづくりなどをやってきました。「ソロキャンプ」の実習は、その集大成という位置づけになります。
── キャンパス内で本格的なキャンプができるなんて、贅沢な環境ですね。
でしょう? こうやって実際に「やってみる」ことの重要性がいま、とても増していると思うんですよ。
Google検索やYouTubeなどで知識や情報を取り入れることはできても、実際にやってみるとうまくできないということがよくあります。焚き火にしてもテントの設営にしてもそうで、情報を知っているだけでうまくできるとは限らない。うまくやるには、ちょっとした知恵やコツが必要です。
そうした知恵やコツは本来、直接体験する中で会得するものですが、いまの子どもたちはバーチャルな体験だけで「知っているつもり」になっている子も多い。デジタルデトックスや非日常を体験できる野外教育は、いまこそ特に重要だと思っているんです。
── 履修しているのは女子学生が中心と聞きました。ソロキャンプはなかなかハードルが高そうにも思うのですが。
大変でしょうが、大変だからこそ学ぶことが多いと言えます。そんななかでも「やり抜く力」や「折れない心」というのは、このソロキャンプ体験を通じて育みたいゴールのひとつです。
さらには、一人でやり抜く体験を通じて、普段いかに人に助けられていたのかを知り、仲間の大切さを実感する機会にしてもらいたいとも思っています。
冒険教育、折れない心、人間の成長

── 先生が専門とする「冒険教育」とはどのようなものか、ご説明いただけますか?
「冒険」と言っても、実際に北極や南極に行って学ぶという話ではありません。冒険教育は、冒険のエッセンスをさまざまなかたちでプログラムや活動に活かした教育を指します。
学校現場においては、たとえば授業で一回も手を挙げたことのない子どもが手を挙げることも、ひとつの「冒険」ですよね。そうやってチャレンジできる環境を整えることで、子どもが一歩踏み出す体験をつくるのが、冒険教育の目的です。
冒険教育のルーツは、イギリスにあると言われています。ドイツ出身の教育者クルト・ハーンが第二次世界大戦中に亡命先のイギリスで開校した、アウトドア活動のための短期スクール「アウトワード・バウンド・スクール(OBS)」がそれです。
OBSはもともと、若い兵士向けに折れない心やチャレンジする気持ちを養う目的でつくられたもの。さまざまな危険の伴う自然のなかでサバイブすることが、強い心を鍛えるのに有効だと考えられたのです。
── なるほど。もともとは強い軍隊を組織するためのものだった。
1970年ごろになると、そのエッセンスを学校教育にも取り入れようという動き「プロジェクト・アドベンチャー」がアメリカで生まれます。これが冒険教育の始まりです。
ちなみに、冒険教育は社会人にも有効と考えられており、企業研修に用いられている例も多いです。私自身、大学教員になる前には「プロジェクト・アドベンチャー」の日本版を運営する会社にも関わっていて、冒険教育のエッセンスを活かした自然体験や研修のプログラム作りをしていました。

── 今回のソロキャンプの授業にも、冒険教育のエッセンスが入っているわけですか?
そうですね。たとえば、キャンプ前には学生に自分で目標を設定させます。場合によっては自分の力を過信して、できないことを「できる」と思って目標にすることもあるでしょう。
そうすると、実際にやってみることで目標と現実の差分が生まれますから、終わった後に「なにができて、なにができなかったのか」「なぜできなかったのか」といったことを自分で振り返るのです。
できなくてもいいんです。まずはチャレンジすることが大事。チャレンジして初めて、自分になにができて、なにができないのかが見えてきます。そうすると次のアクションもおのずと決まる。その繰り返しが人を成長させるのだと思います。
── ということは、先生は「チャレンジのない人生には意味がない」とお考えですか。
いえ、そこは一概には言えないと思っていてですね……。私自身も若いころは挑戦し続ける人生でしたが、最近は挑戦というより順応、共生という感じでして。

たとえば、私は渓流釣りが好きなのですが、釣った渓流魚は基本的にはリリースします。生かし、生かされる関係、最近の言葉だと「持続可能」になるのでしょうが、私自身はいま、そんな感じで北海道で生活しています。
とはいえ、授業などを通じていまの学生と接していると、思うところもありますよ。若いうちはもっとチャレンジする時期もあっていいのではないかと。いきなり共生ではなく、まずはチャレンジなんじゃないか?ってね。
自然と隣り合わせの日常の豊かさ

── 田中先生ご自身は、子どものころから自然と触れ合ってきたんですか?
ボーイスカウトに入っていたので、比較的そうだったと思います。草刈りをして自分たちでキャンプサイトを作り、月に一回キャンプに行ったりしていました。……言っていて気づきましたけど、いまやっていることとそんなに変わらないですね。
大学では部活には入らず、在学中からキャンプ場やキャンププログラムの企画・運営を行う民間企業の「野外計画」でキャンプリーダーやキャンプ場駐在員などをしながら学んでいました。「プロジェクト・アドベンチャー」の活動もそのひとつです。
1990年代後半、日本にも自治体のつくったキャンプ場はたくさんありましたが、とりあえず草を刈っただけという状態で、鳴かず飛ばずのところも多かった。利用者側も、BBQやカレーを食べて終わり。要は、日本のキャンプにはソフトがなかったんです。
その状況を変えたい自治体の要請を受けて、マンハッタンから300kmくらい離れたところにある「フロストバレーYMCA」という超巨大なキャンプ場を視察に行ったり。ハワイ諸島のモロカイ島というフラダンス発祥の地にも、ある会社のオファーで視察に行き、レポートを書きました。
そういう生活がとにかく楽しかったですね。渓流釣りやバックカントリースキーは当時からいまも続く趣味ですが、若いころはより高い山に、より遠くに行きたい感覚がいまより強かったです。
── そういうライフスタイルや価値観が変わったのはなぜでしょう?
ひとつは結婚したことが大きかったと思います。家庭を持ったことで、それまでのように自由に遠くには行けなくなった。ある種の責任や強制力が働いたことにより、身近なものに目を向けるようになりました。
当時は東京の阿佐ケ谷に住んでいたので、遠くの渓流釣りに行けなくなった代わりに、家の近所の釣り堀で鯉釣りをやるようになりました。
正直、「東京の釣り堀なんて」とバカにしていたんですけど、「これはこれでおもしろいカルチャーじゃないか」と思うようになって。ここにも冒険のエッセンスはあるし、ここにしかない居心地の良さがあることにも気づいたんです。
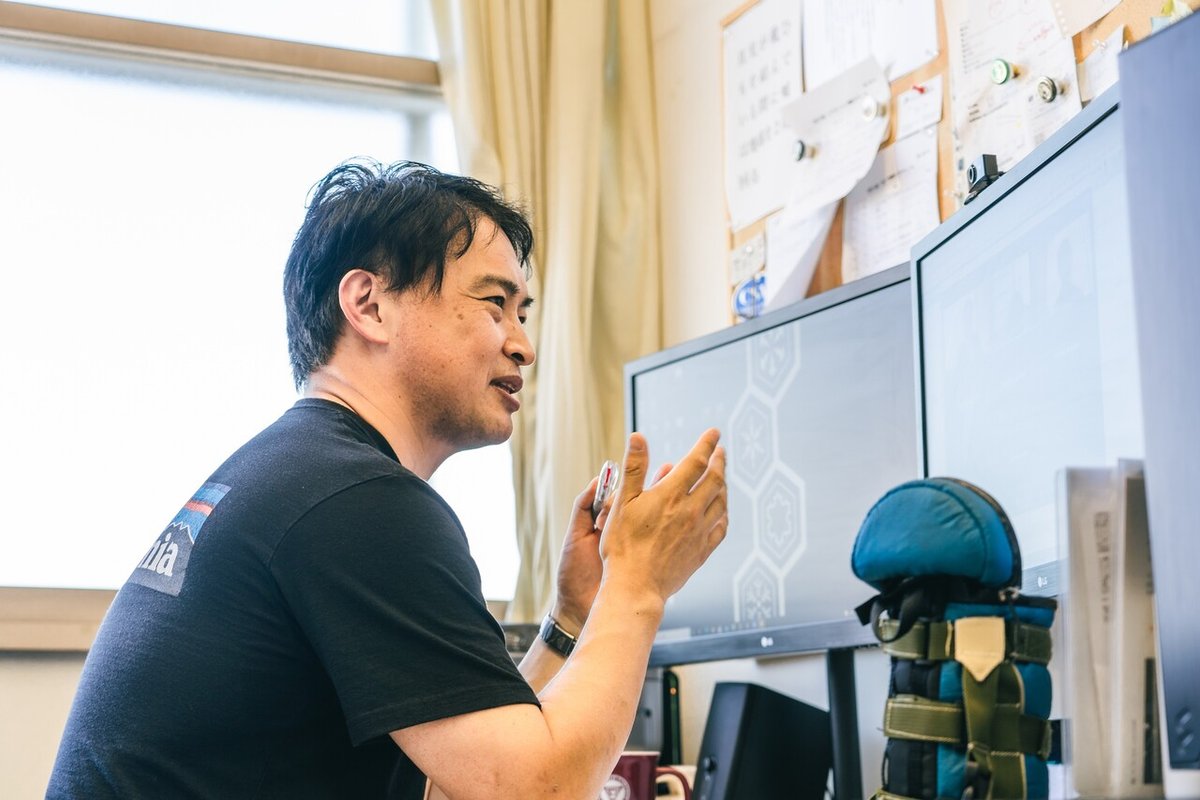
── コロナ禍がきっかけで日常に目を向ける人が増えたのと通じるお話ですね。
そういう意味では、いま住んでいる北海道は日常の延長上で自然を深く味わうのにこの上ない環境です。
なぜって、車で30分も行けばニジマスが釣れる渓流がある。毎朝ひと釣りしてから出勤できるんです。そうやって毎日同じところを訪れていると、天候や季節による自然の小さな変化にも気づくようになります。
山菜採りやキノコ狩りも日常のなかにあります。ですから、仮に今日採れなかったとしても、1週間後には懲りずにまた行くことになるでしょう。
東京だとこうはいきませんよね。たまの休みに渋滞のなか何時間もかけて行くことを思えば「今月はここに行ったから、来月は別の場所に」となるのが自然です。
── 先日、青木先生にうかがったときにも、都市と自然が溶け合い、日常のなかに自然がある状態こそが理想だというお話がありました。
そう思います。ですから、いまはあくせく飛び回ったりしないで、日常を、この地域をじっくり見て味わおうという気持ちになっています。
とはいえ、チャレンジしてこその人生では?

── 最近は世の中的にも「競争よりも共生」のメッセージが強いですよね。
ええ。そのこと自体は間違ってないと思いますし、私自身もそういう生活をしているわけです。ですが、先ほども申し上げたように、一方で若いうちは、もっとチャレンジする時期もあっていいのではないかと思うんです。
そもそも私たち人類は、そういうことを繰り返してここまで生きてきた、というのが私の持論でして。
── どういうことでしょうか?
最近話題となったハラリによる『サピエンス全史』にも書かれていますが、人類は時に他者とぶつかりながらも、絶えず新しい環境や状況に合わせて挑戦し続けてきました。だからこそ、今日まで生きながらえているのではないかと思うんです。
最近はせっかく新しい環境があってもチャレンジをしない学生も多いです。これにはやはりネットの影響が大きいのかもしれません。なにかわからないことがあってもスマートフォンですぐに検索できてしまう。そうすることで、実際にやらなくてもわかった気持ちになっている。

でも、冒頭にも言ったように、知識としては知っていても、できるかどうかはまた別の話。だから「やってみて」と言われていざやってみても、できないということが往々にしてあります。
焚き火なんてのはその典型です。いまはアニメやYouTubeなど情報源が充実しているから、学生たちにも知識はある。でも実際にはやったことがないので、でかいままの薪にいきなり火をつけようとする。「それではつかないよ」と言ってナイフやのこぎりを与えても、ちょっと削っただけですぐにまた火をつけようとしちゃう。
ですから、私が学生に伝えたいことは、わかっているつもりでなにもやらないのではなく、もっとチャレンジしようよということです。一回やってみることから気づいたり、わかることもたくさんある。そういった体験の機会を増やしたくて、いろいろと仕掛けているんです。
教科書にはない新しいものに触れたり、知らないものを体験してもらったり。その機会や環境を提供することこそが、大学の学びのかたちだと思っています。

■田中先生によるランタントーク本編はこちら
國學院メディアではさまざまなジャンルの教授陣による、記事を公開しています。本記事と合わせてぜひご覧ください。
執筆:鈴木陸夫
写真:渡辺 誠舟
編集:日向コイケ(Huuuu)
