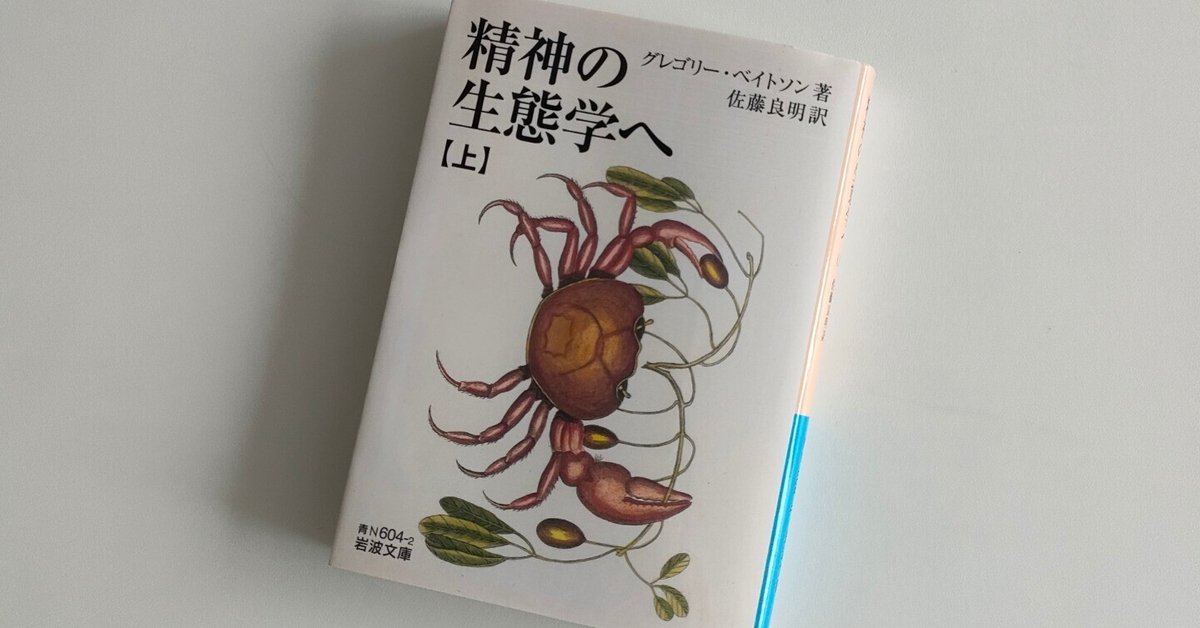
【書評】グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学へ』(上)--コントロールを手放す
どうしても読めない本というものがある。僕の場合この『精神の生態学へ』がそうだった。大学時代にはもう、ハードカバーの翻訳が出ていて、なんとなく良さそうだし読んでみよう、と何度か挑戦したのだが、メタローグという対談部分から先はさっぱり歯が立たなかった。でも、なんとなく面白い感じだけは残っていた。
今回、岩波文庫になって読んでみたら、なぜかスルスル読める。これは自分の頭が劇的に良くなったのかな、と思ったけど、そういうことではなく、たぶん過去の版よりも翻訳がすごく読みやすくなっているのだろう。
今回驚いたのは、ベイトソンがフロイトやマルクスをすごく意識した上でこの本を書いている、ということだ。フロイトについて、ベイトソンはすごく高く評価している。フロイトが使う概念はあまり精密とは言えないが、人間精神や家族について、フロイト以上に深い理解に達した理論はない。確かに性こそが全てを決める最終的な段階だ、とされていることには疑問があるが、こうした無意識が主体である、という議論はいまだ説得力がある。
この無意識の議論から、コミュニケーションや芸術全体と話を広げていくところはまさに、ベイトソンの真骨頂である。言葉を論理や意味ではなく、むしろ身振りや口調の総合的なシステムとして、人間と動物のコミュニケーションを両方見ながら考えていこう、という議論は興味深い。
あるいは、関係性について、私があなたをどう思っている、という発言とは全く関係なく、表情や身体の意思を超えた動きによってもう相手にメッセージは伝わってしまっている、という議論も納得である。
反対に、マルクス主義についてベイトソンは批判的だ。マルクス主義の、資本家と労働者の二つの階級間の対立が限りなく亢進して革命に至る、という考え方を彼は批判する。それは誇張なのではないか。
むしろ、二つの集団が隣接して存続している場合、当然相互に規定しあっているだろう。ならば対立の亢進だけでなく、対立の減少の回路もあるはずだ。でないと長年こうした状態が保たれるわけはない。
僕が非常に強い印象を受けたのはコントロールの話だ。意識によって物事をコントロールしようとばかりしている人は結局、怒りと憎しみに支配されることになる。なぜなら懸命に頭で考えて行ったことも、それが世界に投げられた途端、予想外の結果を招く。
しかも多くの場合、良かれと思ってやったことが逆効果になったりする。そうすると、その人物は驚き、怒りに包まれてしまう。問題が敵のせいだと考え、相手を全員滅ぼしたところで、そのことがまた逆効果を呼びこむ。
こうした部分を読むと、依存症の治療の話を思い出す。患者が意志で自分自身をコントロールしようとしてもうまくいかないときにどうするか、という議論で、ベイトソンの研究が言及される理由もよくわかる。
自分を世界との関係の中で捉え直しながら逆効果を楽しむ。そうやってコントロールを投げ出してはじめて、依存症は治癒へと向かっていく。モリス・バーマン『デカルトからベイトソンへ』などの議論も、こうしたベイトソンの思考に支えられていることがよくわかる。
上巻だけでも充分に読み応えがあった。中巻と下巻が出るのも楽しみだ。
