
臨床ファッシア瘀血学(11)肥田式「聖中心」から思うこと
前回は、臨床的な事柄から推測される連続性と局所性をキーワードに、これまでの話をまとめてみました。そこから今回は少し想像の羽を羽ばたかせて、いわゆる超人の技法との関連性などを考えてみたいと思います。
甲野善紀先生との勉強会の話題は、以前このブログでも少し紹介しましたが、ファッシアと肥田式との関連についてです。
肥田春充は、いわゆる丹田とされる聖中心を、自ら創出した技法の中心にしていったわけですが、その位置を、解剖学的構造ではなく、幾何学的な説明により提示していました。つまりランドマークは解剖的な構造ですが、聖中心というものを示すには「円」を規定しその中心としました。
そしてその中心を、腰椎からの直線が通過している説明図を提示しています。つまり考え方によっては、それぞれの解剖的な構造物との関係性、位置を規定する張力のようなもの、と考えてもよいのかもしれません。これまでのファッシア理論からすると「O-F」にあたる関係です。
また、甲野先生からの示唆で気づいたのですが、球状の円(球)が規定されているのですが、これには何らかの実体があるのではないか、という考え方もできます。ここ(球)に臓器の実態を当てるとすれば、それはまさに「腸管」、特に腸間膜に吊り下げられえた小腸となります。(甲野先生は腸管の何らかの膨張を想定されているようです)
この小腸は後腹壁から「フレアスカート」状に吊り下げられ、斜め下方向に集塊をなす様は「球」といえなくもありません。
学生時代の解剖学での記憶と合わせても、この「聖中心」と考えても矛盾なさそうに思います。
ただしここで注意すべきは、聖中心が腸管であるか否かという問題ではなく、肥田春充が幾何学的に表現したものの位置に、そうしたものが存在するという意味だけです。安易な同一化をしようとするものではありません。
こうした問題は「三焦」の捉え方にも適応できます(三焦を東洋医学の教科書的に捉えるだけでなく、腹腔動脈、上腸間膜動脈、下腸間膜動脈から腸間膜が栄養されるさまを三焦としたのではないか、という視点も実際の解剖所見からするとアリなのではないかとも思います)。機能総体としての三焦ではなく、何らかの「実体」を古人は捉えていたのではないかという考察です。これは大きな塊のように見える腸間膜と周辺の脂肪組織を古人は一塊の臓器として捉えていたのではないか、そしてそこには臓器としては当時認識されていない「膵臓」も含まれてきます(実際の解剖所見としては全てが一塊に見えます)。
そしてこのフレアスカートの吊りあげている視点が「腸間膜根」となり、後腹壁を左上から右下へ向けて、腰椎を跨いで下降しているのです。解剖的に腰椎1番2番あたりから下降しているので、横隔膜後脚が3番あたりまで来ていますので、呼吸におけるファッシア的な連動は十分考えられます。
そしてその終結は右側の仙腸関節上部に至ります。つまりここもファッシア的な接続を考えることができます。つまり骨盤調整との連動の可能性です。この「根」は当然、腰椎4番5番あたりで腰椎を跨いでいるので、いわゆるヤコビー線と腰椎との交点を、肥田春充が示唆しているのと関連するようにもみえます。腸間膜根の吊り上げ作用の重心が、腰椎4番5番の意識や調整と直接関連することは容易に示唆されるでしょう。
なぜ肥田春充が、こうした幾何学的な説明によりその位置を示そうとしたのか。それこそが当時(今もそれほど大きな変わりはありませんが)の解剖学がファッシアの存在を、半ば無視していたことと無関係ではないように思います。
解剖実習を行った経験がある人であれば、すぐわかることですが、解剖実習とはこの「ファッシア」から、いかにして目的の「臓器」取り出すか、つまり見やすくするかにつきます。ファッシアは取り除かれるべき「不要物」であり、臓器の「背景」にしか過ぎないというわけです。
解剖するという行為の究極が、解剖学の図譜や教科書ですから、そこには当然ファッシアの記載はありません。いくら肥田春充が超人であったとしても、当時の(今も?)解剖図に記載されていないものを、実体として認識していたとは思えません。これは近年、「ニューズウィーク」誌に皮膚を上回る「巨大な臓器」としてファッシアの発見が報道されたことからも、「存在していた」にも関わらず「認識されていなかった」臓器であることがうかがわれます。
春充は、自らの体感と、熟読した解剖書とを見比べて、その関係の体感を幾何学的に示そうとしたのではないでしょうか。これは眼光紙背に徹するかの如く解剖書を読み込んだであろう春充の、正確な解剖的知識があればこそ、「そこにないもの」を記載することが出来たのではないと考えます。「在る」ものを強く意識するほどに、認識の反転が生じた際に「ないはずのもの」がより強烈に認識されてくるのではないか。「図と地の反転」を基盤として考えるべき、ファッシアとの関連がここに出てくるように思います。春充の聖中心の体感の瞬間などは、まさにこの認識の反転として捉えることで、理解できるのではないでしょうか。
腸間膜根から壁側腹膜として折れ返ることで、腸管の状態が全身へと接続されます。これはまさにファッシア論でいう「O-F」の引張構造で説明されます。
室町時代に隆盛を極めた「腹部打鍼術」が、腹部のみの刺激で、全身のあらゆる症状に対応していた事実からも、この関係は意外に大きな連携を有していることが推測されます。
進化学的にも体幹である腹から四肢が形成されてきたことを思うとその中心が「腹」の「腸管」にあることも矛盾しません。ここに「火事場の馬鹿力」発揮のカギがあるようにも思えます(甲野先生のご指摘による)。
こうした身体(とりわけ四肢)の関係のみならず、近年は「脳腸相関」として神経系との関連が最新医学のテーマとしても注目されています。神経伝達物質において、脳→腸、または腸→脳の関連が、詳細に研究されています。こうした関連においても、腸管の占有する位置が、その機能に関係する可能性は大いにありそうです。
腹腔内での腸間膜と腸管を一塊としたものの位置により、四肢における運動能力が大きく影響される可能性を、聖中心は持っているように思われます。そして加えて、それらの正しい位置関係が、「脳腸相関」においても生体に有利に働く可能性も想定されます。(筋膜の張力の均等化や、結合組織表面における水分子の量子的ふるまいの正常化、等が要因として考えられます)
筋トレにおける筋肉のイメージのように、腸の塊の鮮明なイメージ化によって身体的かつ精神的な超絶した能力の開花が可能になるのではないか、そんな可能性を「聖中心」は与えてくれるのではないでしょうか。

機関誌 聖中心道
肥田 春充 NextPublishing Authors Press 2019-12-04
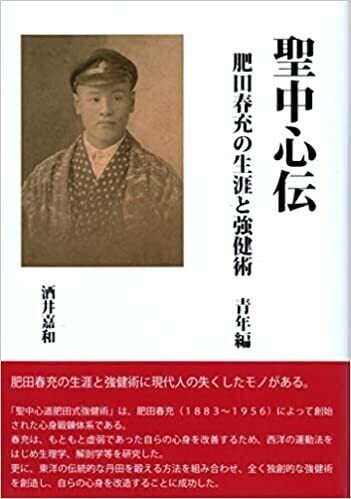
聖中心伝 肥田春充の生涯と強健術 青年編
酒井嘉和 壮神社 2020-02-29
