
第4回 指揮者という夢
こんなに笑える書き出しだったっけ? と思いながら、徐々に記憶がよみがってきました。
岩城宏之『森のうた――山本直純との藝大青春記』(河出文庫)——朝日文庫、講談社文庫に続いて、今回が3度目の文庫化です。

「藝大のタイコの二年生だった」という“ぼく”が、著者の岩城さん。1932年東京生まれ、東京藝術大学在学中にNHK交響楽団副指揮者になり、2年後の1956年にN響を指揮して24歳でデビューします。
その“ぼく”の前に現れるのが、やたらに生っちろいハンペン顔、手が出ないようなダブダブの上着を着て、食堂の隅からこちらへ向かって走ってくるオランウータンみたいな男です。威勢よく「イヨーッ」と大声で、土建屋まがいの挨拶を誰かれかまわず繰り返します。
「なんだ、こいつ?」とあきれていると、「すごい才能の作曲科一年生」なのだと紹介されます。
藝大の音楽学部には、独特のヒエラルキーがあって、最上位に作曲科、指揮科の少数エリート民族がいて、これにピアノ科、弦楽器科が続いて先進民族をなし、あとは人数の多い声楽科があり、楽理科、邦楽科ときて、いちばん下に管・打楽器科があって、タイコ屋はその劣勢民族中の最下層だという、ヒガミ根性が“ぼく”にはありました。
そこへ「イヨーッ」が現われ、「岩城サン、オレのことをナオズミっていってよ。ナオは不正直のジキ、ズミは不純のジュンです」と初対面の挨拶をするのです。こうして「山本直純との藝大青春記」は始まります。

(『森のうた』河出文庫より)
岩城さんがタイコ屋になるまでの紆余曲折もケッサクですが、何につけても大らかな「よき時代」の大学(しかも藝大!)で、1年間好き勝手をやっていた“ぼく”の前に、入りたての一年生のくせに、こんな自信満々なヤツは想像を絶する、というナオズミが出現します。
後年、ともに日本を代表する指揮者になるわけですが、最初からウマが合うというか、惹かれ合うものがあったのでしょう。さっそく喫茶店のはしごをしながら、音楽談議に花を咲かせます。
父親が戦前の有名な作曲家・指揮者、母親がピアニストという家庭に育ったナオズミは、英才教育を受けた音楽一家の超エリート。「ピアノはパラパラ弾けるし、バイオリンでもトランペットでも、何でもござれ」のサラブレッド。
しばらく話すうちに、「オメェ、どんな風に音楽をやってきたんだ?」「何となくオメェの音楽教育は貧しそうだから、これ読むと何かの参考になるかもしれねぇヨ」などと言いたい放題で、いつの間にか上級生が聞き役に――。
そして2、3日後に見せられたのが、古ぼけたぶ厚い皮表紙の「オレの小学校二年のときの日記」だったというのです。
中身は読んで確かめていただくのが何よりですが、かの指揮者の山田一雄先生に、ベートーベン交響曲第1番の講義を直々に受け、来週までに「第一楽章の最後までピアノで弾けるようにしておいで」と言われ、「いつしようけんめいべんきやうしやう」と結ばれます。
<参考になんかなるものか。ぼくは打ちひしがれた。ぼくがオモチャの木琴をいじりだし、半音のないその木琴で、どうも、ファとソの間に何か音があるはずだ、と考えこんでいたのが、ナオズミのこの日記より四年も後なのだ。音楽家の息子って何て恵まれているのだろう。>
ナオズミの「天才的な耳」にも驚嘆します。ただ、そのナオズミも、藝大の試験には一度失敗しています。自伝『紅いタキシード』(山本直純、東京書籍)によると、変声期にぶつかった直純さんは、歌の試験で手痛いしくじりを演じます。

声が出ない! 「シオカラ声を振り絞ってひどい歌を無理やり歌った」ものの、ここではじめての大挫折を味わいます。
<「あの三人は絶対入る」といわれた“三羽ガラス”(略)の一羽が落ちたというので、ボクよりみんながびっくりして、たちまち大ニュースになった。
こんなことがあって、ボクはもしかしたら音痴ではないかと考えるようになってしまった。>
やがて指揮者の渡邉暁雄(あけお)先生に、直純さん、岩城さんの二人が聴音テストを受けます。
<「きみ、いまたたく和音の中の、上から三番目の音の、五度下の音を声に出してごらん」
和音なんていうものではない。指十本の全部を使った目茶苦茶な不協和音だ。
ナオズミは即座に、「アーッ」とダミ声をあげた。
聞いているぼくにはまったくわからない。どうせ思った音程を声には出せないやつなのだ。デタラメに怒鳴っているのだろう。
先生は指定した音、つまり上から三番目の音の五度下のキーを、ポ-ンと叩いた。
ダミ声と同じ音だった。>
先生がゆっくりうなずいて、もう一度、違う不協和音で試します。またもやダミ声が、こともなげに正解を連発。
<ぼくは自分がガタガタ震えているのも忘れて呆れかえった。こんなことをできるやつは、日本に何人といないだろう。完全無欠な絶対音感教育の、しかももともと天才的な感覚を持っている人間でなければありえない。
テストをする先生自身、絶対にできないに決まっている。これは断言できる。>
“ぼく”の結果は推して知るべし。すっかり落ち込んでしまいます。
「あとがき」で岩城さんは、こう述べます。
<われわれ二人は大学では作曲科と打楽器科だったが、なんとか指揮者になりたかった。学生時代は二十四時間一緒だったといってもよかった。ぼくはナオズミの才能のすごさには、まったく太刀打(たちう)ちできず、とにかく彼に追いつこう、というのだけがぼくの学生生活だった。>
こうして始まる二人のドラマは、一日でも早く“棒が振りたい”——ともかくオーケストラの指揮がしたくて、したくて仕方がない――という情熱とエネルギーがほとばしる涙と笑いの青春物語です。
顔を合わせれば、“棒の振り方”をめぐって真剣にぶつかり、しばしば壮絶な議論——何時間も大声を張り上げてやりあう、けなしあう、つまりはケンカ――になります。
探求心、向上心の火の玉になった2人組が、「上野の杜(もり)」に巻き起こす、縦横無尽、疾風怒濤の音楽修行。失恋あり、大学祭でのバカ騒ぎあり、ただでコンサートにモグりこむ、カラヤンの練習場にこっそり忍び入る、などなど、奔放な逸話が満載ですが、夢に向かって突き進む真っすぐな眼差しと、ひたすらな意思が、この破天荒を貫く心棒です。
以前はそれほど意識しませんでしたが、直純さんへの対抗心を燃やしつつ、真摯に学び、問いかけ、考え抜いていく岩城さんの批評的な眼力には目を見張ります。これはという場面、言葉を記憶に刻みつけ、それを見事に再現していく著者の筆力にも驚かされます。
カラヤンの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」を聞いたナオズミが、「ヨー、すごいテクニックをしてやがるな。出だしのタタキなんか、完璧だぜ」と言ったひと言から、齋藤秀雄氏の指導の極意、「タタキ」について岩城さんが解説します。齋藤秀雄といえば、小澤征爾、山本直純らの師であり、やがては岩城さんも門下に入る指揮者です。
「タタキ」とは、指揮棒で空間の一点を打つテクニックであり、「齋藤理論」のキーワードです。これを説明するなんとも微妙な言いまわしに、岩城さんらしさがにじみます。
さらに驚いたのは、終章「森の歌」の記述です。『森のうた』という本のタイトルは、てっきり「上野の杜」が舞台だから、と思い込んでいましたが、この物語のクライマックスは、ショスタコーヴィッチ作曲のオラトリオ「森の歌」を、岩城、山本が結成した学生オーケストラ「学響」で演奏する(直純さんが指揮をする)という場面でした。それをすっかり忘れていました。
そして亀山郁夫さんの、芸術家の苦闘の日々を描いた『ショスタコーヴィチ――引き裂かれた栄光』(岩波書店、2018年)を読んだいまでは、この終章の印象もまた異なります。「森の歌」がどういう由来の作品で、いかなる曲想を持ち、それがこの日、藝大の学生たちによってどのように演奏され、それを聴衆がどう聴いたか?
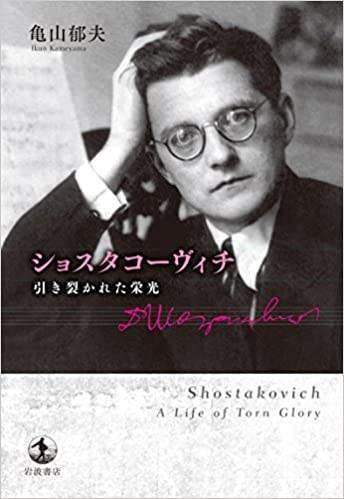
そのライブの再現を、オーケストラの一員でありながら、同時に、驚くほどにクールに、多面的に描いてみせる著者の目に、指揮者の「脳内」――いや、まさに「身体」を感じます。この本の圧巻中の圧巻です。
「森の歌」をショスタコーヴィッチが完成させるのは1949年8月で、初演は同年11月。したがって、1953年の秋、これを日本で演奏するのは画期的な出来事です(日本初演は同年6月、京都)。
藝大「学響」の秋の特別演奏会は、これが2回目で、前年は上級生である岩城さんが指揮をし、今年は「ナオズミに譲る」ことになりました。
<ナオズミは、ドエライことを考えついたのだ。当時世界中でセンセーショナルに迎えられていたショスタコーヴィッチの「森の歌」である。歌のソリスト二人、大合唱付きの大曲だ。大勢の合唱団を集めるなんて、ぼくには考えもつかないことだった。
ヤラレタ、と思った。いまいましいが、ぼくは打楽器のほうにまわる。>
ショスタコーヴィッチはまぎれもなく20世紀を代表する偉大な作曲家の一人です。ただ、1948年の有名な「ジダーノフ批判(ソ連共産党中央委員会による芸術統制)」以後は、スターリン体制下の社会主義国家で、作曲活動を続けるためには、さまざまな妥協を余儀なくされました。
亀山郁夫さんは、こう記します。
<『森の歌』は、当時のスターリンが提唱していた国土緑化計画に呼応する音楽である。約四年間に及ぶ独ソ戦で、ソヴィエトの国土は荒廃し、各地で旱魃が頻発していたが、スターリンはそれをこの自然改造によって乗り越える計画をたてた。
詩人ドルマトフスキーの詩につけたこのオラトリオはある意味で完全にスターリン主義の産物である。全体で七つの曲から構成されているが、多くの部分にスターリンに対する礼賛の言葉が埋め込まれている。>
岩城さんもこう言います。
<はっきりいえば、全盛時代のスターリンへの、大ゴマスリである。だから、この時期の彼の一連の作品は、芸術的価値に、大きな疑問がある。要するに、社会主義リアリズムとやらに従ったわけである。(略)
しかし、とにかく、世界中で、この「森の歌」は超大ヒットになった。
曲のあちこちに、さすがはショスタコーヴィッチと思われる、きらきら輝く作風は見られるけれど、全体としては、どんな人にでも受け入れられるような、実にわかりやすい音楽である。>
評判が評判を呼び、とんでもない数の聴衆が押しかけます。明治期に建てられた奏楽堂に、100人近くのオケ、200人以上ものコーラスが一度にのっかると、ステージの床が抜けるのではないか、という懸念にくわえ、超満員の客席です。
ギュウギュウに詰め込んでも、外にはまだ長い行列が続きます。その時、ナオズミの大声が響きます。「オオ、いいじゃねーか。二回やったるで!」。
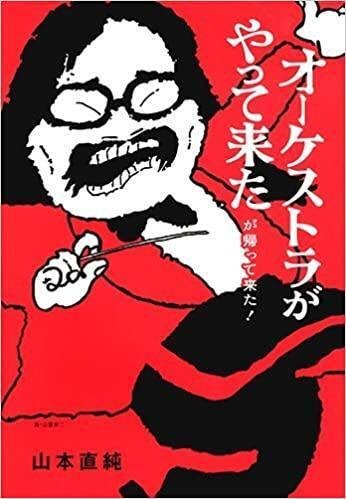
緊張と興奮のステージが始まります。
<「オイ、しっかりな」
ぼくはそっとステージに出て、シンバルの前にすわった。ややあって、ナオズミが颯爽(さっそう)と出てきた。すごい拍手だ。シンバルのぼくは、内心クヤシイ。>
ナオズミの表情を追いながら、“ぼく”自身の揺れ動く心を見つめ、躍動する文章が続きます。
<一回目も大成功だった。ぼくは、うんとうれしいのと、うんとくやしいのと、両方の、複雑な気持ちだった。
そして、この二回目は、待ちに待って並んでいた客で、さっきよりももっと、超満員だったのである。(略)学校が何をいおうが、奏楽堂がつぶれようが、知ったこっちゃないと、ギュウギュウに立ち見を詰めこんでしまったのだ。>
ここからのライブの描写は疾走します。映像が目に浮かび、音が聞こえてくる、そして堂内の熱気が押し寄せてくるような再現です。
「森の歌」という曲の流れを語り尽くし、指揮するナオズミの高ぶり、見守る“ぼく”の感動、そして「本心はスターリンへのくやしいゴマスリであったにせよ」、見事に構成され、「さすがにショスタコーヴィッチ」と唸らせる音楽の強さ、深さ、魅力。
バスが、テノールが、コーラスが歌い上げ、指揮台の上でナオズミが暴れ狂い、自分がそれを見届けている――この日、超満員の奏楽堂で一体となって奏でられた「森のうた」の臨場感が、余すところなく活写されます。
<だれよりも指揮者が興奮していた。何度もとびはねた。シンバルを打ち鳴らしながら、何度も「ウォーッ、ウォーッ」の叫び声を聞いた。オーケストラとコーラスの、全員のフォルティッシモをこえて、ナオズミの叫びが響きわたったのである。
これでわれわれの「祭り」が終わるのだ。なんだか惜しくてたまらない。永遠にこのまま続けたい、というような熱気が、奏楽堂全体に溢(あふ)れていた。>
“ぼく”はこの日、藝大の宝物ともいえる「とっておきのシンバル」を借り出していました。
<最後の一発。指揮台のナオズミと目が合った。渾身(こんしん)の力で打ち鳴らした。>
<……「ブラボー」の嵐の中、興奮の極みのぼくは、指揮者のナオズミだけを凝視していた。ナオズミは両手を大きく挙げ、オーケストラ全員を立たせてほめたたえた。ぼくも胸を張って客席を見渡した。すると得意満面で客席におじぎをするナオズミの背中がとてつもなく大きく視野いっぱいに広がったのだった。
「祭り」が終わった。>
これが『森のうた』の物語です。青春を駆け抜けた岩城さんと直純さんの「祭り」。
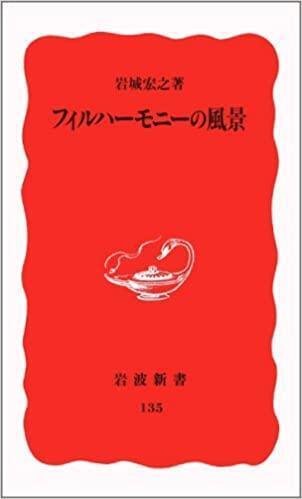
読む前でも読んでからでも「森の歌」を聞いておくと(YouTubeでもなんでも)、このライブの場面がいっそう際立つと思います。ショスタコーヴィッチについての予備知識があれば、なおのこと――。
これを書いた岩城さんに、「ブラボー!」を言う機会がなかったなぁ……。本を閉じながら、そんな心残りがめざめました。
