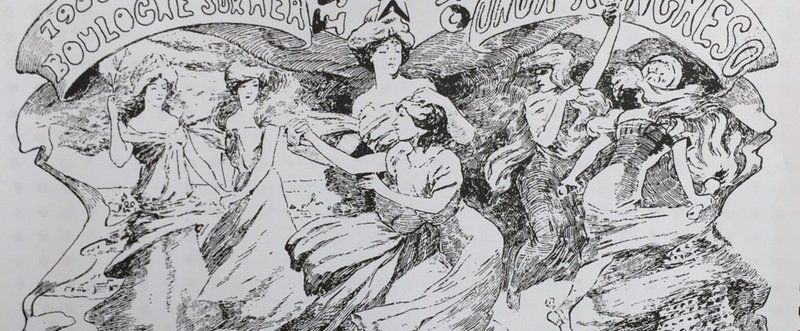ファーストコンタクトは相互理解への第一歩。このマガジンでは、私が考えていることの第一歩をできるだけそのままの形で公開していきたいと思います。話題は、アドラー心理学、教える技術、研…
¥500
- 運営しているクリエイター
#インストラクショナルデザイン

【本】市川尚・根本淳子編著『インストラクショナルデザインの道具箱101』→インストラクショナルデザイン入門の1冊目として実用的
2017年3月9日 (木曜日はお勧めの本を紹介しています) 市川尚・根本淳子編著『インストラクショナルデザインの道具箱101』(北大路書房, 2016) ■要約インストラクショナルデザイン(ID)とは学びの「効果・効率・魅力」の向上を目指した技法とモデルの総称である。それを101個集めたこの本を眺めて、自分の現場に導入していけばあなたの教える技術は高まるだろう。 ■お勧めのポイントIDの技法とモデルを101個も集めたら、それをどのように分類、構造化して示すかというとこ