
反転授業の設計と実践(Part 2)
2016年12月30日
■グループワーク「自分の授業ビデオを作るとしたら」
それでは、グループワークをやりましょう。皆さん方がもし自分の授業ビデオを作るとしたら、どのようなものにしたいですか、ということを考えていただいて、グループ・ディスカッションをしていきたいと思います。それでは最初に2分ぐらい考える時間を差し上げますので、考えていただいて、ポストイットにメモしておいてください。その後、1人1分で、グループ内で発表していきたいと思います。では、お願いします。
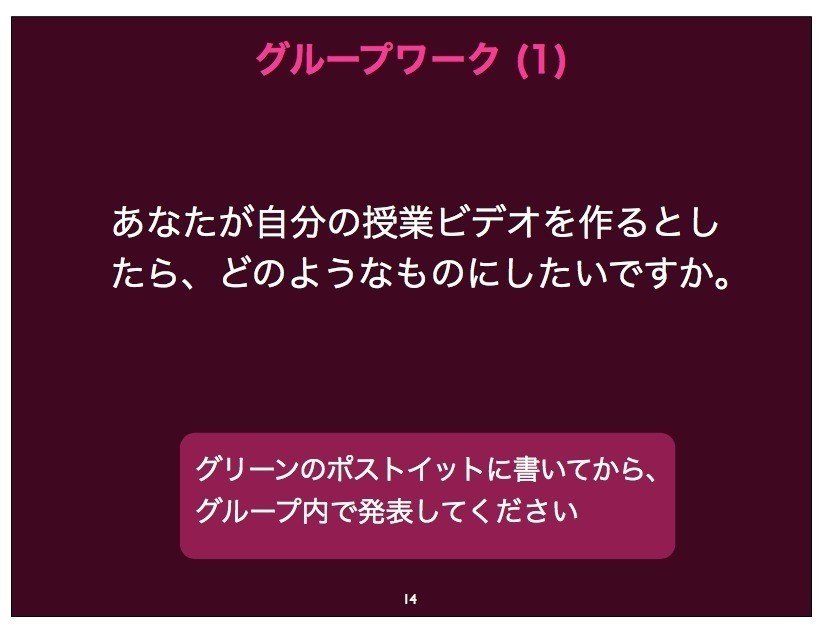
向後 はい、ありがとうございました。それでは、せっかくですので、どこかグループを指名して、発表していただきたいと思います。今日はグループが多いので、二つサイコロを同時に振りますので、オレンジのほうが列で、もう1つのが行とします。(サイコロを振る)はい、10列めの2番めです。では、順番にお1人ずつお願いします。
川田 これほどたくさんいるのに、アンラッキーな日で、当たってしまいました。情報メディア学科の川田と申します。とても参考になると思って、お話を聞かせていただきました。情報ビジネス起業論という授業で財務諸表を教えるのですが、損益計算書など割と簡単なのですが、分かってくれないので、授業で何回も説明する時間がもったいないと思っています。財務諸表だけを、簡単に解説をこのような動画にしておいたらいいのではないかと思って、ぜひ来年からしたいと思っています。
向後 はい、ありがとうございます。では、2番めの方、お願いします。
川崎 薬学部の川崎といいます。当たると分かっていたらもう少し違うものを考えたのですが、ここで発表したものをそのまま言うと、授業で流せばそれで講義の代わりになるようなものを作るのがいいのではないかと思います。そして15分間、15分、15分、15分と用意しておいて、ここで毎回15分流して、その間、学生は聞いていて、私は座っています。そして適当に質問などがあったら、毎年同じもので済むし、先生がおっしゃっていた、反転授業ができるという、まさにそれが実践できるのではないかと思いました。以上です。
向後 はい、ありがとうございます。では、3人め、お願いします。
野々口 看護学部の実習助手の野々口と申します。私は授業を自分ですることがありませんので、とても悩んだのですが、演習の補助に入らせていただくときなどにデモを見せるときがあります。そのようなデモのビデオを撮っておいて、事前に学生に見ておいてもらうと、演習のときにどこが難しかったかというところを確認しながらやっていけるのではないかと思いました。以上です。
向後 はい、ありがとうございます。では、最後、お願いします。
高橋 日本語日本文学科の高橋です。日本語日本文学科では1年生必修の基礎リテラシーという科目があります。簡単な言語に関する調査と、レポートを書かせるのですが、高校生から上がりたてなので、情報の授業などのリテラシーは学生によってかなり差があって、コンピューターを全然開けない子から、ワードで上手に文章を作る子もいます。そのような授業で、簡単なワードやエクセルの操作などをビデオで撮影しておいて流すと、複数の教員が担当しますが、教員によって指導の内容の差もなくなりますし、QRコードなどを配付する資料に載せておけば、すぐに自宅等でも確認できる、うまく使えるのではないかと思ったりしました。
向後 はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。今聞かせていただいたように、いろいろな形での活用ができます。特に、最初の発表の、財務諸表を毎回教えなければいけないということと、最後の発表の、パソコンの使い方など、手を動かすようなものをビデオ化すると効果的です。
■ビデオ教材を使うことの効果
先ほど紹介したカムタジアというソフトは、スライドだけでなく、パソコン画面に映っているものすべてを、自分の顔と同時に、収録します。たとえば、エクセルを開いて、このようにコピーして、このように式を入れてコピーして、このようにすると一発で出ますよ、というようなことを話しながら操作します。そうすると、操作している画面と自分の声が同時に録画されているので、それを後でどれくらいの大きさでレイアウトすればいいかを決めるだけで、教材ビデオができるのです。このような操作系の授業は結構あると思いますが、毎年やって、同じところで学生がつまずきます。そのようなことがなくなると思います。
ビデオ化すると、学生のほうも、1回ビデオを見ただけでそれで終わりということは、実はあまりないのです。学生の視聴記録(ログデータ)を検討してみると、普通のレクチャービデオであっても、2回から3回は見ています。一方、教員が教室で話して、学生がそれを聞き逃したといっても、もう1回同じことは話せません。しかし、eラーニングのビデオであれば、2回とか3回見てくれます。自分が聞き逃したと思ったところも、巻き戻してもう1回見てくれます。
操作系のビデオを見ながら、自分でもエクセルを開いて、練習する場合でも、何回も見てくれますので、非常に効率が良くなります。もし、これを対面で、一斉にパソコンを広げてもらって実習するとなると、必ず、「うまくできません」「パソコンが止まりました」などということになります。ビデオを使えば、そのような非効率的なところがなくなることが期待できます。
それから、薬学部の方が「授業を全部撮っておけばいいのではないでしょうか」ということを言われました。まさにその通りで、ぜひやっていただきたいです。私の経験から言うと、1回収録すると、3年間は使えます。基礎的な、たとえば哲学の授業であれば、10年ぐらい使えるのではないかと思います。法律を含む科目で、もし法律が変わって、その変更に合わせて内容を変えなければいけない場合でも、法律が変わるまでは使えます。
ですから、1回撮ったらその年だけで終わりではありません。通常は、3年か4年、放送大学だと4年で入れ替わりますが、大体4年ぐらい使ってもOKだと思います。同じことを毎年話すのが嫌だというのであれば、絶対にビデオを撮ったほうがいいです。新しい知識や情報については、そのビデオを年ごとに追加して、古いものを削除していく形でアップデートしていけば、学生に最新の情報を提供することができます。
看護の方から、デモンストレーションビデオの提案が出ましたが、これもぜひ撮っていただきたいです。現場で、実際に体をどのように動かすのか、採血をどうやるのかなどをきちんと撮っておけば、非常に良い教材になると思います。その場合は、パソコンの前で座って話すのではなくて、実際の実習の様子を、ビデオカメラやスマホのビデオで撮ることになります。
(Part 2 終わり)
ここから先は
ご愛読ありがとうございます。もしお気に召しましたらマガジン「ちはるのファーストコンタクト」をご購読ください(月500円)。また、メンバーシップではマガジン購読に加え、掲示板に短い記事を投稿していますのでお得です(月300円)。記事は一週間は全文無料公開しています。

