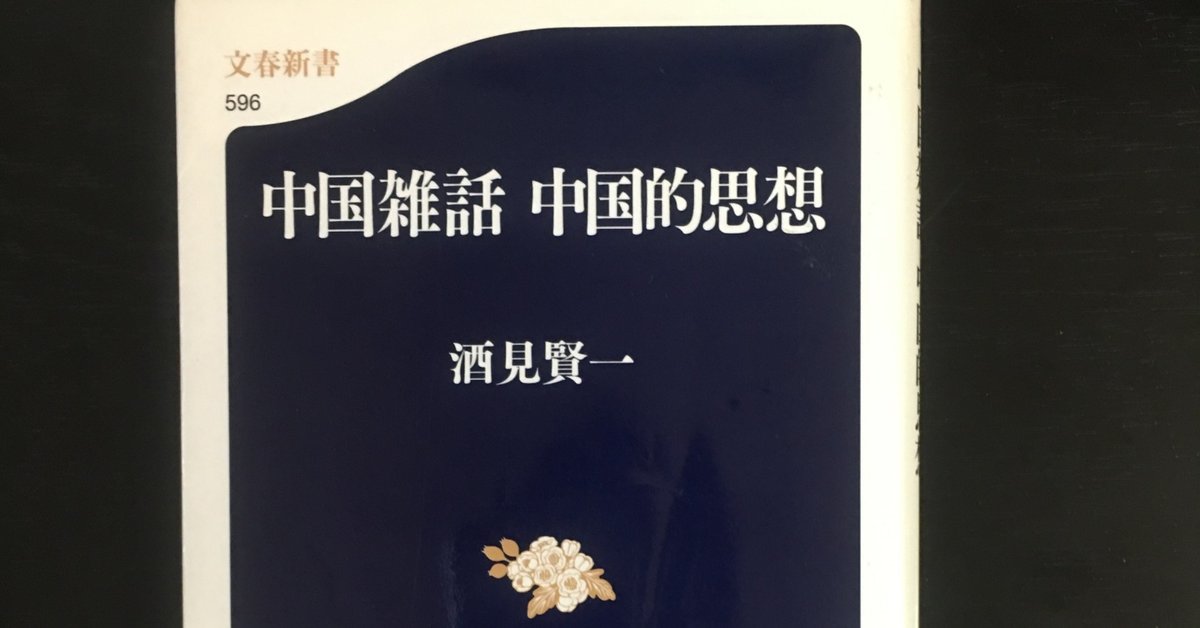
中国雑話 中国的思想
『中国雑話 中国的思想』酒見賢一 2007年10月刊 文春新書
本書はNHKラジオの中国語講座テキストに掲載されていた「中国古今人物論」に加筆・修正が施され出版されました。
・劉備
・仙人
・関羽
・易的世界
・孫子
・李衛公問対
・中国拳法
・王向斎
上記、項目の8章からなり、日本でも比較的ポピュラーな人物や思想の魅力を通じて、中国ならではの人間観や世界観の面白さを紹介しています。
劉備や関羽、孫子であれば三国志などの歴史好きな方のほとんどはご存じかと思われますが、本書で紹介されている「李衛公問対」を知っている方はなかなかいないのではないでしょうか。
中国の古典的兵書は7つあるといわれ、「孫子」「呉子」「六韜(りくとう)」「三略」「司馬法」「尉繚子(うつりょうし)」に「李衛公問対」を加えたものが武経七書と呼ばれています。
「李衛公問対」以外の六書はどれも漢代までに書かれたもので、「李衛公問対」だけは唐代末から宋代にかけて編纂され、武経七書の中ではもっとも歴史の浅い兵法書となります(それでも千年以上の前の書物なのですが)
この兵書のユニークなところは、他の六書と異なり、唐の太宗李世民とその重臣の李靖が兵法について問答するという構成をとっている点にあります。
共に戦場を駆け抜けた歴戦の武将であった二人が中国史上に残る過去の有名な戦いを論評し、自分たちであったら実際にどうしたのかを検証するといったある種の歴史番組のような趣きがあるそうです。
二人は最後に歴史上の軍略かのランク付けをしているそうなのですが、このランキングもその理由も本書に記載されており、大変面白いものでした。
他の章も大変、興味をひくものが多く、「易」や「中国拳法」を扱った章は個人的に特にツボでした。
「易」は一般には占いの一種として知られていますが、よくよく深掘りしていくと、ある種の宇宙論が展開されおり、一つの哲学体系ともいえるのです。
私自身も数年間、易について学んでいた時期があったのですが、知れば知る程、その深さは底なしで、最近は年に数度、易占を立てるくらいで、易そのものを理解しようということは諦めるに至りました。
西洋においては、心理学者のユングは易の研究に傾倒し、作家のヘッセはノーベル文学賞を受賞する契機となった作品「ガラス玉遊戯」の作中で易を取り上げてもいます。
しかし、なんといっても本書の白眉は「中国拳法」の章でした。
太極拳や形意拳、八卦掌と呼ばれる中国拳法の歴史や達人たちのエピソード、解説が本書の約半分のページを占めており、最終章は中国武術史上、屈指の名人とされる「王向斎」その人の逸話で締めくくられておりました。
この王向斎という人は本当に凄いです!
実戦の腕前で名高い中国拳法家というと、ブルースリーやその師匠であるイップマン(葉問)が映画にもなり、大変、有名ですが、私は王向斎も挙げずにはおられません。
王向斎の生きた時代は清の末期で、西欧の列強が中国に進出し、国中が荒れ果てており、治安も悪く、人々の生活が危険に冒される機会は相当なものであったことが推測されます。
そんな命のやりとりが日常茶飯事な時代の中、圧倒的な他流試合の実績を残し、記録も残っているのが王向斎だったのです。
当時、魔都と呼ばれ、様々な国の外国人たちが行き交う上海において、ハンガリー人の世界ライト級ボクシング元王者が、上海の武術家たちと試合を行って全勝し、「中国の武術は語るに足りぬ」と豪語していたそうです。
そこで、中国武術の名誉復活の為に白羽の矢がたったのが当時、40歳の王向斎であり、相手との体重差は10キロ以上あったと言われていたのですが、衆人環視のもとリングにあがり、ゴングがあがるやいなや、たった一撃で元王者をリングに沈め、失神させたとのことでした。
のちに対戦相手のこの元王者は「わたしがみた中国拳法」のタイトルの記事をロンドンタイムスに寄稿しています。
他にも外国人で唯一の直弟子となった日本人、澤井健一は当時、軍人として、中国に訪れていたそうですが、柔道、剣道の有段者でもあり、腕に自信があったため、王向斎に勝負を挑みに行ったところ、武器においも、素手においても、全くかなわず、コテンパンにのされ、弟子入りをしたとのことでした。
他にも王向斎は柔道家を相手に自分の袖と襟を自由にとらせ、技をかけさせたのだが、投げるどころか、重心を崩すこともできなかったという逸話も残しております。
体格も痩せていて、小柄。体重も50キロ前後とされており、物腰穏やかで、学者の様であったとも言われています。
本書には王向斎の生前の写真も掲載されておりますので、是非、確認いただければと思います。
最近、香港での国家安全法をめぐる騒動や以前から指摘されているウイグルやチベットでの民族浄化、監視体制等、問題や脅威が山積みの中国ですが、長年の歴史が培ってきた文化的、民族的な遺産はまだ数多くあります。
本書、脅威は脅威として認識しつつも、中国より、学ぶべき点、その豊穣な思想や発想を取り入れてゆくための一助となるのではないでしょうか。
「しがみつくことで強くなれると考える者もいる。しかし時には手放すことで強くなれるのだ」 ヘルマン・ヘッセ
いいなと思ったら応援しよう!

