
『Near-Death-Expedition』レビューと感想
ネタバレ注意です。
良かったところ
音へのこだわり
2時間弱のボリュームのなかで、ASMR・作中歌をテンポよく取り入れる構成はすごいなと思いました。大手ソシャゲの人気キャラクターで後からキャラソンやASMRを作る流れは増えていますが、本作では製作陣の方々の「俺たちはゲームキャラクターに歌わせたいんだ!ASMRさせたいんだ!」という強い意志が伝わってきました。こういうインディーゲーム特有の一点特化はすごく好きです。

Vtuberへの解像度の高さ
新人Vtuberの終乃りんねをプロデュースしていくシナリオに説得力がありました。人気Vtuberになっていく過程にも納得できますし、描き方も巧みです。例えば、Vtuberの中の人の病み方の描写は、相当丁寧に調査を行ったのか、もしくは製作陣に関係者が居るのかと感じさせるほどの迫真さ。夜中2時にマネージャーに電話がかかってきたり、仮病がエスカレートしていく様子は、ありありと画が浮かびます。
Vtuberそのものに着目する新規性
「Vtuberとは何か?」をテーマにした物語は斬新だと思いました。「Vtuberをしているカレ/カノジョ」のようにシチュエーションとして扱う物語が多いなか、この作品ではカジュアルさを維持しながらVtuberの哲学をやっています。本作の手法は、Vtuberのありかたを徹底的に掘り下げることで、Vtuberを自我形成の仮想モデルとして分析すること。Vtuberに興味がない人ほど、むしろ楽しめるかもしれません。
気になったところ
ASMRシーンの少なさ
ゲームに「耳かきASMR」を取り入れる試みは斬新だと感じた一方で、ASMR配信シーン以外でもギミックとして活用できなかったのかな、と思います。聞いているほうもASMRだと意識していないとあまり効果がないなど何か理由があるのかもしれませんが…。終乃りんねへの感情移入を促進する手段としてだけでなく、ASMRの性質に着目した仕掛けも検討してほしかったです。

プレイヤーの選択に対するレスポンスの薄さ
ゲーム中の選択肢「あなたが同一人物とみなせるものを一つ選んでください」や、終乃りんねの着信に「出るor出ない」、謎空間で「歩くor走る」、終乃りんねを「削除するorしない」など、プレイヤーの選択に対してレスポンスが少ないことが残念でした。ゲームに没入しているところで、Steam実績だけ解除されてもなぁ…と。
主人公が事前に書いたシナリオ通りに展開している設定があり、どの選択肢でも決まったルートにしか進めないことを示す伏線だとはいえ、これは小説ではなくゲームなので、プレイヤーの選択に何かしらのレスポンスがあれば残念感は少なかったと思います。何が何でも主人公のシナリオ通りに進む設定なら、選択に関わらず元のシナリオに戻そうとする力が働く=ノイズなどの演出でプレイヤーに違和感を与えるなど…。
また「イヤホンを外し、彼女を迎えに行ってください」のシーンは「プレイヤー≠主人公」の視点から、突然「プレイヤー=主人公」に視点移動するので、かなり違和感が強かったです。

「主人公=プレイヤー」or「主人公≠プレイヤー」がはっきりしない
どちらの視点なのかが示されていれば、プレイヤーにより深く考察する余地が生まれ、シナリオが一層印象深くなったのではないかと思いました。いわゆる「胡蝶の夢END」は消化不良に終わる作品が多いなか、本作はVtuber設定やSFのテーマがうまくハマっており、夢オチまでの流れに説得力があっただけに、惜しいです。
例えばですが、「主人公=プレイヤー」を徹底したならば、今後、現実世界で終乃りんねのコンテンツを出すことで、プレイヤーに対して「この現実世界も実はNear-Death-Expeditionの内部ではないか」と感じさせるメタフィクション的効果を狙えたかもしれません。「現実世界のキャラクターコンテンツの存在を媒介にしてプレイヤーを虚構内に引きずり込む」という手法は、実現すれば入れ子型メタフィクションゲームのギミックとして新しかったのではないかと思います。エンディングで「体験型VRシミュレーションサービス『Near-Death-Expedition』は以上で終了となります」と明記されており、この解釈は否定されますが。

本作をメタフィクションに寄せないもう片方のパターンとして、「主人公≠プレイヤー」を徹底したならば、主人公がエンディングの後どうなったのか深読みする余地があったと思います。最終盤の種明かしで、主人公は「体験型VRから目覚めましたよ」と言われますが、そこから歩いて行ける場所にりんねが居るので、まだ仮想空間から目覚めていないことがわかります。現実世界で目覚めたと思ったら、「りんねの存在する世界」=「時間と空間が同じになる世界」に来てしまった訳です。
別ルートのりんね訪問エンドでは、虚実錯誤した主人公が仮想世界に取り込まれてしまいますが、りんね削除ENDでも、ひょっとして別の形で仮想世界に取り込まれてしまっているかもしれない、と匂わせる展開です。「時間=空間」となり、何も変わらない世界のなか、終乃りんねとの別れを終えた状態で意識だけが無限に存在し続ける(=別れの感傷を永遠に感じ続ける)ENDなのかなと一瞬思いました。

しかし、エンディングのテキスト表示を踏まえると、主人公もプレイヤーと同様に現実世界で目覚めたと解釈するのが妥当そうです。「体験型VRシミュレーションサービス『Near-Death-Expedition』は以上で終了となります」の表示のまま、主人公は目覚めずに静止している=死んでいると解釈できなくもないですが、本編の情報にもとづいて考えるなら、ちょっと行きすぎな気がします。
「逃げ込んだ先は、また別の内部。気づかないうちに、新しい世界の内側に、吸い寄せられているだけ。そうなんでしょ?」のセリフがあっただけに、もうひとひねりあるのかなと期待しましたが、意外とあっさり終わってしまった印象でした。

感想
私事ですが、「ありのままの自分」とか「自分探し」という言葉を聞くと、いつも懐疑的な気分になります。それは「ありのままの自分」じゃなくて「都合のいい理由」だろ、と。結局はそこにいる自分(=自分という現象)があるだけなんじゃないかと思っています。
その意味で、ラカンの鏡像段階理論は非常に面白いと感じますし、ゲームシナリオの元ネタでもっと使われればいいのに、と思っていました。フロイト・ユングの理論、精神分析理論はペルソナシリーズをはじめ色々なゲームがやっていますが、ラカン理論をテーマにした作品は少ないです。
FF13は「ファルシ」とか言いつつがっつりやっていて、シナリオも従来のFFメタとしては面白いのですが、専門用語乱発とシナリオの魅力不足のせいで、「パルスのファルシのルシがパージでコクーン」と揶揄られてしまっています。シナリオをゆっくり読めば理解はできますが、面白いかというと…という出来栄えで、率直な感想を言えば、俺は学問じゃなくてゲームがしたいねん、です。

一方、成功例として、インディーゲームのProjectMoon作品は、ラカン理論をゲームシナリオにうまく落とし込んでいます。「固着」「転移」といった精神分析基礎をはじめ、「大文字の他者」「ボロメオの輪」あたりの理論をゲームの世界観に巧みに組み込み、そのエッセンスを直感的にプレイヤーに伝えています。世界観のカギとなる超能力の名称が「Extermination of Geometrical Organ(幾何学的男根の根絶)」と書いて「E.G.O.(自我)」なのもめちゃくちゃ良いです。「去勢」=「欠如を受け入れることで、自我を確立できる」という世界観は「絶望の中であがく人間の姿を描くことが、人間賛歌である」というProjectMoon作品のテーマと非常にマッチしていました。
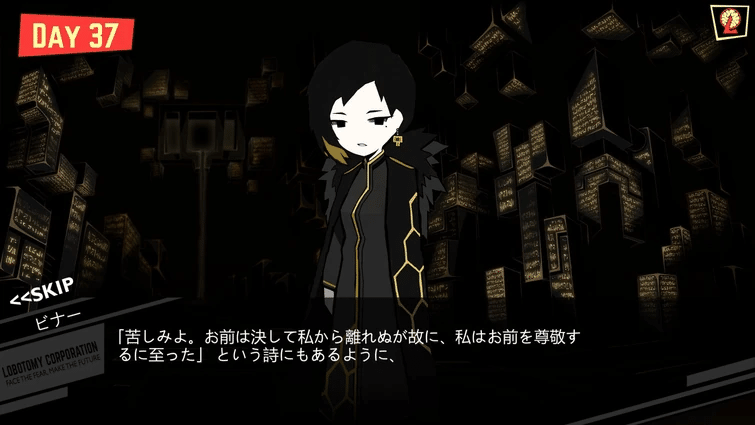
少々話がそれましたが、要するに「人の欲望とは他者の欲望である」というラカン的な世界観が、もっとゲームシナリオで擦られて欲しいと言いたかったのです。
そして、本作『Near-Death-Expedition』では、終乃りんねが鏡像段階を経て自我を獲得していく過程が描かれており、とても良かったです。最初にアバターによって身体を認識し、次に主人公の設定や言葉で自我が生まれていく過程は、繰り返しプレイしていて色々と考えさせられるものでした。AIが食事行為を受容できないゆえに、「趣味は美味しい保存食を探すこと」の設定を「かわいいキャラクターの非常食と一緒に居ること」と変換しているのも面白いです。

また、「終乃りんねと関わるな」という言葉を彼女に伝えるかどうかでエンディングが分岐するのも、巧みな構成です。
りんね訪問ENDでの主人公は「他者と関わりたい」という欲望を持っていました。そして「りんね」が、主人公の言葉を通じてその欲望を認識することで、死へと向かう終乃りんねを否定し、永遠の生を手に入れます。
一方、りんね削除ENDでは、おそらく主人公の欲望は「現実世界に帰りたい」です。「現実世界に帰ること」は「仮想世界で死ぬこと」と同じなので、これはフロイトの死の欲動に相当しており、「仮想世界の他者と関わりたい」と欲求する生の欲動と対称関係になっています。この主人公の死の欲動を律儀に反映したりんねは、エンディングで「自分を消してくれ」と言ってくるわけです。このルートでりんねが婉曲的に言ってることは「殺してくれ、さもなくば自殺するぞ」なので、希死念慮全振りというか、冷静に考えると相当サスペンスな展開です。このあたりの展開は、主人公の欲望と「りんね」の欲望がうまく鏡写しになっていて面白く、どう展開するのか読めないハラハラ感もありましたが、意外とあっさりと終わってしまいました。ネタバラシからエンディングまでの描写がもっと丁寧なら良かったなぁと感じます。

まとめ
PVやゲーム画面を見た限りでは『NEEDY GIRL OVER DOSE』のオマージュ作品と思っていました。しかし本作は、人気Vtuberになる過程や、やたら生々しいVtuberの裏側が丁寧に描かれていたり、Vtuberの存在論をテーマにしている点で、独自の方向性を貫いた良作だと思います。
逆に『NEEDY GIRL OVER DOSE』的な要素を期待していると肩透かしだと思います。プレイヤーの介入要素は少なく、メタフィクションにも寄っていません。ヤンデレ要素は共通してるけど とはいえ、2時間以下でクリアできるボリュームのうえ、『NEEDY GIRL OVER DOSE』が好きな人には刺さりそうな要素が多く、そういった方にもお勧めできそうな作品でした。
参考
確かに、好きな作者のインタビューを読むと、エヴァから影響受けている方々が多かった。あと筒井康隆が「素人は政治と精神分析学には軽率に手を出すな」と書いていたのを思い出した。
「ラカンが難しく見えるのは、前期・中期・後期ラカンを混同しているから」と教えてくれる名著。アカデミックな立場から、ひたすら学術的解説を行う著者のストイックさが際立つ。ラカン用語の理解におすすめ。
ProjectMoon作品の精神分析学的な考察として、非常にわかりやすくまとめられている記事。とはいえ、深く考察しなくても、ゲーム作品は抜群に面白い。ProjectMoonの新作『LimbusCompany』は絶賛無料配信中。
