
まとめ。シンガポールにおける「中華系の特権」に関する論争
昨年末辺りから人種と「中華系の特権」に関する一連の論文が、シンガポールで論争の的になっています。元々の論文はもとより、その後の学会や社会の反応が非常に興味深いので報告します。
2019年9月、南洋工科大の研究員のフマイラ・ザイナル博士が、同僚のワリッド・アブドゥッラー博士と共に「政治における中華系の特権:シンガポールの支配エリートに関するケーススタディ」(Chinese privilege in politics: a case study of Singapore's ruling elites)という論文を発表しました。Asian Ethnicityという、専門家の間では知名度のあるジャーナルからです。
↑論文へのリンク。
著者たちに言わせると、内容は以下のようなものです。
本稿は、シンガポール政治における中華系の特権に関するケーススタディを通し、特権という概念のニュアンスのある理解に貢献する。まず、理論的なレベルでは、特権の分析における政治的ヘゲモニーの重要性を強調する。第二に、実証的なレベルにおいて、シンガポールに言及しながら特権のアジアにおける文脈を調査する。私達は、特権の分析は、政権与党であり続ける人民行動党内部の階級的特権の分析と共に行われるべきだと主張する。なぜならば、人民行動党のヘゲモニーが、シンガポールにおける人種という概念の(社会的)構築、理解、包有に関して大きな役割を担ってきたからである。人民行動党の人種に基づいた政治へのアプローチは、意図せずとも中華系の特権を永続化し、また少数派の議会における代表性に矛盾をきたし、政府の(主張する)能力主義と(社会的に構築されている)中華系の特権の摩擦を生み出している。
ザイナル博士は私の修士時代のクラスメイトでもあるので、彼女がこの論文を発表するまでの過程は多少知っているのですが、比較的静かなものでした。論文掲載前のワークショップがシンガポール国立大で行われて、そのQ&Aにおいて、ザイナル博士たちと聴衆との間で「中華系の特権というのは妥当な概念なのか」という議論がありました。ですが、論文掲載後、1年ほど学会で彼らの論文について議論する人はいませんでした。
しかし去年の暮れ、つまり2020年12月、シンガポール国立大の社会学科の副学科長であるダニエル・ゴー教授とYusof Ishak Instituteの所長であるテレンス・チョン教授が、同じAsian Ethnicityから「シンガポールにおけるショートカットとしての中華系の特権:返答」("Chinese privilege" as shortcut in Singapore: a rejoinder)という論文を発表しました。ザイナル博士とアブドゥッラー博士が若手でマイノリティー出身であるのに対して、こちらの二人は中華系で学会での階級制で言えばもっとお偉い人たちです。
↑ゴーとチョンの論文。彼らの要約によれば、こんな論文です。
私達は、中華系の特権がシンガポール政治に存在し、それが長らく与党で有り続けている人民行動党のヘゲモニーによって永続化されているというフマイラ・ザイナルとワリッド・ジュムラット・アブドゥッラーの考えに反対する。結果的に、『中華系の特権』という概念がシンガポール政治の理解に有用だという考えにも反対する。(彼らの論文において)中華系の特権という概念は、特殊化されないままに非文脈化されており、人民行動党の長期政権の(人種的)結果を無批判にショートカットしている。これはシンガポールにおける反人種差別主義的な言説と理解を推進するには逆効果である。私達は著者たちが既存の政権与党の特権を中華系の特権と取り違えていると主張する。そして私達は、議会における与党と野党の人種的多数派と少数派は、コミュニティの指導者であると同時に国民的利益を代表せざるを得なかったとも主張する。
要は、ゴーとチョンは、「シンガポールには中華系の政治的特権というものは無い」という考えを同じジャーナルから発表したのです。客観的に見ると、年上の中華系の男性教員が、若手の男女の少数派研究員の意見を変えさせるために書いた論文です。
ですが、より知名度の高い学者が若手の意見を潰すような論文を発表したこともあり、(炎上商法的に)両方の論文がシンガポールの知識層に読まれることとなりました。
そして今月、NUSのリー・クアン・ユー公共政策学院のInstitute of Policy Studies(IPS)が8つの公開パネルを行いました。ダニエル・ゴーがコメンテーターをしていたパネルで、「中華系の特権」の有用性の問題が再度議論されました。
そこで、パネリストのひとり、メイ・リンファンが「この概念に触発された」「リー・クアン・ユーが生きていたらそんな概念は捻り潰していたわよ」と発言。
ここから先は
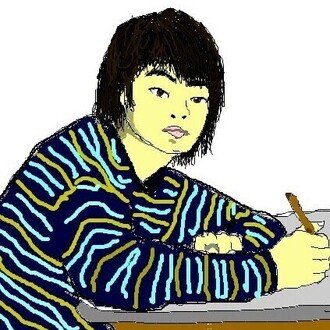
きしぉう博士のアジア研究ノート
きしぉう博士が書いたアジア研究や歴史学関連の2020年10月から2021年1月までの有料記事の全てが読めるマガジンです。
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
この記事が参加している募集
よろしければサポートお願いします。活動費にします。困窮したらうちの子供達の生活費になります。
