
『カゴメ—トマトの力で食文化を変えたパイオニア』後編調査ノート飲食業界編⑤全6話
「毎日飲んでいるトマトジュース。実は、その歴史には、日本の食文化を変えた壮大な物語が隠されているんです。」
――前編では、カゴメが1899年の創業当初からトマトの可能性を信じ続け、日本人の食卓に「トマト料理」や「トマトジュース」を根付かせてきた軌跡や理念を紹介しました。国内でのトマト普及に向けた奮闘、ケチャップやトマトジュースなどの定番商品開発、そして「自然を、おいしく、楽しく」という合言葉に象徴されるサステナブルな姿勢――どれも日本の食文化に大きな影響を与えてきたと言えます。
今回の後編では、さらに踏み込んでカゴメの海外展開や機能性食品の最前線、サステナビリティへの取り組み、競合他社との比較、そしてパーソナライズ栄養などの未来展望を深掘りします。あわせて、カゴメがどのように社員を育成し、社会と向き合ってきたのかにも注目してみましょう。私(ユキ)と“うさぎ先生”(闇の組織によってウサギの姿に変えられた元大学教授)の夜ふかしトークはまだまだ続きます。「日本の食卓をトマトで変えた企業」が、これから世界に何をもたらそうとしているのか――そのヒントを一緒に探っていきたいと思います。
前編はこちらから👇
●飲食業界編
①『食の未来を創る—飲食業界の全体像と代表企業』
②『ケンタッキー・フライド・チキン—11種類のスパイスが生んだ伝説』
③『タリーズコーヒー—シアトル発、日本流のコーヒーカルチャー』
④『サイゼリヤ—低価格×高品質を実現したイタリアンの魔法』
⑤『カゴメ—トマトの力で食文化を変えたパイオニア』
⑥『出前館—日本のフードデリバリー革命』
全6話でお届けします!
サイトマップはこちらから👇

1. 植物由来食品の強化と健康な食生活の提案
1.1 植物性たんぱく質や食物繊維などへの注目
健康志向や環境意識の高まりを背景に、ここ数年日本でも“プラントベース”や“代替肉”という言葉が急速に広がっています。牛肉や豚肉などの動物性たんぱく質を、大豆や豆類、キノコなどの植物性原料で代替する動きは欧米が先行していましたが、日本でも大手食品メーカーや外食チェーンが次々と参入しています。うさぎ先生はソファで耳をピョンと動かしながら、「もともとカゴメは‘トマトを中心に、野菜を活かした食品づくり’を得意としてきた企業だよね。だから植物性たんぱく質や食物繊維を活かした商品開発に取り組みやすい土壌があるんだよ」と語ります。
実際、カゴメの研究所ではリコピンだけでなく、植物性タンパク質の加工技術や食感再現などにも注目し、“トマトソースを活かした大豆ミートパスタ”や“野菜の旨味を活かすベジタリアンカレー”などを試作しているという報道もあります。私(ユキ)が「へえ、あのケチャップやトマト缶で有名なカゴメが、代替肉業界にも入ってくる可能性があるんですね」とワクワクすると、先生は「そうさ。カゴメの強みはトマトの旨味を使って ‘物足りない感’ を補うこと。例えば大豆ミートだけだと淡白になりがちだけど、トマトの酸味や甘味が加われば満足度を高められる。そこにイノベーションの余地があるんだ」と解説します。
植物由来食品を扱うにあたり、“食物繊維”の重要性も高まりつつあります。カゴメは以前から野菜ジュースで食物繊維の摂取を提案してきましたが、近年は“トマトの皮や種”など加工時に出る副産物を活かした繊維リッチな製品開発にも注目しているようです。先生は「単なる廃棄物ではなく、栄養価の高い成分が詰まっているから、有効利用すれば機能性食品として展開できるかもしれない。カゴメはそうした副産物の再利用でも先頭を走れる企業だよ」と耳をピョコピョコ。
1.2 ベジタリアン・ヴィーガン向け商品の拡充と背景
日本ではまだベジタリアンやヴィーガン人口は少ないといわれていますが、健康志向や動物福祉、環境保護などの意識が高まるにつれ、それらに対応する商品の需要も増えています。先生は「カゴメは ‘野菜を軸にした食品づくり’ が得意だから、動物性原料を使わずに美味しさや栄養を実現するのは比較的やりやすいはずだね。実際、ベジタリアン対応のパスタソースやトマト缶レシピをいくつも提案しているし、今後はこの動きが加速しそうだよ」と話します。
私が「大豆ミートや野菜だけで作ったトマト煮込みとか、家で簡単に作れる商品があると嬉しいなあ。ヴィーガンの友達が家に来た時にも助かりますし…」と言うと、先生は「そうさ。料理初心者でもトマトソースを使えば、それなりに味がまとまるのが利点。そこにカゴメが培った ‘素材の旨味を活かす技術’ を加えれば、ヴィーガンやアレルギー対応でも美味しく仕上げられるからね」と笑顔を見せます。
カゴメは今後“動物性原料フリー”の商品開発をさらに拡大し、家庭だけでなく外食向けやレストラン業界に向けてもアピールできるかもしれません。そうなれば日本の“野菜中心の食文化”がさらに盛り上がり、海外のヴィーガン観光客にも対応しやすくなるなど、広い社会的意義があると先生は言います。
1.3 多様化する食文化をリードするビジョン
以上の動きから見えてくるのは、カゴメが“トマトおよび野菜を通じて、あらゆる食スタイルに対応できる総合メーカー”へと進化しようとしているということ。先生は「日本では ‘朝食にパン派かご飯派か’ くらいの議論だった昔に比べ、今は『ベジタリアン』『フレキシタリアン(普段は菜食中心だが時々肉も食べる)』など、多様な食文化が広がっている。カゴメがその流れを捉えて対応策を出せば、さらに大きな市場を獲得できる可能性があるんだ」と語ります。
私が「確かに、トマトはどんな国でも使われる食材ですし、ベジタリアンにも適してるし、機能性もあるし…世界的に見ても強い武器になりますよね」と整理すると、先生は「うん。だからカゴメの‘多様化する食文化をトマトで支える’というビジョンは、理にかなっている。今後は海外展開も含めて大きな飛躍が期待できるね」と結びます。こうして見ると、“トマト=カゴメ”という定番イメージから、一歩先の新市場を狙う姿勢が感じられますね。

2. 食品ロス削減に向けた取り組みとサプライチェーンの透明性
2.1 食品ロス問題の現状と、カゴメが取り組む具体的な対策
日本では年間600万トン以上の食品ロスが出ているとされ、これをどう削減するかが社会的課題となっています。カゴメのような大手食品メーカーは、原材料の調達や加工、流通、販売といった各段階でロスを減らす工夫を行うことが可能です。先生は「カゴメが契約農家と密接に連携するのは、“作りすぎない・収穫時期を調整する”などで余分な生産を抑えられるから。さらに工場加工での廃棄を最小限にする技術開発も進んでいるらしい」と解説します。
例えば、トマトを搾る際に出る“皮や種”を副産物として何か活かせないか——飼料や肥料に再利用するだけでなく、機能性成分の抽出なども検討されていると言われます。私が「たしかに、リコピンは皮や種に多く含まれるって聞きますし、それをサプリメントに使うのもありかも」と思いつくと、先生は「そうさ。そうすれば廃棄物を減らしつつ新たな価値を生み出せる。カゴメはこうした ‘副産物活用’ の研究も積極的に行ってるんだよ」と補足します。
また、消費者サイドでも“使いきれずに捨ててしまう”というロスを減らすため、カゴメがレシピ提案や少量パック商品を展開する例も増えています。先生は「大容量トマト缶だと一度に使い切れない家族もいるから、小分けタイプにして無駄を減らす。これも食品メーカーができる工夫のひとつさ」と耳を動かします。
2.2 生産から消費までのサプライチェーンにおける透明性とトレーサビリティの重要性
カゴメは契約農家や自社農園でのトマト栽培を重視し、生産履歴を可視化して安全・安心の確保に努めています。先生は「これを‘トレーサビリティ’と呼ぶんだけど、どの農場でどんな肥料を使って育てられたか、収穫・加工の工程がどうなっているかを追跡できる仕組みだね」と解説します。近年は消費者の意識が高まり、「このトマトは国産? 海外産? 安全なの?」といった疑問を持つ人が増えているため、企業側の情報開示が求められているわけです。
私が「なるほど、カゴメは昔から農家との契約をしっかりしてて、そこが強みなんですね。品質管理もしやすく、ロスも減らせるし…」と頷くと、先生は「そう。しかも今後はIoTやドローンによる農地管理などを活用することで、さらに精密な生産管理が可能になる。カゴメが先進技術と伝統的な農業ノウハウを組み合わせれば、サプライチェーン全体がより透明かつ効率的になるだろうね」と耳をピョコン。
これができると、消費者は「カゴメが作るトマト製品はどこで育てたトマトで、どんな過程を経てここに来てるんだろう?」といった疑問にすぐ答えを得られます。その安心感がブランド力を高め、無駄なロスを減らすことにも繋がるのです。
2.3 地産地消やフードシェアリングなど、地域社会との連携
食品ロスを減らし、地域を活性化する手段として地産地消の取り組みも注目されています。カゴメは各地の契約農家との連携を通じて、地元の特産トマトを商品化したり、ご当地レシピを提案したりする試みを行っているという。先生は「例えば北海道や九州など、地域によってトマトの品種や味わいが違うから、それを活かした限定商品やイベントを企画している。そうやって ‘トマトを通じて地元を盛り上げる’ というスタンスさ」と解説します。
私が「たしかにその地域限定のトマトジュースとか地元産のケチャップってお土産にも良さそうですね。生産者にとっても販路拡大になるし、みんながハッピーかも」と盛り上がると、先生は「そうさ。さらに近年はフードシェアリングの仕組みを活用して、在庫品をお得に提供する動きも出てきた。カゴメも何らかの形で余剰品をシェアリングサービスと連携する可能性がある。 ‘作ったけど売りきれないトマトジュースを、アプリで割引販売’ なんて形でロス削減を目指せるね」と言います。
こうした取り組みは“SDGs(持続可能な開発目標)”への貢献にも繋がり、企業イメージ向上と社会的意義を両立できる利点があります。カゴメがこれからも地域やNPOと協力し、食品ロス削減やフードシェアを拡大していけば、日本の食全体がよりサステナブルになることが期待されます。
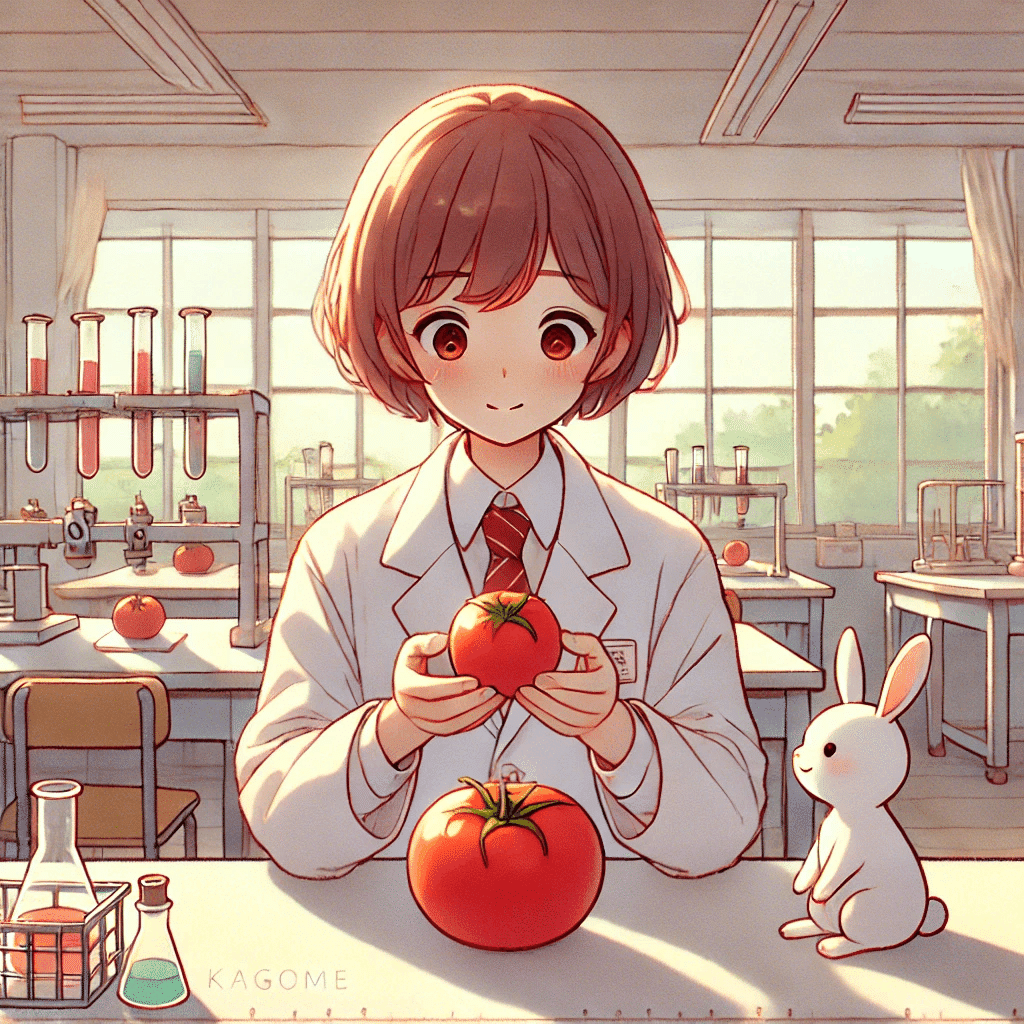
3. 次世代の健康食の研究開発と未来への展望
3.1 最新の栄養学に基づいた商品開発、そしてパーソナライズ栄養への挑戦
カゴメが機能性食品やベジタリアン向け商品の開発にとどまらず、さらに“次世代の健康食”へ挑戦しているのをご存じでしょうか。先生いわく、「研究所ではパーソナライズ栄養やゲノム解析など、最新技術を活用し、個人の健康状態や体質に合わせて最適な栄養を提供する試みを検討しているらしい。 ‘AIがあなたの健康診断データを解析して、このトマトジュースを勧める’ みたいな未来が来るかもしれないね」とのこと。
私が「SFのような話ですね。でもカゴメならリコピンやGABAなど、すでに機能性成分の研究に慣れてますし、一人ひとりの健康課題に合わせて配合をカスタマイズするジュースがあっても面白そう」と夢を膨らませると、先生は「うん。まだ制度上やコスト面の課題は多いが、将来的には ‘医療機関や健康保険組合と連携して、特定の病気リスクがある人向けトマトジュースを処方する’ といったシナリオもあり得るよ」と語ります。
加えて、カゴメはスポーツ選手向けの栄養補助食品を開発するなど、ターゲット別の商品展開も視野に入れているようです。たとえば「運動後のリカバリーに最適な野菜ジュース」や「美容にいい成分を強化したトマトサプリ」など、多様なニーズに応えることで売上を拡大しつつ人々の健康をサポートする路線を志向していると言えます。
3.2 食を通じて健康寿命を延ばすための取り組み、そして社会への貢献
日本は高齢化社会が進行しており、健康寿命をいかに伸ばすかが国としての課題です。先生は「カゴメは長年 ‘野菜をもっと摂りましょう’ と呼びかけてきたが、それは健康寿命の延伸にも直結する話だよね。野菜不足が生活習慣病を引き起こしやすくするという研究もあるし、トマトに含まれるリコピンは血圧・コレステロール・肌などに良い影響が期待される」と説明します。
こうした取り組みは単に製品を売るだけでなく、イベントやSNSを通じた健康情報の発信という面でも評価されています。カゴメの公式サイトには多数のレシピや栄養コラムが掲載され、食育や家庭向けの勉強会なども実施されているのです。私が「確かにカゴメのレシピサイト、以前利用したときに ‘野菜をたっぷり摂るメニュー’ がすごく充実していて助かりました。健康寿命を考えるなら、そういう地道な啓蒙活動が大事なんですね」とコメントすると、先生は「そうさ。社会貢献と企業の利益が両立できる典型例だ。健康になればなるほど、トマトや野菜ジュースの消費が増え、結果的にカゴメがもうかる仕組みが成立している」と笑います。
3.3 カゴメが目指す未来の食卓の姿
ここまで見てきたように、カゴメはトマトジュースやケチャップという伝統的商品だけでなく、機能性食品やベジタリアン向け商品、パーソナライズ栄養などの新分野に踏み込もうとしています。その先にあるのは、“一人ひとりに最適化された、サステナブルで美味しい食のスタイル”とも言えます。先生は「日本人がトマトを嫌わずに食べるようになったのはカゴメの功績が大きいが、今度は世界中の人々に向けても ‘トマトを軸にした健康食’ を普及させる可能性があるね。カゴメが海外で事業展開を強化すれば、トマトジュース文化がもっと広がるかもしれないよ」と予測します。
私が「確かに海外でも ‘日本式のトマトジュース’ や ‘和風ケチャップ’ が受け入れられるかも… 将来は海外店舗で ‘Kagome Restaurant’ みたいなのが展開されるとか…」と想像を巡らせると、先生は「夢が膨らむね。実際、海外でもカゴメのケチャップやソースを使うレストランはあるし、‘トマトの味がマイルドで美味しい’ と評判になったりする。気候変動や人口増の時代に、栄養豊富なトマトを安定供給できる仕組みを作るのは大きなチャレンジだけど、カゴメならやれる可能性があるさ」と耳をパタパタさせます。

4. 就職・転職の視点:カゴメで働くということ
4.1 多彩なキャリアパス(研究、開発、営業、海外事業)
前編でも少し触れましたが、カゴメは多様なキャリアを提供できる食品メーカーです。研究開発職としてトマトの新品種改良や機能性成分の研究をする道もあれば、商品開発部門で新しいソースやジュースのレシピを考案する道もある。さらに国内営業でスーパーや外食産業と取引を行う人、海外支店でアジアや欧米市場を開拓する人など、それぞれに専門スキルが活かせる場がある。
先生は「食品業界の中でも ‘トマトに特化’ しているからこそ、ニッチな研究開発や農業連携の知見が得られる。理系だけでなく、農学、栄養学、食品工学などの学生が興味を持つことが多い。また海外志向がある人にとっても市場拡大中のエリアで活躍できるチャンスがある」と語ります。私が「たしかに ‘トマトの専門家’ は世界的に見ても限られそうなので、研究面では面白そうですよね」とイメージを膨らませます。
4.2 社員教育と働きやすい環境
大手食品メーカーとして、カゴメは“働きやすい環境づくり”や“社員教育”にも力を入れているとされています。先生は「社内研修で栄養学や農業の基礎を学んだり、工場見学や研修農場で実習したりする仕組みが整っている。また若手でも新商品開発や海外展開プロジェクトに参加できるチャンスがあるなど、意欲次第で大きく成長できると言われるね」と解説する。
私が「会社によっては ‘専門部署に閉じ込められて仕事が単調’ なんて話も聞きますが、カゴメは横の連携が多い感じでしょうか?」と疑問を投げかけると、先生は「そう。研究と商品開発、営業とマーケティングなど、部門同士がコラボして新企画を生み出す例が多い。最近は ‘野菜ジュース+機能性表示+デジタルマーケティング’ みたいな複数分野の掛け合わせが鍵になるから、部門を越えた連携が求められるんだろうね」と語ります。
4.3 グローバル人材とダイバーシティ推進
カゴメは日本国内だけでなく、海外事業にも本格的に力を入れ始めています。したがってグローバル人材を求める動きが年々強まり、語学力や異文化理解、国際ビジネスのノウハウを持つ人材を積極的に採用する傾向がある。先生は「英語はもちろん、アジア圏向けには中国語やタイ語なども役立つかもしれない。現地法人でのマーケティングや現地農家との契約など、活躍の場は多いだろうね」と期待を寄せます。
さらにダイバーシティ推進の流れも加速しており、女性管理職の登用やワークライフバランスを実現する制度づくりなどが進められている。私が「食品メーカーって女性が多い職場のイメージがありますが、研究や工場勤務は男性比率が高いこともありますよね。その辺り、カゴメはどう取り組んでるんでしょう?」と興味を持つと、先生は「比較的、女性の活躍推進に前向きと言われる企業だよ。育児休暇や時短制度を整備し、復職後のキャリアも支援するなど、徐々に整いつつある」と耳を動かす。
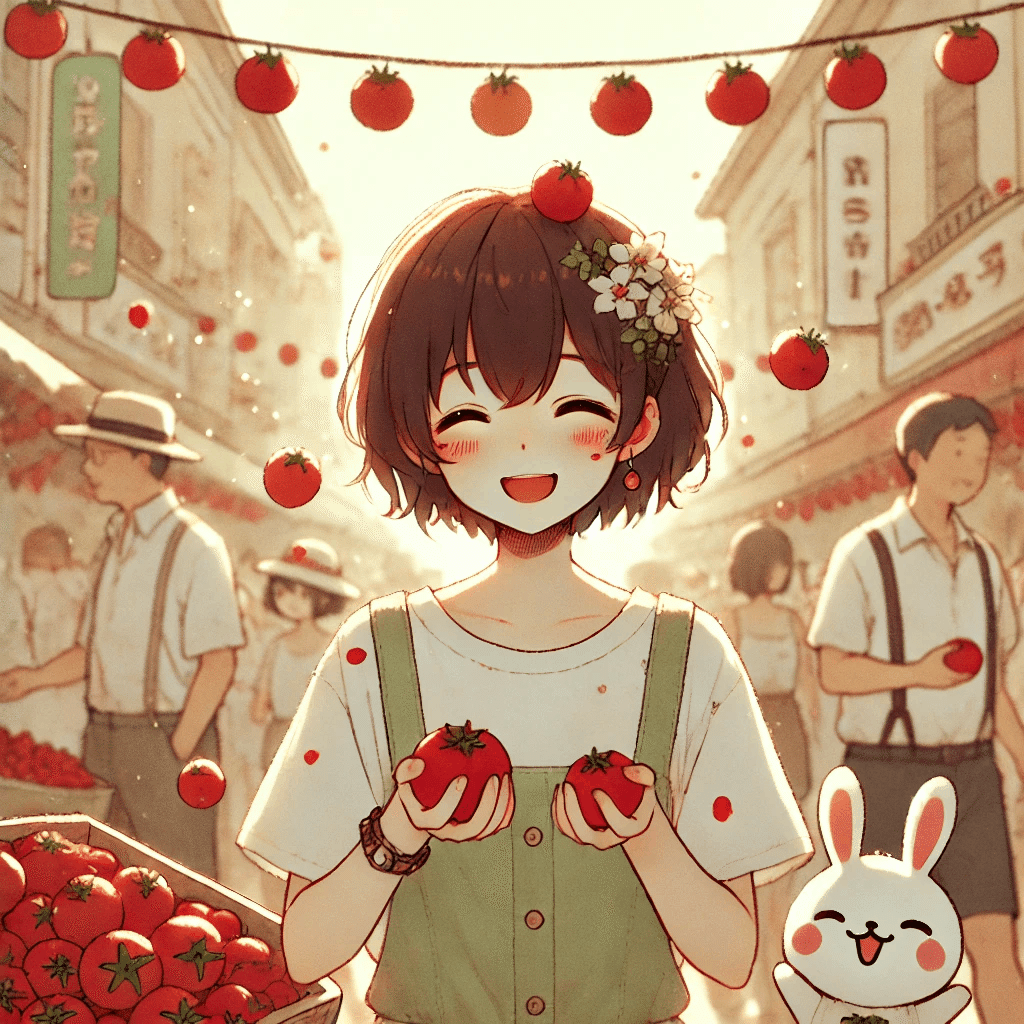
5. 今後の未来予測と総括:カゴメが食文化をどう変えていくのか
5.1 海外展開の加速と文化交流
前編・後編を通じて見てきたように、カゴメはすでにアジア市場への進出を強化している。特に中国や東南アジアなど、野菜ジュース文化がまだ成熟していない地域で “健康志向×トマト製品” を売り込めば、新たな市場を開拓するチャンスが大きい。うさぎ先生は「中国では ‘飲むヨーグルト’ や ‘豆乳ドリンク’ が普及し始めているし、野菜ジュースにも抵抗がない人が増えている。そこにカゴメのノウハウを持ち込めば ‘やさしい味のトマトジュース’ が日常的に飲まれる可能性があるね」と語ります。
また、西洋圏でもトマトケチャップが普及している一方で、日本らしい繊細な味付けや栄養設計で差別化できる余地がある。先生は「たとえば ‘日本の野菜ジュース’ がヘルシーでバランス良いと海外で評判になれば、海外の健康志向層を取り込める。コロナ後の世界でますます ‘免疫力’ や ‘栄養管理’ が注目されているから、活路は広いはず」と言います。
5.2 コラボレーションと異業種連携
食品業界のトレンドとして、飲料メーカーや外食チェーンとのコラボレーションが増えている。カゴメも過去に「トマトラーメン」などのレシピ開発でラーメンチェーンとコラボしたり、コンビニ弁当にトマトソースを提供する形で商品化したりといった例がある。先生は「これからは AIやIoT を活かして農業や物流をスマート化する動きもあるし、ヘルスケア企業やIT企業との連携で ‘トマトを軸にした健康管理アプリ’ なんて可能性もあるよね」と耳を動かします。
私が「トマトを通じていろんな食品とコラボしたり、外食チェーンのメニューを共同開発したりするのも面白そうですね。たとえばサイゼリヤと組んで ‘カゴメ監修の新トマトソース’ なんて…」と思いつくと、先生は「それは確かに魅力的だね。外食と食品メーカーの垣根が低くなっている時代だからこそ、カゴメがさらにコラボを増やすと新しい市場が広がるはず」と笑います。
5.3 食の未来――パーソナライズと地球規模の課題
最後に、先生は「カゴメが今後大きく寄与できるのは、地球規模の食料問題やパーソナライズ栄養の分野だと思う。『食べる人』と『作る人』をつなぎ、健康と環境の両方を守る。トマトの機能性をさらに高めたり、AI分析で個人に最適化した野菜ジュースを提案したり、やることは尽きないんだ」と総括します。
私(ユキ)は「それってすごくワクワクしますね。トマト一つから始まった企業が、今や世界の健康と環境に貢献できるポジションにいるなんて…『トマトで世界を変える』というのがSFじゃなく現実味を帯びてくるのか」と感激。先生は「うん。実際に ‘世界の飢餓問題をトマト技術で解決する’ とか ‘砂漠地帯でも育つ耐熱性トマトを開発する’ など壮大なプロジェクトに繋がる可能性もある。カゴメの歴史を見れば、新たな挑戦はやってくれるんじゃないかと期待できるね」と耳をピョンピョンさせています。
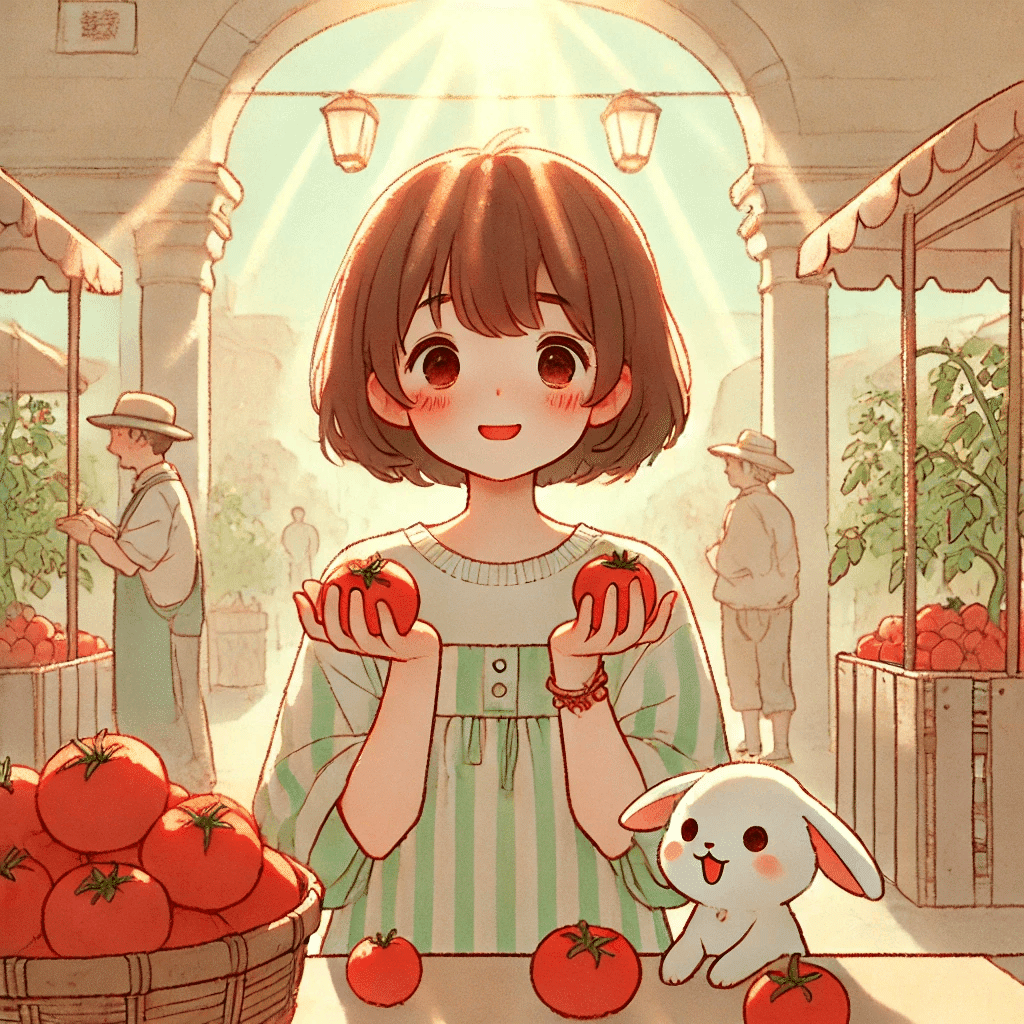
後編まとめ:カゴメが描く“トマトで世界を変える”未来
ここまでの後編では、カゴメの海外展開やプラントベース強化、食品ロス削減への取り組み、そしてパーソナライズ栄養などの未来展望について詳しく見てきました。前編が“トマトジュースを日本に広めた歴史や理念”を主軸にしていたのに対し、後編ではより先進的・グローバルな視点から“カゴメがこれからどのように食文化や健康、環境を変えていくのか”*というテーマを掘り下げたました。まとめると、カゴメが目指す未来は次の通りです。
トマト・野菜を通じた健康価値の訴求: リコピンやGABAなど機能性成分の研究を深め、さらなる機能性表示食品を拡充。個人の健康状態に合わせて最適な栄養を提供するパーソナライズ分野にも進出の可能性。
サステナビリティと農業・食品ロスの改革: 自社農場や契約農家と連携し、循環型農業や廃棄物削減に取り組む。副産物や搾りかすを活用する技術を高め、環境負荷の低い生産システムを作り上げる。
海外展開とローカル適応: 中国などアジア地域での事業拡大とローカライズを進める。欧米でも “日本の健康感” を打ち出し、トマト製品や野菜ジュースの新市場を開拓。
多様な食ニーズ(ベジタリアン、アレルギー対応など)への対応: プラントベース製品やベジタリアン向けソース・食品のラインアップを増やし、国内外で広がる特殊ニーズを取り込む。
食育・コミュニティとの連携: 子ども向けイベントや農業体験、学校給食などを通じて “トマトのある暮らし” “野菜を楽しむ文化” を普及。地元農家や自治体との協力で地域活性化にも寄与。
うさぎ先生は夜更けのリビングで、「ユキくん、こうして見るとカゴメは ‘トマトが好きだから販売してる’ というレベルを超えて、農業や栄養学、環境問題まで幅広くカバーしてる企業だよね。日本の食文化をここまで変えてきたのに、まだ次のステージを目指すというのは素晴らしい挑戦だと思わない?」と感慨深そうに微笑む。
私も「はい、食品メーカーとして ‘健康と食’ に正面から取り組む姿勢がすごく魅力的です。これまで何気なく飲んでいたトマトジュースの裏に、こんな壮大なドラマがあるとは…ますますカゴメを応援したくなります」と感心。先生は「うん、きっと多くの人が知らないだろうから、今回の記事で少しでも伝われば嬉しいね」と満足げだ。

専門用語の解説
パーソナライズ栄養
個人の遺伝子情報や生活習慣、健康データに基づいて最適な栄養やメニューを提案する手法。カゴメなど食品メーカーが応用すると、個々人に合った野菜ジュースやトマト製品を提供できる。プラントベースフード
植物性原料のみで作られた食品。動物性食材を使わず、大豆ミートや穀物で肉の食感を再現した商品などが代表例。カゴメはトマトソースや野菜で味を補うことが得意。食品ロス
まだ食べられるのに廃棄される食品。カゴメは契約農家との連携や副産物の有効活用でロスを減らす取り組みを推進している。トレーサビリティ
食品の生産・加工・流通各段階を追跡可能にする仕組み。カゴメは契約農家や自社農場で栽培したトマトの品質管理に活用し、安全・安心をアピール。地産地消
地元で生産された食材を地元で消費すること。カゴメは地域の特産トマトを活かした限定商品やイベントを企画し、地域の農家を支援している。フードシェアリング
余った食品をアプリなどを通じて割引販売し、廃棄を削減する仕組み。カゴメも余剰在庫の活用やコラボレーションの可能性を模索しているとされる。GABA(ギャバ)
アミノ酸の一種で、血圧を下げるなどの健康効果が期待される成分。カゴメのトマトジュースや野菜ジュースにも配合され、機能性表示食品として展開されている。機能性表示食品
科学的根拠に基づき、商品パッケージに健康効果を表示できる制度。カゴメはリコピンやGABAなどの成分で機能性表示を行う商品を展開している。サステナビリティ
持続可能性。環境保護や社会的課題解決を視野に入れ、資源を枯渇させずに事業を営む姿勢。カゴメは契約農家との連携や食品ロス削減でサステナブルな農業・食を目指す。パーソナライズ栄養
個々人の遺伝子情報や生活習慣データに基づき、最適な栄養を提案する形態。カゴメは機能性成分の研究を進めており、将来的に個別最適な野菜ジュースなどを提供する可能性がある。プラントベース食品
植物性原料のみで作られた食品。大豆ミートなどが代表例。カゴメは野菜加工技術を活かし、ベジタリアン向けソースや代替肉関連商品を開発する可能性が高い。ローカライズ(海外市場対応)
国や地域の食文化や嗜好に合わせて商品の味付けやパッケージを変更すること。カゴメは中国を中心に現地ニーズに合った野菜ジュースやケチャップを展開している。サイエンス×農業
AIやIoT、バイオテクノロジーを活かし、生産効率や栄養価の高い作物づくりを行う取り組み。カゴメは農業研究所や契約農家と協力してトマト栽培を最適化している。食育
子どもや消費者に対して正しい食の知識や調理方法、健康意識を啓蒙する活動。カゴメは学校給食への商品提供や食育イベント開催などを通じて “食の楽しさ” を広める。
次回予告
以上、第5話(後編)「カゴメ—トマトで日本の食文化を変えた企業」を締めくくります。前編ではカゴメの歴史・理念・功績を、後編では海外展開や機能性食品、サステナビリティ、そしてパーソナライズ栄養まで多角的に分析してきました。今や“トマトと言えばカゴメ”というほど日本の食卓に浸透した同社ですが、実際には健康・環境・農業・海外市場など多方面で未来への挑戦を続けていることが伝わったのではないでしょうか。
さて、飲食業界編もいよいよクライマックスが近づいてきました。次回(第6話)はデリバリー分野として「出前館—日本のフードデリバリー革命」を扱う予定です。Uber Eatsだけじゃない、日本独自のデリバリー文化を築き上げた出前館が、どのような戦略で市場を拡大し、ゴーストレストランやAI配送などの新潮流にどう対応しようとしているのか――外食から“一歩先” のフードテックが詰まった世界をのぞいてみましょう。
夜も遅くなり、うさぎ先生が「ユキくん、これでカゴメの話もひと段落だね。トマトを通じて日本の食生活を変えたって、改めて考えるとすごいよね。今度は出前館か…どんな革命が待ってるか楽しみだ」と微笑む。私は「はい、次回のデリバリー分野もめちゃくちゃ気になります。カゴメと出前館がコラボする未来なんかもあったりして…」なんて想像を膨らませながら、今日の執筆を終えるのだった。
出前館の記事はこちらから👇

サイトマップはこちらから👇

『うさ×ゆき』の支援をお願いします🙇
記事の購入やメンバーシップは余裕のある方だけで構いません。ストーリーで学べるコンテンツを幅広く使っていただける様にいいなと思っていただけた方はスキ❤️やシェアいただけると幸いです。
#眠れない夜に #歴史 #企業の歴史
#うさぎ先生とユキちゃん
#飲食業界 #学び #カゴメ #トマト #トマティーナ #GABA #トレーサビリティ
いいなと思ったら応援しよう!

