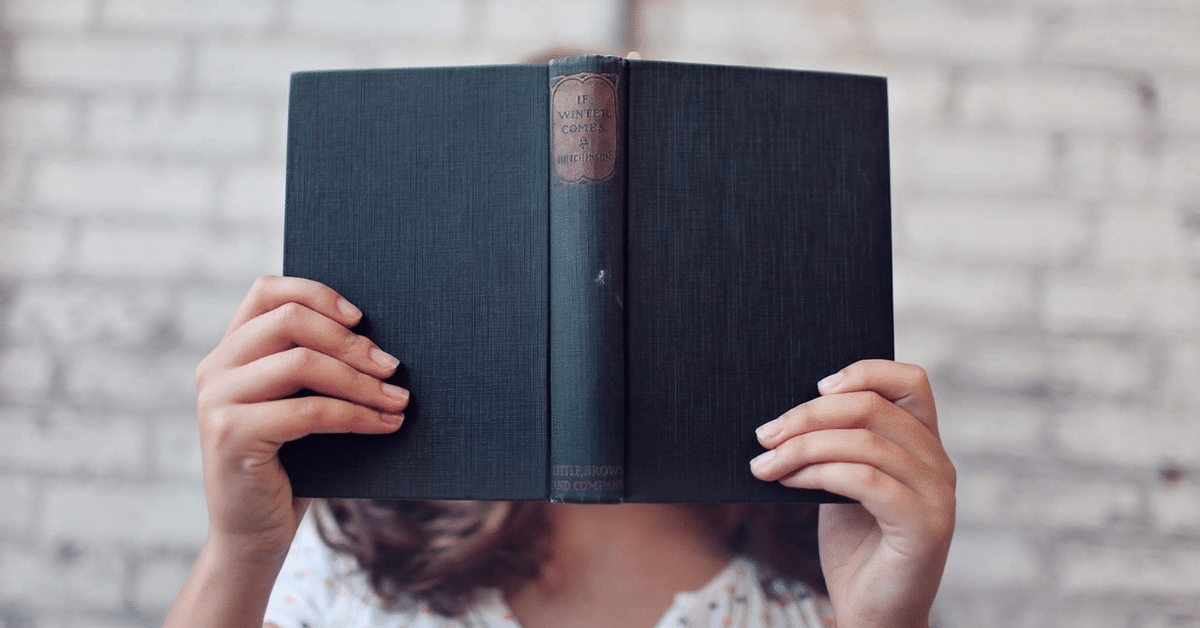
本屋で見つけた一番わかりやすい「黄帝内経」
中医学を勉強していてめちゃくちゃ読みたくなった「黄帝内経(こうていだいけい)」。
中医学の三大古典の一つで、紀元前770年〜221年以来の医学体験を記したもの。
紀元前770年〜221年は日本でいうと縄文〜弥生時代だって!
その頃にはもう医学書があったなんて・・すごいなぁ。
黄帝内経は「素問(そもん):医学の基本理論」と「霊枢(れいすう):臨床的な内容」の2つから構成されてて、
伝説の皇帝・黄帝が名医に質問・名医が回答する問答形式で書かれているもの。
難しい内容でも、問答形式で理解しやすいように工夫されてて素晴らしいなぁ。。
古典だけど、今でも中医学の基礎となっていると知って読みたくなり、都内一大きい本屋・池袋のジュンク堂本店に行ってきた。笑
黄帝内経を探してみたところ、たくさん解説書が出ていてテンション爆上がり。笑
1時間くらいかけて全部手に取って中身を読んでみたんだけど、個人的に一番読みやすかったのは・・・これ!!↓
東洋医学・鍼灸を志すものが一度は通る中国古典医学の源流をたずねて、ひとりでも多くの方々にと、現代にも通ずる養生法と治療法を説いた。
原書のもつ素朴さと鋭さを平易に解説した入門書。
初めて読む人のための、ってある通り、文章がわかりやすいし、良い意味で古典感、昔感がない。
例えば始めのページ。
黄帝が岐伯先生に問うのです。
「昔の人は百歳になっても元気だった。今時の人は五十歳になるともうヨボヨボだ。その理由を聞かせてくれ」
岐伯先生は次のように答えています。
①飲食に過不足がないようにすること。
現代にも通じる解答です。好きだからといって食べすぎてはだめです。
〜中略〜
②心身共の過労を戒める。
俗にいうストレスでしょう。最近西洋医学でもその重要性に着目してきた心身医学がこの時代にあったのです。
怒りすぎてイライラするとのぼせます。
のぼせると頭痛、不眠などになります。
↑ヨボヨボだ。とか可愛いし笑、「怒りすぎてイライラするとのぼせます」とか例えもシンプルに書いてある。
イメージがつきやすいからスルスル読めて面白い〜〜。
霊枢ハンドブックもあったんだけど、一旦素問だけ買った。
素問を読んでからまた見に行こうと思う。
来週からは漢方養生指導士の中級講座もスタート!
たくさん勉強するぞ〜〜(•̀ᴗ•́)و ̑̑
