
読書感想文:「首里の馬」は沖縄が舞台のSF(スコシフシギ)
2020年上期の芥川賞受賞作「首里の馬」を読みました。
沖縄に暮らす主人公が世界の端っこで身動きできない人たちとクイズを通して交流する話です。
身動きできないというのは、心理的ではなく物理的な状態です。
ひとりは海底、ひとりは戦場で幽閉され、ひとりは宇宙空間。
主人公はこの3人に日本語でクイズを出すという仕事をしています。
なんじゃそりゃ、と思いますよね。
私もそう思いました。
誰がお金を払ってるの、とか日本語での通信に暗号を含める可能性があるから許されないだろ、とか。
物語の中盤、主人公の家の庭にどこからともなく迷い馬がやってきます。
「なぜ?」と思ったのですが、「あ。そういえばタイトルに馬ってあるか」と納得。
途中、琉球競馬についてのウンチクが語られます。
走る速度ではなく、美しさを競う競技だったとか。
これってつまり、物語のなかの「馬」というのはかつて存在し消えていったものを象徴しているのでしょう。
終盤、主人公はクイズ出しの仕事を辞めることになり、3人から身の上話を聞きます。
もし映画化されるとしても、このシーンはあえて語りだけで済ませてほしいですね。
たどたどしい日本語による一生懸命の語りはかなりパワーのある場面になるはずです。
大事なことなのでもう一度。
映像化するとしても身の上話を回想シーンにはしないでください。
今のところ、映像化の話があるのかどうかわかりませんが。
あと、終盤「アメリカ横断ウルトラクイズ」についての言及があります。懐かしいのでイラストを描いてみました。
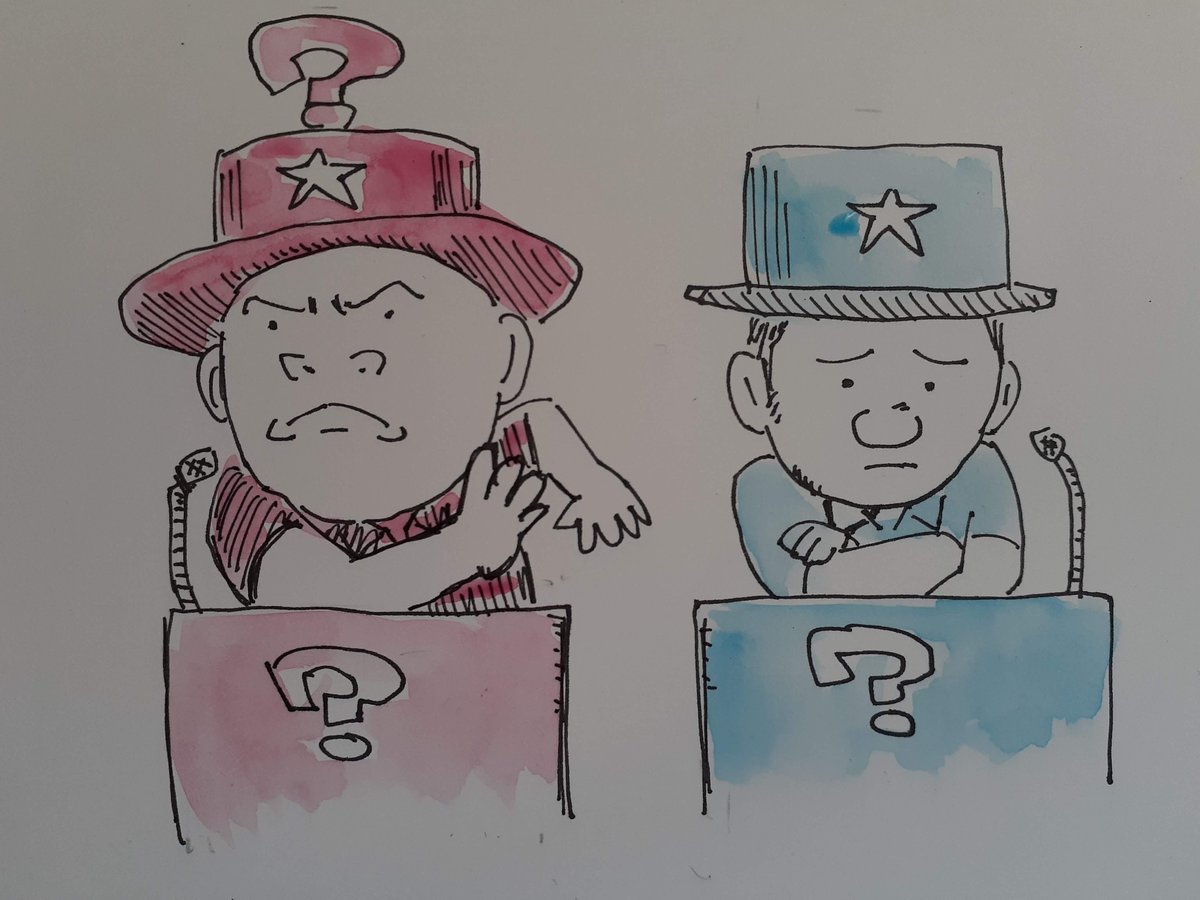
以上です。
いいなと思ったら応援しよう!

