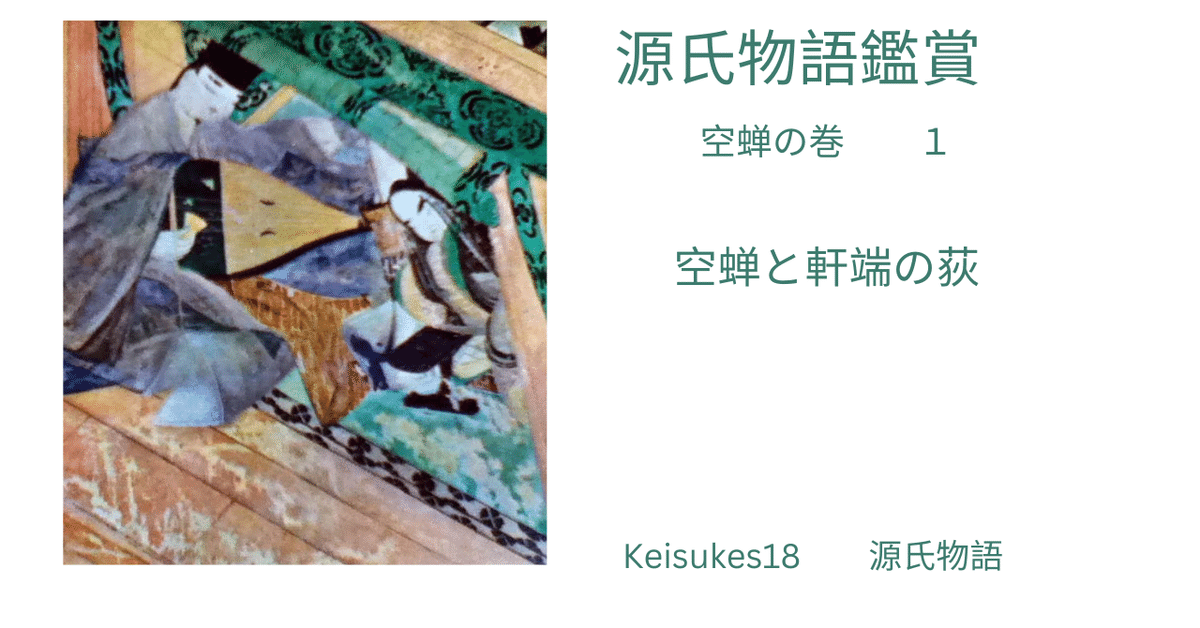
🔲 空蝉と軒端の荻「空蝉の巻」 1
空蝉の弟、小君の手引きによって、源氏は、中河にある伊予の介邸に再び忍び込み、偶然にも空蝉を垣間見ることができました。暑い夏の夜のことで、風を入れるために、いつもよりは開け放った様子なのです。
東の妻戸の辺りから中を見ると、火をともして二人の女性が、くつろいだ様子で碁を打っています。勝負も付いたようでその勝ち負けを話し合っているのです。女性たちのこんな様子をじっと見たことは初めて。源氏の好奇心は掻き立てられます。
奥の方にじっとしているような方が、思い人の空蝉。正面で少し騒がしいのが伊予の介の娘(読者が軒端の荻と名付けた)のようです。この二人、例のように対照的に描かれています。
空蝉は、顔を隠すようにして目立たぬ風情です。小柄で地味。手付きなどは、痩せている。でも、服装の趣味はとっても良く、繊細な心の持ち主のようです。
一方、軒端の荻は、全てあけっぴろげで隠すこともなくだらしないんです。大柄で色白でふっくらしていて大らかなんですね。髪なんかもふさふさして伊予の介の自慢の娘のようなんです。明るくって快活で愛嬌がある美人で、得意そうにふるまっているのです。
紫式部は、この二人の対照的な点を徹底的に描くことによって、空蝉という地味で目立たない人物像を明確にしているのです。頭はよくって機転が利き繊細な人物像を描くという事はとっても難しいんですよね。そんな空蝉という女性は、軒端の荻という華やかで少しお転婆な女と比べると、その存在感を際立たせて来るのです。対比によってのみ浮かび上がってくる女性といったらよいようです。
比較・対照は、貫之たちが和歌の中で磨いてきた技法でした。そんな技法が紫式部の人物描写の根源とかかわっているのでしょうか。
ところで、首尾よく、源氏が、手にしたのは、実は、空蝉ではなく、軒端の荻だったのです。源氏は、人違いに気づいたのですが、知らぬ顔で軒端の荻と次の約束をして帰ってきます。でも、心の中は、逃げられた空蝉への思いが募るばかり。脱ぎ棄てた空蝉の衣を抱きしめ恍惚とする源氏なんです。
可哀そうなのは、待ち続ける軒端の荻です。軒端の荻のような話って何かネタがあったのでしょうか。こういう物語・話を構想するのには、モデルがあったのでしょうか。知りたいものです。
ところで、空蝉という目立たぬ地味女。実は、作者の自画像ではないかなんて言う研究者もいるようです。繊細で頭の回転がよくすばしっこい女。顔立ちは良くないが頭の良いやり手の女性という事です。紫式部ってそんな物語作者だったのでしょうか。
