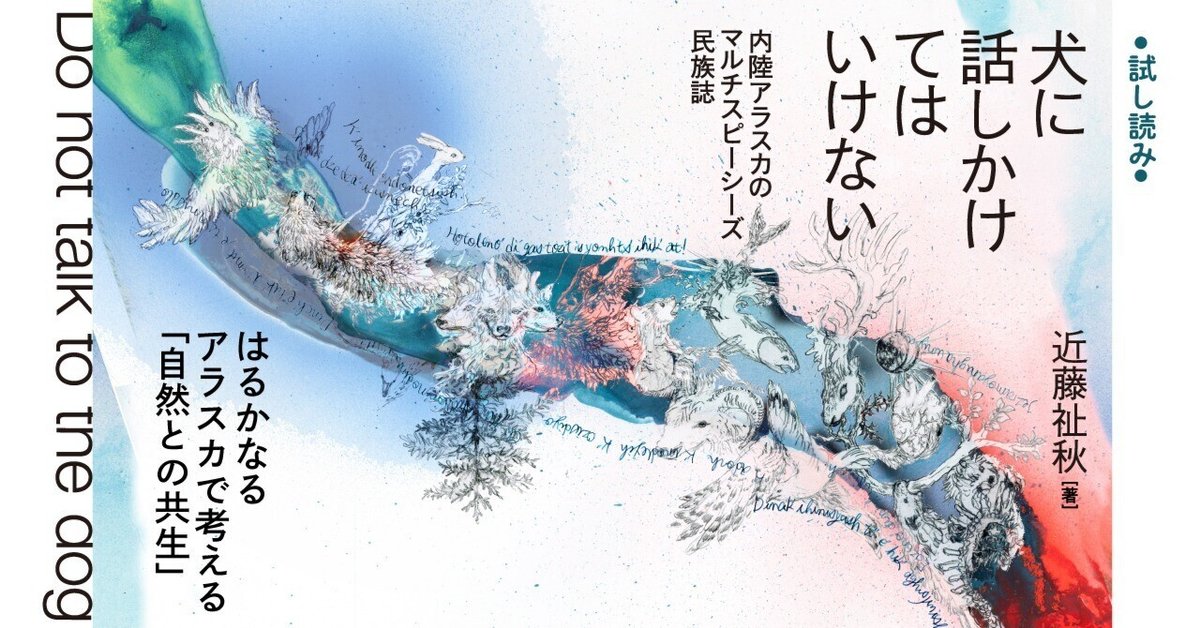
【試し読み】『犬に話しかけてはいけない――内陸アラスカのマルチスピーシーズ民族誌』はるかなるアラスカで考える「自然との共生」
かつて内陸アラスカには「犬に話しかけてはいけない」という禁忌がありました。その禁忌を破ると、病で人々が多く亡くなるような異常事態を引き起こすと昔は考えられていたそうです。なぜそのような禁忌があったのでしょうか。2022年10月中旬発売予定の『犬に話しかけてはいけない――内陸アラスカのマルチスピーシーズ民族誌』では、そういった禁忌や神話や日常の知恵を通して内陸アラスカの人々が実践する「自然との共生」について考えます。
ここでは、著者が先住民のダニエルとクスコクィム川を上ってニコライ村へとボートに乗るところから始まる冒頭を公開します。ぜひご覧ください。
※画像はすべて著者撮影
***
はじめに──ある日の野帳から
2015年夏のある日、内陸アラスカ先住民ディチナニクのダニエル・イーサイと私はボートに乗り、蛇行するクスコクィム川を上ってニコライ村まで向かおうとしていた。ボートは、風を切って進む。氷河から流れるシルト(沈泥)で、川の水は黄土色をしている。頰に当たる風が冷たく心地よい。ボートに乗る際にはあたりをうかがい、ヘラジカやクマといった野生動物にばったり遭遇しないか、流木などの危険物や良い薪となる枯れた立木がないかと目を凝らすのが日課となっていた。
その日、私はふと後ろを振り返ったとき、遠くの空に灰色の雲がかかり、雨が降っているようなかすんだ空模様となっていたのが見えた。風向きから考えてそろそろ私がいるあたりでも雨が降るかもしれない。使い込まれた金属製のボートは川での移動に適した平たい形状をしており、屋根もない。雨が降れば村までずっと雨に打たれたまま過ごすしかない。前を向いてボートの運転に集中しているダニエルに「雨が降るかもしれない」と告げた。彼は一瞬顔をしかめてうなずいたあと、何も返事をしなかった。案の定、雨雲は私たちに追いつき、小一時間ほど冷たい雨に打たれながら私たちは家にたどり着いた。
家に着くとダニエルから「君が雨を呼び寄せた」と小言を言われた。私はダニエルに雨雲が近づいていることを知らせたつもりでいたのだが、彼からすれば私が雨雲を呼んだのだという。ダニエルによれば、雲は人間の言葉を理解することができる。雨雲は、私の言葉を聞いて、こちらに向かってきた、というのが彼の見立てであった。ダニエルの言葉は、突然雨が降ってずぶ濡れになったことを私に責任転嫁するもののようにも思えたが、この言葉を聞いて、いくつかこれまでの調査で耳にしたことが頭に浮かんだ。

まずはダニエルの父である故フィリップ・イーサイが語っていた注意喚起の言葉である。フィリップは、現在の世界がいつか大きな洪水という災厄に見舞われることになると考えていた。というのも、人類はアポロ計画で月面に降り立つことによって、月を怒らせてしまったからだ。フィリップが先祖から聞いた神話によれば、あらゆる存在が人間の姿をしていたはるか昔、月は自分が殺した兄弟の死体を抱えながら天上に上がり、現在の月となった。月は自分のおこないを恥じており、人々から度を超えて注視されると恥辱に耐えられず洪水を引き起こす。ただでさえ、情緒不安定で扱いに困る月に対して、「白人」たちは土足で踏み込んでしまったのだ。いつ洪水に襲われるかもしれない世界で生きのびるためにフィリップの家族は村の中でも少し高いところにある坂の上に家を建てており、彼らが所有する野営地の土地も周囲よりも高いところを選んでいる。
もう一つは、クマ狩猟をめぐるものだ。2014年10月に、私はダニエルの甥たちとともにクマ狩猟に出かけていた。その場所はギンザケの遡上地であり、産卵して力尽きたギンザケを狙うハイイログマが現れるのを待ち伏せして撃つという狩猟方法がおこなわれていた。ダニエルの甥たちはこの時期、川の氷が張ってボートが出せなくなるまでの間、数回にわたって出猟することになっていた。しかし、ボートの故障などさまざまな事情があり、初回と2回目の狩猟行の間に10日間ほど日が空いてしまっていた。狩猟行に出かけるのが延期になるたび、私は村の男たち数人が共同で使っているサウナ(現地語では「ニンリー」と呼ばれる)で、「今日もボートが出なかった」と友人たちに報告していた。2回目の狩猟行では獲物の新しい足跡がまったく見つからず、クマはすでに他の場所に移動したのではないかという結論に達した。
その後、ある友人は酒の席で「君がクマについて話すことで狩猟パーティの運をまるつぶしにしてしまった」と忠告した。クマは人々が自分について話していることを聞いて、逃げてしまうのだという。村の猟師たちはクマ狩猟について女性の前で話すことを縁起が良くないこととし、「ボートに乗ってくる」というぼかした表現を使っていた。私はそのことを踏まえて、「クマ」や「狩猟」という言葉を使わずに話していたのだが、そもそもできるかぎり関連するようなことを気軽に口にしない方が賢明だと考えられているようだ。

これらの事例を総合すると、彼らは人間の言葉や視線が野生生物のみならず、気象現象や天体にまで影響を与えると考えていることがわかる。人々の周囲には数多の生ある存在が取り巻いていて、彼らの一挙手一投足はそれらが知るところとなる。ダニエルの甥であるアンドリューは以前こんなことを話してくれた。森の中を歩いていると突然誰かに見られているような気がすることがある。そのようなときは、「山の人々」と呼ばれる小人が人間を監視しているのだとされる。「山の人々」は、タバコや干し魚などの供物と引き換えに狩猟者に獲物を授けてくれる精霊であるが、同時にキャンプ地から物を盗んだり、子どもを誘拐したりすることさえある危険な存在でもある。
このような生ある存在がひしめきあっている世界では、どのようにふるまうのが正しい生存戦略であろうか。フィリップやダニエルといった年長者たちの言葉に照らして考えれば、それは不用心に異なる存在の世界に首を突っ込むのではなく、自重することである。人類学者マテイ・カンデアの言葉を借りれば、互いに「無為を積極的に生みだすこと」としての「相互—忍耐」の態度が求められていると言えるかもしれない。しかし、カンデアは科学者が「客観」的なデータを得るために観察対象であるミーアキャットを馴致しすぎないように考慮する点に着目していたのに対し、先ほど挙げたいくつかの事例では、人間の声や視線に敏感に反応する雨雲や月、小人といった存在に対して適切な距離を保つようなハビトゥスが念頭に置かれていた。内陸アラスカの事例を通して、「相互—忍耐」の思想をより精緻化していく必要がある。

哲学者のエマヌエーレ・コッチャは、呼吸を通じた世界との関わりについて以下のように論じている。「息を吸い込むとは、わたしたちの中に世界を到来させること、つまり世界が私たちの内にあるようにすること、息を吐くとは、わたしたち自身にほかならない世界に、自分自身を投げ出すことである」。世界は常に呼吸を通じて「混合」しつつあり、「相互の内在、あるいは相互に入り組むこと」を意味する「浸り」が生命の原初的条件である。呼吸をやめることはできない以上、私たちは世界への「浸り」を回避することはできないが、目を伏せ、声を抑え、息をひそめることはできる。
このような「浸り」の中で「息をひそめる」あり方は、環境倫理を考える上で示唆的である。一部の環境思想では、現代文明に生きる私たちが人間と自然の「つながり」を忘れてしまっているため、環境破壊が進んでいると論じられる。この理路から導き出されるのは、人間と自然の「つながり」を取り戻すことが何よりも重要という考え方だ。しかし、それは私にとっては見当違いの努力のように思われる。コッチャが指摘するように、わざわざ環境との「つながり」を求めなくとも私たちはすでに世界と「混合」している。ハイイログマが吸った空気をアンドリューも私も吸い、ヘラジカが飲んだ水が蒸発して、雨となり、ダニエルと私に降り注ぐ。
本書は、マルチスピーシーズ民族誌と環境人文学の視点から、アラスカ先住民の人々といわゆる「自然環境」との関わりについて考察することを目的としている。この作業を通じて、アラスカ先住民の知恵とは何かという問いに取りくみたい。
***
著者プロフィール

近藤 祉秋(こんどう しあき)
専門は、文化人類学、アラスカ先住民研究。博士(文学)。
共編著に『食う、食われる、食いあう――マルチスピーシーズ民族誌の思考』(青土社、2021年)、論文に「危機の「予言」が生み出す異種集合体——内陸アラスカ先住民の過去回帰言説を事例として」『文化人類学』86巻3号、「内陸アラスカ先住民の世界と「刹那的な絡まりあい」――人新世における自然=文化批評としてのマルチスピーシーズ民族誌」『文化人類学』86巻1号などがある
目次
はじめに――ある日の野帳から
第1章 マルチスピーシーズ民族誌へようこそ
現代人類学への道
マルチスピーシーズ民族誌の誕生
人新世と環境人文学――マルチスピーシーズ民族誌との関連から
第2章 ニコライ村への道のり
ニコライ村
フィールドワークの始まり
本書のおもな登場人物
個人主義的な人々?
徒弟的なフィールドワーク
フィールドワークの身体性
第3章 ワタリガラスのいかもの食い──ある神話モチーフを考える
トリックスターとしてのワタリガラス
神話は子育てによく効く?
犬の屠畜とワタリガラス神話
犬屠畜モチーフが他地域からもたらされた可能性はあるか?
〈ワタリガラス〉の犬肉食は、動物行動学で説明できるか?
〈ワタリガラス〉の犬肉嗜好モチーフは修辞戦略としてみなしうるか?
多種の因縁を語る神話
第4章 犬に話しかけてはいけない──禁忌から考える人間と動物の距離
ある禁忌の語りから
運搬・護衛・狩猟
犬ぞりの受容と二〇世紀初頭の変化
犬ぞりの現在
犬―人間のハビトゥス
第5章 ビーバーとともに川をつくる──「多種を真剣に受け取ること」を目指して
ビーバー論争
生態学・生物学と対話するマルチスピーシーズ民族誌
ビーバーとディチナニクの人々の関わり
ビーバーダムとギンザケ
ビーバー擁護派と反対派の二項対立を超えて
キーストーン種とともに考える
マルチスピーシーズ民族誌が目指すこと
第6章 「残り鳥」とともに生きる──ドムス・シェアリングとドメスティケーション
ドメスティケーションの周辺から考える
野鳥の餌づけ・保護・飼育
「残り鳥」と住まう
野鳥とのドムス・シェアリング
ドムス・シェアリングとドメスティケーション
第7章 カリブーの毛には青い炎がある──デネの共異身体をめぐって
北方アサバスカンの身体
共異体と社会身体
サイボーグ・インディアン
カリブーの民とオーロラ
巨大動物と超自我
ぬくもりの共異身体
第8章 コウモリの身内──環境文学と人類学から「交感」を考える
悪魔からロールモデルへ
目的としての「交感」と実用的な「交感」
生きものとの会話と非会話
「交感しすぎない」という知恵
おわりに――内陸アラスカ先住民の知恵とは何か?
マルチスピーシーズ民族誌の射程
各章の概要
アラスカ先住民の知恵
第三の道を探る
↓書籍の詳細はこちらから

#犬に話しかけてはいけない #近藤祉秋 #内陸アラスカ
#マルチスピーシーズ民族誌 #慶應義塾大学出版会 #keioup #kup
