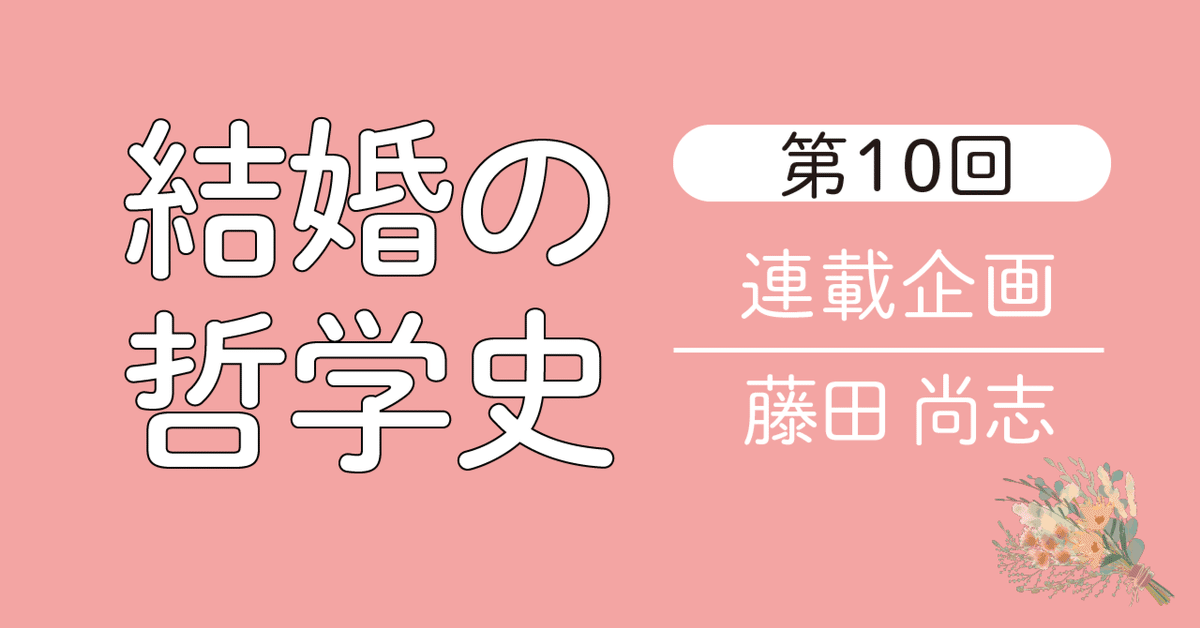
連載第10回:『結婚の哲学史』第3章 キェルケゴール 第1節 キェルケゴールの時代と生涯
結婚に賛成か反対か、性急に結論を下す前に、愛・ 性・家族の可能なさまざまなかたちを考える必要があるのではないか。昨今、結婚をめぐってさまざまな問題が生じ、多様な議論が展開されている現状について、哲学は何を語りうるのか――
九州産業大学で哲学を教える藤田先生による論考。今回から第3章、キェルケゴールの生涯とその思想を探ります。
↓これまでの連載はこちらからご覧ください
***
1.クライスレリアーナ――キェルケゴールとシューマン
「キェルケゴールと音楽」と言えば、『あれか、これか』第一部「直接的、エロス的な諸段階、あるいは音楽的=エロス的なもの」におけるモーツァルトの『ドン・ジョヴァンニ』論が有名だが、私としては「キェルケゴールとシューマン」を論じてみたい。調べた限りでは一つも研究論文が出てこなかったので、おそらくはまったく見当外れの試みなのだろうが、まずは辛抱強く耳を傾けてもらいたい。

セーレン・キェルケゴール(Søren Kierkegaard, 1813-1855)は、明確にヘーゲル的な弁証法を意識しつつ、自らの逆説弁証法を練り上げていった思想家である。客観性や共同体、自らを否定してくる〈外部〉と向き合い続けたのがヘーゲルだとすれば、主体性と神、自らを否定してくる〈内面〉と向き合い続けたのがキェルケゴールだと言える。
ロベルト・シューマン(Robert Schumann, 1810-1856)はドイツ・ロマン派を代表する作曲家であり、ベートーヴェンやシューベルトの音楽のロマン派的後継者として位置づけられる。吉田秀和が編訳したシューマンの『音楽と音楽家』から、ベートーヴェンに関する言葉を幾つか拾ってみれば、その関係性を感じ取ってもらえるだろう。シューマンは一方で、当時の「ベートーヴェン・ファン」の浅薄な熱狂ぶりに辟易しつつ、自らも称賛を惜しまないが、他方で “楽聖”とは違う方向を敢えて模索し、ベートーヴェンの中でも「冗談より愉快な」「ボタンをすっかり外した」銅貨狂騒曲のようなマイナーな側面に注目する姿勢を絶えず垣間見せてもいるのだ。
しかし今度という今度こそ、君らベートーヴェン・ファンの急所を抑えたぞ!――今後もし君らが、感激のあまり我を忘れて、「ベートーヴェンは常に無限なものを望みながら、塵の浮世を離れて、星から星へと飛んでいた」などと目玉をむき出して大見得をきるようなことがあったら、(…)僕はこの〔銅貨〕狂騒曲で君らを殴ってやる。(…)芸術の甦りの日に、真理の守り神が裁きの秤を手にとって、この銅貨狂騒曲を片方の皿に載せ、近頃の悲愴な序曲を十も束にしてもう一方の皿に載せたら――序曲のほうの皿は高々と天まではねあがるだろう。
ベートーヴェンの第九交響曲は、外面的に言えば、現存する器楽曲中、最大のものであって、これ以後は量と目標は汲み尽くされて、もう伸びる余地がないのではないかと思われた。(…)もちろんシューベルトはベートーヴェンの第九交響曲の道を続けて行こうとは夢にも思わなかった。彼は最も勤勉な芸術家であったから、いつも自分自身の泉から次々と交響曲を創り出した。
“楽聖”とは違う方向を敢えて模索しようとする意志というのは、例えば「事実ベートーヴェン以来、真に重要な進歩をしたものは、おそらくリート〔歌曲〕のみであろう」(シューマン 1958:184)といった言葉や、次のような指摘に表れているように思われる。
ベートーヴェンの曲を別とすれば、〔シューベルトの〕この曲ほど楽器の取り扱いが人の声と似ているものはない。しかも思いがけないところで、それが表れるのだ。(…)あたかも自分のいっそう控えめな力を意識していたかの如く、彼はベートーヴェンの後期作品に見られるグロテスクな形式と放胆な諸関係を模倣することを避けていた。
以上を踏まえれば、少なくともキェルケゴール/ヘーゲルとシューマン/ベートーヴェンを並行的に捉えようという私たちの企図の枠内では、次のような対比もあながち間違いではあるまい。ピアノ曲や弦楽四重奏もさることながら、やはり九つの交響曲で壮大な音楽世界を作り上げたのがベートーヴェンだとすれば、交響曲から合唱曲まで幅広い分野で作品を残したものの、特にピアノ曲や歌曲といった、より個人的なスケールの曲で真価を発揮したのがシューマンである、と。ベートーヴェンにおいては二つの主題が闘争し続けた果てに圧倒的な大団円に至るという構造的に確固とした形式が力強く聴き手を圧倒するのに対し、何かにせき立てられるように、せわしなく動き回るシューマンの音楽においては、多様な要素が混在し、さまざまな形式をとりつつも、その都度その形式の枠は移ろう和声によって大胆かつ軽やかに乗り越えられ、いわば破調によってシューマンが抱えていた心の闇が描かれるのだと。
文学的才能・仮名の使用
まずは大枠で並行性を認めてもらえたことにして、さらに細部に踏み込んでいこう。キェルケゴールはまずもって実存主義哲学の先駆者、キリスト教的な思想家・神学者として知られているが、その豊かな文学的才能によって多くの読者を得ている。シューマンも音楽的才能だけでなく、文学的な才能を遺憾なく発揮し、1834年には『新音楽時報』(Neue Zeitschrift für Musik)の創刊に携わるなど、音楽評論を精力的に執筆した。ショパンを評して言った(登場人物の一人オイゼビウスに言わせた)「諸君、脱帽したまえ、天才だ」という言葉は有名である。
キェルケゴールは42年の短い生涯に数多くの著作を刊行したが、今なお読み継がれている代表的な著作はほぼすべて仮名や偽名を用いて発表されたものである。シューマンは音楽評論を書く際に「ダヴィッド同盟」という架空の団体に属するフロレスタンやオイゼビウスといった人物を登場させ、異なるさまざまな視点を代弁させた。

〈父〉と〈最愛の女性〉
そしてシューマンにとってもキェルケゴールにとっても、〈父〉と〈最愛の女性〉が決定的な役割を果たしている。シューマンは裕福な家庭に生まれ育ち、書籍販売・出版業を営む父アウグストは彼が音楽の道を志すことに心から賛同していたという。彼が文学の才を早々に発揮できた一つの理由はこの家業にあるだろう。だが、彼の生涯にとってさらに重要なのは、もう一人の〈父〉フリードリヒ・ヴィーク(1785-1873)と、その愛娘でヨーロッパ中で喝采を浴びたピアニストのクララ・ヴィーク(Clara Wieck, 1819-1896)との関係である。クララとの恋愛と結婚は、シューマンの創作活動と密接に関連している。師でありクララの父であったヴィークは二人の交際に猛反対していた。ヴィークはクララに一人での外出を禁じ、シューマンはクララと会うことも、手紙のやり取りさえ禁止されていたが、秘密裡に文通を続けていた。クララはヴィークとともに演奏旅行に出かけていたが、コンサートでシューマンの作品を演奏し、「音楽によって二人は一体化した」(ブリオン 1984:188-189)。ピアノソナタ第一番、『子どもの情景』、『クライスレリアーナ』といったシューマンの代表的な作品は、クララとの結婚をめぐるヴィークとの闘いの日々に成立したものである。
1839年6月、もはやヴィークとの和解は不可能と考えたシューマンは、クララの同意を得て、弁護士に依頼して訴訟手続きを開始する。父親の同意なしで結婚できる措置を求めてのことであった。1840年8月、シューマンとクララの結婚を許可する判決が下され、ひと月後二人は結婚する。この1840年は、「歌曲の年」と呼ばれている。結婚を機に作曲家としての才能を爆発させたシューマンがこの年、多くの優れた歌曲を次々と世に問うたことに因んでのことである。
「わが肉の内なる棘(Paalen i Kjødet)」――父の罪
一方キェルケゴールの父ミカエルは彼が生まれた頃には裕福な毛織物商人であったが、元々はユラン(ユトランド)半島の教会の借家に住む貧しい農家の生まれであり、青年時代にコペンハーゲンに出て財を成した人物である。彼は荒地での惨めな牧童時代に神を激しく呪ったことに怯え、自分が一代で富豪になれたのはその“代償”なのだと考えていた。また先妻の死後、その下女だった女性を強引に身ごもらせ妻にしたが(3人の兄と3人の姉、そして末っ子のセーレンも含め、7人全員が彼女の子である)、神の前で愛を誓うこともなく妊娠させたことを罪として畏れ、そのような罪に対する神の罰として、子どもたちも短命に終わるだろうと悲観していた。実際、17歳のセーレンがコペンハーゲン大学神学部に進んだ1830年頃には、彼の兄2人と姉3人そして母が、世を去っていた。子どもたちに禁欲を強いる宗教教育を施したのは、そのような理由からであろう。キルケゴールが父から自分の過去と神への畏れを告白されたのはこの頃である。衝撃は大きく、彼もまた罪の意識を背負ったと思われる。セーレンの罪悪感(Brøde)と憂愁(Tungsind)の感情は、父譲りのものだと言える。その父も1838年に死亡する。
レギーネ体験――婚約破棄
父が死ぬ一年前の1837年5月、9歳年下(当時は14歳)の少女レギーネ・オルセン(Regine Olsen, 1822-1904)と出会い、やがてキルケゴールが27歳、レギーネが17歳になった1840年9月に婚約した。「しかし婚約の次の日に、私は過失を犯したことに気づいた。私のような懺悔者、私の経歴、私の憂鬱、それだけでもう十分であった」。一年後の1841年8月に婚約を一方的に破棄することになるが、その理由を彼は語っていない。婚約破棄の原因は何か。神への罪の意識、自身の呪われた生に引きずり込むまいとしたのか、それは生来の憂愁な性格なのか、性的・身体的理由なのか、真相は未だ謎に包まれている。レギーネはキェルケゴールに婚約破棄の撤回を求める手紙をしたためるなどしたため、キェルケゴールは『あれか、これか』や『人生行路の諸段階』などでレギーネを突き放そうと試みている。レギーネは5歳年上で以前彼女の家庭教師を務めていたフレゼリク・スレーゲル(1817-1896)と1843年に21歳で婚約し、1847年に25歳で結婚した。
シューマンが義理の父と決定的に対立しつつ、最愛の女性と結婚することで爆発的な生産力を得た作曲家であるとすれば、キェルケゴールは実の父から植え付けられた罪悪感と憂愁と向き合いつつ、最愛の女性と婚約破棄することで旺盛な執筆力を得た思想家である。
死
1842年に倒れたあたりからシューマンは幻聴や耳鳴りのために次第に作曲できなくなり、双極性障害など精神障害の症状に悩まされるようになる。1854年にライン川に投身自殺を図り、療養所で2年を過ごした後、1856年7月に46歳で死去した。危篤を知らされたクララは療養所のあるエンデニヒに赴き、シューマンの最期を看取った。
キェルケゴールはデンマーク教会の改革を求めた教会闘争の真っただ中にいた1855年の晩秋コペンハーゲンの路上で倒れ、その数日後に42歳で死去したが、その頃レギーネは、総督に任命されていた夫スレーゲルに帯同して、当時デンマーク領であった西インド諸島にいた。彼は兄宛ての手紙の形で遺書を残し、レギーネを「私のものすべての相続人」に指定していた。彼女は遺産の相続は断ったが、書簡類も含めた遺稿の引き取りには応じている。
《フモレスケ》
「キェルケゴールとシューマン」というこの節を締めくくるにあたって、シューマンの“キェルケゴール的”なピアノ曲を二曲取り上げておきたい。この二曲に関する考察は、音楽学者の広瀬大介が「トモシャ〔音楽之友社〕の誇るシューマン書籍群」とともに展開した考察に大きく依拠していることをお断りしておく。私の眼目は、この考察がキェルケゴールにも当てはまるものであることを指摘することにある。
《フモレスケ》は、既存の形式の枠では解釈することが難しく、全体の構成の捉え方が最も難しい作品の一つである。曲の成立はクララの父との「結婚闘争」の渦中にあった1839年であり、当時の友人への手紙には「《フモレスケ》はあまり楽しい曲ではない。おそらく私の作品の中では最もメランコリックなもの」と書かれているが、しかし、その曲にフモレスケと名づけている。シューマン自身の説明によれば、「フモール」とは「夢幻的」で「涙の下から微笑む」心であり、「フモレスケ」とはドイツの国民性に根ざした二つの特性「夢想的な熱狂とフモール」を一語で表現した概念である(前田 1983:35-36)。英語の「ユーモア」よりも広く、機知(ウィット)と耽溺・情緒、喜びと悲しみといった真逆の感情が絡み合い、ペーソスを湛えた幸せのうちに溶融したものと言えようか。
《クライスレリアーナ》
ここでもまた、①結婚と音楽の密接な関係や②偽名嗜好(架空の団体「ダヴィッド同盟」による座談会という形の音楽評論)が見られる。正式名称『クライスレリアーナ ピアノのための幻想曲集』は、E.T.A.ホフマンの小説に登場する「楽長クライスラー」から着想して、シューマンが1838年に作曲した8曲からなるピアノ曲集である。シューマンは自分より一世代上の作家ホフマンに傾倒しており、かなわぬ恋を描いたこの小説に自分とクララとの恋愛を重ねていた。先にも述べたが、この作品が生まれたのはクララの父ヴィークに結婚を反対され苦しんでいた時期であり、音楽の創作が唯一の救いとなってピアノ作品の傑作が多く生まれたのもこの頃である。未来の妻クララに贈られるはずだったが、なぜかショパンに献呈されたというのも実に興味深い。
広瀬によれば、《クライスレリアーナ》は変奏曲でも小品集でもなく、各曲それぞれの表現が自然と統一へとつながるやり方が見事に結実している作品の一つである。次のような作品の構成を見るだけでも、短調と長調、遅速するテンポが交互に繰り返され、その至るところにsehrが散りばめられ過剰さが強調されていることが見て取れる。
作品の構成
第1曲 Äußerst bewegt ニ短調 激しく躍動して
第2曲 Sehr innig und nicht zu rasch 変ロ長調 大変心をこめて速すぎず
第3曲 Sehr aufgeregt ト短調 激しく駆り立てるように~いくぶんゆっくりと
第4曲 Sehr langsam 変ロ長調 きわめて遅く~いくぶん動きをもって
第5曲 Sehr lebhaft ト短調 非常に生き生きと
第6曲 Sehr langsam 変ロ長調 きわめて遅くいくぶん動きをもって
第7曲 Sehr rasch ハ短調→変ホ長調 非常に速く~さらに速く
第8曲 Schnell und spielend ト短調 速くそして遊び心をもって
自らを「音の詩人」(Tondichter)と呼んだシューマンは、曲集を「遊び心をもって」諧謔(イロニー/フモール)的な音楽で結んだ。初めの主題へと戻り、全曲が閉じられる静けさの中で、諧謔と『子どもの情景』における子どものような天真爛漫が織り交ぜられている。
マルセル・ブリオン、井上和雄、そして広瀬大介の《フモレスケ》についての考察は、気分の分裂という点にだけ注目すれば、《クライスレリアーナ》にもあてはまるように思われる。ブリオンは、ショパンのピアノ曲を、上述したような目まぐるしい気分の「悲愴な分裂」の表現だとした。これに対して井上は、この曲はシューマンの分裂性そのものの表現ではなく、シューマンがその変容を楽しんでいることの表現だと捉える。分裂状態をそのまま並べているのではなく、分裂を美的原理に従って統御し、その内側に自立的な様式美を保っているものとして音楽で表現しようとするクリティカルな目が働いているのだ、と。この井上の主張に対して、広瀬がオープンエンドの問いかけとして投げかけている問いが私たちのキェルケゴール読解の紋章として役立ってくれるだろう。
作曲家はみずからのうちに、荒れ狂う激情に苦しむ自分と、それを外から冷ややかに見つめる自分を飼い慣らしているものだから。シューマン自身もそのような自らの二面性を、フロレスタンとオイゼビウス、というかたちで擬人化し、言葉に託し、そしてそれを音楽の世界でも描こうとした。/だが、それでも、シューマンの音楽には、そのようなクリティカルな視点、冷ややかに見つめる視点をかいくぐり、指の間からこぼれ落ちるなにものかがある。(広瀬大介「シューマンの音楽にひそむ「なにものか」を言葉にする3作」)
キェルケゴールの思想にも、彼自身の透徹したクリティカルな視点をかいくぐり、指の間からこぼれ落ちるなにものかがある。
次回:4月12日(金)更新予定
↓これまでの連載はこちらからご覧ください
#結婚 #結婚の哲学史 #藤田尚志 #連載企画 #ニーチェ #ソクラテス #ヘーゲル #シューマン #キェルケゴール #フーリエ #ドゥルーズ #特別公開 #慶應義塾大学出版会 #Keioup
