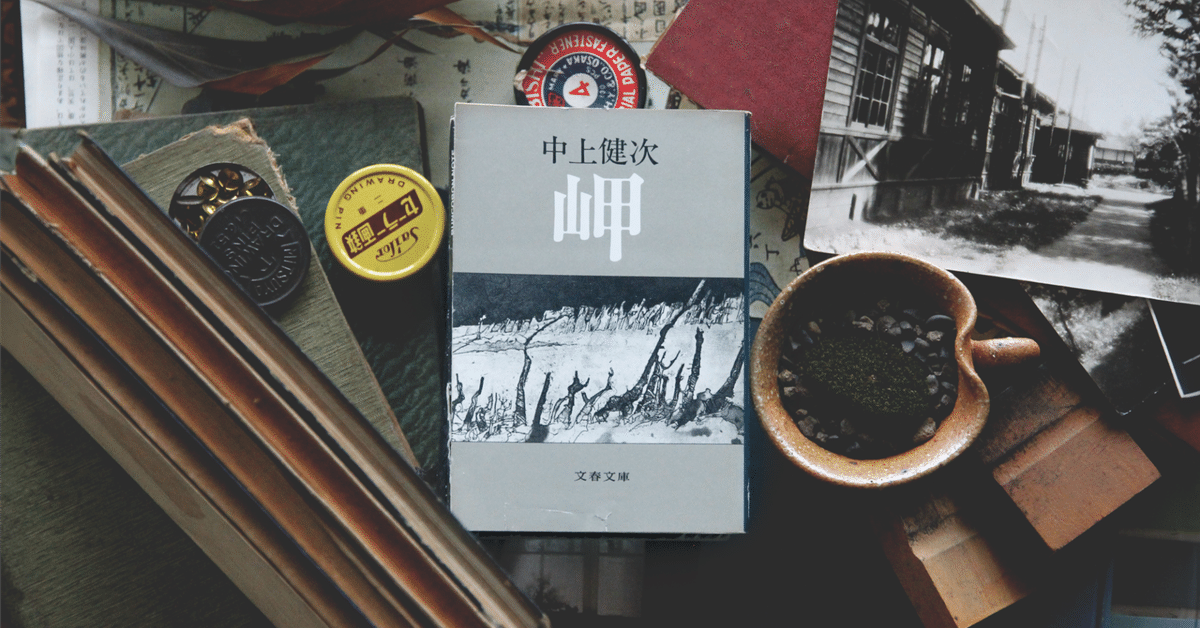
中上健次『火宅』冒頭を整理すれば読み始められる
今回は冒頭の話だけ執拗にしていこうと思うので言及する箇所だけ引用しておきます。
大きな体の男だった。いったいその男がどこからやってきたのか、誰も知らなかった。いや、狭い町のことだ。おおよその見当はついた。まず言葉だ。阿田和から木本、せいぜい行って尾鷲あたりらしい訛だった。男は、カーキ色のズボン、カーキ色のチョッキを着、ハンチングをかぶっていた。いつのことか忘れたが、母が、彼に、そう語った。その時、家のすぐそばを通る汽車の音がした。
「あれがよお」彼の兄が、男にむかって横柄な口をきいた。男は、外に立ったままだった。男は、裏の麦畑の脇につくられた溝に唾を吐いた。「あがってくれよお」と彼の兄は、いまにも涙を流しそうな顔で男に行った。「いや」と男は唾をまた掃き、手で口元を拭いながら言った。「またにする。それに今日のうちに、これからひとつやらにゃいかんことがある」兄は、家の外に出た。(後略)
能汁が出るのは二段落目。
「あれがよお」彼の兄が、男にむかって横柄な口をきいた。
これが二段落目の最初の文章。
なぜ能汁が出るのかというと、一段落目での約束が破られるから。
このとき、「ルール違反だ」としらける人もいるかもしれない。「おぅおぅどういう了見でぃ」と江戸っ子になる人もいるかもしれない。僕はといえばしばらく虚を突かれて、目の前で文章に嘲笑われているのに阿保みたいに静観した。
2ページくらい進んでから「はっ、これ混乱しちゃうやつだ」って思ったとき、また冒頭一段落目から読みなおし、仕切り直して読み進めた。どうしてだか面白いと思った。
早い段階で「面白いかも」と思える小説は貴重ですね。大きな事件、衝撃的な文章はなくとも最初から惹き込まれるって多分こういうケースもあるんだろう。違和感・混乱・一種の不快さ。そういうのもフックになる。
この記事では、一段落目と二段落目のごく最初の部分だけに話を絞って、「面白く読めそうだ」と思った理由について書いてみようと思います。
『火宅』において作者は自然に構築された読者との約束を蔑ろにしました。
物語の冒頭、一段落目を改めて引用してみます。
大きな体の男だった。いったいその男がどこからやってきたのか、誰も知らなかった。いや、狭い町のことだ。おおよその見当はついた。まず言葉だ。阿田和から木本、せいぜい行って尾鷲あたりらしい訛だった。男は、カーキ色のズボン、カーキ色のチョッキを着、ハンチングをかぶっていた。いつのことか忘れたが、母が、彼に、そう語った。その時、家のすぐそばを通る汽車の音がした。
この文章の内容は伝聞だと理解できる。約束と言ったら大袈裟だけど、これは読者と文章との約束の一つだと思う。
母が、彼に、そう語った。と書かれた時点で、「彼」という人物が、「母に」話を聞き、それを我々読者に伝えるということなのだろうと感じるわけです。理解するというより、無意識に了解してるって感じ。
ただし伝え方は、彼自身が語るのではなく、「何かしら思い出している彼を含めて語られる」らしい。これも頭で考える以前に了解する。
でも正直ちょっと納得いかない気もすると思います。素直に伝聞調で書いてくれたら良いのに、と思ったりする。
そんな風に思っているからかどうか分からないけど、何だか、彼自身の声が聞こえてくるような文章。彼自身が「男」を見て語っているようにすら見える。
いくら彼が語っているように見えても彼自身が語られる側。
「客体」であり、これは三人称小説で、この文章の声は、やたら肉声らしく聞こえるけれど、神とか作者とかの視点であることがとりあえず推測できる。
とりあえずここまでが「約束」で、二段落目でこれを蔑ろにされるから驚くのではないかと思います。
神の視点ということが理解できるなら、彼の兄と男のやりとりが始まる二段落目以降も混乱する必要はないと思うけれど、どうして混乱したんだろう。どうして約束が破られた、ルール違反だ、と被害者面をしてしまうことになるんだろう。
二段落目の冒頭以降の文章も改めて引用します。
「あれがよお」彼の兄が、男にむかって横柄な口をきいた。男は、外に立ったままだった。男は、裏の麦畑の脇につくられた溝に唾を吐いた。「あがってくれよお」と彼の兄は、いまにも涙を流しそうな顔で男に行った。「いや」と男は唾をまた掃き、手で口元を拭いながら言った。「またにする。それに今日のうちに、これからひとつやらにゃいかんことがある」兄は、家の外に出た。
単に場面が変わって、彼の兄と男のやりとりが描写されるだけのことなのだけど、混乱するように、一段落目に仕掛けてある。
大きな体の男だった。いったいその男がどこからやってきたのか、誰も知らなかった。いや、狭い町のことだ。おおよその見当はついた。まず言葉だ。阿田和から木本、せいぜい行って尾鷲あたりらしい訛だった。男は、カーキ色のズボン、カーキ色のチョッキを着、ハンチングをかぶっていた。いつのことか忘れたが、母が、彼に、そう語った。その時、家のすぐそばを通る汽車の音がした。
まず、男に関することは伝聞であることが一段落目でちゃんと示されている。母が、彼に、そう語った。のだから。ただし伝聞調でなく、聞いた男の話を思い出している彼ごと、次元の違う存在が語っていることも分かる。
男にまつわる出来事は母からだけ聞いたわけではないことも後に分かります。
冒頭だけの話をすると言ったけれど、ここだけちょっと引用させてもらいます。
ふっとまた彼は、子供のころの兄を想像した。その男を想像した。三人の姉や母や、いまの父に昔からくり返しくり返し聞いていたので、わけないことだった。
それにしても男の話は複数の度重なる伝聞によって、彼が想起する形で示されている、ということに変わりない。
なら、章を跨ぐわけでもない、ただの二段落目から始まる「彼の兄」と「男」の出来事も伝聞によって知り得たことを想起している、という設定が生きているはず。
しかしそれにしては内容が微に入り細を穿ちすぎているし、さっきも書いたけど彼自身が見て来たように書かれている。
だから、神の視点だから問題ないんだわ、と思いつつ、でもやっぱり彼の声がやたら残ってる感じがする。
それは何故かというと、やはり一段落目に仕掛けがある。
最後の文章がその仕掛け。
その時、家のすぐそばを通る汽車の音がした。
もしこれが映像作品なら、回想をひとまず終えた「彼」の顔が画面に映り、何か気付いたように窓の外を見るような表現になるかもしれない。少し遠くを見つめる彼の目が、汽車の音を探すような仕草をして、汽車の音が大きくなりながら暗転、場面が変わる、みたいな。
いやフェードアウトか。汽車の音が大きくなるのはちょっと不吉な予感がしてしまいますから、回想へつなげるという意味なら、音もだんだん小さくなった方が良い。まあいいかそんなことは今。
このような想像を文章からするわけだから、当然「彼の感覚」というものが以降に引き継がれることになる。
「彼が」「自発的に」「自分の感覚で」思いだした出来事が、以降語られるって僕らは自然に思う。神の視点だろうがなんだろうが、彼が彼の感覚で思いだす男のことを神は描写する。これも明言されているわけじゃないけど約束。
まとめると、伝聞ではあるが「男」のことを、彼の感覚で思い出している、というプログラムみたいなものが、読者の頭の中では自然に構築されている。
しかし二段落目以降、エピソード内に彼は不在だし、母も知りようのないことだし、ならば兄から聞いた話なのかとも思うがこの時点ではまだ保留。
読者はあくまで勝手にではあるが構築した約束を手に読み進めるわけだから、彼が「兄と男」の間に起きた出来事を知るにたる根拠を求めるけれどそれが示される前に兄と男の話は進んでいく。
だから、混乱する不親切な文章、と取ることもできるのだけど、このような書きだし方をすることでどんな面白さが発揮されるのかと言うと、以下のようになると思う。
一段落目で伝聞であることが示されており、彼は聞いた話をもとに「男」のことを思い出している。
汽車の音が云々という文章で一段落目を締めることで、想起の時間を一度終え、現在の彼に焦点を当てると共に、音を聞くという感覚を加えることで、「男と兄に関する出来事を自分で得た感覚のように想起する」という設定付けができる。
これに一瞬でついていくことが難しいので、二段落目以降、僕ら読者は「彼」の存在をなんとはなしに引きずったまま、彼も母も不在のエピソードを読むことになるので混乱する。
しかし「男と兄に関する出来事を自分で得た感覚のように想起する」という設定が一段落目で作り上げられたんだなと思えば、神の視点とは言えこれはあくまで「彼の感覚を持った神」なんだな、と了解できる。
彼の感覚を持った神というのは彼自身と言っても良い、のでしょうか。
分からないけどそう言い切るとして、もし「彼の感覚を持った神」が物語を語るのだとしたら、その狙いはなんだろう。
『火宅』は、そういう風に読み始めるとぐっと引き込まれる、んじゃないかなーって話でした。
