
詩誌『回生』製作のための新たな装幀の試み
詩誌『回生』は、今年2024年に2月10日に「が号」を発行したことを最後に、製作方法を活版印刷による印刷と手製本に変更しました。殊更、活版印刷という「ページ物」ではあまり使われない印刷方法を強調する気はないのですが、自分が努力して知識や技術を身につけながら会得した印刷方法なので、詩誌『回生』という詩の雑誌という主目的とは切り離して今回発行する「ぎ号」の装幀に関する製作のことを書き記したいと思います。
詩誌『回生』ぎ号の装幀に関しては寸法を除けば、これといった新しい試みはありません。もちろん、姿形は変わりましたが、
なぜかと言えば、
用紙

用紙は、ほぼ余り紙を使っています。表紙は、現実レコーズさんの「pocopen + koji shibuya『鬼火 / たのもしい王子』7" (maboroshi-03)」のジャケットに使った深山さんの「パルシャンホワイト フレースPRO」 の余り紙です。本文の「ビオトープGA FS ナチュラルホワイト 60kg」は、復刻版尾形亀之助『障子のある家』の見返しに使った用紙(45kgは本文に使った用紙)の余り紙です。誤植表の「プレインホワイト100g」は、ハグルマさんからだいぶ前に買ったもので、縦目だったので使い道が決まらずに放置されていた紙です。見返しの竹尾さんの羊皮紙スミ80kgだけが新たに購入したものです。竹尾さんの羊皮紙は好きな紙で、たびたび使ってきて慣れ親しんだ紙です。
コーティングされた光沢のある表紙の紙への印刷は、現実レコーズさんのジャケットの製作で、ある程度は印刷に際しての注意点を知っていました。インクが乾くまでに時間を要すること、印刷直後は他の紙に触れないように立てて乾かすこと、その後に合紙を入れて重ねて最低1月は乾かすことなどです。
見返し
見返しには、廃色となった竹尾さんの羊皮紙すみを使っています。当初は、本文用紙と同じ「ビオトープGA FS ナチュラルホワイト 60kg」を使う予定でしたが、どうも面白くないので、黒い紙にしようと思いつき、廃色となっていましたがネットで探し、最低必要な全紙判で6枚を購入して束見本を作ってみたら、とてもよい雰囲気でした。そして、そこに白のインクで造形を印刷したくなりました。
造形の製作は、2022年に曲線さんで行った展示「曲線的なアルゴ」で罫と格闘し、試行錯誤しながら展示作品や販売物を作ったことの経験が土台にあります。インクは白のインクに少し黄色を混ぜています。このことで、白の透明感が少し消え、紙の濃い色とのコントラストが増します(わたしが勝手に思っているだけかもしれません)。


印刷
印刷は、あえて印圧を強くして裏面に凹凸感が出るようにしています。活版印刷の職人の技術としては、凹凸感を出さないということが求められるのですが、それはやりませんでした。理由は、できないからです。名刺やハガキ程度の端物であれば、時間と手間をかけて苦労すればできないこともないかもしれませんが、その手間暇をきっぱりと省きました。ページ物ではわたしの技術や道具、機械では無理です。できないことをやろうとしないことは最初から決めていました。ならば、できることをやろう、積極的にやろうということです。


本文の用紙「ビオトープGA FS ナチュラルホワイト」は、弾力があり、表面がけっこうざらざらした紙です。なので、組版や胴張、用紙の少しの歪みでも、印字にムラが出やすい用紙だと思っています。しかし、印圧をかけると文字がくっきりと現れます。60kgの厚みだと、墨のインクの色が裏面から透かして見えることはあまりないだろうなと考えました。

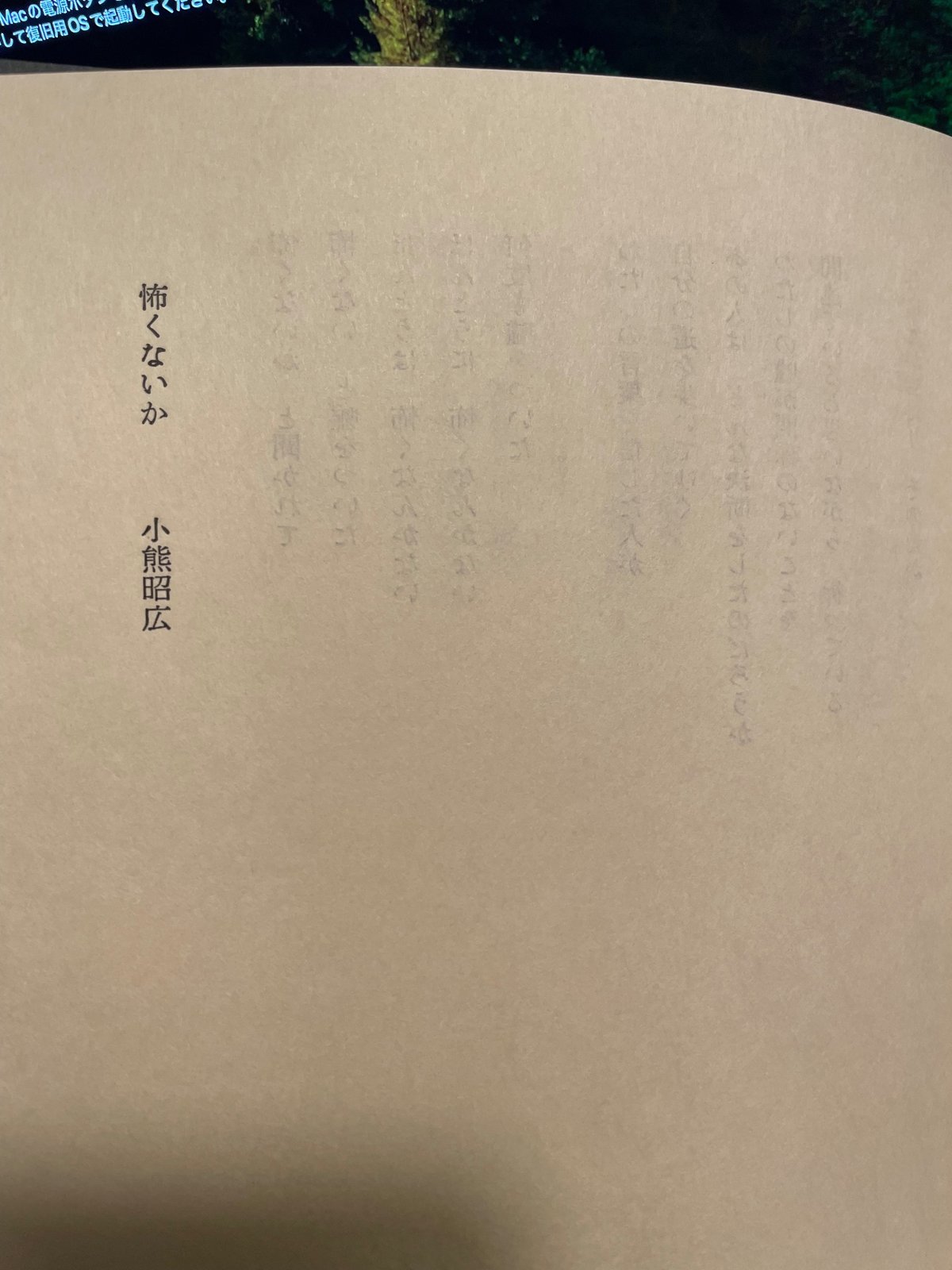

用紙の綴じ
用紙の綴じは平綴じです。これは、復刻版尾形亀之助『障子のある家』と同じ綴じ方です。綴じ穴を開けるためのスケール(厚紙で作った手製の簡単なもの)もその時に使ったものを使いました。表紙の糊付けも同じ要領です。違うのは、がんだれにしないで、表紙と本文を合体したら、天と地と小口を一気に化粧断ちします。
一番工夫したのは、閉じる前の用紙の重ね方、折丁の整え方です。書籍となると一般的には八つ折り(16ページ)や四つ折り(8ページ)の折丁を重ねて糸綴じするのですが、詩誌『回生』は単純に二つ折りしたものを重ねています。これを行うことで、全体のページの割り振りをあまり考えずに単純に作品を印刷して次々に重ねてゆけば冊子ができあがります。途中に割り込ませたいときは、ページ数に子番号を割り振れば問題はありません。

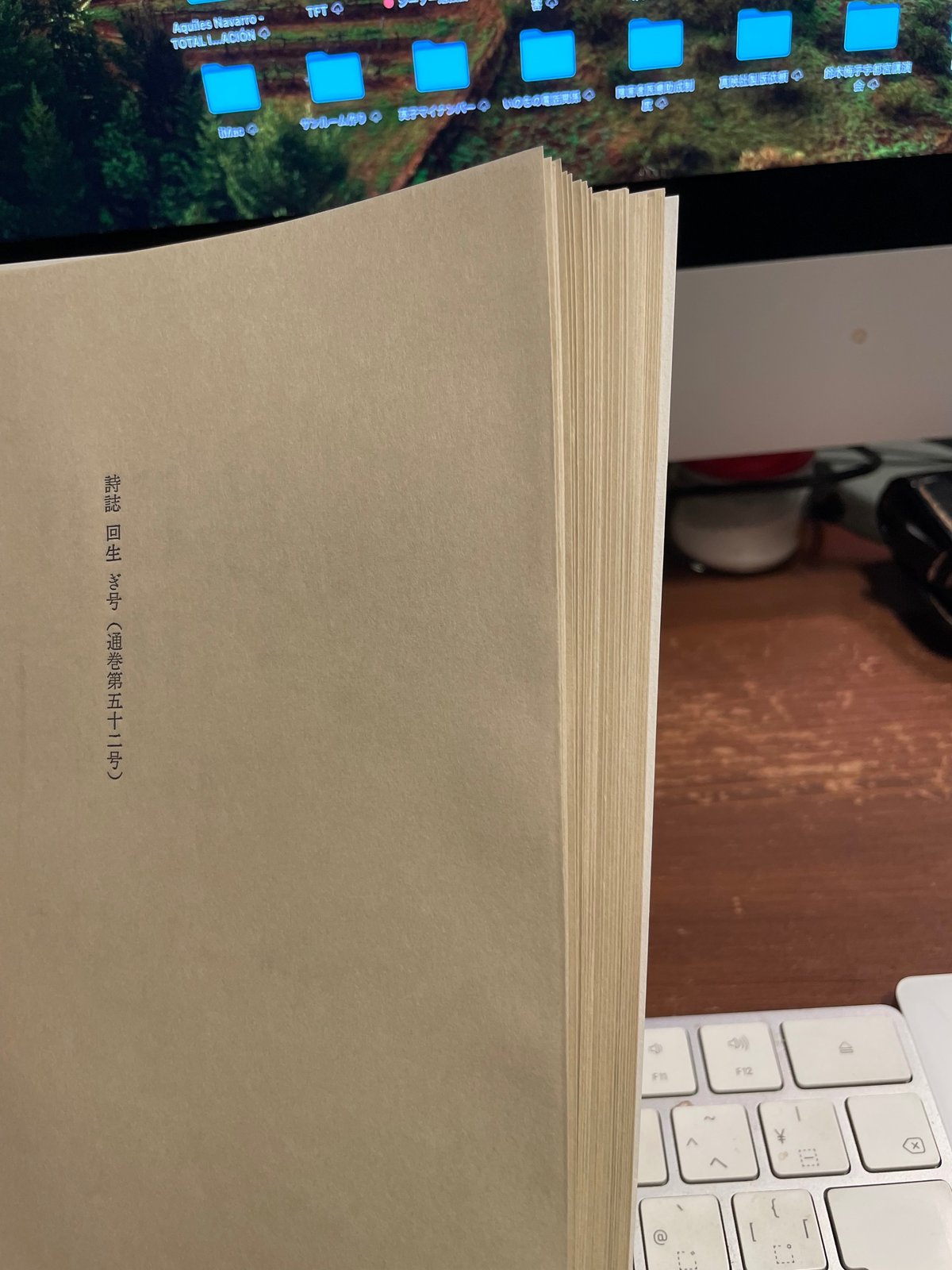
最後に
結局、これまでわたしが何年も行ってきた作業の積み重ねを無駄にしないようにした結果がこの詩誌『回生』ぎ号に現れています。そんなに新しい取り組みはしていません。
この note では装幀のことばかり書きましたが、基本的には詩があっての詩誌です。では、詩とは何か、となるのですが。わたしの考えは、文字や言葉だけではないということです。ですから、書かれている文字や言葉、その用紙の質感、さらに冊子の形や色合いやだらしなさ、収められている形、それら全体があって一つの詩誌にとしての存在が生まれるということかなということです。
今回は、30部しか作ることはできませんでした。何のための印刷かを考えると、それは多くの人に読んでもらうための印刷です。製本は、中身を守るためにある技術です。それが基本だと思います。次回は、50部作れたらいいなと思っています。
※蛇足
わたしはテキンという簡易な手動式の印刷機で紙一枚々々、一つのページずつ印刷しています。それを糸で綴じ、表紙で包み、冊子にしているわけです。一般的に「ページ物」とは、面付けして一度に両面16ページとか、8ページとかを印刷することで、わたしはそうしているわけではありません。わたしがしていることを「ページ物」と言っていいのか、甚だ疑問ではあります。言うとすれば、ただ単に冊子を作っている。と言うことだと思います。
