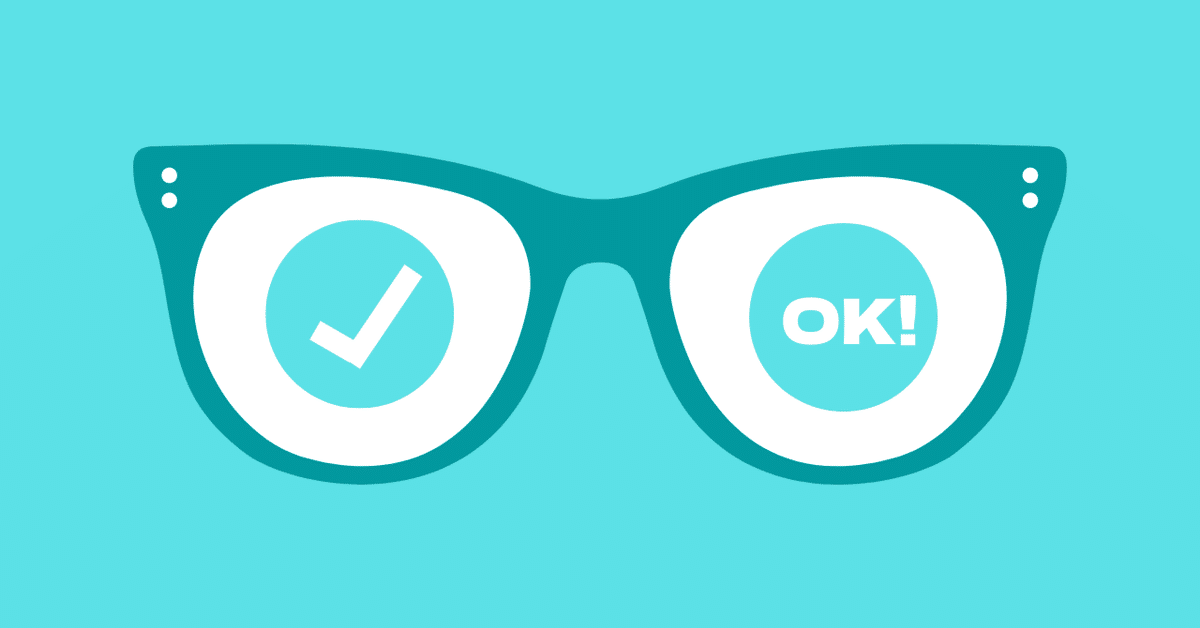
【書評】固定観念というメガネを外すには『THINK AGAIN』
認知バイアス(先入観・固定観念・思い込み)は誰もが持っている。
それは当然のことで「個人個人の世界観」でもあるからだ。1つの事象に対してどう感じ、何を思うかは誰もが違う。誰しも自分だけのレンズで世界を覗いているが、年齢とともにバイアスは強度を増していく。近視眼的になり、やがては盲目になってしまうこともある。
他人の意見を聞かず、頑固で絶対に自分の意見を曲げない老人を思い浮かべてみるといい。自分が盲目であることにすら気付いていない。まさに「盲目であることに盲目」な人もいる。
私も例外なく「認知のメガネ」によって考え方が近眼となり、柔軟性が乏しくなっている。自分に自信を持っている性格なので、その弊害ともいえる。
「俺の考えは正しい」
その自信は大いに結構だが、ただの自信過剰である可能性は否定できない。誰しも自分のことを特別視してしまうのが「ダニング=クルーガー効果」だ。
「ダニング=クルーガー効果」
自分に対する過大評価のこと。人は能力が欠如している時、自信過剰になる傾向がある。
また、自信というものは新たに何かを学ぼうとする時、そしてもっと自分を成長させたいと思うなら、とんでもない足枷になってしまうものだ。
そんな問題意識が芽生え始めた時に出会った本を紹介していきたい。それが「THINK AGAIN 発想を変える、思い込みを手放す」という本だ。
「脳の処理速度」が速いからといって「柔軟な思考の持ち主」であるとは限らない。人は疑うことの不快感よりも、確信することの安心感を好む。既存の考え方を新たな観点から見つめ直すことがいかに大事であるか、それを伝えるのが本書の目的である。
思考力と柔軟性はトレードオフの関係にあると本書は述べている。また『変化の激しい時代では、信念を柔軟にリニューアルする必要がある』とも。つまり考えることよりも考え直すことにこそ思考能力の本質がある。
私たちの思考様式は、「牧師」「検察官」「政治家」と言う3つの職業の思考モードに無意識的に切り替わる。すなわち、自分の信念を貫くこと、他者の過ちを指摘すること、多くの支持を獲得すること。そのことに没頭するあまり、自分の見解が間違っているかもしれないなどと再考しなくなる。柔軟性を持つために必要なのは「科学者」の思考モードである。
SNSには「牧師」や「検察官」や「政治家」の発言をする人で溢れているし、私自身もそうだ。「科学者」のようにデータを重要視して俯瞰して考えること、自分が間違っているときには素直に認めること、試行錯誤して発想を作り変えることを意識して行動しなければならない。本書では「科学者」になるために必要なことを次のように述べている。
まずは知的に謙虚であること。つまり、無知を自覚することから始まる。
自信に満ちた謙虚さを持つバランスが重要。そのためには、自分の知識に対してではなく自分の学ぶ能力を信じ、確信を持つよりも自分の無知を自覚することである。自分のやり方を疑っても、自分には学ぶ力があると確信する姿勢を持つ。
科学者の思考モードを維持するためのカギは、自分の信念をアイデンティティから切り離すこと。固執を分離するためには①現在の自分を過去の自分から分離する②自分の意見や考え(信念)を自分のアイデンティティ(価値観)から分離する。
自分の信念や見解を頻繁に改めるのは悪いことではない。それを悪いと思うことこそが固定観念にすぎない。個人を形成している価値観はブレず、信念をアップデートしようとする姿勢こそが大事なことなのだ。信念を変えるためには、主義主張の異なる他者に耳を傾けることが手っ取り早いと本書は言う。
自分に同調してくれる人よりも、自分の見解に意見してくれる人からより多くを学ぶことができる。
また情報に対して健全な疑問をもつことも重要だ。
健全な懐疑心と探究心を育てるためには、事実かどうかを検証する。①情報をそのまま受け取るだけではなく、くまなく調べる②信頼性の格付けや評判で判断しない③情報の発信者は必ずしも情報源ではないことを理解する。
私もSNSやニュースに対して鵜呑みにしないように気をつけている。その際にポイントになるのは、情報が「データがある事実」なのか、それとも「個人的な主張」なのかを判断すること。
他にも本書には素晴らしいエッセンスが多くあり、もう一つ紹介したい。
人は、他者の行動や考え方を変えることはできない。人々を変えようとするのではなく、自力で変われるように動機を見つける手助けをする方がずっと効果的である。説得よりも、相手への関心と共感を伴う傾聴が大事。
「分かってくれない」なんて当然のことなのだ。上から目線で変わってくれることに期待するよりも、本書でいうところの『ダンスするように相手と一緒に変わっていく』方が遥かに建設的である。
400ページ以上あるが、本の評価は文句なしの★★★★★満点。
心理学の権威である教授が執筆した本で、アップルのiPhone制作秘話などの具体例が数多く盛り込まれており、内容も理解しやすい。
もしも歪んだ認知を変えたいと思うなら、自分の世界を広げたいと思うなら、購読をおススメする。本書を読めば「認知のメガネ」をかけ替えて、視界をクリアにすることができるだろう。
#書評 #レビュー #内容紹介 #THINKAGAIN #心理学 #読書の秋2022
いいなと思ったら応援しよう!

